榎本武揚の晩年を訪ねて徘徊
何故、榎本武揚か、それは私どもの会社名が『武揚堂』だからです。
今日は、その会社のOBたちと、向島界隈を散歩しました。
散策のコース図は下の図の通りです。
赤の破線が墨田区内循環バス路線です。そして緑実線が散策のルートです。
5名の小グループで、押上駅から出発しました。
東京スカイツリーが出来た為か、周囲は極めてよく整備されていました。
榎本武揚像入口バス停からすこー し歩いて立像の前に行きました。
晩年はこのあたりの墨堤を馬に乗り、悠々自適の生活をしていたようです。
そして、再度バスで地蔵坂まで行き、白髭神社にお詣りしました。
地蔵坂には『旧墨堤の道』の説明板(区教育委員会)が建ていました。
このあたりが櫻の名所の中心で、榎本武揚も馬で逍遥していた土地のようです。
当時の写真が掲示板に添えてありましたので掲載します。
そして、同行の人の勧めで狭い路地に進みました。鳩の街通りだそうです。
昔、赤線の在った地域だそうです。
狭い道が延々と続いています。戦災に逢わず残ったからだそうです。
途中に、吉川英治の旧宅(現在は保育園)がありました。20歳の頃のわびしい佇まい跡だそうです。
そして、途中から道を隅田川沿いにそれたら、目の前に『榎本武揚旧居跡』と記した掲示板に出くわせました。
今日の我々が来るのを待っていたかのように。
その掲示板を拝借すると
「父は将軍側近で天文方として伊能忠敬にも師事した知識人であった。
武揚も幼いころから学才に長け、昌平黌で儒学を、江川太郎左衛門から蘭語、中濱満次郎から英語をそれぞれ学び、恵まれた環境で洋学の素養を身に着けた。
19歳で函館奉行の従者として蝦夷地に赴き、樺太探検に参加する。
安政3(1856)年には長崎海軍伝習所に学び、蘭学や造船学、航海術などを身につけた。
文久2(1862)年に幕府留学生としてオランダに渡って、船舶に関する知識をさらに深める一方、国際法や軍学を深めた。
慶応3(1867)年、幕府が発注した軍艦『開陽』に乗艦して帰国、翌4年に海軍副総裁に任ぜられた。
戊辰戦争では徹底抗戦を唱えたが、五稜郭で降伏、3年間投獄された。
この函館戦争で敵将ながらその非凡の才に感服した黒田清隆の擁護を受け、北海道開拓使に出仕。
明治7(1874)年に駐露特命全権公使となり、樺太・千島交換条約を締結。海軍卿、駐清公使を経て文部大臣、外務大臣などを歴任した。
明治38(1905)年から、73歳で没する同41年までこの地で暮らし、墨堤を馬で毎日散歩する姿が見られたという。」
この掲示に「父は将軍側近で天文方として伊能忠敬にも師事した知識人であった。…」とあるように、榎本武揚の血筋には地図とのかかわりが感じられます。
また、晩年の12年間は、既に「武揚堂」(明治30年創業)が出来ていたことと、かかわりがないとは思えません。
名前の拝借は公認されていたようです。
さらには、昭和16年陸軍省検閲済の『戦陣訓』の奥付(下の写真参照)にも、「発行所 株式会社 武揚堂」と明示してあることからも、榎本武揚との関係が歴然としているように思えます。
「・・・晩年は向島に住み、墨堤を馬に乗って散歩する等悠々自適の生活を楽しみ、同四十一年に七十三歳で死去しました。
隅田公園内の『墨堤植櫻之碑』や多門寺の『毘沙門天』の標石等、武揚の筆跡が区内の諸所に残されています。 平成十八年三月 墨田区教育委員会」
と、先の墨田区堤通二丁目の「榎本武揚像」の説明板にもありました。
書を好む氏の『武揚堂』の筆跡が、必ずどこかにあるはず。
墨田区教育委員会に訊くのも一つの方法では?・・・(保存されてないとのことでした。)
そこで案内された「すずめの御宿」でそばを、
そして後から駆けつけてくれた一人を加え6人で、浅草一丁目1番1号の神谷バーでビールと電気ブランを頂いて賑やかに散会しました。
浅草は、何時行ってもいいですな~!

























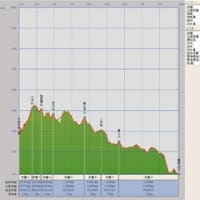
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます