
皆さんもよくご存知の「赤とんぼ」の歌で、最近ジ~ンとくる深い意味があることを知ったのでご紹介します。
夕焼け小焼けの赤とんぼ おわれてみたのはいつの日か
山の畑の桑の実を 小かごに摘んだはまぼろしか
十五で姐(ねえ)やは嫁にいき お里の便りも絶えはてた
夕焼け小焼けの赤とんぼ とまっているよ竿の先
「赤とんぼ」の作詞は三木露風ですが(大正10年に発表・作曲は山田耕作)、詞の内容は露風自身の幼少時代の思い出を正直に書いたものと思われます。
露風は5歳の時両親が離婚することになり、以降母親とは生き別れで祖父に養育されることになったのですが、実際は子守り奉公の姐やに面倒を見てもらい、そのときの印象を歌にしたものです。
だから詞の第一節の「おわれてみたのは」を漢字で書けば「追われてみたのは」ではなく、「負われて見たのは」であり、姐やの背中におんぶされて肩越しに見た夕焼け という意味です。
姐やといっても15歳で嫁に行ったのですから、当時の農家は赤貧のため口べらしもあっての子守り奉公で、しばらくして嫁いでいったわけですが、嫁入り先の農業労働力としての意味もあり、その後の姐やも働きづめの一生を送ったのでしょうね。
また、「お里の便りも絶えはてた」の意味は、姐やが嫁に行ってからは彼女の便りがなくなった と解釈する人もいますが、私の推薦する解釈では、お母さんは離婚し実家に出戻っているのですが、実のお母さんが実家の近くの娘を子守り奉公に出すように図ることにより、彼は姐やからお母さんの便りを聞くことが出来たのですが、姐やも嫁に行くことになって、もうお母さんの消息も聞くことが出来なくなったという意味だと思います。
第一節の「夕焼け小焼け」は幼少時代の思い出で、最後第四節の「夕焼け小焼け」は、あれから幾年月を経た今見る風景であり、実に時空を越えた詞の内容なのです。
この詞の中に3つの叙情がひとつの思いに重なりあっています。
ひとつは、真っ赤な夕焼けと赤とんぼの、美しくそして鮮烈な情景、忘れえぬ情景。
ふたつは、姐やの背中に感じる体温の暖かさと、姐やへのほのかな恋慕の情。
そしてみっつは、もう会うことが出来ない、母への強く切ない未練の心。
この短い詞の中に万感の思いが込められていたわけで、だからこそ時代を超えて私たち日本人の心を揺さぶる理由がそこにあったのですね~。
夕焼け小焼けの赤とんぼ おわれてみたのはいつの日か
山の畑の桑の実を 小かごに摘んだはまぼろしか
十五で姐(ねえ)やは嫁にいき お里の便りも絶えはてた
夕焼け小焼けの赤とんぼ とまっているよ竿の先
「赤とんぼ」の作詞は三木露風ですが(大正10年に発表・作曲は山田耕作)、詞の内容は露風自身の幼少時代の思い出を正直に書いたものと思われます。
露風は5歳の時両親が離婚することになり、以降母親とは生き別れで祖父に養育されることになったのですが、実際は子守り奉公の姐やに面倒を見てもらい、そのときの印象を歌にしたものです。
だから詞の第一節の「おわれてみたのは」を漢字で書けば「追われてみたのは」ではなく、「負われて見たのは」であり、姐やの背中におんぶされて肩越しに見た夕焼け という意味です。
姐やといっても15歳で嫁に行ったのですから、当時の農家は赤貧のため口べらしもあっての子守り奉公で、しばらくして嫁いでいったわけですが、嫁入り先の農業労働力としての意味もあり、その後の姐やも働きづめの一生を送ったのでしょうね。
また、「お里の便りも絶えはてた」の意味は、姐やが嫁に行ってからは彼女の便りがなくなった と解釈する人もいますが、私の推薦する解釈では、お母さんは離婚し実家に出戻っているのですが、実のお母さんが実家の近くの娘を子守り奉公に出すように図ることにより、彼は姐やからお母さんの便りを聞くことが出来たのですが、姐やも嫁に行くことになって、もうお母さんの消息も聞くことが出来なくなったという意味だと思います。
第一節の「夕焼け小焼け」は幼少時代の思い出で、最後第四節の「夕焼け小焼け」は、あれから幾年月を経た今見る風景であり、実に時空を越えた詞の内容なのです。
この詞の中に3つの叙情がひとつの思いに重なりあっています。
ひとつは、真っ赤な夕焼けと赤とんぼの、美しくそして鮮烈な情景、忘れえぬ情景。
ふたつは、姐やの背中に感じる体温の暖かさと、姐やへのほのかな恋慕の情。
そしてみっつは、もう会うことが出来ない、母への強く切ない未練の心。
この短い詞の中に万感の思いが込められていたわけで、だからこそ時代を超えて私たち日本人の心を揺さぶる理由がそこにあったのですね~。










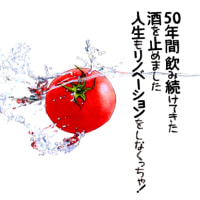


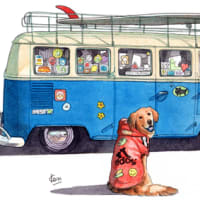



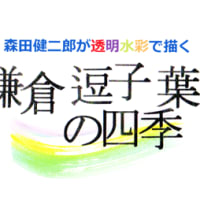
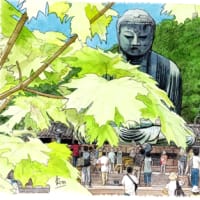
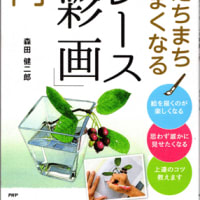
感謝致します。
ありがとうございました。
先程、口ずさんで歌ったりしていました。
15でお嫁に行った・・・・あたりに意味を知りたくなりました。
子守歌も似た内容ですね。
ちなみに、江戸時代までの絵巻、屏風絵に
女児が子守をしている絵が全く無いのはなぜか?
皆で考えてみましょう。
(検索=「5世紀頃のイスラムの子育て」
文科省は国辱ゆえ決して教えません。)
この歌詞のそんな奇妙奇天烈な解釈をはじめて
聞きました。
この歌詞のどこをどう読めばそんな妙ちくりんな
解釈が出てくるのでしょう。
「負はれて見た」を追われて見たと勘違いしてる輩を
笑えまへんで。
あほくさ。
「お里のたより」が姐やの生まれ育った実家を指すのか
それとも姐やの嫁入り先を指すのかという論議は
昔からあります。
勝手に姐やの母親を離婚させるような妄想は聞いたことがありまへん。
この歌詞の背景となった龍野時代に
母親と別れたことからの考察でしょう
それと「ねえやの母親」は誤読ですね
上の考察の母親は
あくまで詞の主体の母親と書かれていますよ
悲しい歌ですね。今度、合唱団のオーディションで歌います。意味を理解して歌います。きっと合格すると思います。。
ありがとうございますU+203CU+FE0FU+1F602
お姉さんからお母さんのの情報が、お姉さんの結婚によって途切れてしまった・・・
本当に悲しく、寂しい気持ちを美しい日本語で
短くまとめた能力は素晴らしいですね。
この曲の救い、素晴らしさは、とても悲しい詩を、
美しいメロディによって芸術の域に昇華させたことだと
思います。