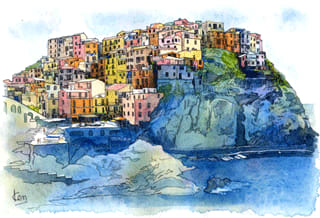2011年を総括すると、何といっても東日本大震災に尽きるようです。
マグネチュード9.0の地震とその後に来た巨大津波により、死者と被害者を合わせて1万9千人を越える犠牲者が出、原発の放射能漏れは社会に深刻なダメージをあたえました。
もっと被害を小さくできなかったのか、そのキーワードは「まさか!」という言葉に集約されているようです。
私は神奈川県逗子の自宅で震災に遭遇しましたが、震源地から600キロも離れているにもかかわらず、これまで体験したことのない揺れが襲って地域全体が停電となり、そのため自家用車に篭り、自動車用小型テレビを固唾を呑んでみる観ることとなりました。
その中で自衛隊のヘリコプターからの津波が、家や田畑を悪魔の影のように飲み込んでいく映像と、10メートル以上の津波であることを知らされたとき、私はそのすごさに「まさか!」と叫ぶしかありませんでした。
以降の東日本大震災は「まさか!」の連続でした。
街を走る自動車のフトントガラスから見る建物の間から突然水が溢れ出し、あっという間に津波に車が飲み込まれて九死に一生を得た人は「まさか、こんなに巨大な津波が来るとは思いもよりませんでした」と言うコメントが印象的でした。
わが家は大丈夫という高台の自宅や、避難所にいる人までも、「まさか!」の津波にやられ、多くの方が犠牲になりました。
安全の上にも安全に作られた福島第一原発は、「まさか!」の巨大津波によるメルトダウンと水素爆発により、大量の放射能の外部流出事故となり、その後の社会に甚大なダメージをもたらしました。
ここでいう「まさか!」とは「想定外の巨大津波」のことを意味しているのですが、それではどの大きさまでを想定していたのでしょう。
被害地の三陸地方一帯の歴史を紐解けば、過去に幾度もの巨大津波に襲われてきたのですが、その巨大地震を分析すれば、100年に1度の間隔で5メートル内の津波が襲い、1000年に1度の間隔で10メートル以上の津波が襲ったとのことです。
東日本大震災の甚大な被害の原因は、行政も東京電力も1000年に1度の津波ではなく、100年に1度の津波にしか対応していなかったからなのです。
その理由は1000年の対応は100年より圧倒的な経費がかかるからであり、それが「まさか!」の甚大な被害をもたらした主たる原因となったのです。
2011年の日本の総括の後に、私の今年を総括するにはちょっと気が引けますが、今年は無事安泰、ぬるま湯に浸かっているような1年でした。
考えてみれば、それは今年だけでなく、私の60代(現在は68歳)は実に安泰な年代であり、喜怒哀楽の怒と哀がぬけて、喜と楽の日々だったかもしれません。
しかしこれまではラッキーだっただけで、これからの人生・特に私のようなノー天気の人間にこそ「まさか!」の悪魔が突然訪れるのです。
その「まさか!」は深刻な病気かもしれないし、不運な事故かもしれません。
今回のような自然災害かもしれないし、もしかして振込詐欺に騙されるかもしれません。
2012年以降もこのままずっと喜と楽だけのぬるま湯生活を続けるには、1000年級の「まさか!」対策をしっかり講じることも必要かもしれません。