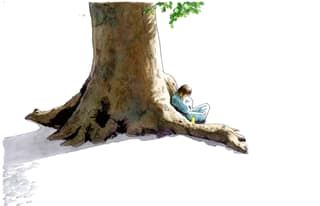Facebookを始めたのですが、それがすごく面白いのです。
Facebook(フェイスブック)は、世界最大のソーシャルネットサービスで、実名での人と人とがネット上でつながり、情報や意見などを共有できるなどの交流サイトです。
類似のサービスとしては日本ではmixiやgreeがありますが、これらはバーチャル(架空)での交流に対し、Facebookは実名での人と人とのリアルな交流のため、内容に現実性とリアル感というインパクトがあり、たとえば中東の民主化などはFacebookだからこそ政治変革の原動力となったのであり、多くの恋が生まれカップルが誕生したのもFacebookだからこそだと思います。
Facebookのもうひとつの特色は、会員数が非常に多いということです。
世界では8億人が登録しており、発祥の地アメリカでは人口3億人の中で約半分の1.5億人がFacebookを活用するなど、社会の中に深く浸透しており、日本では現在600万人程度ですが、急速な増加をたどると予測され、社会生活での必須アイテムとなる可能性を秘めています。
それは若者や働き盛りのビジネスもさることながら、主婦や中高年の方こそ人生の充実のための強い味方となるのではと思っています。
上の絵の人物は、品格のある上にただ者ではない雰囲気を持つ紳士ですが、それが私が描いた私の自画像でFacebookのプロフィールに貼ってあります。
このようにFacebookでは実名だけではなく原則本人の写真を載せることにより、たとえば私の名前の「森田健二郎」を検索すると、同姓同名の2つのサイトが出てきますが、画像により私と確認できる機能を持っているのです。
だから懐かしい昔の友達を探す場合、名前と顔の記憶さえあれば、「すっかり禿げたおじさんになったけど、面影ある~!」と簡単に探し出せるなど抜群の友人検索ができるので、試しにあなたもとりあえず初恋の人など軽~くチャレンジいてみてはいかがでしょう。
私はFacebookへ登録してそんなに期日が経っていなく、まだお話するほどFacebookに詳しくはありませんが、1日1枚の作品をちょっとユーモラスなコメントとともに更新しているため、それを通していろいろな方から友達になりたいとの希望が来ています。
その中でも気のせいか女性・それも美しい女性や昔美しかった女性からの希望者が多く、それぞれの方のそれぞれの出来事の記事をFacebookで見ることもできるため、それが毎日の大きな楽しみのひとつになっています。
あなたもFacebookの登録をしませんか。Facebookに参加することは現代人の身だしなみになるかもしれません。
無料の上にとても簡単・・・インターネットでの「Facebook 日本語」を検索し、指示通り書き込めば、あっというまに登録できます。
Facebookは友達の輪を広けるサイトですから、気が向いたら私とも友達になってください。大歓迎です。