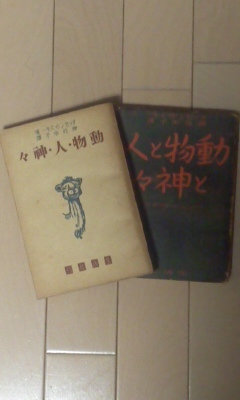白土三平は貸本界の大スターであり、その「忍者武芸帳」はいつも引っ張りだこで、一向に巡り会えない伝説的な漫画本だった。何人待ちという予約の制度があったかどうかは知らないが、ともかく全巻を制覇しないうちに貸本時代は終わりを告げてしまったような気がする。全巻どころか、わずか数巻しか借りて読んだ記憶がない以上、事実はそうだったのだろう。
ただ、家では『少年』を購読していたおかげで、漫画に事欠くことはなかった。かの「鉄腕アトム」、「鉄人28号」、「どんぐり天狗」、「だるまくん」、「少年ザンバ」などなど、廊下に棚を作って本誌から付録まで、ずらっと列べて何遍も読み返すのである。なにせ本を置いていない家だったから、活字に触れるとしたら『少年』か『平凡』くらいしかない。要するに漫画と芸能記事だけが文字に親しむ唯一の場面だったわけである。
月刊誌だから当たり前だが、一箇月に一回本屋から雑誌が届くと、一日もかからずに全部読み切ってしまう。一息に読み切ってしまうと言った方がいい。だから、親からは毎度必ず「もう読んじまったのか。どうしてそんなに一度に読んでしまうんだ。もっとゆっくり大事に読め。」と叱言を言われていた。漫画を熟読玩味するなんて、そんな抑制心は子供にはない。ウサギを目の前にした餓狼なのである。そして、残りの三十日近くは、廊下の棚に入り乱れている既刊号を無限回遊して過ごすのである。偶に古い号から少量処分して棚の容量の辻褄合わせをするのだが、漫画本がなくなって行くのはとても嫌な心持のするものである。いわば二度と読めなくなるための儀式なので、処分の日は処刑の日のような、大きな喪失感に襲われる、がっかりの日でもあった。
貸本屋には兄に連れて行ってもらったのだが、そこは『少年』で知っている漫画とは一線を画す世界だった。大人向けの小説本や教養本も数を揃えていたのかも知れないが、勿論そんなものは眼中にない。目に入るのは漫画本しかないのだが、貸本屋にある漫画は、家で慣れ親しんだ漫画とは明らかに質感を異にした描線とストーリーでできたものだった。ただ、だからといって違和感があったということは全然なくて、漫画は漫画という感覚で、親から駄賃がもらえたときに借りてきては無分別に読んでいた。 今となってみれば、それが貸本漫画という世界の、劇画というものであったことを知識として知っているが、貸本屋のおじさんとおばさんから親切にされ、新しい漫画を読むのが一日の最大の愉しみだった頃、まだ意識は朦朧、未分化のまま漫画の世界を無境界に生きていたのである。当然、そこにある漫画を借りて読んで返すということ以外に貸本屋で覚える必要のあることはなにもなく、読みふけった貸本漫画の題名も作者も、すべて漫画という一言のなかに消え去ってしまっている。実は、それらの漫画が貸本屋に行かなければ読めない漫画だとすら気が付いていなかったのである。
唯一、それをそれとして兄から教えられたのが、白土三平の「忍者武芸帳」であった。同じ貸本漫画のなかでも抜きん出て面白く、剛線によって死闘が繰り広げられていく。原初的な暴力を画面に叩き付け、毛物めいた臭いを吹き上げてくるキャラクターと出会った驚きは今に忘れない。何巻にも及ぶ長篇大河の歴史動乱のなかで、かろうじて読むことができた巻に登場するくされ、しびれとか蔵六とか、生まれ付いての異能によって危地を脱し敵を倒す忍者たちは、豪傑でない人間の必殺技で胸躍らせてくれるとともに、旧来の漫画にはない異形の力というようなものを初めて感じさせてくれた。しかも、この「忍者武芸帳」たるや、どこに行っても手に入らない、貸本屋にしか姿を現さない、いつ行っても落手できないという隠秘の本に近くなっていて、どんなにか読みたいと切望しても叶えられない、その飢渇感は尋常大抵のものではなかったのである。そしていまや、様々に版を変えて出版され、文庫版などは古本屋の均一台にばらまかれるような時代になってしまった。
大島渚監督の御宅の写真をグラフ雑誌かなにかで見かけたことがある。居間に置かれたサイドボードの内奥に、貸本オリジナル版「忍者武芸帳」の一揃いが、あたかも深海魚のようにひっそりと潜んでいるのを垣間見たときは、じんわりと懐かしい思いが湧いてきた。復刻版でも愛蔵版でも代えられない、身辺にあったこの本でなければならない必然の体験があるからこそ、摺れて傷んで修復の痕そのままの古本は、生きた時代のかけがいない形見の一つとして残ったのだと思いつつ、監督の影丸映画は未見である。
最新の画像[もっと見る]
-
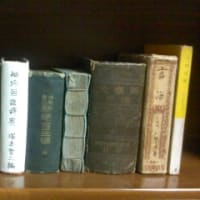 辞書は大小を超越する宇宙書物である
9年前
辞書は大小を超越する宇宙書物である
9年前
-
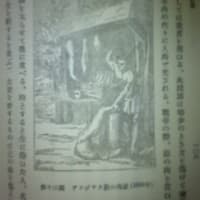 ラブクラフトが夢想した『コンゴ王国』
14年前
ラブクラフトが夢想した『コンゴ王国』
14年前
-
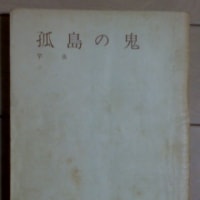 乱歩「孤島の鬼」は西日を浴びて読む
16年前
乱歩「孤島の鬼」は西日を浴びて読む
16年前
「瓶詰の古本」カテゴリの最新記事
 数多ある怪異不可思議話が文学作品になり得ることを発見し、神秘的詩謡にも親しい...
数多ある怪異不可思議話が文学作品になり得ることを発見し、神秘的詩謡にも親しい... 「大辭林」序(宇野圓空)
「大辭林」序(宇野圓空) ひょっとしたら、その人なりに文学を生きようとしたのかも知れない
ひょっとしたら、その人なりに文学を生きようとしたのかも知れない 地道な古本病者は心底手に入れたい本の名を漫りに明かさない(本棚の至高形態はカ...
地道な古本病者は心底手に入れたい本の名を漫りに明かさない(本棚の至高形態はカ... ずっと閉じ込められても生理的大惨事だけは心配ないが、しかし非常に狭苦しいので...
ずっと閉じ込められても生理的大惨事だけは心配ないが、しかし非常に狭苦しいので... 沼とそれを包む濃霧という別世界、小暗い神秘の国(モーパッサン)
沼とそれを包む濃霧という別世界、小暗い神秘の国(モーパッサン) 辞書を編む人たちなら、手塩にかけた辞書がひとりぼっちで働き詰めに働くのは可哀...
辞書を編む人たちなら、手塩にかけた辞書がひとりぼっちで働き詰めに働くのは可哀... 予知と予測は同じことではないので、適切に使い分ける必要があるらしい(佐野利器)
予知と予測は同じことではないので、適切に使い分ける必要があるらしい(佐野利器) 実利に偏した頭脳は人物の為した業績の精神的価値に思い及ぶなど毛頭なく、利得効...
実利に偏した頭脳は人物の為した業績の精神的価値に思い及ぶなど毛頭なく、利得効... 木村鷹太郎という審美の熱源(木村鷹太郎)
木村鷹太郎という審美の熱源(木村鷹太郎)