先日イタリア文化会館の講演会を聴講したのだが、《ウルビーノのヴィーナス》は壁により中央から左右に分断され、侍女たちのいる後景は画中画のように見える、というお話を聴き、おお、なるほど!と唸ってしまった。
実はそれを確かめに、講演会で当たった招待券を握って(笑)再度展覧会を観てきた。で、やはり!室内の壁の下部分からの延長線はタイル貼りの領域と区別するようにはっきりと壁色に塗られていた。確かに「後景」は「絵画」のように見えるのだ(・.・;)
さて、話を展覧会感想に戻すが、今回、シモーネ・ペテルツァーノ(Simone Peterzano 1540~1596頃)の《ヴィーナス、キューピッド、二人のサテュロス》(1570年)も展示されていた。ちなみに、ペテルツァーノ作品だと特定したのはミーナ・グレゴーリだった。やはり守備範囲だろうなぁ。

シモーネ・ペテルツァーノ《ヴィーナス、キューピッド、二人のサテュロス》
眠るヴィーナスに好色そうなサテュロスが悪戯をしかけるのだが、あまりにも無防備なヴィーナスの輝く肢体が美しい。サテュロスの野蛮そうな赤黒肌があるから、よけいにヴィーナスの白い肌が輝いてみえるのかも。この主題ってきっと人気があって注文も多かったのだろうなぁ、と思いながら見てしまった(笑)
【補足】実は向かって右のサテュロスがどうも気になっていた。彼が持つ果物はヴィーナスのものを失敬しようとしているのか、それとも彼女のために置いているのか、私的にちょっと迷っていたのだ。しかし、ヤギ(山羊)は「犠牲」を象徴するから、やはりヴィーナスのための供物として「愛の犠牲」的な面を象徴するのではないかと思う。要するにこれも好色なサテュロスが「地上の愛」で右のサテュロスが「天上の愛」なのかも。私的な推測だが、きっとこの新プラトン主義的な図式って当時のエクスキューズ的お約束事だったんじゃないだろうか?(^^;;;
ところで、ペテルツァーノはヴェネツィアのティツィアーノ工房で学び、それを誇りにしていたようで、背景の風景や空の光、甘美なヴィーナスの肢体などにヴェネツィア派の影響を見てしまう。ヴィーナスの敷いている光沢のある布地(きっと絹)の赤と青なんてまさにティツィアーノ色!ヴィーナスの眠るポーズもヴェネツィア派の系統っぽい。サテュロスの握る果物の葉(?)なんて《ウルビーノのヴィーナス》の紅薔薇に似ているような気もするし…。

シモーネ・ペテルツァーノ《ヴィーナス、キューピッド、二人のサテュロス》


ティツィアーノ《ウルビーノのヴィーナス》 カラヴァッジョ《病めるバッカス》
で、私的に特に注目したのはサテュロス達の筋肉質で自然主義的な描写や、手で掴んだり下草に置いてある果物などの静物描写だった。さすがロンバルディアの画家!♪
横にちょこんと顔を見せるヤギもなんだか気になる。すなわち、カラヴァッジョ的世界の断片がそこかしこに散見できたような気がしたのだ。

カラヴァッジョ《バッカス》

カラヴァッジョ《イサクの犠牲》
なにしろペテルツァーノはカラヴァッジョのミラノ時代の師匠なのだから。カラヴァッジョは1584年にペテルツァーノ工房の徒弟となっている。
ところが、今回の図録を読んでいたら興味ある記述があった。
ペテルツァーノは1585~89年までローマに滞在し、1589年にはミラノに戻っていたと考えられるとのこと。で、カラヴァッジョは1584年にペテルツァーノ工房と4年間の徒弟契約をしており、契約終了の1588年には師匠はまだローマだということになる。ペテルツァーノと工房で顔を合わせたのは1584~85年の1年間だけなのだろうか??
ちなみに、カラヴァッジョがミラノからローマに向かうのは1592年ごろだが、犯罪事件を起こしたのでミラノを出たという説があるけど、ローマから戻ったペテルツァーノ情報で触発された部分も少しはあるかもしれない、などとあれこれ想いを馳せてしまった。もちろん、ド素人の勝手な憶測の楽しみなのでご容赦あれ(^^;;;
実はそれを確かめに、講演会で当たった招待券を握って(笑)再度展覧会を観てきた。で、やはり!室内の壁の下部分からの延長線はタイル貼りの領域と区別するようにはっきりと壁色に塗られていた。確かに「後景」は「絵画」のように見えるのだ(・.・;)
さて、話を展覧会感想に戻すが、今回、シモーネ・ペテルツァーノ(Simone Peterzano 1540~1596頃)の《ヴィーナス、キューピッド、二人のサテュロス》(1570年)も展示されていた。ちなみに、ペテルツァーノ作品だと特定したのはミーナ・グレゴーリだった。やはり守備範囲だろうなぁ。

シモーネ・ペテルツァーノ《ヴィーナス、キューピッド、二人のサテュロス》
眠るヴィーナスに好色そうなサテュロスが悪戯をしかけるのだが、あまりにも無防備なヴィーナスの輝く肢体が美しい。サテュロスの野蛮そうな赤黒肌があるから、よけいにヴィーナスの白い肌が輝いてみえるのかも。この主題ってきっと人気があって注文も多かったのだろうなぁ、と思いながら見てしまった(笑)
【補足】実は向かって右のサテュロスがどうも気になっていた。彼が持つ果物はヴィーナスのものを失敬しようとしているのか、それとも彼女のために置いているのか、私的にちょっと迷っていたのだ。しかし、ヤギ(山羊)は「犠牲」を象徴するから、やはりヴィーナスのための供物として「愛の犠牲」的な面を象徴するのではないかと思う。要するにこれも好色なサテュロスが「地上の愛」で右のサテュロスが「天上の愛」なのかも。私的な推測だが、きっとこの新プラトン主義的な図式って当時のエクスキューズ的お約束事だったんじゃないだろうか?(^^;;;
ところで、ペテルツァーノはヴェネツィアのティツィアーノ工房で学び、それを誇りにしていたようで、背景の風景や空の光、甘美なヴィーナスの肢体などにヴェネツィア派の影響を見てしまう。ヴィーナスの敷いている光沢のある布地(きっと絹)の赤と青なんてまさにティツィアーノ色!ヴィーナスの眠るポーズもヴェネツィア派の系統っぽい。サテュロスの握る果物の葉(?)なんて《ウルビーノのヴィーナス》の紅薔薇に似ているような気もするし…。

シモーネ・ペテルツァーノ《ヴィーナス、キューピッド、二人のサテュロス》


ティツィアーノ《ウルビーノのヴィーナス》 カラヴァッジョ《病めるバッカス》
で、私的に特に注目したのはサテュロス達の筋肉質で自然主義的な描写や、手で掴んだり下草に置いてある果物などの静物描写だった。さすがロンバルディアの画家!♪
横にちょこんと顔を見せるヤギもなんだか気になる。すなわち、カラヴァッジョ的世界の断片がそこかしこに散見できたような気がしたのだ。

カラヴァッジョ《バッカス》

カラヴァッジョ《イサクの犠牲》
なにしろペテルツァーノはカラヴァッジョのミラノ時代の師匠なのだから。カラヴァッジョは1584年にペテルツァーノ工房の徒弟となっている。
ところが、今回の図録を読んでいたら興味ある記述があった。
ペテルツァーノは1585~89年までローマに滞在し、1589年にはミラノに戻っていたと考えられるとのこと。で、カラヴァッジョは1584年にペテルツァーノ工房と4年間の徒弟契約をしており、契約終了の1588年には師匠はまだローマだということになる。ペテルツァーノと工房で顔を合わせたのは1584~85年の1年間だけなのだろうか??
ちなみに、カラヴァッジョがミラノからローマに向かうのは1592年ごろだが、犯罪事件を起こしたのでミラノを出たという説があるけど、ローマから戻ったペテルツァーノ情報で触発された部分も少しはあるかもしれない、などとあれこれ想いを馳せてしまった。もちろん、ド素人の勝手な憶測の楽しみなのでご容赦あれ(^^;;;




















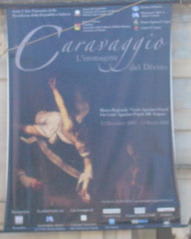




 拡大は
拡大は