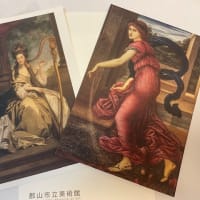次の展示室は「展覧会」らしい展示室だった。
まずは、《マッフェオ・バルベリーニの肖像》が2枚並ぶ。今回の展覧会は、カラヴァッジョ真作である《マッフェオ・バルベリーニの肖像》がパラッツォ・バルベリーニに戻った帰館祝いのようなもであるのだし...。



左)カラヴァッジョ「?」《マッフェオ・バルベリーニの肖像》(1595年頃)個人蔵(フィレンツェ)
右)カラヴァッジョ《マッフェオ・バルベリーニの肖像》(1598-99年)個人蔵
私的にも以前からこの並び展示を熱望していた。なぜなら、左の日本に来日したこともあるフィレンツェ作品は以前から私的に「?」作品であり、真作である右の個人蔵作品と並べ比較してみたかったのだ。
当然と言うか、今回の並び展示から2つの作品の質と完成度の違いがはっきりと了解された。あくまでも美術ド素人眼ではあるが(汗)、フイレンツェ作品はマッフェオ自身を描く描写力にやや稚拙さを感じるのだ。画面から溢れる生気(リアル感)が全然違う!! 静物画を得意とするカラヴァッジョにしては構成要素の机上の花瓶と花も「らしく」はあるがイマイチであり、白ブラウスの襞描写もありきたりである。
それに、1595年頃? デル・モンテ枢機卿に庇護されとしても、早々に肖像画を描くほどマッフェオ・バルベリーニと懇意にできたのだろうか??
※ご参考(拙ブログ):「カラヴァッジョ《マッフェオ・バルベリーニの肖像》初公開展」サクッと感想
https://blog.goo.ne.jp/kal1123/e/5c8d69d658f0391cb197b0eeafa1b7a9
続いて並んだのは《マグダラのマリアの回心》と《ホロフェルネスの首を斬るユディット》だった。


左)カラヴァッジョ《マルタとマグダラのマリア》(1598-99年頃)デトロイト美術館
右)カラヴァッジョ《ホロフェルネスの首を斬るユディット》(1599-1600年頃)バルベリーニ国立古典絵画館
あらためて2作品を並べて観ると、カラヴァッジョの「紅(赤)」の使い方に目が惹かれた。マグダラのマリアの衣装の袖の紅色とユディットの背景のカーテンの紅色、そのドレープ(襞)の複雑な波打ち方が二人の感情と画面の緊張感に大いに寄与しているのだ。特にユディットの紅カーテンはホロフェルネスの血飛沫と呼応したように禍々しくうねる。カラヴァッジョは他作品でも紅(赤)ドレープを多用しており、その使い方が実に長けていると思う。
そして....今回の展覧会の顔となっていた《聖カテリナの殉教》が続く。この作品はマッフェオ・バルベリーニ(教皇ウルバヌス8世)の甥であるアントニオ・バルベリーニ枢機卿がMet《リュート奏者》とともにコレクションしていたものだが、要するに、バルベリーニ企画ならではの含みがあったわけ...かな?

カラヴァッジョ《アレキサンドリアの聖カテリナ》(1598-99年頃)ティッセン・ボルネミッサ美術館
聖カテリナの紅(赤)は赤いクッションもだが、何と言っても彼女の持つ剣先に付着する血色である。自らを死に追いやった剣の禍々しさを暗黙の裡に私たちに示しているのだと思う。
この3作品が並んだのはモデルが同一であり、そのモデルはカラヴァッジョが懇意にしていたコルティジャーナのフィリーデ・メランドローニとされる。確かに、目元から鼻筋にかけてよく似ているのだ。

カラヴァッジョ《フィリーデ・メランドローニの肖像》(1597年頃)(元)カイザー・フリードリッヒ美術館(ボーデ美術館)(1945年焼失)のカラー復元写真
カラヴァッジョの同一モデル作品を並べることのできた今回の展覧会は、ある意味でとても贅沢だと思った。