江戸時代の宝暦4年(1754)の遠野は大洪水による凶作、また翌年の宝暦5年は冷害による凶作と2年続けての凶作となったと記録されている。
宝暦年中(1751~1763)の遠野は、各方面ともに順調な発展を遂げ、人口も2万人弱、約19,400余人、家屋数約3,500軒との記録である。(紫波佐比内村含む)
宝暦5年は遠野領空前絶後の大凶作といわれ、春の田植時期は寒く綿入れを着たまま、さらに近くに焚き火をして手を暖めながらの田植作業と伝えられる。
初夏の頃は毎日のように霧雨が降り、太陽は隠れたままで、盛夏になりようやく暑い日もあったと伝えられますが、細いながらも幾らかの穂が出、初夏までの低温での遅れを完全挽回に至らずとも、このまま暑い日が続けば家族でなんとか食べていける程度の収穫は期待できると皆でホッとしかけた矢先、8月16、17日、二日続けて霜が降りたという・・・。
米は全くという程採れず、稗、粟、豆といった雑穀類も同様、まさに大凶作となり、米、雑穀の類の価格が急騰、宝暦4年当時の人口約1万9千余人の内、救済を受けた者7千5百人余、餓死者は、3千人と記録されている。
また領内から出奔した男女5百人弱、主を失った空家が目立ち、また疲弊していたところに労力が足りず、さらに宝暦6年も凶作、7年も凶作となり田畑は不毛の地と化したともある。
さらに後年の天明、天保時代にも大凶作が発生、宝暦の大飢饉をも凌ぐ甚大な被害となった。

松崎字洞の里・・・・現松崎町光興寺宮代
飢饉無縁塔

飢饉の碑ともいわれますが、別説として他領から流れついた人々がこの地で亡くなり、その無縁仏を鎮魂する碑ともいわれますが、遠野古事記には3千人前後の餓死者(遠野旧事記には40名弱、ここでは遠野古事記を採用)とあり、いかに大飢饉だったかを物語ものでもあり、無縁塔は遠野領内各地から食を求めた人々が彷徨い力尽きて亡くなった方々の霊全てを鎮魂するものであったと私は認識しております。
私も含み現代人には、到底想像も出来ない凄惨な場面があったのだろう・・・。
今年は台風直撃かと心配される災害も発生しましたが、なんとか大きな被害は免れ、米も平年作といわれております。
しかし、米価は年々下落、しかも美味しく、かつ安全なお米でなければ競争には打ち勝てないという時代となり、小規模農家にとっては実入りの少ない分野となっております。


松崎町松崎・・・遠野市内でも米処である松崎町
余談となりますが、十数年前の平成の大凶作、私の母親なんかは、餓死だと騒ぎ、うどんや蕎麦を食べなければならない、配給される米では足りないと騒ぎたててましたが、今だから言いますが、我が家には古米、古々米はある程度備蓄されておりやんした・・・汗
今考えれば凶作が数年も続けば、それこそ飽食の時代どころではなく、現代人はどうなるのだろう、私のように魚介類が苦手とか偏食人間が言うことではないが、母親のように強かに食に関しては考えなくてはと思いますし、基幹産業は農、これ人間の根底にあるもので最も大事なことではないでしょうか、つくづくこの歳になり考えるようになりました。

松崎町駒木
もうひとつ・・・
10月17日(水)は福泉寺秋の大祭であります。
このお祭りでの役割を決めるため、檀家筆頭家の面々が集まり取り決めました。
今回は、檀家役員での事務局長的な方が先月亡くなられ、大きな穴が空いたようでもありましたが、我家の本家的な家のご当主様をお迎えして、なんとか滞りなく取り決めることができました。
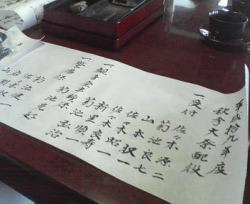
今回も最年少は親父年齢の私です・・・笑
宝暦年中(1751~1763)の遠野は、各方面ともに順調な発展を遂げ、人口も2万人弱、約19,400余人、家屋数約3,500軒との記録である。(紫波佐比内村含む)
宝暦5年は遠野領空前絶後の大凶作といわれ、春の田植時期は寒く綿入れを着たまま、さらに近くに焚き火をして手を暖めながらの田植作業と伝えられる。
初夏の頃は毎日のように霧雨が降り、太陽は隠れたままで、盛夏になりようやく暑い日もあったと伝えられますが、細いながらも幾らかの穂が出、初夏までの低温での遅れを完全挽回に至らずとも、このまま暑い日が続けば家族でなんとか食べていける程度の収穫は期待できると皆でホッとしかけた矢先、8月16、17日、二日続けて霜が降りたという・・・。
米は全くという程採れず、稗、粟、豆といった雑穀類も同様、まさに大凶作となり、米、雑穀の類の価格が急騰、宝暦4年当時の人口約1万9千余人の内、救済を受けた者7千5百人余、餓死者は、3千人と記録されている。
また領内から出奔した男女5百人弱、主を失った空家が目立ち、また疲弊していたところに労力が足りず、さらに宝暦6年も凶作、7年も凶作となり田畑は不毛の地と化したともある。
さらに後年の天明、天保時代にも大凶作が発生、宝暦の大飢饉をも凌ぐ甚大な被害となった。

松崎字洞の里・・・・現松崎町光興寺宮代
飢饉無縁塔

飢饉の碑ともいわれますが、別説として他領から流れついた人々がこの地で亡くなり、その無縁仏を鎮魂する碑ともいわれますが、遠野古事記には3千人前後の餓死者(遠野旧事記には40名弱、ここでは遠野古事記を採用)とあり、いかに大飢饉だったかを物語ものでもあり、無縁塔は遠野領内各地から食を求めた人々が彷徨い力尽きて亡くなった方々の霊全てを鎮魂するものであったと私は認識しております。
私も含み現代人には、到底想像も出来ない凄惨な場面があったのだろう・・・。
今年は台風直撃かと心配される災害も発生しましたが、なんとか大きな被害は免れ、米も平年作といわれております。
しかし、米価は年々下落、しかも美味しく、かつ安全なお米でなければ競争には打ち勝てないという時代となり、小規模農家にとっては実入りの少ない分野となっております。


松崎町松崎・・・遠野市内でも米処である松崎町
余談となりますが、十数年前の平成の大凶作、私の母親なんかは、餓死だと騒ぎ、うどんや蕎麦を食べなければならない、配給される米では足りないと騒ぎたててましたが、今だから言いますが、我が家には古米、古々米はある程度備蓄されておりやんした・・・汗
今考えれば凶作が数年も続けば、それこそ飽食の時代どころではなく、現代人はどうなるのだろう、私のように魚介類が苦手とか偏食人間が言うことではないが、母親のように強かに食に関しては考えなくてはと思いますし、基幹産業は農、これ人間の根底にあるもので最も大事なことではないでしょうか、つくづくこの歳になり考えるようになりました。

松崎町駒木
もうひとつ・・・
10月17日(水)は福泉寺秋の大祭であります。
このお祭りでの役割を決めるため、檀家筆頭家の面々が集まり取り決めました。
今回は、檀家役員での事務局長的な方が先月亡くなられ、大きな穴が空いたようでもありましたが、我家の本家的な家のご当主様をお迎えして、なんとか滞りなく取り決めることができました。
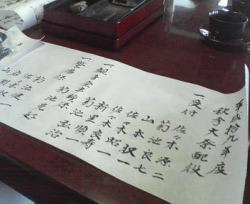
今回も最年少は親父年齢の私です・・・笑




















食糧事情は一変して地球の裏側から調達する時代となりました。
しかし農民魂は遺伝子に組み込まれております。
種籾は必ず残す・・・・一粒万倍とならん源ですから、そして収穫までは油断がならないと言う事。
自然のあらゆる恐怖に慄いていた時代が先ごろまであったのです。
余分に取っておくのは知恵です。農家はコメを隠していると言われた平成の凶作でした。
代用する食べ物があってもコメがなければパニックになるんですね。
自給率からしても国の方策が正しいとはいえないのが現状ですね。
自然を敬い、共に生きる百姓(百の姓で尊敬語と自身は考えているのであえて使わせていただく)無くしてこの国は滅びてしまいます!!!
百姓に片足のみ突っ込んで引っ込めた身では説得力のない我身、しかし、人間の根源はまずは食、昔から食う為に働く、食わねば死んでしまう、エネルギーの源、色んな食が溢れかえっている日本、餓死の話はナンセンスと若い奴らに一蹴されたこともございます。
米以外でも食べるものはなんでもあるという錯覚なのでしょう・・・確かにその通りながらも、いつかとてつもない大どんでん返しに遭ったとき、日本の農をないがしろにしたツケは大きな犠牲を払うことになるかもしれませんね。
若者は、米穀通帳なんか知らないだろうな
今の子供達から「はらへった」の言葉を聞いたことがない。
本来人間が食べるべき穀物を美味しい肉を食べたいが為に牛に喰わせ、車を走らせる燃料にしたり・・・考えさせられる事ばかり。
肉1㎏作るのに何㎏穀物を食わせなければならないかの計算をした場合によると、人間が肉食を止めれば食糧難は地球から無くなるそうです。
八戸の対泉院にある餓死萬霊等供養塔には人肉を食べたという記述を削り取った跡があります。
子供の頃その話を聞いたときはぞっとしたものです。
今の日本、もっと農業に力を入れて敬意を払っていかないと将来どうなるんだろう、と柄にもなく不安になります。
農家に生まれながらも農業のほとんどから遠ざかってしまった私ですのでなんともいえませんが、農業も新たな道に足を踏み入れているといった時代でしょうね。
今は世界各地から食が輸入され、ありとあらゆるものを食べることのできる時代、「腹減った」の声、確かに多くは聞かれませんね。
腹へっても私の子供時代はおやつも食べれる環境ではなく、強いていえば白い米に納豆があれば沢山食べる、これだけでも贅沢だったかもしれません。
なのに私は魚介類がダメ・・・まだまだ修行が足りませんね・・・汗
昔の飢饉は現代人の想像を遙かに超えるものだったと思います。
遠野で人肉はどうかはわかりませんが、赤子や幼児が川へ捨てられた、或いは一家で入水した、こういったことはあったものと思ってます。
こんなことから流された幼児達をみて河童という話もなくは無く、また生き残った子供が岸へ這い上がる姿が河童に連想された、こんな説もあるのですが、いずれ飢饉では凄惨な光景だったと思われます。
ゴエガッパ様(本業電気工事業)にみてもらった。すると、「近くに大勢の骨のうまってるところがある・・・。供養されてない」趣旨の話をしてた。確かに近場に思い当たる節が・・・古廟山の手前に宝暦?天明?の飢饉供養碑があった。伝承で「かつて工事かなんかで掘り返したたら夥しい人骨がでてきて移転をあきらめた云々」。土地勘すらまったくない河童様の千里眼には思わずゾーっとしました。