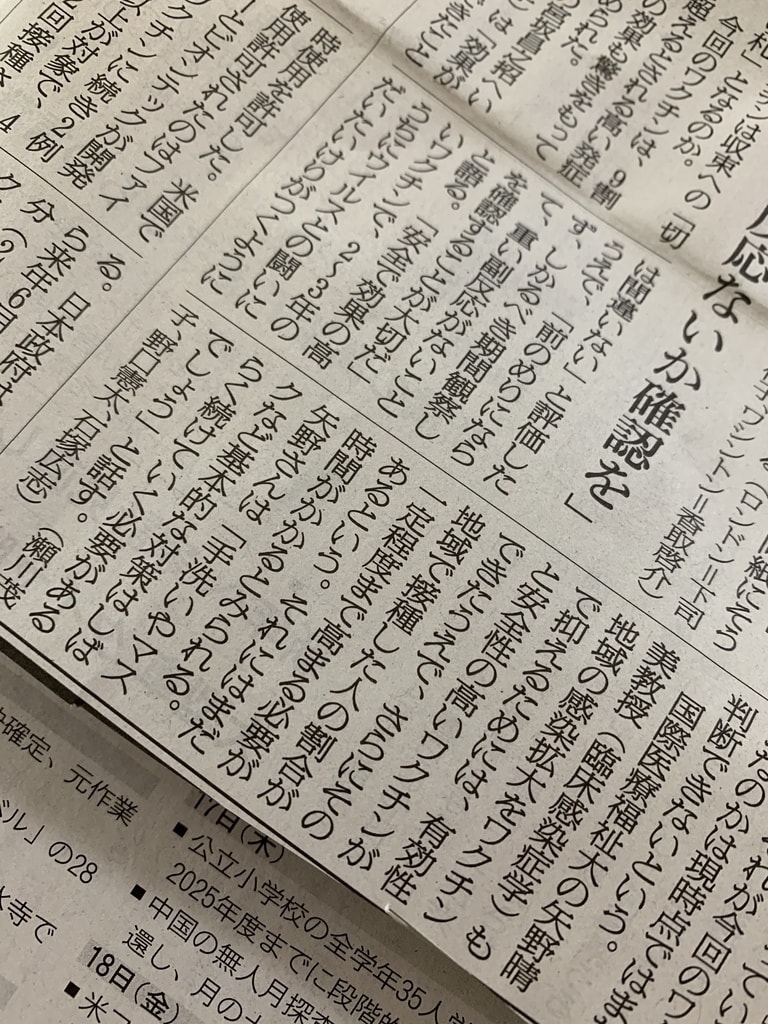本日は、お休みをいただき自宅で休養しております。
”自分のための勉強時間”がなかなかとれない状況で、本日は”自分の時間”にすることを決めていました。
独協医大の志水太郎先生の話題の”フィジカル・エポニム”
医学の歴史と臨床現場の身体診察の精緻なスキルが融合した大変、興味深い
特集です。これを読んでいます。
身体診察は、私自身、トレーニングが不十分な神経診察の部分などまだまだ
強くしたい部分があります。Babinskiの項、Frank 徴候の項、など
興味のある部分を読みました。
そして、take home messageは、
身体診察の根幹・真髄の " Fixed HER"
沖縄県立中部病院の成田雅先生の圧巻の一項。
("Fixed HER"の私の実践)
1. ルーティンで、順序を決めて、もれなく診察すること
呼吸数を数えること、瞳孔を見ること、対光反射も確認すること
2. 医療面接から、陽性・陰性所見を想定した診察
特に、Janeway lesion, Osler's node, 人工物の挿入部位
3. しっかり曝露して、所見をくまなく探すこと
例 高齢者やリスクのある患者の末梢パルスの確認
高齢者やリスクのある患者の頸動脈の雑音の確認
糖尿病患者の両側の足と足指の間の診察
入院患者の褥瘡の有無の観察
腋窩や陰部も、探す(ツツガムシの刺し口など)
4. 身体診察を毎日、繰り返すこと
日々の変化・変化の有無を、確実にカルテに記載すること
米国で総合内科のレジデントのころ、ICUに入院中の薬物中毒で、右心系の感染性心内膜炎の20代女性の心雑音が、前日と大きく異なり大きくなって、MRを併発した日の診察は今でも鮮明に覚えています。
冒頭の症例もとても示唆に富み、勉強になりました。教育効果の面では、この症例部分、NEJMのMGH Case recordに匹敵する学習価値があります!
若手の方には、日本語と英語と両方で、良質な教材・情報源を選び、効果的に学習していただきたいと思います。
自分自身も、生涯教育として、弱い部分を補強しつつ、楽しみながら勉強していきたいです。
最後に、実は、幸いにも、この総合診療11月号(2020)の"フィジカルエポニム” とともに、私の女性医師としてのキャリアのエッセイも記載されております。
"我、bacterium(杖)とならん”も掲載されており、そのご縁と幸運に感謝しております!
日本の近代医学の父 感染症学の世界的な大家である北里柴三郎の言葉、
"国家の杖 Bacteriumとならん”を目標に、今後もキャリア展開したいと
考えております。
ぜひ、読んでみてください。