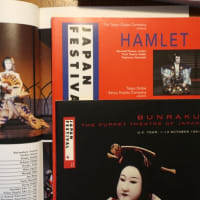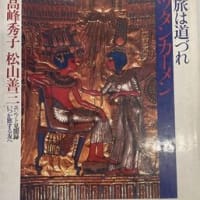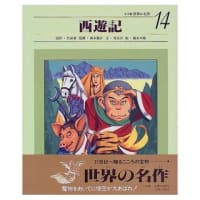円覚寺では、11月3日から5日まで、宝物風入(円覚寺が所蔵する宝物の虫干しを
兼ねた展示会)を開催、と言うことで、広い大方丈が、宝物風入(特別展示会)会場となっていて、沢山の宝物が展示されている。
その風入期間中に、普段は、一般開放していない、鎌倉で唯一の国宝建築である舎利殿が特別公開されると言うことで、楽しみに出かけた。
円覚寺には、何度も訪れているのだが、いつも、門の外から、遠く、舎利殿の屋根を望むだけだったので、今回は、舎利殿の直近までアプローチできると言うことであるから、千載一遇のチャンスである。



この建物には、源実朝公が宋の能仁寺から請来した「佛牙舎利」というお釈迦様の歯が祀られていることから「舎利殿」と呼ばれる。
13世紀に建てられた当初の舎利殿は焼失して、1573年に、北条氏康によって西御門にあった尼寺太平寺の仏殿が移築されたと言うことで、日本最古の唐様(禅宗様)建築物である。
サワラ木葺の屋根の勾配や軒の反りの美しさが特徴で、特に屋根の軒下から出ている上の段の垂木は、扇子の骨のように広がっており、「扇垂木」とよばれ、これが屋根を一層大きく、建物全体を小さいながらも壮大に見せている。と言うのだが、尼寺であった所為もあろう、実に優雅で美しいのである。
興味深いのは弓欄間で、火焔欄間とも言われるようだが、この欄間が、空調の機能を果たしているようで、この空間を通して入る日の光が独特の雰囲気をかもし出していると言うから美意識も大したものである。
弓欄間の中央にある、シンプルな宝珠形の飾りが面白い。
また、江戸時代の花頭窓は下部が広がっていくのに対し、この舎利殿の外枠は縦の線が真っ直ぐで、その質素な形は鎌倉時代後期の花頭窓の特徴だと言う。






正面の扉が開いているので、中が暗いのだけれど、微かに厨子と仏像が見える。
肉眼では定かではないのだが、露光を調節して望遠で撮って見ると、かなり、はっきりと見える。
仏舎利を安置した厨子を真中にして、その左右には地蔵菩薩像と観音菩薩像が立っているのが、良く分かる。




ところで、舎利殿の正面に立つと、舎利殿の歴史や建物の特徴など、テープで流されているので、小一時間もいたので、非常に勉強になった。
当日は、昨夜のNHKニュースを聞いた所為か、結構拝観者が沢山来ていて、混雑していたが、ほんの束の間、建物の前の人影が途切れる瞬間があるので、それを待って写真を撮ったので、この掲載写真には、人が写っていない。
普通、舎利殿が公開されていない時には、この写真の唐門しか見えないので、これが舎利殿のような錯覚を覚えるのだが、舎利殿は、その後ろの建物なのである。
また、気付かなかったのだが、舎利殿の左肩の山側は、切り立った崖になっている。


兼ねた展示会)を開催、と言うことで、広い大方丈が、宝物風入(特別展示会)会場となっていて、沢山の宝物が展示されている。
その風入期間中に、普段は、一般開放していない、鎌倉で唯一の国宝建築である舎利殿が特別公開されると言うことで、楽しみに出かけた。
円覚寺には、何度も訪れているのだが、いつも、門の外から、遠く、舎利殿の屋根を望むだけだったので、今回は、舎利殿の直近までアプローチできると言うことであるから、千載一遇のチャンスである。



この建物には、源実朝公が宋の能仁寺から請来した「佛牙舎利」というお釈迦様の歯が祀られていることから「舎利殿」と呼ばれる。
13世紀に建てられた当初の舎利殿は焼失して、1573年に、北条氏康によって西御門にあった尼寺太平寺の仏殿が移築されたと言うことで、日本最古の唐様(禅宗様)建築物である。
サワラ木葺の屋根の勾配や軒の反りの美しさが特徴で、特に屋根の軒下から出ている上の段の垂木は、扇子の骨のように広がっており、「扇垂木」とよばれ、これが屋根を一層大きく、建物全体を小さいながらも壮大に見せている。と言うのだが、尼寺であった所為もあろう、実に優雅で美しいのである。
興味深いのは弓欄間で、火焔欄間とも言われるようだが、この欄間が、空調の機能を果たしているようで、この空間を通して入る日の光が独特の雰囲気をかもし出していると言うから美意識も大したものである。
弓欄間の中央にある、シンプルな宝珠形の飾りが面白い。
また、江戸時代の花頭窓は下部が広がっていくのに対し、この舎利殿の外枠は縦の線が真っ直ぐで、その質素な形は鎌倉時代後期の花頭窓の特徴だと言う。






正面の扉が開いているので、中が暗いのだけれど、微かに厨子と仏像が見える。
肉眼では定かではないのだが、露光を調節して望遠で撮って見ると、かなり、はっきりと見える。
仏舎利を安置した厨子を真中にして、その左右には地蔵菩薩像と観音菩薩像が立っているのが、良く分かる。




ところで、舎利殿の正面に立つと、舎利殿の歴史や建物の特徴など、テープで流されているので、小一時間もいたので、非常に勉強になった。
当日は、昨夜のNHKニュースを聞いた所為か、結構拝観者が沢山来ていて、混雑していたが、ほんの束の間、建物の前の人影が途切れる瞬間があるので、それを待って写真を撮ったので、この掲載写真には、人が写っていない。
普通、舎利殿が公開されていない時には、この写真の唐門しか見えないので、これが舎利殿のような錯覚を覚えるのだが、舎利殿は、その後ろの建物なのである。
また、気付かなかったのだが、舎利殿の左肩の山側は、切り立った崖になっている。