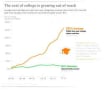”世界はフラットか?コークの味は国ごとに違うべきか?”
前回は、ITC革命とグローバリゼーションの拡大によって、これまで一般的に考えられていた、ロストウなどの段階的な経済発展論が、必ずしも通用しなくなったことを論じてきた。
新興国経済が、成長段階過程をショートカットして、一気にグローバル経済に台頭し、インドのIT産業のように最高水準のサービス経済への高度化によって国家経済の成長を加速させ、企業にしても新興国のBOPビジネスが国際事業となり、リバース・イノベーション製品が国際商品となり、あるいは、個人のデザインした製品がインターネットで世界を駆け巡ると言った、本来、先進国経済から波及してきた筈の経済活動が逆流すると言う、下克上とも言うべき時代になって来たことを述べてきた。
さて、世界はフラット化したとフリードマンが宣言するまでもなく、ICT革命とグローバリゼーションの恩恵を受けて、時空を超えて、あらゆるところで、グローバル・ベースでビジネスが展開されている。
ところが、現実の世界は、特に、ビジネスの世界では、決してフラットではないと説く専門書が出ている。バンカジ・ゲマワットの「コークの味は国ごとに違うべきか REDEFINING GLOBAL STRATEGY」であり、デビッド・スミックの「世界はカーブしている THE WORLD IS CURVED」などだが、ゲマワット教授の「セミ・グローバリゼーション」論が、非常に現実的で興味深い。
ハーバード・ビジネス・スクールのゲマワット教授は、海外直接投資のフローが世界の固定資本形成に占める割合を手始めに、色々な視点から国際化のデータを調査して、国際化・グローバル化の進展が10%前後ないしそれ以下に過ぎないことを検証して、グローバリゼーションはまだ道半ばであるとして、「セミ・グローバリゼーション」と捉えて議論を展開している。
この書物の目的は、グローバル・ビジネスに対する企業戦略論であるから、この視点に立って、市場の規模やボーダーレスな世界の錯覚に惑わされずに、国境をうまく越えたいと思うのなら、経営者は、戦略の策定や評価に当たって、国ごとに根強く残る差異を真剣に受け取るべきだとして、国境を越えるための洞察力やツールを提供すべく、その戦略論を説いている。
世界を理想化された単一の市場として見るのではなく、国ごとの差異に着目して、企業のグローバル戦略を説いているのだが、そのような観点から、グローバル企業、多国籍企業と言った国境を越えた企業の成功や失敗を見ると、見えなかった戦略の功罪が浮き彫りになってくるから面白い。
たとえば、ウォルマートやカルフールが日本市場に馴染めず苦労したのも、日本の家電メーカーなどが、新興国や発展途上国への参入で苦心惨憺しているのも、文化文明、発展段階、国民性などの差異を戦略に上手く取り込めなかった結果と言うことであろうか。
世界はフラット化したと言うグローバリゼーション津波論の台頭で、国際的な標準化と規模の拡大を重視しすぎた、国際統合が完成した市場を想定した行き過ぎた企業戦略論が、幅を利かせ始めていることに対して、国ごとの類似性と同時に、差異が如何に企業戦略の可否に大きな影響を与えているかを示しながら、
セミ・グローバリゼーションの現実においては、少なくとも、短・中期的には、国ごとの類似点と差異の両方を考慮した戦略こそが、より効果的なクロスボーダー戦略だと説いている。
フリードマンも、多くの異論に応えて、「厳密に言えば、世界はフラットではない。しかし、丸くもない。フラットと言う単純な概念を使ったのは、これまでになく平等な力を持った人々が、接続し、遊び、結びつき、協力し合うことが出来るようになった、と言いたかったからだ。」と述べているのだが、この単純なフラットと言う表現で、世界の政治経済社会、と言うよりも、文化文明の軌道軸の大転換とも言うべき現象を悟らせた貢献は、極めて大きいと思っている。
現実には、ゲマワット教授の説くように、コークの味は、国ごとに違うべきだと言う「セミ・グローバリゼーション」の段階にあることは、事実であろう。
問題は、そのコークの味を、どのようにして、国ごとに違わせるべきか、その手段、方法、そして、その戦略戦術が、資本主義の大変質によって、大きく変わってしまったと言うことである。
大変革を遂げた市場経済に対応すべく、人類の未来を見据えて、企業は、どのようなグローバル・ビジネスを展開すべきか、考えてみることにしたい。
前回は、ITC革命とグローバリゼーションの拡大によって、これまで一般的に考えられていた、ロストウなどの段階的な経済発展論が、必ずしも通用しなくなったことを論じてきた。
新興国経済が、成長段階過程をショートカットして、一気にグローバル経済に台頭し、インドのIT産業のように最高水準のサービス経済への高度化によって国家経済の成長を加速させ、企業にしても新興国のBOPビジネスが国際事業となり、リバース・イノベーション製品が国際商品となり、あるいは、個人のデザインした製品がインターネットで世界を駆け巡ると言った、本来、先進国経済から波及してきた筈の経済活動が逆流すると言う、下克上とも言うべき時代になって来たことを述べてきた。
さて、世界はフラット化したとフリードマンが宣言するまでもなく、ICT革命とグローバリゼーションの恩恵を受けて、時空を超えて、あらゆるところで、グローバル・ベースでビジネスが展開されている。
ところが、現実の世界は、特に、ビジネスの世界では、決してフラットではないと説く専門書が出ている。バンカジ・ゲマワットの「コークの味は国ごとに違うべきか REDEFINING GLOBAL STRATEGY」であり、デビッド・スミックの「世界はカーブしている THE WORLD IS CURVED」などだが、ゲマワット教授の「セミ・グローバリゼーション」論が、非常に現実的で興味深い。
ハーバード・ビジネス・スクールのゲマワット教授は、海外直接投資のフローが世界の固定資本形成に占める割合を手始めに、色々な視点から国際化のデータを調査して、国際化・グローバル化の進展が10%前後ないしそれ以下に過ぎないことを検証して、グローバリゼーションはまだ道半ばであるとして、「セミ・グローバリゼーション」と捉えて議論を展開している。
この書物の目的は、グローバル・ビジネスに対する企業戦略論であるから、この視点に立って、市場の規模やボーダーレスな世界の錯覚に惑わされずに、国境をうまく越えたいと思うのなら、経営者は、戦略の策定や評価に当たって、国ごとに根強く残る差異を真剣に受け取るべきだとして、国境を越えるための洞察力やツールを提供すべく、その戦略論を説いている。
世界を理想化された単一の市場として見るのではなく、国ごとの差異に着目して、企業のグローバル戦略を説いているのだが、そのような観点から、グローバル企業、多国籍企業と言った国境を越えた企業の成功や失敗を見ると、見えなかった戦略の功罪が浮き彫りになってくるから面白い。
たとえば、ウォルマートやカルフールが日本市場に馴染めず苦労したのも、日本の家電メーカーなどが、新興国や発展途上国への参入で苦心惨憺しているのも、文化文明、発展段階、国民性などの差異を戦略に上手く取り込めなかった結果と言うことであろうか。
世界はフラット化したと言うグローバリゼーション津波論の台頭で、国際的な標準化と規模の拡大を重視しすぎた、国際統合が完成した市場を想定した行き過ぎた企業戦略論が、幅を利かせ始めていることに対して、国ごとの類似性と同時に、差異が如何に企業戦略の可否に大きな影響を与えているかを示しながら、
セミ・グローバリゼーションの現実においては、少なくとも、短・中期的には、国ごとの類似点と差異の両方を考慮した戦略こそが、より効果的なクロスボーダー戦略だと説いている。
フリードマンも、多くの異論に応えて、「厳密に言えば、世界はフラットではない。しかし、丸くもない。フラットと言う単純な概念を使ったのは、これまでになく平等な力を持った人々が、接続し、遊び、結びつき、協力し合うことが出来るようになった、と言いたかったからだ。」と述べているのだが、この単純なフラットと言う表現で、世界の政治経済社会、と言うよりも、文化文明の軌道軸の大転換とも言うべき現象を悟らせた貢献は、極めて大きいと思っている。
現実には、ゲマワット教授の説くように、コークの味は、国ごとに違うべきだと言う「セミ・グローバリゼーション」の段階にあることは、事実であろう。
問題は、そのコークの味を、どのようにして、国ごとに違わせるべきか、その手段、方法、そして、その戦略戦術が、資本主義の大変質によって、大きく変わってしまったと言うことである。
大変革を遂げた市場経済に対応すべく、人類の未来を見据えて、企業は、どのようなグローバル・ビジネスを展開すべきか、考えてみることにしたい。