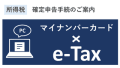インタネットを叩いていたら、ダイヤモンド・オンラインのびーやま氏の「「高学歴と低学歴の思考の差」。学歴社会だからこそ身に付く「本当の頭の良さ」とは。」と言う記事が目についた。
何となく読んでみて、自分の考えに近いのに気づいた。
著書『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』に詳しいようだが、勉強の意義と、大学受験勉強の重要性を強調していることである。
まず、高学歴な人と低学歴な人には「思考の差」がある。と言う。
大学受験の勉強はとてもむずかしく、難関大学の問題に関しては解説を読んでも理解できないなんてことが多々あり、それを複数科目やるのが大学受験。そんな過酷な大学受験を乗り切り、合格を勝ち取るためには正しい思考力が必要となり、その思考力とは「考える」「調べる」「自分の中に落とし込む」の3ステップからできている。
要するに、目の前の問題について考えて、解けなかったら「どこができないのか」調べて、次は解けるように自分の中に落とし込むのが大学受験での思考力で、そうすることで、自然と知識は増えていき、思考力も磨かれていき、その意味で、高学歴の人は本当の意味で考える力を持っている。
低学歴の人はそうではない 。勉強から逃げて低学歴になった人は、思考の3ステップが第1段階の「考える」だけで終わってしまって、そのあとに続く「調べる」と「自分の中に落とし込む」という段階がないため、いつまで経っても知識が増えず、視野が広がっていかないので、高学歴の人に比べて思考力は劣る。
なぜ「受験勉強」が社会でも役立つのか。
「考える」「調べる」「自分の中に落とし込む」の3ステップは普遍的な思考力であり、社会に出てからもこの思考力を駆使すれば、仕事の効率は上がるはずだし、答えのない課題にも挑める。その意味では、大学受験の勉強は社会にしっかりと繋がっている。
「大学受験はそのときだけのものだから意味がない」と言う大人がいるが、もし本当にそうなのだったら、なぜ大企業や政治家、官僚は高学歴で占められているのであろうか。説明がつかないはずである。
受験生にはぜひ、大学受験を通してこういった本物の思考力も磨いていってほしい。しかもそれは特別意識せずとも、勉強を頑張りさえすれば自動的に手に入るものであるから、まずは目の前のことに集中すればいいだけである。 少しでも多くの学生が受験を通して考える力を磨いていくことを願っている。
以上が、この記事のびーやまの見解である。
一寸、表現には多少問題なしとはしないが、ほぼ同感である。
大学の受験勉強に関しては、京大の経済学部であったので、私の受験科目は、英語、国語、数学は数1、数2、幾何、社会は世界史と地理、理科は化学と生物、と多岐にわたっていてウエイトも同点であったので、全科目とも手を抜かずに勉強せざるを得なかった。
これらは高校の授業で勉強してはいたが、受験勉強では更なる知識の深堀であり、特に、基本の英数国以外に、社会や理科の勉強で積み重ねた知識が以降大変に役立った。視野の拡大と思考力の深化であり、海外に出てから特に生きてきた。
この受験科目の多い受験勉強が、リベラルアーツの涵養に大きく貢献した意義は大きいと思っている。特に、旧帝大の大学生の教養水準の底上げ効果である。
更に、世界屈指のアメリカのビジネススクールのMBAを取得しているので、この受験勉強も大いに役に立っている。
しかし、びーまるは言及していなかったが、これらの受験勉強による貢献よりも、更に、重要なのは、
最後の6年間の最高学府で学び研鑽した多くの貴重な学問とその学び舎で経験した知的環境の凄さ素晴らしさであって、いくら強調してもし過ぎることはなく、特筆に値する。
尤も、これらの学問経験が、私の人生に益したかどうか分からない。
しかし、真善美を追求して、あっちこっちを駆け回り、勉強をし続けてきた。紆余曲折、大変な苦難の連続ではあったが、長い人生、やっと、見るべきものは見た、と言う心境まで、人生を歩んで来ることができた。と言う自負だけは感じている。