早い所でスキー場オープン、先週木曜(12月8日)札幌国際スキー場のシニアデイに、近場の手稲ハイランドもオープンしていますがシニア向け2時間券が今年は値上がりして3,400円(加森観光さんは観光客シフト?)、今年は1時間半ほどかけても・・・。
真駒内のスケートリンクは今年もクローズ、この3年改修の検討中!(改修する気なし)、スケート少年団は週一かで帯広まで?(事故なければいいのですが)、当然2030年札幌冬季オリパラのスピードは帯広か長野、今の大倉山のシャンツェも鉄骨むき出しの仮設コース?。
それでも札幌の名前冠して?、ある人が言っていました、「兎も角お金が動かないことにはお金を抜けない!」と、IOC、JOC、各業者さん、皆さん優雅な生活が懸かってる?
先週スキーの話、シニアデイ一日券2,000円、一時間半の運転も年金生活者の稼ぎのうち?(ガソリン代が・・)、でも事故ったら・・、で、慎重運転で。
積雪は充分、これで青空あれば・・・。

もう観光客も入ってます 香港からのシニア、スキー場を見に来た?
香港からのシニア、スキー場を見に来た?
コース点描
ゴンドラの中で中国語が耳に、若者3人組、で「nimen shi zhongguoren ma?」「はい!中国人です」「cong nali」「彼女は広東、私はハルピンです、中国語お上手ですね、私達は留学生です」
私は中国語、彼らは日本語、これコミニケーション???。
今シーズン初め、もう後期高齢、まずは感覚慣らし、6本2時間半休みなく滑ってそろそろ限界?もう一本を止めて!
お昼、温泉我慢で2時過ぎには帰宅!まずは初滑り無事終了でした!
12月2日10:40 いつものウオーキング、柔軟体操をしていると通りかかった人が何やら、何言ってるのかと振り返ると犬が???、いやキツネです。

街中、マンションタウンの中から、人なれしています、エヒノコックスという寄生虫病の宿主、札幌もクマといい野生動物との境界があいまいになってきたのかも(野生動物が人慣れしてきた!)
さてお隣中国の今日この頃
中国共産党統治下ではしばしば"無かった事に!"があります、そう都合の悪いことはノーコメントでなく事実そのものを消してしまう!。
6・4事件、新幹線車両の落下事故、地方の騒乱等々。
そこで今回習近平のゼロコロナ政策!上海をはじめとする都市のロックダウンや行動制限、ある日を境に無かった事にしてしまうようです、皇帝は誤りを犯さない!面子が!そこで無かった事にすればいいのです、そこをほじれば社会不安を人民扇動での罪で隔離するのです。
何千、何百万人のPCR検査、絶対まとめてやってると思っていましたが、やはり!中国共産党らしい!!
そう1000人の検体をまとめて検査で絞り込むとすると一人の陽性者には31回の検査?でたどり着きます、ただしその為に陽性者のグループに入った人は最高4回PCR検査に駆り出されます。中国共産党でなければ出来ないことですが。
中国の人達は解っています、逃げ出すことはできない、あとは各自政策あれば対策ありで。でもなんだかマグマが動き始めてるような。
こういった時我が国は相手にならないで細心の注意をもって、もちろん中国の人達と中国共産党はかように別です。
コラムを
ダイヤモンドオンライン 2022.11.13 4:50 ふるまいよしこ:フリーランスライター ふるまいよしこ「マスコミでは読めない中国事情」
中国ゼロコロナ政策は「成功」だから終わらない…iPhone工場大脱走、消毒液漬けの自宅
 中国・上海の封鎖された道路 Photo:Jackal Pan/gettyimages
中国・上海の封鎖された道路 Photo:Jackal Pan/gettyimages
党大会から1カ月たっても、中国の強硬なゼロコロナ政策はまったく終わる気配がない。隔離施設から戻った女性が自殺、iPhone工場からの集団大脱走、いつまでたっても自宅に帰れない――メディアが沈黙する中で、突発的に起きた事件だけが目撃者によってネットを通して広がるという事態が続いている。「党大会までは締め付けが厳しくても仕方ない」と我慢していた人たちからも不満の声が上がっている。(フリーライター ふるまいよしこ)
新体制のナンバー2・李強は、上海ロックダウンを主導した人物
中国共産党の第20次全国代表大会(以下、党大会)から約1カ月。前回の記事でお伝えした胡錦濤・前総書記の「強制退場」という前代未聞の事態の謎も明らかにならないまま、李強・上海市党委員会書記が、習近平に次ぐ党のナンバー2につくという数段階特進もいまだに大きな驚愕(きょうがく)をもって語られ続けている。
政治局員にはなるだろうという予想はあったものの、よもや、今春の上海ロックダウンを主導した人物が堂々と習の真横に並ぶとは、ほとんどの人が思ってもいなかった。中国最大の経済都市上海のロックダウンの惨状を思い起こし、人びとの思いはかなり複雑である。
東西の中国ウオッチャーたちは口々に、今回の政治局人事は徹底的に「習近平への忠誠」を柱にしたものだと分析している。つまり、あの国内外に衝撃と大混乱と全国的な経済不況をもたらしたロックダウンは、「習への忠誠」の証しだと見なされた、ということである。
あれほど大規模で常識はずれなロックダウンを敢行した裏には、上海市政府幹部の判断のみならず、習を中心とした中国中央政府の強い意志があった。そう考えると、こうした後先を考えない強硬手段に出ることが、習家軍(「習家の軍隊」の意味。転じて、習近平のもとに集まった腹心たちを指す)の姿勢であることは間違いないだろう。だが、今後もそれが礼賛されるならば、そのリスクはかなり大きなものになる。
経済や金融の基本的な知識を持たない最高幹部が国を動かしている
「今の最高指導者たちは経済や金融に対する基本的な知識を持たないまま、さまざまなことをやっている。彼らはそれとはまったく別の独自のイデオロギーによってそれらを動かしている」
中国出身で米国在住の経済学者の許成鋼氏は、「ニューヨーク・タイムズ 中国語版」の袁莉・編集長の問いかけにこう答えている。今の政府トップは経済の理論どころか、その成り立ちすらも理解しておらず、一方で政治的な目的に問題をすり替えて政策を行っていると述べ、「コロナゼロ化」についてもまったく同じであり、「彼らは伝染病について理解しておらず、mRNAワクチンについても何も知らず、一連の基礎的な理解ができていない」と指摘した。
その結果、「感染症や感染防止の視点からすると完全に間違ったやり方でも、彼らの政治的観点で物事が決められている」と、聞く者にとって恐ろしい事象にも触れていた(同インタビューは著作権者の許可を得て、筆者のnoteで無料全文公開中)。
上海ロックダウンは「成功例」だった?
そんな「伝染病のなんたるか」も理解していない党指導層が進めた上海ロックダウンは、政治的には「成功例」とされてしまった。この国で最も現代的な生活を送ってきた2000万人が2カ月間も自宅に閉じ込められて、文字通りの飢餓にまで直面したあの惨状を、「成果」と評価しているのだ。あのロックダウンで塗炭の苦しみを舐めた人たちにとって、これほど恐ろしい話はない。
だが、政府が上海を「成功例」としたことで、各地はそれをお手本に「コロナゼロ化」政策を進めている。さらに恐ろしいことに、それが常態化するにつれて、メディアが堂々とそれを「異常事態」として取り上げることが難しくなった。だが、その生々しい失敗は突然起こる悲惨な事件で衝撃的に伝えられるようになった。
隔離施設から自宅に戻った女性が飛び降り自殺
例えば今の中国では、感染者のみならず、濃厚接触や通常の接触が疑われる人たちまでも強制隔離されることになっている。そうした人たちが暮らす集合住宅では、全住民を「接触者」とみなし、アパートの入り口を鉄板や鉄柵で塞ぎ、一切の出入りができなくされてしまうのだ。
今月5日、内蒙古自治区の中心都市フフホトで、隔離施設からそんなアパートに帰宅した女性が自宅中にまかれた消毒液によって家の中がめちゃくちゃになっているのを目にして衝撃を受け、窓から飛び降りるという事件が起きた。それに気づいた娘はすぐに階下に駆け下りたが、はんだ付けされた鉄板にさえぎられ、飛び降りた母の元にたどり着けない。救急車が到着するまでの約1時間、彼女が鉄板をたたきながら泣き叫ぶ声だけが団地内に響き渡った。
さらに団地の管理者は横たわる遺体を住民の目にさらすまいと街灯を切ってしまい、周囲は真っ暗に。娘の金切り声に同情を禁じえない住民たちは自宅の部屋の電灯をあかあかとつけて、スマホの光で遺体を照らし続けたという。
また、甘粛省蘭州では、ロックダウンが行われている中、一酸化炭素中毒になった3歳の子どもが救急車を待つ間に亡くなるという事件があった。救急車が到着するまで1時間近くも待たされ続けた父親と近所の人が団地管理者を拝み倒し、やっと団地の外に出てタクシーで病院に運び込んだが、すでに子どもは事切れていたという。ネットにはこの事件を受けて、「3歳……この子の一生はコロナとともに始まり、コロナの間に終わってしまった」というつぶやきが流れ、それを多くの人たちが怒りとともにシェアしていた。
iPhone生産工場から工員が集団大脱走
河南省鄭州市では先月、20万人余りを雇用してiPhoneの生産を請け負っている工場内で感染事例が発生した。作業に出てくる同僚が日に日に減っていくのを目のあたりにした工員たちの間で恐慌が巻き起こり、手持ちの荷物だけをまとめて工場から脱出し、徒歩で数百キロ先の故郷を目指すという事態に発展した。
鄭州市全体がコロナ措置でロックダウンされていたため、彼らは公共交通機関を使うことができなかった。そのため工場からあふれ出た大量の人たちは農地を横切り、高速道路の脇を歩き続けるという異様な姿がメディアでも大きく取り上げられた。だが鄭州市としては、河南省の輸出額の80%を握るこの工場を罰することもできず、記者会見を開いた鄭州市の衛生担当局は善処を約束するしかできなかった。だが、その会見で担当者の1人が、「コロナ対策でクタクタ。娘の成人のお祝いにも出られなかった」と声を詰まらせたことが、これまた大非難を巻き起こした。
この記者会見ではさらに、出席した感染症専門家が「BMWを運転するウイルスを、我々はトラクターで追いかけている状態だ」と述べて、「我々のスピードは、まったくウイルスに追いつけず、感染制御が難しい」と、「コロナゼロ化」政策への弱気ともとれる発言をしていたことも話題になった。
新規感染者がいないエリアから、感染者が増える北京に戻るためになぜ隔離?
トラクターではBMWに追いつけなくても、中国が世界に誇る、世界最速の時速200キロで走る高速鉄道ではどうだろう?筆者はネットでこんな書き込みを目にした。
ある北京在住の80代の老夫婦が、夫の出張に合わせて浙江省湖州市に滞在した。2人は同じ日にともに自宅から同じルートで高速鉄道を利用して移動。夫人は「時が時だから」と出発前から毎日湖州市の感染事情をチェックし続け、同市内では感染者は報告されないまま、北京に戻る日が近づいた。
帰りの高速鉄道のチケットを予約しようとした時、北京市が運営する、スマホの健康コードに、ポップアップメッセージが出現した。
「あなたは、感染事例が疑われる地域に滞在した可能性があります。当局が要求する衛生基準を満たすため、現在地で7日間の隔離を行ってから陰性証明を取ってください」
だが、2人は湖州滞在中、注意深く体温を測り続け、体調不良や発熱の兆候もない。前述のとおり、湖州市ではこのところ感染者の報告はゼロ。一方、彼らが帰ろうとしている北京市では連日数十人の新規感染者が出ている。「感染リスクが低いところから高いところへ戻るのに、なぜ隔離が必要なの?」と夫人は不満を抱いた。
また不思議なことに、ずっと行動をともにしていたのに、妻の方には前述のポップアップが現れるが、夫の健康コードは正常を示す緑コードのまま。しかしそれでも、夫婦ともに北京に戻るための高速鉄道チケットを購入できない状態が続いたという。
北京から市外に出た人たちが自宅へ戻れない
北京の衛生担当局の問い合わせ窓口に電話をしても、味気ないAIの決まりきった応答が続くばかりで、いつまでたっても係員にはつながらない。80代にとってこんなやり取りはどれほど大変だっただろうと想像したが、夫人のこんな書き込みに思わず笑ってしまった。
「AIが対応しますって胸を張るけど、その応答も提案してくる選択肢もお決まりのものを繰り返すばかり。人間を見習ってもっと気の利いた対応ができるようになるにはまだまだね」
この期に及んでこの余裕。さすが80代で「出張」に出かけるだけのパワーのあるご夫婦である。
だが結局、「7日間の自己隔離とはいつから数えるのか?到着した日から?それとも帰る準備を始めた日から?」「湖州より北京のほうが感染はひどいのに、なぜ北京の自宅に帰れないのか?」……そんな二人の疑問は解決されないままだ、と書き込みでは訴えていた。
この例以外にも、北京から市外に出た人たちが「自宅に戻れない」というケースがますます増えている。
5日から上海で開かれている中国国際輸入博覧会に北京から取材に行った記者たちの間でも、帰京しようとしたら健康コードのポップアップに阻まれてチケットが買えないと騒ぎが起きていた。SNSを使って必死に同博覧会の主催者に「対応してほしい」と頼み込む政府系メディア関係者のやりとりをキャプチャしてシェアした友人がこうつぶやいていた。
「お前ら、国の宣伝機関なんだから、寄ってたかってペンの力を使えばどうにかできるはずだろ?」
ネットの書き込みはすぐに消される
こうした「出張に出たまま北京に帰れない」という悲痛な叫びは、ネットに上がっても次々に消されている。人によっては帰宅予定日から2カ月以上北京に戻れないという人もいるらしい。先月の今頃なら「党大会前でセキュリティーが厳しくなっている」と理解できていた人たちも、党大会が終わり、季節が秋から冬に変わったのになぜ帰れないのか分からないままだ。
上海のロックダウンという「成功例」以降、当局はすでにむやみやたらに市民の行動をコントロールし始めるようになった。なぜそうなるのか、どうしてこうなるのか、どうすればそれを回避できるのか……誰に問いかけても、誰一人その理屈を答えてくれないのである。
「コロナ対策が始まって3年目。1年目は恐怖、2年目は無頓着、そして3年目は疲れと怒り。一体いつになったら家に帰れるんだ」というSNSの書きこみは、もちろんすでにネットから削除されてしまった。
ダイヤモンドオンライン 2022.12.10 3:25 加藤嘉一:国際コラムニスト ライフ・社会嫌われる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教え
日本発の自己啓発書が示す、権力に抗議する中国民衆の「勇気」とは?
中国ではいま、「ゼロコロナ」政策へのデモ活動が拡大し、政府に対する憤りの声が各地で噴出している。厳しい言論統制が敷かれている同国で、民衆はいかにして勇気を奮い立たせて行動を起こしたのか。中国で約300万部、そして世界累計で1000万部を突破した、大ベストセラーシリーズ『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』の2冊を手がかりに、国際コラムニスト・加藤嘉一氏がその背景を探る。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
沈黙を破り、立ち上がった中国の民衆
いま、中国国内では、市民による、お上に対する抗議活動が行われている。お上は習近平総書記率いる中国共産党を指し、抗議の引き金は「ゼロコロナ」策である。
1984年静岡県生まれ。2003年高校卒業後、単身で北京大学留学。同大学国際関係学院大学院修士課程修了。英フィナンシャルタイムズ中国語版コラムニスト、復旦大学新聞学院講座学者、慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)、ハーバード大学ケネディ・スクール(公共政策大学院)フェロー、ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院客員研究員、香港大学アジアグローバル研究所兼任准教授などを歴任。著書に『われ日本海の橋とならん』『中国民主化研究:紅い皇帝・習近平が2021年に描く夢』『リバランス:米中衝突に日本はどう対するか』(いずれもダイヤモンド社)など。
11月24日夜、新疆ウイグル自治区ウルムチ市にある高層マンションで火災が発生し、少なくとも10人が亡くなった。地元政府による都市封鎖措置が、火災からの救出を妨げた、もしくは少なくとも遅らせたために、助かる生命が助からなかったとの声が上がっていた。
ウルムチで亡くなった市民を哀悼するための集会が、上海や北京など全国各地に広がった。大学生も立ち上がった。「習近平は退陣せよ」「PCR検査じゃなくて自由をよこせ」といった掛け声のもと、白い紙を掲げてお上に対する不満を表明した。
厳しい言論統制が敷かれるなか、自分たちには声を発する権利が与えられていない、故に「白紙」を突き付けているのだ。いま自分たちに必要なことは、無批判に我慢し続けることではなく、声を上げることである、と。
そんな光景を眺めながら脳裏をよぎったのが、「勇気」という生き様である。
中国で圧倒的な支持を得た、日本発の自己啓発書とは?
勇気、と言えば、『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』の2冊が思い浮かぶ。私も2回熟読し、生きていくための勇気をもらった。同書は世界40以上の国・地域・言語で翻訳され、シリーズ累計で1000万部以上の部数を誇る。うち、日本では累計約370万部、中国では今年11月時点で300万部近くが売れている。
「不安だから、外に出られない」という原因論に立脚するフロイト心理学とは対照的に、「外に出たくないから、不安という感情を作り出している」という目的論を提唱するアドラー心理学が、日本の読者の間で多くの共感を呼び、勇気を与えた事実は、正直想像に難くない。
幼少期から「人様に迷惑をかけないように」と教育されてきた日本人は、自分がどうありたいかよりも、他人にどう見られるかを気にする。嫌われないためにはどうすべきかを最優先し、行動規範とする傾向が強い。一方、私を含め、多くの国民はそんな生き方に息苦しさを感じてきた。「課題の分離」を通じて、「いま、ここ、わたし」を生きること、「自由とは、他者から嫌われることである」と説くアドラーの教えが心に響く所以であろう。
多くの中国人は「嫌われること」を気にしない
2003年、高校卒業後中国に渡って以来、中国本土、米国、香港などで多くの中国人と時空を共有してきた。中国は多様的であり、地域、性別、世代、民族、職業、生い立ちなどによって、中国人の生き様もまちまちであるが、私なりの「中国人観」に基づいて言えば、『嫌われる勇気』が“あの中国”でベストセラーと化している現実には、若干の違和感を覚える。
というのは、私から見て、小中高生、大学生、都市部の中産階級、農村部の低所得者、海外に移住した富裕層などを含め、「いま、ここ、わたし」を生きることに精一杯な大多数の中国人は「嫌われること」など恐れていない。
チェコのプラハを訪れたことがある。カレル橋を歩いていると、橋上の半分くらいが中国人観光客で埋め尽くされていることに気づいた。中国の存在感について色々考えていると、中高年の女性が、地元の住民に対して、東北訛りの中国語で、ものすごい形相で言い寄っていた。困惑する住民は当然、女性が何を言っているのか、なぜ怒りをあらわにしているのかなど知る由もない。付近を通過する女性の同胞たちも、意に介している様子ではない。
彼らはそこを異国の地だとは見なさない。自分が、中国人が、訪問先でどう思われるか、相手が自分の放っている言葉を聞き取れているかなど気にしない。ただ、そのときそうしたかったから、そうしただけである。中国国内でそうやって生きてきたように。
ある中国人女性の読後感
勇気シリーズを読んだ武漢市出身の女性(40代、国有企業勤務)は言う。「この本は特に日本人が読むべきと思います。日本人は他者に迷惑をかけることを恐れ、他者の目に映る自分をとても気にする。そして、本当の自分を演じようとしない」
一方で、この女性は、勇気シリーズが今を生きる中国人に、自分への向き合い方やこれからの生き方を考える上で、一定の示唆を与えるものであったとも主張する。
「いくつかの概念は従来の考え方を完全に覆すものです。例えば、『過去は存在しない』。一方、アドラー心理学はフロイト心理学などに比べて近づきやすい。『嫌われる勇気』というタイトルには好奇心がくすぐられるし、内容も読み取りやすい。『なぜなのか』ではなく、『どうしたいか』に主眼を置くアドラーの教えも、中国人の生き方に合っていると思います」
文化大革命など激動の時代を生き抜いてきた中国人は、過去がどうあろうと、それにとらわれることなく、これからどう生きたいかだけを考えて、いま、ここで、わたしができることに精一杯取り組んでいるように見受けられる。「大切なことは、何が与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかである」というアドラーの教えにも共感するだろう
アドラーの教えと中国民衆の「勇気」
わたしが、いま、ここを生きられなくなったとき、中国人は何を思うだろうか。
日本人を含めた多くの外国人は、中国という共産党一党支配の社会主義国家は、習近平の3期目入りによってますます独裁化していく、そして、厳しい言論統制下に生きる中国人は、自らが置かれた環境について何も知らないという見方をしている。
一方、インテリジェンスとネットワーキング、言い換えれば、情報力と人脈力に長けた中国人の多くは、自らが置かれた状況を相対的に客観視する資質を備えている。習近平が従来の慣例や前提を破って権力の一極集中と個人崇拝を強化すること、新型コロナウイルスの感染拡大防止という「大義名分」に便乗して監視システムを徹底強化すること、西側の自由や民主主義を真っ向から否定し、唯我独尊の進路を歩むことが、中国という国民国家の将来にどれだけの不都合な真実をもたらすかを、彼らは想像し、そこに困惑する。
習近平の、中国共産党の権力は絶大である。そこに歯向かうことは、少なくとも経済的、社会的、政治的に、「死」を意味する。自分は前途を失い、家族は路頭に迷う。中国人にとって、権力に異を唱え、意見することは、我々が想像するほど容易(たやす)いことではないのだ。
ただ、沈黙は無為を意味しない。現に、ウルムチでの事件が引き金となり、多くの中国人が立ち上がった。勇気を持って。彼らは今こそ奮い立たされるだろう。『嫌われる勇気』に記された「人生における最大の嘘、それは『いま、ここ』を生きないこと」「人生の意味は、あなたが自分自身に与えるものだ」というアドラーの教えに。
絶大な権力を前に、勇気を持てたとしても、一人では立ち上がれない。彼らは共産党を、習近平を恐れているけれども、なめてはいない。幸いなことに、彼らには仲間がいた。ウルムチ、北京、上海……地域、民族を越えて、他者を仲間だと見なし、他者に貢献することで、自分の居場所を見出そうとしている。アドラーが説く「共同体感覚」がそこにはあった。
「所属感」は、自らの手で獲得していくもの
2012年8月、私は10年過ごした北京を離れ、ボストンにいた。米ハーバード大学ケネディ・スクール(公共政策大学院)に遊学するためだ。多くの中国人留学生も学びに来ていた。
雪が降りしきるほど寒くなった冬のある日、3人の中国人とケネディ・スクールにやって来た。そのうちの1人が入り口にある同大学院の「座右の銘」を指さし、「これっていい言葉だよな。そう生きるべきだ」とつぶやいた。私たちは前方に目をやり、無言で頷(うなず)いた。
Ask What You Can Do?
1961年の就任演説で、ジョン・F・ケネディ元大統領が語り掛けた、あの言葉である。
「国があなたのために何をしてくれるのかを問うのではなく、あなたが国のために何を成すことができるのかを問うて欲しい」(My fellow Americans: ask not what your country can do for you -- ask what you can do for your country.)
異国の地で学んだ多くの中国人は、ケネディの残した言葉を見て、感じて、祖国に対して何かを思い、その後の日々を過ごしてきたはずである。
アドラーは、「この人は私に何を与えてくれるのか」ではなく、「私はこの人に何を与えられるか」を考えるべきだと説く。所属感とは、生まれながらに与えられるものではなく、自らの手で獲得していくものなのだと。
不確実な将来に対し、言葉にできない、想像すらできない不安を抱えながらも、いまを、ここを必死に生きる中国人たちは、それぞれの「人生のタスク」に向き合っていくに違いない。
(終わり)
「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」が中国の民衆に与えた影響とは?加藤嘉一(かとう・よしかず)
国際コラムニスト。楽天証券経済研究所客員研究員
YahooNEWS 12/13(火) 19:42配信 FNNプライムオンライン
「“羊”になって6日目」の意味 中国で日本の風邪薬“爆買い”
頑丈な鍵がかけられたドア。 ゼロコロナ政策が緩和された今、中国・北京の飲食店では、新型コロナウイルスの感染拡大を恐れ、営業を一時停止する店が目立つ。 こうした中、中国独自のPCR検査態勢が、さらなる混乱を呼び起こしている。 FNN上海支局・森雅章記者のPCR検査結果を表示する画面には、未明から「再検査」を必要とする趣旨の表示が出ていた。 「陽性」ではなく、「再検査」。 それは、検査のやり方にある。 森記者が受けた検査は、森記者を含む10人分の検体を1本の試験管にまとめた形で行われた。 中国では、こうした複数の検体を、1つの試験管で調べるのが一般的。 そして、この試験管からウイルスが検出されると、全員がいわばグレーの状態となる。 ここからさらに1人ずつ検査を受け、陰性が証明されるまでの間、自宅待機を余儀なくされる。 新たな混乱をもたらしている、中国のコロナ政策。 当局の管理が行き届かず、感染の拡大がささやかれる中、市民の心配の種の1つが薬不足。 中国製の解熱剤にとどまらず、その余波は日本の薬にも及んでいる。 中国のSNSを見ると、日本のある風邪薬がコロナに効くとのうわさから、その薬を爆買いする様子が、いくつもアップされている。 中には、「現在、すべて日本で購入したものを中国に送ります!」と日本から転売しようとする動きも見られる。 そして、中国のSNSではもう1つ、最近特に目につく文字がある。 投稿されているのは、「“羊”になって6日目」、「“羊”になった。家族も次々と」といった内容。 この「羊」とは、コロナ陽性のこと。 中国の読みでは「羊」と「陽」が同じ発音をするため、陽性を意味する言葉として羊が使われているという。 ゼロコロナ政策の緩和以降、この「羊」の文字がより目につくようになったことから、感染者が急増しているとの見方も出ている。





















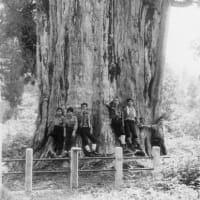














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます