今冬シーズン、雪は例年以下で雪解けも1週間から10日は速まって、一気に気持ちは春。札幌私達の地区でもシーズン平均降雪量は500cm、積雪約1mも。
しかし、冬の交通を確保するのにこのような機械で町中から雪を郊外の雪捨て場へ運びます(これって・・・、何百億です)、でないと車が走れなくなります、生活道路は溜めて溜めてシーズン1回、タイミングで当たり外れが・・・。
スキーは手稲のリフト代値上げ(シニア2時間券3000⇒3400、そもそも・・・)、1回で行きそびれ、近場も入れて3回で終了。
スケートは2020・1・27真駒内屋外リンク(ブログアップ済み)を最後に、リンクダウン?、もう3年改修方法を検討中?(場所を利用して冬キャンプ?)、で冬のトレーニングはただただ歩きです。スケート少年団はどうしてるのか・・・、こんな状態で冬のオリパラ招致?意図が見え見えで賛成できません。
1/9 石狩サーモンファクトリー近くまで用足し?、40,030歩30.8キロ、時間切れでバス乗車。
ファクトリー食堂から茨戸湖のワカサギ釣りの様子
後日我が娘ここで、携帯ドポン!だそう。自己責任ですが、時にマナー違反者?がいるそうで。
2/13、3/9 三角山往復3時間20,000歩コース。 三角山同好会?によるコース整備(ステップ切)完璧。
三角山同好会?によるコース整備(ステップ切)完璧。
2/24 先週に引き続き南5条西6丁目韓国焼肉トトリへ、ランチ石焼ビビンバ770円を食べに報復3時間。
20年?近く味、値段変わらない!?絶品!
 キムチ、サラダ、わかめスープ、コーヒー付き。キムチ入れ混ぜてしまって気づき写真、悪しからず。
キムチ、サラダ、わかめスープ、コーヒー付き。キムチ入れ混ぜてしまって気づき写真、悪しからず。 12時きっかりにシャッターあくので・・・。
12時きっかりにシャッターあくので・・・。
2/4 今年の雪まつり 1/21 孫の誕生ケーキ
1/21 孫の誕生ケーキ 次女の勤める"アンシャルロット" 2/1 町内"お家で雪像つくり"参加作品
次女の勤める"アンシャルロット" 2/1 町内"お家で雪像つくり"参加作品
追加で、出てきた50年以上前の私たち部活の記念品  除雪アルバイト中にハザード点けてたのに1メートルほどバックで・・
除雪アルバイト中にハザード点けてたのに1メートルほどバックで・・ 人身なし、ごめんなさいで・・・。
人身なし、ごめんなさいで・・・。
平和な日本、コロナも"マスクは随意!"で終わったような終わってないような・・、専門家の尾身さんはどこに行ったのか?、中国共産党の判断で良かったの?"マ、いいか!"
さてその中国、一気にコロナを克服?して、習皇帝、毛沢東越えを目指し?て死ぬまで君臨し続ける?。宇宙を目指す今これが通用するのかな~(中国の人達に聞いてみたいが・・・)。
そこで最近の中国関連コメントを。
YahooNEWS 12/16(金) 6:01配信 ダイヤモンドオンライン
中国ゼロコロナ緩和の実態は「突然すぎる全面撤退」、国民に広がる不安
新型コロナの感染予防のため、これまで強固な規制を敷いてきた中国。しかし若者たちの抗議デモが全国に広がったことを受け、突然「新型コロナ感染予防コントロール措置をさらに改善することに関する通知」(新十条)を発表した。PCR検査場が一夜にして消える、スマホアプリによる行動規制がなくなるなど、規制緩和というよりは行政が突然姿を隠してしまった形となり、国民の間には動揺と混乱、そしてオミクロン株による感染が急速に広がっている。北京のスーパーでは桃の缶詰が売り切れるという不思議な事態も起きている。(フリーライター ふるまいよしこ) 【この記事の画像を見る】 ● 一夜にして、中国政府の 新型コロナ対策措置政策が激変した 12月7日、中国国務院(内閣に相当)直轄の共同防疫対策本部が全国の新型コロナウイルス対策措置の緩和を盛り込んだ「新十条」を発表してから1週間余り。この2年半以上、1~2日ごとに義務付けられていたPCR検査や、どこに行くにも必須だった健康コードの提示の廃止が続々と進んだ。 それとほぼ同時に、今度は各地から「陽了」(陽性になった)という声が相次いで上がり始めた。香港紙「サウスチャイナ・モーニングポスト」は、一夜にして一転して現地政府が感染者数ゼロと報告した河北省保定市で、「罹患した」と自己申告する人たちがたくさん存在していると報道。また彼ら自身がそれぞれ、身辺に他の感染者がいるのを確認しており、明らかに政府発表のデータが現状と合致しなくなっていると伝えている。住民は、いまだに閉店中の商店やずっと届かないままの宅配に不安な思いを抱えながら、できるだけ自宅から出ずに過ごしており、今回の緩和措置が「措置解禁へのロードマップ」が示されないことで人びとに大きな不安をもたらしていると述べている。
● 「手のひら返し」で街は大混乱、 急速に感染者が増えている 首都・北京で暮らす筆者の知り合いも、このところ次々に、いや立て続けに自身や家族、同僚が「感染した」と言い始めている。ネットでも自身のSNSアカウントで感染を報告する例が続き、中国に関わりを持つ海外在住者たちが複数、「中国の知り合いの間で感染が急速に広がっている感じだ」とつぶやいていた。これまで何度か感染拡大を繰り返してきた過去3年間を振り返っても、ここまで頻繁に身近な人たちから「陽性報告」を受けた記憶はない。 もちろん、厳しい対策措置下にあったときは、誰かがSNSで感染を報告しようものなら、すぐに実名ネット利用制度によって居場所が割り出され、政府が準備した隔離施設に有無を言わさず送り込まれる可能性があった。そしてすでに多くの経験者の証言から、その隔離施設とはきちんとした医療設備が整えられ、治療を目的とした施設ではなく、各地の政府がデータ的に「“社会面”感染者ゼロ」を宣言するためのツールでしかないことが明らかになっていた。行政が感染者を市内から連れ出して隔離施設に放り込むことで、「一般的な社会で流通する感染ケースを排除する」ことを目的とした施設だったのだ。 だからたとえ発熱したり、突然の筋肉痛を覚えたり、あるいは検査キットで感染を確認しても、できるだけ声を上げずに、周囲に知らせずに過ごそうとした人も少なくなかった。それが、「新十条」で「無症状患者および軽症者は自宅での隔離を認める」という一文が盛り込まれ、それを受けて政府の御用専門家たちが次々と「オミクロン株の致死率はインフルエンザ以下だ」と異口同音に自宅での療養を勧めるようになったおかげで、人びとも自分の感染をためらわず周囲に告知できるようになったという一面がある。 だが、その「手のひら返し」が街中に恐慌を引き起こした。あちこちに存在し、すでに日常の一部になっていたPCR検査場のほとんどが突然閉鎖された結果、市中にどれだけ感染者や自宅自主隔離者がいるのかも把握できなくなった。どこに感染者がいるかも分からなくなり、自身や家族の感染の不安におびえる人たちが薬局に殺到し、抗原検査キットや当局が感染治療に効くと喧伝する(ものの、実際の臨床検査結果は公開されていない)中薬製剤※はあっという間に売り切れてしまった。 ※中薬製剤…生薬を使う中国の伝統薬を、飲みやすいように錠剤や顆粒などの形に製品化したもの
● 病院の発熱外来は長蛇の列、 人々は自宅で息を潜めて暮らす日々 PCR検査場は病院などの医療機関に制限されてしまった結果、その検査にやってくる人たちで発熱外来は長蛇の列となる一方で、かなりの数の人たちが自宅で息を潜めて過ごすようになった。実際、「陽了」宣言をした筆者の友人たちも、ほぼ全員がそんな感じで過ごしている。つまり突然の措置緩和によって、文字通り「データ化されない」まま、感染が爆発的に広がっているようなのだ。 ある北京在住の元メディア関係者の友人とチャットしているときに、「感染者が増えたのはPCR検査が中止されたためだろうか?」と尋ねてみた。すると彼は言った。「いや、たぶん『新十条』でPCR検査が中止される以前に、感染はすでに手に負えないほど広がっていたんじゃないかと疑っている。だって拡大するのが速すぎるよ」。もちろん、これは根拠となるデータはなく、北京で暮らす彼の、体感による推測でしかないのだが。 「新十条」が発表されたのは、11月末に世界をあっと言わせた、いわゆる「白紙運動」の結果だったのは間違いない。新疆ウイグル自治区で起きたマンションの火災で長期化し、すでに硬直化していたコロナ対策措置が邪魔して救援活動が進まず、10人もの死者を出したことで、「もうたくさんだ!」と若者たちが立ち上がって街角で叫んだ。ウイグル自治区で起きたその行動は急速に各地で同調者を立ち上がらせ、南京、上海、北京、成都……と拡散しただけではなく、そこから中国共産党や習近平を名指しで批判する声、さらには「自由を」「民主を」という要求が上がったことはすでにご存じであろう。 参考:抗議デモ、段ボール犬と散歩、うつ…青春をゼロコロナ政策で封じ込まれた中国の大学生 筆者にとっては、それが激しい暴力的な鎮圧行動へと発展しなかったことも、またある意味驚きだった。そこには明らかに、突然各地に飛び火した抗議活動に対する行政側の思索があった。ただその一方で、各地の活動の中心人物とみられた人は人知れず拘束されており、今も家族がどこにいるのか分からないとSNSで訴え、心ある人たちがその安否を気遣っていることは特筆しておく。あの国で行動を起こすにはまだまだリスクが伴うにもかかわらず、そしてそのことを知らないわけでもないのに立ち上がった若者たちの勇気に、静かにエールを送る人たちもまた少なくない。 思索したはずの政府は、表面上は抗議の声に応えたかのように措置の緩和を決め、「新十条」を発表した。だが、実際に出現したのは「行政の突然の全面撤退」だったのである。 3年の間、PCR検査を繰り返し、そしてそこから受け取る緑色の健康コードでルール付けられた生活にすっかり慣らされた人たちは、一夜のうちに消え去ったPCR検査場を前にぼうぜん。さらに、地下鉄やバスなどの公共の場でもコードの提示が不必要になったことに不安を覚えた。そして前述した薬局では「爆買い」どころか、手当たり次第に解熱剤、風邪薬、頭痛薬などを買い占めたのである。
● 北京では、黄桃の缶詰が売り切れて 店から姿を消す事態に 買い占め関連の話題で注目を集めたのが、北京で黄桃の缶詰が売り切れ状態になったことだった。スーパーのカットフルーツ缶詰の棚に並ぶ商品のうち、なぜか黄桃の棚だけがどこも空っぽになっているというのである。職員は黄桃缶詰の売り切れに落胆を隠せない客に対して、「ミックスフルーツはいかが? ミックスフルーツにもカット黄桃が入っていますよ」と声をかけたという。 もちろん、黄桃が特に風邪に効く、さらには新型コロナに効くという話は聞いたことがない。「黄桃缶詰売り切れ」ムードにあおられてスーパーに行った誰もが空になった商品棚を前に首をひねっていたときに、ネットの書き込みがその答えをくれた。 きっかけとなったのは中国東北地方のあるスーパーが黄桃の缶詰の売り出しに「桃でコロナから逃げる」というキャッチコピーを付けたところ、飛ぶように売れたことだったという。中国語の「桃」と「逃」は発音が同じで、それにひっかけたのが大当たりしたというのが真相らしい。まぁ、中国ではよくある販促プロモーションである。 ただ、別の書き込みによると、東北地方出身者にとって黄桃は、子どもの頃、風邪を引いて熱を出し、寝込んだときには親が特別に食べさせてくれたという思い出があるという。療養効果がないのは分かっているが、子ども心にはひんやりと冷たくて、甘く、喉越しの良い黄桃が、熱を冷まし、元気にしてくれるような「心の薬」だったというのである。「黄桃の缶詰は子どもたちの精神のよりどころだった」と書かれていた。 それもあり、東北出身者が多く暮らす北京に黄桃缶詰ブームが飛び火した。「妙な漢方製剤を買い込むよりも、黄桃の缶詰を買い込んだほうが何倍も心が安らぐ」というネットの書き込みも目にした。
● 北京だけで400万~500万人が陽性反応 中国全土で急速に感染拡大中 現実に目を戻そう。前掲の友人によれば、北京ではすでに人口の3分の1、あるいは400万~500万人に陽性反応が出ており、同様に全国でも急速な勢いで広がっているという。中国当局もその直後に「把握できない」ことを理由に無症状患者のデータ公開を中止すると発表したが、実際には無症状患者だけではなく、自分で自宅療養に入った人たちの数すらもすでに把握できていない状態なのである。
ふるまいよしこ
ダイヤモンドオンライン 2022.12.23 4:20 姫田小夏:ジャーナリスト China Report 中国は今
中国のゼロコロナ緩和で「市民の理想社会の幕開け」と騒ぐのはまだ早い
 11月27日、中国・北京で行われた抗議デモの様子 Photo:Anadolu Agency/gettyimages
11月27日、中国・北京で行われた抗議デモの様子 Photo:Anadolu Agency/gettyimages
中国のゼロコロナ政策は、各地で行われた抗議活動をきっかけに突如、緩和された。市民の要求を異例の速さで実現したゼロコロナ緩和措置は意表を突いたが、緩和の喜びもつかの間、中国社会は混乱に陥った。市民の力が国の政策を変えたこの足跡の意味は大きいが、果たしてこれが「中国新時代の幕開け」につながっていくのだろうか。(ジャーナリスト 姫田小夏)
抗議の声は無視することもできた
間もなく幕を閉じる激動の2022年、中国の人々にとって最大のニュースは他でもない“ゼロコロナ政策の緩和”だ。12月半ば、都内在住の中国人の友人たちはみなこれを喜んでいた。措置の緩和は感染拡大を生み、かえって市井に混乱をもたらしているが、「一時的には感染拡大の反動があっても緩和すべきだ」というのが彼らに共通した考えだった。
ゼロコロナ政策がもたらした悲劇は“移動の不自由”に加え、失わなくていい命が失われたことだった。その典型が新疆ウイグル自治区でのマンション火災だ。封鎖措置によりバリケードが敷かれ、扉は針金で固定され、救助隊が駆けつけても容易に現場に入れない状況だったからだ。
類似のケースは他にもあった。甘粛省蘭州市では3歳の子どもが救命措置を求めていたが、同じような理由で命を落とした。3歳といえば、ちょうどコロナ感染拡大前後に誕生した命だ。戸外で太陽を浴びることもなく、隔離とPCR検査の繰り返しだけで生涯が尽きた我が子に対する父母の無念は計り知れない。また、都市封鎖による経済の悪化で職を失い路頭に迷う人々も無数に存在する。
こうした市民の怒りは国家主席である習近平氏に向けられ、上海では、中国で異例ともいえる“名指し”の抗議活動さえ行われた。抗議活動はあっという間に鎮圧されたが、ゼロコロナ政策の規制は緩和された。
ただ、10月下旬に行われた第20回共産党大会の開幕前夜にも、北京では市民が横断幕を掲げてゼロコロナ反対を訴えていたが、習氏は微動だにせず報告書の中で政策の継続を示していた。「ゼロコロナ政策」は習政権の“揺るぎない国家統治モデル”とみなされていたのだ。
それだけに、11月末に起こった同時多発デモを契機とした緩和への転換は注目に値する。
“習近平、大したもんだ説”すら聞こえる
台湾在住の現代中国の研究者によると、「中国には道理があるとされる抗議デモが三つある」という。それが反日デモ、労働争議、環境デモだ。
今回の抗議デモはそのいずれでもなく、時の指導者に向けられたものだったが、規制の緩和という市民が望む変化が起こった。
中国では、「政府は市民運動で変わるのではないか」と期待する若者も出始め、「習指導部がこれを無視しなかった」という点に、3期目に入った政権の方向性を見いだそうとする人もいる。
実は先の党大会と前後して、意外な評価を耳にすることが増えた。中国某省の政治協商会議にパイプを持つ在日華僑は「習氏は、国内外で独裁者と評されていることは十分に認識している」と前置きした上で次のように語った。
「中国経済は市場性もなく、一部を除けば企業経営もボロボロ、モラルある住民も一握りです。中国の危機的状況は誰の目にも明らかで、誰もがそんな中国で自ら火中の栗を拾いたいとは思っていません。日本以上に複雑な問題を抱えた中国で、誰が国家主席などやりたいものか。それでも3期目も続けようというのだから、それはそれで大したものです」
一方で、あれだけ頑なだった習氏がゼロコロナの措置を緩和させたことについても、一部で驚きの声が上がった。すぐに措置を緩和させた習氏に対し、「彼はバカじゃなかった」といった評価さえあった。
“ディストピア中国”を誰かが止めなければ
2022年4月に亡くなった愛知大学名誉教授・加々美光行氏は現代中国研究の第一人者で、「対話ありき」の研究姿勢は多くの学生の間で共感を呼んだ。その加々美氏は今の中国をジョージ・オーウェルの小説「一九八四年」(1949年作)が描くディストピアの世界に重ね、生前次のように語っていた。
「小説では盗聴器がしかけられ、テレビが人々の生活を監視する受像機となる。この小説は『まさかこんな社会があるのか』と思わせる夢物語だが、中国はそれをなぞっているといえるような社会になった。しかも、そこに加速度がついている。2030年にはすごい社会になる。誰かがブレーキをかけなければ。いや、かけてもダメかもしれないが。もう無力感しかない・・・」
小説のすべてが中国に一致するわけではないが、テクノロジーを通して市民を支配しようとする中国の体制は日々進化を見せている。今回の抗議デモは一定の成果をもたらしたとはいえ、「いつ、どこで、誰が何をしていたか」を録画する監視カメラやそれを解析するサーバーの存在は、今後の若者の抗議活動をなえさせるに十分だ。
2019年、英・調査会社のIHSマークイットは、2021年末までに世界で10億台以上の監視カメラが普及し、そのうち54%が中国で設置されると予測した。ゼロコロナ政策下においても監視カメラの生産台数は驚異的な成長を見せており、トップシェアのHikvision(杭州海康威視数字技術)の2021年の売上高は814億2000万元(約1.6兆円)で、前年比28.2%増となった。
もはや市民は手も足も出ない。抗議活動を通して市民の声を上層部に伝えるのは至難だ。長い歴史の中で、中国人に刻み込まれたのは「政府に求めても無駄」というあきらめの境地である。
過去に破滅した王朝と「習王朝」には共通点も
中国史上で初めて国を統一したのは、秦の始皇帝(紀元前259~前210年)だといわれている。中央集権化を進め、天下を統一し、富国強兵に乗り出し、大がかりな宮殿建設を行ったが、農民への酷使や収奪が、中国史上初の農民の反乱「陳勝・呉広の乱」(前209年)に火をつけた。
漢の時代の全盛期は、武帝(前156~前87年)が中央集権化のもと、対外拡張に力を入れ、シルクロード交易を促進させ、朝鮮やベトナムにも侵攻した。1世紀前後には、豪族の大土地所有の進展が社会に動揺をもたらし、後漢半ばには疫病も流行。こうした状況が「黄巾の乱」(184年)を招く。
これらは現代の中国に共通するところがある。習近平氏を頂点とする中央集権体制と民衆支配の強化、現代版シルクロードといわれる「一帯一路」を軸とする対外拡張、また現代中国でも“富裕層のマンション購入の偏在”という不動産問題が社会を不安定化させている。疫病(新型コロナウイルス)の流行も重なる。
一つの王朝は全盛期を迎え、いずれ衰退期に入る。歴史はその繰り返しだが、“習王朝”が第3期を迎える頃になると、コロナ対策に無益な措置が過剰に導入され、人々は大混乱の渦の中に引きずり込まれた。これが「白紙を掲げた抗議デモ」につながっていった。
民衆の反乱が国家崩壊のきっかけを作る――中国共産党がSNSを厳しく統制するのは歴史の教訓があるからこそ。今回の抗議デモをきっかけに、当局は市民のスマホまでも調べ始めたと報じられているが、これでは市民の声がつくる“理想社会”など夢のまた夢だ。
社会の混沌は次なる火種をも生むか
上海在住の日本人は「ウィズコロナになった瞬間、感染は恐るべきスピードで拡大し、混乱はますますひどくなっています」と話す。こうした状況に対し、中国の医学界と接点を持つ千葉県のある医師は、「中国の専門家の医学的知識も結局政治に左右されてしまいます」と言い、いきなり正反対の措置を講じる中国政府に疑問を向ける。
ゼロコロナ政策で規制を強めてもダメ、逆に規制を緩めてもダメ――。中国では政策がもたらす反動が大きく、市民が動揺し翻弄させられるケースは枚挙にいとまがない。
「感染はいずれピークを過ぎれば落ち着く」という見方もある一方で、社会の不安定化は次なる火種をも生む可能性もある。中国生活が長い米系コンサルタントは「中国共産党は天安門事件のような動きを恐れ、今後、数カ月先に再度引き締めに転じるかもしれない」と警告する。
習氏は混乱を恐れる市民の心理を利用し、政権の正統性をより強調するために、「言わんこっちゃない」とばかりに市民の管理をさらに厳しくする可能性さえある。
「市民が上げた声」は政策転換を促した。確かにそれは、3期目の習政権下の中国を占う意味で前向きなものとなったが、これが“新時代の到来”の扉を開けるものとなるかはまだわからない。
YahooNEWS 3/4(土) 6:02配信 現代ビジネス
医療保険制度改悪でキレた中国定年退職者たちが「俺たちのカネ返せ」と大規模抗議、これでも共産主義国か
 白髪の武漢デモ 写真提供: 現代ビジネス
白髪の武漢デモ 写真提供: 現代ビジネス
湖北省の省都・武漢市は2020年1月に中国で最初に新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の蔓延が確認され、1月23日から4月8日までの2ヵ月半にわたって都市封鎖(ロックダウン)が行われたことで知られている。 【写真】こんな北朝鮮、見たことない…!写真家が29年間撮り続けた「凄すぎる光景」 その武漢市で2月8日とその1週間後の15日に大規模な抗議行動が行われた。この抗議行動は「職工基本医療保険(企業従業者基本医療保険)」(以下「職工医保」)の改革に反対するものであったが、その主体は「退休人員(定年退職者)」であり、その多くが白髪の老人であったことから、ネット上では当該抗議行動を「白髪革命」と呼んでいる。 2月8日の抗議行動は1万人以上の定年退職者が武漢市政府前に集まった。当日はあいにくの雨天であったが、定年退職者たちは傘を差しながら「職工医保制度の改革反対」、「俺たちのカネを返せ」などとシュプレヒコールを上げた。この日、彼らはこのまま事態の改善がなされないなら2月15日に再び抗議行動を実施する旨を予告していたが、武漢市政府からは何らの改善案も示されなかったので、予告通り15日に大規模な抗議行動が実施された。 2月15日、十数万人に膨れ上がった定年退職者の群れが武漢市の中心部に位置する解放大道や中山公園などの地点に集まり、「職工医保制度の変更反対」などのスローガンを叫びつつデモ行進を続けたが、武漢市当局によって事前に動員されていた警察部隊と対峙する中で定年退職者たちからは怒りに任せて「反動政府打倒」の声まで飛び出したのだった。 中国の警察部隊はこうしたデモ行進に対して過激な鎮圧行動に出るのが通常だが、今回は相手が白髪の老人たちであったことからか、警察部隊が過激な行動に出ることはなく、老人たちには負傷者もなく、抗議行動は大きな波乱なく平穏裏に終了したのだった。 なお、この同じ日に武漢市から遠く離れた東北地方・遼寧省の大連市や鞍山市でも同じく「職工医保制度の改革反対」を叫ぶ抗議行動が行われた。 中国では昨年11月末に北京市、上海市、武漢市、広州市など全国の都市十数か所で、中国政府が過去3年間にわたって継続的に実施を強行してきたゼロコロナ政策を批判する抗議行動が行われた。その主体は大学生や一般市民であり、彼らは所定の場所に集合すると、「当局の規制を受ける文言は何も書かれていない」として白紙を掲げて無言の抗議行動を行った。 その規模は1989年6月4日に起こった「天安門事件」以来で最大の反政府活動であったと考えられているが、この抗議行動はネット上で「白紙革命」と呼ばれているので、その白紙革命という呼称に倣って命名されたのがこの「白髪革命」であった。
年金、医療費ともすでにギリギリ
現行の中国における『法定の企業職員定年退職年齢』は、「男:満60歳、女の管理職:満55歳、女の従業員:満50歳」であり、事故に起因する障害などの特殊事情で早期退職せざるを得ない場合には10年以上継続した労働実績と医院の証明書を提出することを条件に「男:満50歳、女:満45歳」の早期退職が認められている。 2022年7月に中国政府「国家衛生健康委員会」が発表した中国の平均寿命は77.93歳(同年7月に日本の厚生労働省が発表した日本の平均寿命は、男:81.47歳、女:87.57歳)であるから、上述した定年退職年齢を差し引くと定年後の時間が、男は約18年間、女は管理職で23年間、従業員で28年間もあることになる。 なお、これは筆者の私見だが、中国と日本で老人の外見を比べると、中国老人は日本老人よりも5歳以上老けて感じる。具体的にその理由を説明できないが、生活環境や食生活の違いによるものなのだろうか。 それでは中国の定年退職者が毎月受領している「養老金(年金)」はどれ程の金額なのか。2022年6月に中国の「星図金融研究院」が公開情報に基づき作成した資料によれば、2022年における中国の定年退職者年金の平均は3158元(約6万3200円)/月であった。これを年間(12か月分)にすると3万7900元(約75万8000円)/年となる。 一方、中国政府「国家統計局」の統計によれば、2021年における「中国都市住民1人当たり平均消費支出」は3万307元(約60万6140円)/年であり、これを「1人当たり平均毎月消費支出」に直すと、2525.6元(約5万500円)/月になる。ただし、上述の「星図金融研究院」の主任によれば、定年退職者の消費支出は一般の都市住民よりも水準が高いので、仮に5パーセント高いとして計算すると、定年退職者の消費支出は2650元(約5万3000円)/月となる。 上記の計算が正しいとすれば、定年退職者は毎月3158元の年金を受領して、毎月2650元を支出することになり、前者から後者を差し引いた508元(約1万160円)が残額になる。従い、この手元に残る508元が彼らの自由に使える金額であり、自分の娯楽や孫たちに「零用銭(小遣い)」や「紅包(お年玉)」などを与える大事な資金なのである。
定年退職者たちを抗議行動に駆り立てたのは何だったのか。 2023年1月17日、武漢市政府は職工医保の改革政策を発表し、当該改革政策を2月1日から実施に移すと宣言した。新たな職工医保改革案は職工医保から定年退職者の個人口座へ毎月振り込まれる医薬補助金を従来の260元(約5200円)前後から80元(約1600円)前後に引き下げるというものだった。 個人口座へ毎月振り込まれる医薬補助金が180元(約3600円)前後も減額されては、今まで通りの病院通いができなくなるだけでなく、医薬費の不足分を年金の残額、すなわち自由に使える金額から充当せざるを得なくなるのだ。 定年退職者の生活は年金に頼らざるを得ないが、その年金額は余裕のある生活を送るには程遠い水準に過ぎず、月260元前後だった医薬補助金を80元前後にまで引き下げられたなら、その分だけ医薬に支出する金額が増大するから生活が苦しくなるのは言わずもがなの話である。 しかし、ここで問題なのは、職工医保から個人口座へ毎月振り込まれる医薬補助金の原資は何かという事なのである。それは定年退職者たちが現役時代に職工医保の医療保険料として自分の職工医保の個人口座(以下「医保個人口座」」に積み立てたものなのである。 そこで、中国の職工医保の概要を述べると以下の通り。 保険料は被保険者とその所属する企業がそれぞれ支払うが、 1) 保険者は前年平均賃金の2パーセントを保険料として天引きされ、その全額が被害者自身の医保個人口座に積み立てられる。 2) 所属企業は従業者の賃金総額の10パーセントを保険料として徴収され、そのうちの3パーセントは被保険者の医保個人口座に積み立てられ、残りの7パーセントは職工医保の統一基金口座に積み立てられる。 退職者たちが減額されたとして抗議行動を起こした医薬補助金は、2023年1月末までの改革前は企業従業者の平均賃金あるいは個人年金の5パーセント前後を医保個人口座から個人口座へ振り込まれていた。しかし、2023年2月1日の改革後は医薬補助金が基本年金平均額の2パーセント前後に全国規模で統一されたのだった。 個人口座へ振り込まれる医薬補助金を中国語で「医保返還金」と呼ぶが、その原資は退職者たちが在職中に医保個人口座に積み立てたものであり、退職者たちが所有権を持つものなのである。それが証拠に1998年に職工医保が創設された際の国務院の文書には「個人口座の元金と利子は個人所有に帰す」とある。したがって、退職者たちが抗議行動の中で「俺たちのカネを返せ」とシュプレヒコールを上げたのは当然のことだったのだ。
 自分で積み立てたカネを 写真:現代ビジネス
自分で積み立てたカネを 写真:現代ビジネス
新華社「周某」の例で沈静化を図るが
職工医保改革は2023年1月から全国で順次始められたが、1月末時点で中国メディアが調査したところによれば、武漢市で80元前後まで減額された医薬補助金の全国主要都市の水準は以下の通りであった。 広東省・深圳市:251元/月、 広東省・広州市:160元/月、 北京市:100元/月(70歳以下)、110元/月(70歳以上) 上海市:1680元/年(74歳以下)、1890元/年(75歳以上) 遼寧省・大連市:80元/月 湖南省:75元/月 深圳市と広州市は財政的に余裕があることから改革後も比較的高額の医薬補助金を支給できるようだが、物価の高い北京市や上海市の金額はかなり低いと言えるのではなかろうか。また、武漢市と同時に抗議行動が実施された大連市の金額は退職者たちにとって不満なものと言えよう。 退職者たちが抗議行動を起こしたのは医薬補助金の減額だけに起因するものではなく、今回の職工医保改革では「門診(外来診療)」の免責金額が500元に設定されたり、従来は医薬補助金で購入できた基礎疾患薬が購入可能リストから外されたために自腹で購入せざるを得なくなったなど、種々の問題が内在していた。 退職者たちによる抗議行動の発生に肝を冷やした中国政府は国営通信社「新華社」の記事によって退職者たちに職工医保改革への理解を求めた。その記事の中で例示されたのは、武漢市の退職者である周某の例であった。 ---------- 【改革前】周某は年間の年金収入が5万元であり、医薬補助金が毎年2400元(月額200元)振り込まれていた。周某は脳梗塞を患(わずら)ったが、武漢市には脳梗塞に対する職工医保の規定がなく、外来診療を受けても保険金の給付を受けることができなった。 【改革後】周某の個人口座へ振り込まれた医薬補助金は年間996元(月額83元)に調整された。さらに、三級医院(大規模医院)で外来診療を受けて7150元(約14万3000円)の診療費が発生したが、新たな職工医保の給付方式に基づき、免責の500元を差し引いた金額に三級医院の給付比率60パーセントの適用を受けて、3990元(約8万円)の給付を受けることができた。したがって、周某は職工医保の改革後に個人口座へ振り込まれる医薬補助金は1404元(約2万8000円)少なくなったが、外来診療による給付を受けることにより2586元(約5万2000円)の増加という待遇を享受することができた。 ---------- 新華社は周某の例だけでなく、他にも数例を挙げて、退職者たちの不満の鎮静化を図ろうとした。上述した「白紙革命」でも抗議行動の参加者に対しては1~2ヵ月後に公安局による連行・逮捕が行われたが、今回の「白髪革命」でも今後同様な参加者に対する連行・逮捕は行われるものと思われる。こうした行動を中国語の成語で「秋后算賬(時期を見て報復する)」と言うが、尊敬されるべき老人たちに対して公安局はどこまでやるのだろうか。
警察は今のところ見守っているが
今回の「白髪革命」は2月8日の抗議運動の際に、武漢市政府から医薬補助金の減額に対する改善策が出されないなら2月15日に大規模な抗議行動を起こすと予告したのだった。 この種の抗議行動をブログやSNSで予告したり、参加の呼びかけをしようにも、今回の当事者である退職者たちにとっては苦手なだけでなく、スマートフォンの操作すらできない人がかなりいるはずである。もっとも、ブログやSNSを使って抗議行動の予告をしようにも、中国では検閲により直ちにブロックや消去されるに違いない。 そうした環境にもかかわらず、2月15日には武漢市の退職者たち十数万人が抗議行動に集結し、警察部隊と対峙しながら白昼堂々デモ行進を実施したのだった。退職者たちはどのような方法で2月15日の抗議行動の予告ならびに参加呼びかけを行ったのか。恐らくその方法は中国伝統の「小道児消息(うわさ)」や「口信(伝言)」に違いないが、それは社会治安を管轄する公安局にとって最も厄介なものと言えよう。 一方、今回の抗議行動を通じて警察部隊は相手が退職者たちであることもあってか、極めて平和裏に抗議行動を見守ったようだ。それは警察部隊の隊員たちも退職者たちと同じ職工医保の加入者であり、将来的には彼らも退職後は同じ境遇になるからではなかろうか。 今回の白髪革命はこれ以上の騒動にはならないで尻すぼみで終わりそうだが、白紙革命に続く白髪革命の勃発は中国社会の不安定さを浮き彫りにしているように思えてならない。
北村 豊(中国鑑測家)






















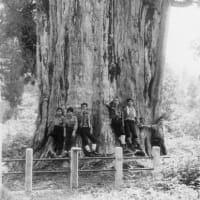














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます