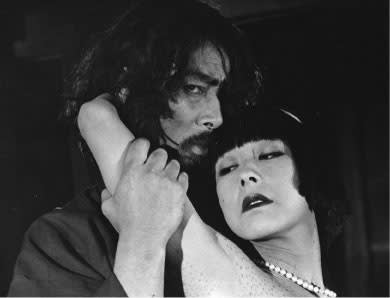これは2018(平成30)年の記事です。日付にご注意ください。
RADWIMPSが6月6日にリリースした曲「HINOMARU」が、「軍歌みたいだ」と物議をかもしている。これを受け、このバンドのフロント(ボーカル)で、同曲の作詞・作曲も担当した野田洋次郎が、11日、ツイッターで謝罪をした。
全文はネットで見られるが、「戦時中のことと結びつけて考えられる可能性があるかと腑に落ちる部分もありました。傷ついた人達、すみませんでした」というくだりがあるから、たんなる「釈明」ではなく、れっきとした謝罪である。
でもネットを見ていると、これで鎮静化ってわけでもなく、15日現在もなお、けっこうな騒ぎがつづいている。
ふつうなら、こんな厄介そうな話題はブログで取り上げないんだけど、野田さんといえば、映画『君の名は。』に、主題歌をふくむ4曲の楽曲を提供し、大きな寄与をした人だ。RADWIMPSの曲のない『君の名は。』なんて考えられない。
ぼくは2年前に劇場で観て年甲斐もなくこのアニメに魅了され、いくつか記事も書いた。今年(2018年)の1月、テレビでの初オンエアを見たのだが、かつての感動はまるで色褪せず、やはり良い作品だと思って、「『君の名は。 Another Side Earthbound』 なぜ町長はとつぜん態度を翻し、町民の避難を敢行したか」を1月5日に再掲した。
そういう縁があるもんで、ブログをやってる以上、この件を避けては通れない。
「HINOMARU」は、通算22枚目のシングル「カタルシスト」のカップリング曲である。「カタルシスト」は、2018年サッカーワールドカップ・ロシア大会の、フジテレビ系テーマ曲だ。
つまり、「HINOMARU」がW杯ロシア大会のテーマ曲ってわけではない。このところ、勘違いしている方もおられるようなので、念を押しておきたい。
とはいえ、カップリング曲なのだから、これと「カタルシスト」とが無関係ってはずもない。裏と表とで補い合って、ひとつの「世界観」をあらわしている……と見るのがふつうだろう。
サッカーW杯のテーマ曲と聞いてすぐ思い出すのは、2014年にNHKからの依頼を受けて作られ、結果として2016年度まで使われることとなった、椎名林檎の「NIPPON」だ。
この「NIPPON」の歌詞も、じつは当時そうとう批判を浴びた。Wikipediaより、すこし編集のうえ引用させていただく。
『週刊朝日』は、2014年7月4日号の誌上にて、「(サッカー日本代表のチームカラーを「混じり気無い青」と表現した歌詞が)『純血性』を強調している」、「(死をイメージさせる歌詞が)特攻隊を思わせる」、「『日本の応援歌なんだから日の丸は当然』と言うが、意味深な歌詞をはためく国旗の下で歌われてしまうと、さすがにいろいろ勘ぐりたくもなる」などと評した。
音楽評論家の石黒隆之は「日本に限定された歌がずっと流れることになるのも、相当にハイリスク」「過剰で、TPOをわきまえていないフレーズ。日本以前にサッカーそのものを想起させる瞬間すらない」と、NHKのワールドカップ中継のテーマとしてふさわしくないと批判した。
ジャーナリストの清義明も「サッカーは民族と文化のミクスチャー(混在)のシンボル」「最近は浦和レッズの一部のサポーターが掲げた『ジャパニーズ・オンリー』という横断幕が差別表現と大批判された事件もあったのに、サッカーのカルチャーをまったくわかってないとしか言いようがない」と批判した。
一方で、音楽評論家の宗像明将は「デビュー当時から和の要素も含む過剰な様式美を押し出してきた人ですから、その要素が過剰に出すぎて議論を呼んでいるだけでしょう」として、椎名の音楽に特段の政治性はないと擁護した。
どんどん長くなってしまうが、これらの批判に対する才媛・林檎嬢の反論も大切なので、もうすこしwikiからの引用をつづける。
椎名自身は、雑誌『SWITCH』のインタビューにて「貧しい。」「諸外国の方々が過去の不幸な出来事を踏まえて何かを問うているなら耳を傾けるべき話もあるかもしれないが、日本人から右寄り云々と言われたのは心外。(それらの批判は)揚げ足を取られたと理解するほかない。趣味嗜好の偏りや個々の美意識の違いなどという話を踏まえた上でも、自分は誰かを鼓舞するものを書こうとはしても誰かに誤って危害を加えるようなものは書いていないつもりだ。」と反論し、不謹慎だと言われた“死”という言葉については「死は生と同じくみんな平等に与えられるもので、勝負時にせよ今しかないという局面にせよ、死の匂いを感じさせる瞬間は日常にもある。ここを逃すなら死んだ方がマシという誇りや負けた後のことまで考えていられないという決死の覚悟をそのまま写し取りたかっただけ。」と答えている。
また、2014年6月14日にゲスト出演したラジオ番組『JA全農 COUNTDOWN JAPAN』においては、「最前線で戦う方だけにわかる、『ここを逃したら死ぬしかない、死んでもいいから突破したい』っていう気持ちはどんな分野にでもある。その瞬間だけを苦しむんじゃなくて、楽しもうという気分を切り出せば成功するだろうと思い、頑張って取り組んだ。」と語っている。
椎名さんは、どのような形であれ、ひとことも謝罪はしていない。そこが今回の野田さんと違う。潔い、とぼくは思うが、ただ、寄せられた批判の声が、野田さんのほうがずっと大きかったのも確かである。
ひとつには、『君の名は。』の世界的ヒットによってRADWIMPSの知名度がワールドワイドとなり、この夏には昨年に続いて、韓国をふくむアジア・ツアーが予定されている、ということもあるだろう。つまり営業上の配慮である。
もうひとつ、歌詞そのものに重大な違いがある。このブログの性格上、ここではこちらを詰めていく。
JASRACが怒るので残念ながら転載できないが、「NIPPON」と「HINOMARU」、双方の歌詞を、あらためてネットで見比べてみた。とりあえず、「椎名林檎は天才だ。」と再確認した。「戦い」の場における「生」の極まり。そこにおいて身体を突き上げてくるタナトス(死への欲動)。くらくらさせられる歌詞だ。いわゆる現代詩人をもふくめ、いまの日本で、ここまで鮮烈に日本語を使いこなせるひとは数えるほどしかいまい。
とはいえ、「現代詩手帖」みたく、日本全国でも数千人単位の読者しかいないメディアに発表するのではなしに、天下のNHKで、天下のサッカーW杯のテーマ曲として流されるのだから、これを「過剰」ととる視聴者はとうぜん想定しうる。上に引いた批判のなかで、「TPOをわきまえていない」とあるのは、まさにそのことであろう。
じつはこれは、「政治」というもののもつエロティシズムにかかわってくる大問題なのである。きちんと論じるつもりなら、あの三島由紀夫まで引き合いに出して、長い評論をでっちあげねばならない。だからここでは深入りしない。そんなトリガーをつい引いてしまいそうになるくらい、林檎嬢の才はすさまじいということだ。
いっぽう、「HINOMARU」の歌詞には、エロティシズムもタナトスもない。こういっちゃナンだが、かなり素人くさい。
もともと野田さんの歌詞は、ぼくの好きな「前前前世」もふくめてどれも素人くさく、ある種のブンガク臭と、やや攻撃的な妄想力が爆発してるのが魅力、というところはある。
「NIPPON」に寄せられた批判のなかで、「HINOMARU」に通じるのは、「『純血性』の強調」だろう。
強調された「純血性」は、わりとたやすく「優越性」につながる。それゆえに危ういというので警戒されるわけだけど、「HINOMARU」のばあい、これに加えて「愛国」がストレートに出てくるもんで、よりいっそう批判を招いた。
全文ではなく、断片だけならJASRACも寛恕してくれると思うので、一部を抜粋させて頂こう。
出だしが、
風にたなびくあの旗に
古(いにしえ)よりはためく旗に
意味もなく懐かしくなり
こみ上げるこの気持ちはなに?
となっている。このテクニックは、「修辞的疑問」というのだけれど、あえて真面目に答えるならば、うんまあそれは、ふつうにいえば愛国心だよね、と、だれしもが言わざるを得まい。
林檎嬢の「NIPPON」には、「愛国心」というワード(概念)を呼び起こす要素がなかった。ここもまた、ぼくが凄いと思うところだ。げんに、上に引用した批判の声でも、「愛国心をかき立てる」みたいなことは言ってない。週刊朝日でさえもだ。それはつまり、彼女がたんなる「詩人」としてのみならず、「商業ポップ」の作り手としても、プロ中のプロだということだろう。むろん、スポンサーたるNHKのチェックがきちんと入っていた、ということもあろうが。
じつは、サッカーのテーマ曲ではないけれど、つい最近、今年の4月に「愛国心扇動ソング」として物議をかもした歌がある。「ゆず」の最新アルバム『BIG YELL』に収録された「ガイコクジンノトモダチ」だ。
この国で生まれ 育ち 愛し 生きる
なのに
どうして胸を張っちゃいけないのか?
この国で泣いて 笑い 怒り 喜ぶ
なのに
「この国で(を)/愛し」と、はっきり明言しちゃってる。「はっきり」と「明言」とは意味がかぶってて、いわゆる「重言」なんだけど、「重言」なんて反則ワザを使いたくなるほど、「愛国」を明瞭に歌っちゃってるのだ。
なお、「なのに」が繰り返されるのは、「なのに」君が代を歌えない、「なのに」国旗を飾れないと続くからである。これはこれで、何だかなあと思うけれども、この方面に踏み込んでいくといよいよ紛糾して収拾がつかなくなるので、ここではただ、「この国で(を)/愛し」と、このくだりにだけ注目したい。
たぶん、戦後のポップス史において、まあアングラ系は別として、オリコンランキング常連クラスのアーティストで、ここまで「愛国(心)」を前面に出した人はこれまでいなかったはずだ。そういう意味では画期的だろう。
歌詞を書いたのは、ゆずの北川悠仁である。
このたびの野田さんにしても、あくまでもぼくの想像だけど、この「ガイコクジンノトモダチ」の歌詞に(いろいろな意味で)触発された面はあったかと思う。まるっきり無関係とは思えない。そして、もしこんな言い方が許されるならば、北川さんは「一線を越えた」のだ。でもって、野田さんはさらにその先を100メートルくらい突っ走っちゃった感がある。
胸に手を当て見上げれば 高鳴る血潮、誇り高く
この身体に流れゆくは 気高きこの御国の御霊
また、
ひと時とて忘れやしない 帰るべきあなたのことを
たとえこの身が滅ぶとて 幾々千代に さぁ咲き誇れ
とか、字面だけ見ても、かなりイカツい。
ネットでこの歌をじっさいに聴かせていただき(ありがとうございます)、歌詞をつぶさに拝見して、ぼく個人も、「うん。軍歌みたいだね。」とほんとに思った。
ただ興味ぶかいのは、擬古文を使おうとしてるわりに、口語は混じるし、文法自体もメチャクチャだし、なんかちょっと、怖いってより笑っちゃいそうになるところだ。
イデオロギーうんぬん以前に、正直いって、ひとりの作詞家としての野田洋次郎に、今回ぼくはまるっきり失望させられちまった。素人くさいってレベルじゃない。
それくらいひどいから、「この歌詞そのものが『愛国心』の空洞を表してるのだ。つまりこの歌はフェイクなのだ。」という「穿った見方」すらネットには出ているのだけれど、でもそれはそれで変な話で、今度は逆サイドから怒られるんじゃないかという気がする。
ところで、野田さんや北川さんは、批判に対する釈明の中で、「自分は右でも左でもない。そういうものとは関係なしにこの詞を書いた。」と述べて、それでまた、「ウソつけ」と言われたりしてるわけだけど、これを書いてるぼく自身は、中立ってよりも、じつはけっこう「右」なんである。
といってもまあ、シンプルにこの国を大切に思ってて(「愛」とはちょっと違う気がする。「愛」ってのはよくわからない)、この国のことば、つまり日本語をものすごく大切に思っている、というていどの話だけれど。
しかし、「日本語を大切に思っている」という点においては人後に落ちないつもりでおり、だから野田さんのこの歌詞については、たんに失望したとか、思わずからかいたくなる、といった段階をこえて、いささか腹を立てている。
「愛国」を歌うんであれば、もっと日本語をきちんと使おうよ、と言いたい。
中途半端に擬古文をもちいて「それっぽい感じ」を出そうとするなら、いっそもう、すべてをそれで統一すべきであった。
風にたなびくあの旗に
古(いにしえ)よりはためく旗に
意味もなく懐かしくなり
こみ上げるこの気持ちはなに?
「意味もなく」は「故知らず」がよい。たんに擬古文だからそのほうがいいってだけでなく、ここで「意味もなく」では文字どおり「意味」をなさない。わからないのは「意味」ではなく「理由」なのだから。
ほかの部分にも違和感はあるが、符割りのこともあるのでうまい言い方が見つからない。でもこの冒頭だけでも、据わりのよくないフレーズだらけなのは確かだ。
胸に手を当て見上げれば 高鳴る血潮、誇り高く
この身体に流れゆくは 気高きこの御国の御霊
見上げれば、ではなく、格調のために、見上ぐれば、としたいところだ。
高鳴る血潮、誇り高く、と、「高く」が重なるのも見(聴き)苦しいが、そもそも「血潮」は「熱く滾る」ものであって「高鳴る」ものじゃない。高鳴るのは「鼓動」だ。
たしかに、「高鳴る血潮」というフレーズを校歌につかってる学校もあるようだ。しかしそれも厳密には誤用だ。「高鳴る潮(うしお)」という言い回しはあり、それを拡張しているのだと思うが、ここでの「潮」は「波の音」であり、だから「高鳴る」のである。「血潮」が高鳴るというのは、誇張法としても無理があるのだ。
「この身体に流れゆく」も変で、「ゆく」は、所定の場所からどこかへ去ってしまうことである。身体のなかを巡っているのだから、「流れたる」だ。あ。いや、「御霊」が流れ込んでくると言いたいのかな? それならば、「流れくる」だ。
「気高き」と、ここでまたさらに「高い」が重なる。品がない。「御国」と「御霊」の重なりも品がない。それにしても「御霊」とはしかし、えらいコトバを持ち出したものだ(これについては後で詳しく述べる)。
ひと時とて忘れやしない 帰るべきあなたのことを
たとえこの身が滅ぶとて 幾々千代に さぁ咲き誇れ
「忘れやしない」は甘ったるい口語だ。気持ち悪い。「ひと時たりと忘るまじ」であろう。「忘るまじ」が固すぎるなら(でも林檎は使いこなしてたよ)、せめて「忘れまい」だ。
「たとえこの身が滅ぶとて」は、文法がおかしい。「たとえこの身が滅ぶとも」である。こういう誤りは、カッコつけて擬古文を使おうとするとき誰しもがやってしまいがちなことだが、仮にも商業ベースに乗せる楽曲が(しかも「愛国」を歌う楽曲が!)、こんな間違いをするのはまことに恥ずべきことである。
どれだけ強き風吹けど 遥か高き波がくれど
擬古文としてもぎこちない。「いかなる強き風吹けど 遥か高き波来たれども」くらいか。
胸に優しき母の声 背中に強き父の教え
こういうのもまあ、「愛国とワンセットになった性差の固定化だっ。」とフェミニストなら気色ばみそうなくだりだが、ぼくとしては、背中(せなか)が気になった。野田さんは「せなか」と歌っているが、「せな」と擬古文ふうに短く読んで「せな‐には」と助詞の「は」を入れたほうがよい。「母」と「父」との対比が際立つからである。細かいことをいうようだが、対比表現において後のほうに「は」を入れるのは、漱石あたりを読みなれてればしぜんにできることである。
こんな具合に、出だしからラストまで全編にわたってデタラメや誤用や残念なフレーズが散見され、JASRACさえ怒らなければ無料でぜんぶ添削してやりたいくらいなのだが、中でも極めつけは「僕らの燃ゆる御霊(みたま)」であろう。
「御霊」はこの歌のキーワード(キーコンセプト)であり、とても重要なのだが、じつはつぶさに読んでも意味がはっきりしない。そこがブキミで、批判を招くところでもあろうが、それはともかく、「御」は敬意を示す接頭辞だから、「僕ら」のものに付けるのは変なのである。
「君、ぼくのおカバンを取ってくれ。」といってるのと同じだ。
この「僕らの燃ゆる御霊」には、ぼくもつくづくがっかりした。そのあとに、「僕らの燃ゆる御霊は、挫けなどしない」というフレーズもある。「古(いにしえ)より脈々とつらなる御霊は僕らのからだに受け継がれ、いかなる困難にも屈せぬ気概(きがい)となって、僕らの芯をつくっている。」と言いたいのだろうけど、そもそも「僕らの御霊」が文法として珍妙なので、まるで心に訴えかけてこないのである。
小林よしのりに「教育」をうけた平成うまれの皆さんは、「いい曲じゃん。」「なんで文句いうの?」くらいのノリで受け入れているようだが、それはやっぱり、この国の近代史について「勉強不足」というよりない。とりあえず、加藤周一さんの『夕陽(せきよう)妄語』(ちくま学芸文庫)をお勧めしたい。ただ、そんなことよりも何よりも、かくも幼稚な日本語でもって「愛国」が歌われちゃってるこのニッポンの現実が、ぼくはしみじみ物悲しいのだった。
追記 18年11月02日)
この記事をほぼ5ヶ月ぶりに読み返して、ほかのところはともかく、ゆず「ガイコクジンノトモダチ」の歌詞についての記述はおかしいと感じた。「この国で 生まれ/育ち/愛し/生きる」のくだりは、「このニッポンという国のなかで生まれ、育ち、(家族やら友人やら恋人やらを)愛して、生きる。」という含意で、「国を愛し」といっているわけではない。どうしてこれを、5ヶ月前のぼくは、「この国で(を)/愛し」なんて強引に読み替えちまったんだろう。やはり平静さを欠いていたんだろうな。むろん、この歌そのものが「愛国心」っぽい気分(と、それをストレートに表現できない屈託)をテーマにしているのは間違いないにせよ、けして「オレはこの国を愛してるぜ!」と高らかに宣言しているわけではないので、この記事におけるぼくの論法は、この歌詞の件に関しては、牽強付会(こじつけ)というべきだろう。
記事そのものを書き直すべきかと思ったが、主眼はRADWIMPS「HINOMARU」のほうにあるんだし、全体の主旨は変わらないので、このままとさせて頂き、「追記」だけを附しておきます。
あともうひとつ、とても肝心なことなのだが、HINOMARUこと「日章旗」は、幕末において国籍を明示するための商船旗として採用されたもので、古来よりニッポンのシンボルであったわけでも何でもない。ただしこれは常識に属することなので、野田さんも承知の上であえて無知を装って押し通したのだろうと判断し、その点について本文では一切ふれなかった。