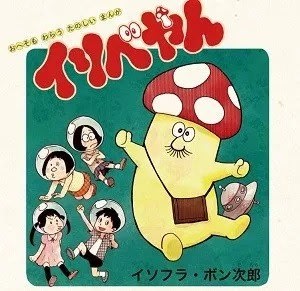30年も前に邦訳が出て、読みたい読みたいと思いながらも高額なため手の出せなかった小説が、なぜかこの1月に唐突な感じで文庫化されて、数日前に届いたもんでご返事が遅れました。まだ半ばほどですが、期待を上回る面白さですな。
それにしても軍事の話は日曜の朝にはふさわしくない気もしますね。じゃあ木曜の晩ならふさわしいのかといわれると、それはそれで困りますけども。とりあえず、4月12日にakiさんから頂いたコメントの末尾の部分を再掲します。
>私は日本のアニメは本当に高い水準にあるとは思いますが、唯一、軍事的な視点については素人の拙劣さの域を脱し切れていないと思います。これは日本が平和だったことの副産物ですね。軍事的に見られるものと言えば、富野由悠季氏や宮崎駿氏など、生年が戦時中に掛かる人々の作品くらいでしょうか。彼らに影響を受けたアニメ作家たちは、彼らの表現や「カッコよさ」「ワクワク感」などは学んでも、「軍事的視点」は学ばなかった、というか学ぼうとも思わなかった、もっと言えば目にも入っていなかった、というのが正しいでしょうか。まあ戦後も戦争を続けてきたアメリカの映画作品群が「軍事的に見られるか」と言われれば、全くそんなことはないんですけどねw
宮崎さんにはメカニックなものへのマニアックな偏愛があるので、兵器や飛行機などの描写が細密なのはわかります。ただぼく個人は、作品全体をトータルでみて軍事学的にどこまで正確なのかはわからない。富野さんのばあい、これは「ロボットアニメ」全般におよぶ初歩的かつ根本的な批判っていうか、まあツッコミなんだけど(『映像研には手を出すな!』でもやってました)、「人間が乗って操縦するタイプの巨大ロボットは物理的に不可能」という時点でじつは一種のファンタジーなんですよね。
華麗なコスチューム姿の戦士に変身して闘う中学生女子が幼い児童(とうぜんもっぱら女の子だと思うけど)の憧憬の投影であるように、「巨大ロボットを手足のように操って闘う」思春期の男子はやはり少年期から青年期(時にはそれ以上)の年齢の男の子たちの欲望の投影でしょう。ぼくは「エヴァンゲリオン」はテレビシリーズ・劇場版とも全作視聴してますが、その源流(のひとつ)というべきガンダムはほとんど観ていない。だからほんとはロボットアニメを語る資格があるかどうか疑わしいけど、一応はそう分析しています。
ご推奨の『SHIROBAKO』にもたしか、ロボットアニメの戦闘シーンで、絵柄もしくはアクションとしての「カッコよさ」「ワクワク感」を追い求める若いアニメーター氏が出てきましたね。ファンタジーとは換言すれば「物理法則の無視」ですけども、いったん足枷を外してしまえば、いくらでも外連(けれん)味をきかせることはできるでしょう。
ただ「巨大ロボットを手足のように操って闘う」ことは物理的にはファンタジーだけど、プリキュアをふくむ優れたファンタジーがそうであるように、身体的なリアリティーはあるわけです。つまりこのばあい、バイクやクルマを運転する、もっといえば派手にぶっ飛ばす時の感覚。身体感覚の拡張ですね。それがあるから多くの視聴者が共鳴できる。
ところで、「巨大なヒーローが敵と闘う」という着想の原点はアニメではなく特撮でしょう。すなわちウルトラマン。このウルトラマンという表象を、戦後サブカル批評の文脈では、「在日米軍」とみるのが定跡となっております。むろん「科学特捜隊」が「自衛隊」となるわけです。
「科特隊」には、怪獣をも、侵略主義的異星人たちをも倒すことはできない。戦闘力が圧倒的に足らない(5人しかいないし。しかもそのうちの一人が毒蝮三太夫だったりするし)。「敵」を倒せるのはあくまでもウルトラマンだけ。
これは2017年に講談社現代新書から『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』という本が出まして、ようやく一般に浸透しつつあるんですけども、首都圏も含め、日本は制空権をアメリカに委ねてるわけです。庵野秀明氏(いうまでもなく「エヴァ」の生みの親です)が総監督を務めた『シン・ゴジラ』では、三沢基地から出撃したF2がJDAM爆弾をゴジラに投下するものの、あっさり跳ね返されてしまう。そのご、もちろん日本政府の要請を受けての形なんだけど、グアムから飛んできた(所要時間は3時間ほど)戦略爆撃機B-2が地中貫通型爆弾を落として、ようやくダメージを与えられる。まあ、それでもゴジラを死に至らしめるどころか、活動停止すらさせられず、怒らせてビーム出されてえらいことになるわけですけど、それはともかく。
戦後ニホンは、「平和ボケ」「お花畑」といわれて、それは紛れもなくそうに違いないんだけど、たんに「軍事について何も知らない。」というのでなく、「あえて見ない」「知ろうとしない」態度が根っこにあると思いますね。つまりシニシズムであり、ニヒリズム。そういった性情がいわば「症例」としてサブカルに反映されているようです。
今回をもって、4月12日のコメントに対するご返事としますが、もちろん軍事の話はまだまだ尽きることはありません。
それにしても軍事の話は日曜の朝にはふさわしくない気もしますね。じゃあ木曜の晩ならふさわしいのかといわれると、それはそれで困りますけども。とりあえず、4月12日にakiさんから頂いたコメントの末尾の部分を再掲します。
>私は日本のアニメは本当に高い水準にあるとは思いますが、唯一、軍事的な視点については素人の拙劣さの域を脱し切れていないと思います。これは日本が平和だったことの副産物ですね。軍事的に見られるものと言えば、富野由悠季氏や宮崎駿氏など、生年が戦時中に掛かる人々の作品くらいでしょうか。彼らに影響を受けたアニメ作家たちは、彼らの表現や「カッコよさ」「ワクワク感」などは学んでも、「軍事的視点」は学ばなかった、というか学ぼうとも思わなかった、もっと言えば目にも入っていなかった、というのが正しいでしょうか。まあ戦後も戦争を続けてきたアメリカの映画作品群が「軍事的に見られるか」と言われれば、全くそんなことはないんですけどねw
宮崎さんにはメカニックなものへのマニアックな偏愛があるので、兵器や飛行機などの描写が細密なのはわかります。ただぼく個人は、作品全体をトータルでみて軍事学的にどこまで正確なのかはわからない。富野さんのばあい、これは「ロボットアニメ」全般におよぶ初歩的かつ根本的な批判っていうか、まあツッコミなんだけど(『映像研には手を出すな!』でもやってました)、「人間が乗って操縦するタイプの巨大ロボットは物理的に不可能」という時点でじつは一種のファンタジーなんですよね。
華麗なコスチューム姿の戦士に変身して闘う中学生女子が幼い児童(とうぜんもっぱら女の子だと思うけど)の憧憬の投影であるように、「巨大ロボットを手足のように操って闘う」思春期の男子はやはり少年期から青年期(時にはそれ以上)の年齢の男の子たちの欲望の投影でしょう。ぼくは「エヴァンゲリオン」はテレビシリーズ・劇場版とも全作視聴してますが、その源流(のひとつ)というべきガンダムはほとんど観ていない。だからほんとはロボットアニメを語る資格があるかどうか疑わしいけど、一応はそう分析しています。
ご推奨の『SHIROBAKO』にもたしか、ロボットアニメの戦闘シーンで、絵柄もしくはアクションとしての「カッコよさ」「ワクワク感」を追い求める若いアニメーター氏が出てきましたね。ファンタジーとは換言すれば「物理法則の無視」ですけども、いったん足枷を外してしまえば、いくらでも外連(けれん)味をきかせることはできるでしょう。
ただ「巨大ロボットを手足のように操って闘う」ことは物理的にはファンタジーだけど、プリキュアをふくむ優れたファンタジーがそうであるように、身体的なリアリティーはあるわけです。つまりこのばあい、バイクやクルマを運転する、もっといえば派手にぶっ飛ばす時の感覚。身体感覚の拡張ですね。それがあるから多くの視聴者が共鳴できる。
ところで、「巨大なヒーローが敵と闘う」という着想の原点はアニメではなく特撮でしょう。すなわちウルトラマン。このウルトラマンという表象を、戦後サブカル批評の文脈では、「在日米軍」とみるのが定跡となっております。むろん「科学特捜隊」が「自衛隊」となるわけです。
「科特隊」には、怪獣をも、侵略主義的異星人たちをも倒すことはできない。戦闘力が圧倒的に足らない(5人しかいないし。しかもそのうちの一人が毒蝮三太夫だったりするし)。「敵」を倒せるのはあくまでもウルトラマンだけ。
これは2017年に講談社現代新書から『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』という本が出まして、ようやく一般に浸透しつつあるんですけども、首都圏も含め、日本は制空権をアメリカに委ねてるわけです。庵野秀明氏(いうまでもなく「エヴァ」の生みの親です)が総監督を務めた『シン・ゴジラ』では、三沢基地から出撃したF2がJDAM爆弾をゴジラに投下するものの、あっさり跳ね返されてしまう。そのご、もちろん日本政府の要請を受けての形なんだけど、グアムから飛んできた(所要時間は3時間ほど)戦略爆撃機B-2が地中貫通型爆弾を落として、ようやくダメージを与えられる。まあ、それでもゴジラを死に至らしめるどころか、活動停止すらさせられず、怒らせてビーム出されてえらいことになるわけですけど、それはともかく。
戦後ニホンは、「平和ボケ」「お花畑」といわれて、それは紛れもなくそうに違いないんだけど、たんに「軍事について何も知らない。」というのでなく、「あえて見ない」「知ろうとしない」態度が根っこにあると思いますね。つまりシニシズムであり、ニヒリズム。そういった性情がいわば「症例」としてサブカルに反映されているようです。
今回をもって、4月12日のコメントに対するご返事としますが、もちろん軍事の話はまだまだ尽きることはありません。