NHK等によると、日本の米は高くてもうまいので、富裕層に的を絞れば中国でも売れるだろう、ということである。
そりゃまあ、日本人のような米の食べ方をすれば、日本米がうまいだろうが、誰もが日本人のような米の食べ方をしているかというと、そういうわけでもないだろうし…。
なんなんだろう、この「食ナショナリズム」とも言える気持ちの悪いナルシストぶりは…と思ったら、この問題は、「米信仰」に端を発する、きわめて複雑で奥深い経過を経てきたものであるらしい。
そもそも日本人は、周知の通り、昔から雑穀を食べてきたので、米を「主食」にするようになったのは明治、それも後期以降で、それまでは、米、特に銀シャリなんかは、贅沢品として、滅多に食べることはできなかった。
ところが、ある時期から、この「贅沢品」が手に入る、正確には「手に入るかのように」思える時期がやってきた。
それは、日清、日露両戦争の勝利により、台湾、朝鮮で米を作るようになってからだが、しかしそれは所謂「外米」で、日本人はそれを蔑む形で、国内産の高い米を崇めるようになった。(特に中国の米は「南京米」と総称され、もっとも侮蔑された。最下層の日本人が食べたからである。その侮蔑ぶりは、漱石の「坑夫」に詳述されている。)
柳田国男は次のように言っているそうである。
『軍は脚気予防のために挽き割りの麦を混食させる方針をとっていたが、にもかかわらず、一般にその混用の歩合が少なくなり、目に見えて飯は白くなった。米しか食わない人の数が激増して、粗悪な外国米(朝鮮、台湾、そして中国)が山奥にも運び入れられることになった。この変化の方が、実は、精白度より大きなことであった。(その結果)米は日本人の主食であることを信じて疑わぬ人たちばかりが日本の日本の生活問題を論じようとしたこと、それと一方に、米の飯は奢りであり、したがって米が食えるのは幸福だと思うような質朴な考えが合体して、始終注意をこの一点に集め、非常に我々の食料問題を窮屈にしたことは事実である。』
この日本人の米に寄せる「窮屈な自意識」は、米騒動で拍車がかかり、窮地に立った日本政府は、東北地方で実績をあげつつあった新種の米を朝鮮半島において移植し、増産を命じたが、こうして生じた「外米」の普及、流入は、前述したように、高価だが、日本人の「口に合う」内地産の米に対する執着心を醸成したのだ。(その中間に位置したのが、朝鮮米の源流地である日本の東北地方。東北人のコンプレックスはここに起因する。)
要するに、「日本人の主食=米」という図式は、海外からの輸入によってはじめて成立したのだが、その「海外」が朝鮮、台湾という近代日本の、はっきり言って帝国主義的侵略(20世紀初頭におけるグローバリズム)の結果得た支配地域だったことが、「米」に関わる、まさに「奢り」を地で行く心理を醸成したのだ。
橋川文三は、「昭和維新論」で、次のように書いているそうだ。
『何かがこの時期(1930年代)に巨大なかげりのようなものとして日本人の心の上をよぎり、それ以前とは異なった精神状態に日本人を引き入れたのではないかという印象を私は持っている。精神的な大亀裂に似たものがあったのではないか、そしてそれ以来、日本人はそのことに気づかないまま、不思議な欲望に操られ始めたのではないだろうか。』
この「精神的な大亀裂」とは何か?
それは、「日本人のすべてが常食として米を食べること」に象徴されるような「奢り」に似た何か、ではないか?
―と書いているのは、一橋大学員博士課程在学中の山内明美という若い研究者で、私はそれを一橋大学大学院言語社会研究科発行の「言語社会2」という分厚い本に収められた「近代日本における稲作ナショナリズム試論」で読み、なるほどと思ったので、ちょっと紹介してみたのである。
ちなみに、「日本人畸形論」の岸田国士は、近代日本人の畸形性を払拭するには、「まず主食という概念を捨てよ」と書いている。
そりゃまあ、日本人のような米の食べ方をすれば、日本米がうまいだろうが、誰もが日本人のような米の食べ方をしているかというと、そういうわけでもないだろうし…。
なんなんだろう、この「食ナショナリズム」とも言える気持ちの悪いナルシストぶりは…と思ったら、この問題は、「米信仰」に端を発する、きわめて複雑で奥深い経過を経てきたものであるらしい。
そもそも日本人は、周知の通り、昔から雑穀を食べてきたので、米を「主食」にするようになったのは明治、それも後期以降で、それまでは、米、特に銀シャリなんかは、贅沢品として、滅多に食べることはできなかった。
ところが、ある時期から、この「贅沢品」が手に入る、正確には「手に入るかのように」思える時期がやってきた。
それは、日清、日露両戦争の勝利により、台湾、朝鮮で米を作るようになってからだが、しかしそれは所謂「外米」で、日本人はそれを蔑む形で、国内産の高い米を崇めるようになった。(特に中国の米は「南京米」と総称され、もっとも侮蔑された。最下層の日本人が食べたからである。その侮蔑ぶりは、漱石の「坑夫」に詳述されている。)
柳田国男は次のように言っているそうである。
『軍は脚気予防のために挽き割りの麦を混食させる方針をとっていたが、にもかかわらず、一般にその混用の歩合が少なくなり、目に見えて飯は白くなった。米しか食わない人の数が激増して、粗悪な外国米(朝鮮、台湾、そして中国)が山奥にも運び入れられることになった。この変化の方が、実は、精白度より大きなことであった。(その結果)米は日本人の主食であることを信じて疑わぬ人たちばかりが日本の日本の生活問題を論じようとしたこと、それと一方に、米の飯は奢りであり、したがって米が食えるのは幸福だと思うような質朴な考えが合体して、始終注意をこの一点に集め、非常に我々の食料問題を窮屈にしたことは事実である。』
この日本人の米に寄せる「窮屈な自意識」は、米騒動で拍車がかかり、窮地に立った日本政府は、東北地方で実績をあげつつあった新種の米を朝鮮半島において移植し、増産を命じたが、こうして生じた「外米」の普及、流入は、前述したように、高価だが、日本人の「口に合う」内地産の米に対する執着心を醸成したのだ。(その中間に位置したのが、朝鮮米の源流地である日本の東北地方。東北人のコンプレックスはここに起因する。)
要するに、「日本人の主食=米」という図式は、海外からの輸入によってはじめて成立したのだが、その「海外」が朝鮮、台湾という近代日本の、はっきり言って帝国主義的侵略(20世紀初頭におけるグローバリズム)の結果得た支配地域だったことが、「米」に関わる、まさに「奢り」を地で行く心理を醸成したのだ。
橋川文三は、「昭和維新論」で、次のように書いているそうだ。
『何かがこの時期(1930年代)に巨大なかげりのようなものとして日本人の心の上をよぎり、それ以前とは異なった精神状態に日本人を引き入れたのではないかという印象を私は持っている。精神的な大亀裂に似たものがあったのではないか、そしてそれ以来、日本人はそのことに気づかないまま、不思議な欲望に操られ始めたのではないだろうか。』
この「精神的な大亀裂」とは何か?
それは、「日本人のすべてが常食として米を食べること」に象徴されるような「奢り」に似た何か、ではないか?
―と書いているのは、一橋大学員博士課程在学中の山内明美という若い研究者で、私はそれを一橋大学大学院言語社会研究科発行の「言語社会2」という分厚い本に収められた「近代日本における稲作ナショナリズム試論」で読み、なるほどと思ったので、ちょっと紹介してみたのである。
ちなみに、「日本人畸形論」の岸田国士は、近代日本人の畸形性を払拭するには、「まず主食という概念を捨てよ」と書いている。














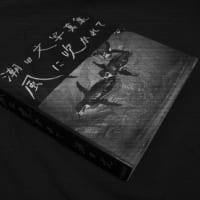

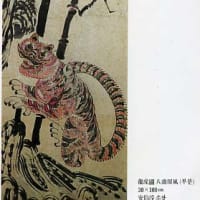
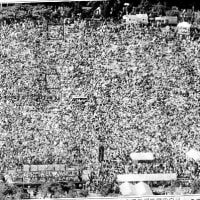

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます