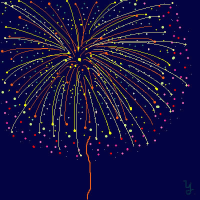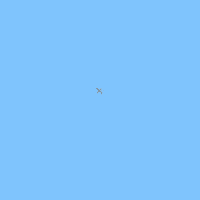研修医が誤診、高校生死亡 上級医に相談せず―日赤名古屋第二病院
時事通信 社会部配信
研修医が誤診、高校生死亡 上級医に相談せず 日赤名古屋第二病院
時事通信配信
研修医が急性胃腸炎と誤診、16歳の高校生死亡 名古屋の第二日赤
嶋田圭一郎
CBCニュース
ただね。
脳脊髄液漏出症の場合、
誤診されて、原因不明の病とか、メニエール症とか、良性発作性頭位めまい症とか、気象病とか、慢性疲労症候群とか、広場恐怖症とか線維筋痛症とか診断されてしまうと、
それを患者が、「私の症状の苦しみにやっと病名をつけてもらえた!」なかなか治らなくても、患者がそれにむしろいたく納得して受け入れてしまい、少しもその診断を疑わず、誤診に気づかない場合が多いと思う。
たとえ、誤診に気づいたとしても、新たな病を合併していると、足し算してしまう。
米倉さんも、最初低髄液圧症候群と言っていたから、そう診断する医師だったのね。
その次に急性腰椎症とか、仙骨関節障害って、
それ診断したの誰?
脳外科医ではないよね?
整形外科医師では?
脳脊髄液減少症の腰の激痛、動けなさを診ればそう診断されてもおかしくないけど、
それは、脳脊髄液減少症の症状ですよ!(体験者が言うのだから間違いない)
たとえば、
線維筋痛症と診断されていた人が、次に別の医師に慢性疲労症候群と診断され、最後の医師に脳脊髄液漏出症と診断されると、本当は最後の一個の病名がすべてを包括する場合でも、前の2つの病名を切り捨てられないで取っておく。
他の医師に見捨てられてた自分の症状に真摯に向き合い、病名をつけてくれた
前の診断の医師への感謝や盲信が強い患者がそうなるのではないか?と私は思う。
医師って、その地位や権威や知識をふりかざすから、
一種の教祖みたいになりがちで、
無知な患者は難なくマインドコントロールされ、教祖の教えを盲信するみたいに信じ込みやすい。
マインドコントロールが解けないと、別の視点で考える事ができないのは、
反社会的教団の教祖を信じ込んでしまった信者と、
本質的にはなんら変わらない気がする。
患者自身がすべてを医師まかせにせず、
自分の症状をしっかり観察して自分で考え、自分の意見をしっかり医師に伝えることが大切だと思います。
医師だって人間なんだし、24時間365日患者の症状を見ているわけじゃないんだから、
たったの5分や10分の診察で、患者のすべてをわかるわけじゃないんだから。
医師に嫌がられてもなんでも、きっちり、自分の考えは自分で伝えなきゃ!