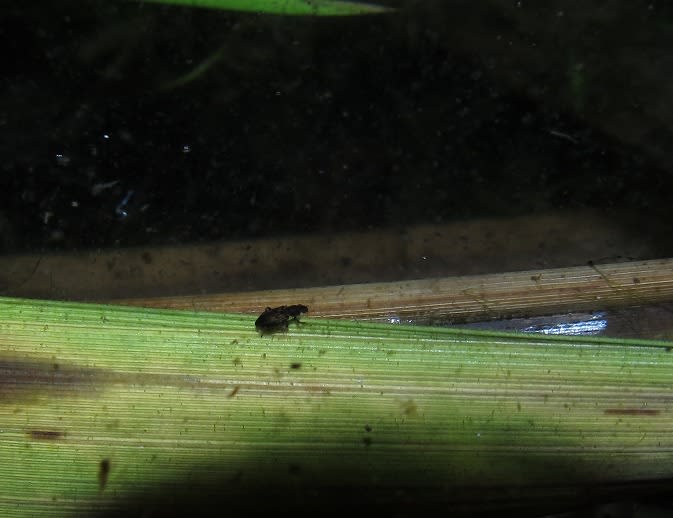エゾゲンゴロウモドキの腹面は一般的には黄褐色で斑紋がなく、近縁種のゲンゴロウモドキ[Dytiscus dauricus]は黒紋を有することからこの特徴は「日本のゲンゴロウ」でも種を同定するときに使われる区別点の一つとなっている。
過去に北海道で採集した際には全ての個体が黄褐色一色で斑紋がなく、図鑑の通りだと思っていたが、山形県で採集した際に斑紋があるものもいるということを知った。

これは2012年の新潟県での採集品。山形県でもこのような感じで後脚付け根付近の左右に黒紋が見られる。
黒紋の大きさには変異があるが、普通はあっても腹節の第1節のみに出ることが多く第2節にまで出ることはあまりない。

これは昨日載せた雌の腹面。左の個体は黒紋が非常に発達しゲンゴロウモドキと見間違えるほど。この場所では11個体(7♂♂4♀♀)を見たが、まったく黒紋がない個体から上の写真左のような非常に発達するものまで様々な変異を見ることが出来た。
本種は他の変異として雌の上翅に溝が有るものと無いものが知られているが、普通は溝があり、溝がないものは非常に稀。
これは遺伝で決まるようで生息地が限られているようですが、私は北海道と山形県でそれぞれ確認済み。今回確認した4♀♀は溝がありましたが、おそらく新潟県内でも溝が無い個体が出ると思うので、今後はこちらも探して行きたいと思ってます。
過去に北海道で採集した際には全ての個体が黄褐色一色で斑紋がなく、図鑑の通りだと思っていたが、山形県で採集した際に斑紋があるものもいるということを知った。

これは2012年の新潟県での採集品。山形県でもこのような感じで後脚付け根付近の左右に黒紋が見られる。
黒紋の大きさには変異があるが、普通はあっても腹節の第1節のみに出ることが多く第2節にまで出ることはあまりない。

これは昨日載せた雌の腹面。左の個体は黒紋が非常に発達しゲンゴロウモドキと見間違えるほど。この場所では11個体(7♂♂4♀♀)を見たが、まったく黒紋がない個体から上の写真左のような非常に発達するものまで様々な変異を見ることが出来た。
本種は他の変異として雌の上翅に溝が有るものと無いものが知られているが、普通は溝があり、溝がないものは非常に稀。
これは遺伝で決まるようで生息地が限られているようですが、私は北海道と山形県でそれぞれ確認済み。今回確認した4♀♀は溝がありましたが、おそらく新潟県内でも溝が無い個体が出ると思うので、今後はこちらも探して行きたいと思ってます。