タイトルでピンと来る人は何人いるのだろうか?
先日、ちょっとこの話題が出た(出した)ので、画像を漁ったら古いが出てきたので紹介。
写真を撮ったのが前の前のデジカメでだいぶ見にくいですが、標本は実家にあるので撮りなおし出来ません

[f.echigo]とは、エゾゼミ[Tibicen japonicus]の型の一つで、越後の名前の通り主に新潟で出現する変異の一つ。
通称エチゴエゾゼミ。
新潟以外の地域では極めて少ないと思うが、詳しいことはよく分かりません

山形県では記録有り。
まずは基本型のエゾゼミ↓

胸のw模様が特徴的なんですが、エチゴエゾゼミになると…↓

全身がオレンジ色になってw模様は分かりにくくなります。
他にも中間のタイプ(f.iwaoiとか)も出ますがこの中にはいくつかのタイプがあるようで、これも詳しくは分かりません。

胸の両脇がオレンジ色になる限りなくエチゴに近いものも出ますが、写真はなし。
このエチゴエゾゼミは地域によって出現率に大きな差があり、最初に書いたように新潟県以外では滅多に出ません。
新潟県内でも地域差が多くあり、県内のどこでも出るというわけではないようです。
過去に出現率を調べた文献がありましたが、たしか10%くらいだったかな?(かなりうろおぼえですが…。)
エゾゼミは小さいころから何度か採集していて、中間タイプなども採集したこともあったのですが、興味を持ったのは2005年。
8月27日にあった市の昆虫観察会で、中間タイプがスズメバチに食べられているのを地元のY先生が見つけ、エゾゼミの話題になったのがきっかけだったと思う。
その4日後、夏休み最終日の31日に「今日はエチゴ採ってくるから」と宣言して家を出て、最初に採集したエゾゼミがf.echigoだった。それ以後も少し通ったが2005年の結果としては
8/27
基本1♂ 中間1♂ エチゴ0
8/31
基本5♂♂7♀♀ 中間1♂ エチゴ2♂♂
9/1
基本6♂♂7♀♀ 中間0 エチゴ0
9/3
基本14♂♂4♀♀ 中間1♀ エチゴ0
9/10
基本6♂♂1♀ 中間1♂ エチゴ1♂
と、五日間でエチゴ3♂♂、中間3♂♂1♀、基本32♂♂19♀♀の58個体を採集。
エチゴの出現率は約5%でしたが、出現率を出すには数が少なすぎますね。
エチゴエゾゼミを採集するには、出現する場所でどれだけエゾゼミが採れるかということだと思う。
エゾゼミは一本の木に集まる習性がありその下で待ってればいいと聞いていたが、それは木を切っていた時代の話。
この場所ではそのような木は無く、ひたすら鳴き声を頼りに、鳴いている木を探し、姿を見つけて採集するしか無かった。
この時はセミの個体数も多かったが、自分の耳と目が鳴いている木、鳴いている高さ、鳴いている枝、そして鳴いている個体を正確に判断できて多数採集することが出来た。が、今の自分ではちと厳しいかも

翌年は一回だけ採集に行ったが、鳴いている個体も少なくエゾゼミが3♂♂しか採集できなかった。でもその内1♂はエチゴでこれは博物館にプレゼントした。
しかし、これ以降エチゴどころかエゾゼミすら採集できていない。北海道時代もお盆は実家に帰って探しに行ったが、2007年は鳴き声も聞けなかったし、2008年の数個体が鳴いたのみ。去年今年は採集に行っていないが、多くはなかった模様。











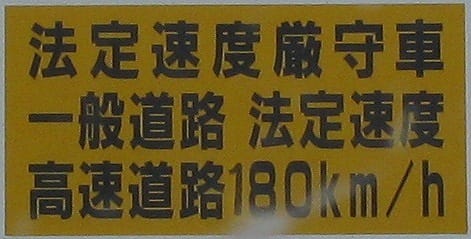


 記念に採集しておくべきだったか
記念に採集しておくべきだったか




 山形県では記録有り。
山形県では記録有り。


