外出しようとして玄関のドアを開けたら、こんな空が目に
飛び込んできました。
興奮して家の中に引き返し、デジカメに収めましたが・・・
こんなじゃなくて もっともっと感動するような光景でした。
あれば、広角レンズで 180度のパノラマで撮りたかった程
ですが雲は捉えようがない気がします。
 9月23日
9月23日







そしてあくる日。
墓地公園にお参りに行った時には、昨日とは又、趣きの
違う雲が空一面に広がっていました。ケータイばかりに視線を
落としている息子に教えたら、「うゎ~~すご~い!」と、
とても驚いた様子で、肩から力が抜けて、あたかも自然界と
一体化したかのような穏やかな表情になっていました。
自然の力ってすごい!
「心が和むよね~ここに寝転がってずっと見ていたいね」と私。
「えっ、墓地のなかで?それはちょっと・・」と息子。
じゃぁ、新しくできた海の見える公園ならいいよね!
でも雲はなかなかジッとしてくれないんです。家から墓地公園
までと、お参りを終えて公園をあとにする時とでは又々様子が
変わりました。


9月24日 墓地公園にて(東と西の空の2枚ともほぼ同じ時刻です)
25日の月曜日、会社に着いて入口の所から空を見上げたら、
↓こう来ました。

9月25日 我が職場の入口から
自由自在に手を替え品を変え私を魅了する雲、
きっときっと、あなたにはストレスなんてなんにもないんだろうね、
雲よ!
そして昨日、今日と生憎の雨日和。

雨の空でも撮ろうかぁと見上げましたが、ど~んよりと一面灰色の空。
や~めた・・

〈女心と秋の空〉
女の男に対する愛情は、秋の空模様のように変わりやすいという事のようですが、
〈男心と秋の空〉が本来のかたちだそうです。ということは、男のが移り気なの?
わたしの心もちょっぴり秋めいてきましたよ~!こんな方の登場で。














 ジャン=アントワーヌ・ウードン 作
ジャン=アントワーヌ・ウードン 作
先日、ご近所のYYさんからお誘いを受け、千葉ポートサイドタワーまで
「大ナポレオン展ー文化の光彩と精神の遺産ー」に行ってきました。
ナポレオン・ボナパルトと言えば、世紀の政治的、軍事的な天才、
とまでは知っていましたが、美術、芸術、諸学問などの文化面に
於いても、これほどの関心と影響力のあった人だ、とは思いも寄りません
でした。
エジプト遠征の際には多くの学者や芸術家からなる「学術団」を同行
させてエジプト文明の調査を行い、その成果を「エジプト誌」という膨大な
記録に纏めたり、ヨーロッパ各地から運び込まれた美術品を収容してある
ルーブル宮殿を美術館として一般市民に開放したり、地方の美術館の
建設にも力を入れたと言います。ルーブル美術館は、そのころは
ナポレオン美術館と呼ばれていたのですね。
今回は絵画のほかに彫刻、工芸、遺品の数々、自筆の原稿に書籍と、
幅広く展示してあり、彼の「皇帝」としての姿よりも、人としての魅力に
触れる事ができた気がします。
レジオン・ド・ヌール勲章は、1802年にナポレオンが創設した勲章です。
「この勲章は、私の創った制度の中でも、生命力が強く、長く生き続けて
いくであろう」と予見していたと言いますが、本当にその通りとなっていますね。


★イタリアの信教の自由を支持する直筆書簡 ★レジオン・ド・ヌール勲章
彼の夢はヨーロッパを「一つの欧州」として、共通の政治、通貨、法制度を
設けることだったようです。そしてその中心には最も美しい都市でなければ
ならぬ、と考え、パリを首都にしたかったのです。ロシア遠征の敗北、そして
ワーテルローの戦いを最後に、その夢は閉ざされました。
流刑の地セント=ヘレナにて、1821年5月5日、51才のナポレオンは、
「フランス・・・軍隊・・・軍の先頭へ」
との言葉を残してその一生を閉じたそうです。
たくさんのナポレオン語録をのこしましたよね。
遠征の時でも、万に及ぶ書物とともに移動していたそうで、知的で聡明、勇敢、
かつ細やかな神経の持ち主であったのではないかと思います。
これを企画した東京富士美術館館長の以下の言葉に納得しました。
それにしても、ナポレオンの人生は、
一人の人間がどれほどの可能性に生きることが
できるかを私たちに教えてくれる。
同じ一生であるならば、「ロマン」ある人生を生き、
なにか生きた証を残したいと思うのは、
人として共通の思いではないだろうか。
↓大ナポレオン展で購入した絵葉書とワイン


〈地球のひとまたぎに邪魔者現る〉
★★★ YY さん、その節はお車つきでのお誘い有難うございました。★★★
ジャック・ルーシェトリオ演奏する、サティーのグノシェンヌを聴きながら・・・雨の日もいいかも。














 メモ
メモ






 車をとあるスーパーの駐車場に置き
車をとあるスーパーの駐車場に置き 「太陽の下の18才」になった感じだわぁ
「太陽の下の18才」になった感じだわぁ



 が先か見るのが先か・・」と書いていましたが、
が先か見るのが先か・・」と書いていましたが、





 我が団地の広報の表紙にも登場しました!
我が団地の広報の表紙にも登場しました!

 図案集「蝶千種」の中の絵を見ていると、
図案集「蝶千種」の中の絵を見ていると、
 「吉野」
「吉野」 「八つ橋」
「八つ橋」


















 駅からすぐの「緑の相談所」(でしたっけ?)
駅からすぐの「緑の相談所」(でしたっけ?)


 フリッツ・マッケンゼン
フリッツ・マッケンゼン オットー・モーダーゾーン
オットー・モーダーゾーン ハンス・アム・エンデ
ハンス・アム・エンデ フリッツ・オーヴァーベック
フリッツ・オーヴァーベック ハインリヒ・フォーゲラー
ハインリヒ・フォーゲラー



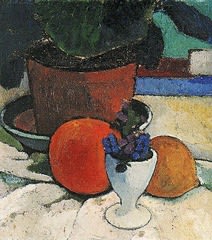





 葉山に行ってきま~す
葉山に行ってきま~す
 お雛様の主人公
お雛様の主人公











