《芸術とは目に見えるものの再現ではなく 見えるようにすることである》 パウル・クレー

「ピラミッド」1932年
友人に誘われて大丸ミュージアムまで、パウル・クレー展を観に行ってきました。
今回の展覧会は、昨年6月に完成したパウル・クレーセンターの開館を記念しての特別展。このセンターは、大雑把に言えばベルンの外科医ミュラー博士が建物を提供し、クレーの孫の代になる遺族が作品を提供、更に国民投票によって、今後、センターの運営への多額の公費の使用も承認されたというのです。
ミュラー博士はこの設計をイタリア人のレンゾ・ピアノに指名。場所も、クレーの住んでいたベルン郊外を指定しました。ベルン市民の情熱に支持されてこのようなセンターが出来上がるとは、なんてステキな国なんでしょう。
(レンゾ・ピアノは、ポンピドーセンターや関西国際空港の設計を手掛けた方です)
また、昨年はアインシュタインが1905年にベルン市に移住して相対性理論を完成させてからちょうど100年目にあたり、同市では大規模なイベントが同時に2つも開催されたということになります。それにしてもこの2人、1879年という同じ年に生まれ、同時代にベルンの街中を歩いていたのだと想像すると、なんだかゾクゾクして来ます。

「情熱の庭」
彼の持つ独特の色合いとシンプルな抽象画は、学生の頃、シャガールの絵と共に、一度見ただけで心の中に残り、K書店の横浜営業所でちょっとばかり営業アシスタントをしていたとき、2割引で購入できる特典があったので、大判の美術全集の中からシャガールとモネ、そしてクレーの3冊を選んで購入したものです。一見、子供でも描けそうな、線と色彩で作り上げ た絵画は濃厚な油彩と違い、グラフィックデザインの要素を多く持っているように見受けられました。 色彩はどれも押さえ気味の、どちらかといえば日本人好みかもしれません。
「目に見えるものをそのまま画面に写しとるのではなく、
内面にあるイメージと、 どのように折り合いをつけるべきか」
クレーは生来、研究心旺盛で、あらゆる素材や画材、技法を駆使して自己の表現力を探り続け、 その芸術性を高めていきました。彼の作品の中には何を使ってどのように描いたものか、長い間不明のものも沢山あったといいます。あるプロセスを越えて、目標に達してしまうと、さらに次への創造への探求が始まり、彼の創造への探究心は留まることを知りません。
「重要なのは〈存在する〉ことではなくて 〈存在へ至る〉過程の方である。」
と言っているように、作品そのものよりも、プロセスに身も心も熱中したようです。
しかし、画家としてのクレーしか知らなかった私は、彼が、高校を卒業する頃に、音楽家になるべきか、画家の道を選ぶべきか相当迷ったということを知り、 吃驚しました。というのも彼の父親は音楽教師、母はオペラ歌手ということで、家庭は常に音楽に溢れていたのだそうです。幼少の頃から習っていたヴァイオリンで頭角を現し、11才の時にすでに、ベルンのオーケストラに籍を置くまでになったのです。
そうなんだ。彼の絵を見ていると、それはあるときは音楽のようで、また、ある時は詩そのもの。
神奈川県立近代美術館の水沢 勉氏が、“恥ずかしがり屋の「謎」” というタイトルで、私が何となく感じた思いに似たようなことを実に上手く表現しています。
「・・・・・・・展覧会会場で観るクレーは、いつでも余所行きの顔をしている。
遠くからみえてしまうことは、 クレーの作品の場合、余りアドヴァンテージには
ならない。それが立派な美術館であればあるほど、この繊細敏捷な小動物は、
ますます身を強張らせ、小さくなってしまうのだ。パリのポンピドゥーセンターや、
ニューヨークのメトロポリタン美術館に並んでいるクレーは、まさに「借りてきた猫
であったに違いないと思う。 小さな美術館での予期せぬ出会い、不意打ち、
こそが、クレーとの出会いにはうってつけではなかろうか。
・・・・・・・
若き日の「クレーの日記」を読んでもわかるように、クレーはまれにみる読書家で
あり、またヴァイオリンの 名手でもあり、いつも書物と楽譜とともに暮らすひとであった。
・・・・・・・
クレーの絵画は、あたかも 書物のようではなかろうか。それは手に取り、
その温もりのなかで、暖められるべき性質のものなのでは なかろうか。
・・・・・・・・
クレーの恥かしがり屋の「謎」も、書物のように受けとめるとき、そのヴェールを
少しだけわたしたちにそっと脱いでくれるのである。」
クレーの作品の横には彼の日記よりの抜粋文や詩が紹介されています。読んでは観て、観ては読んでいるうちに、彼が画家であり、そして音楽家でもあり、さらには詩人であったのだ、と確信してきます。
ぼくたちが形あるものを観察するのは
芸術の表現のためであり
そこに、ぼくたちは自身の魂をも
のぞき込むことが出来る。
哲学と人はいうが、たしかに哲学には
芸術に似通ったものがある。
はじめは哲学がどれほど魂を
観察できるかを知って
ぼくは驚いたものだ。
▲ ▲ ▲
ぼくは
手を休める。ぼくのなかで
奥深く、優しくわきおこる思いがある。
ぼくはそれを感じる。苦労もなく自信に満ちあふれた何かを。
色彩がぼくをとらえたのだ。ぼくの方から追いかける必要もない。色彩がいつ
でもぼくをとらえるだろう。これが幸福というものだ。色彩と
ぼくはひとつになった。ぼくは絵描きなのだ。
▲ ▲ ▲
創造とは、作品の目に見える表情の陰で作用する生成のことである。
知的な人間はみな、それが起こった後になって知るが、
創造的な者は前もって知っている。
彼が総合工芸学校バウハウスで教鞭を執っていた頃に書かれたというクレーの日記文を読みながら、ミュージアムの中を行きつ戻りつしていましたが、そんな中で わたしの興味を引いたものの一つに、「文字絵」がありました。 これは一つの試みとして、文字を描き込み、それに彩色したもので、言葉と絵画を直接結びつけた作品です。下の文字絵は、中国の王僧孺の詩のドイツ語訳をテキストにした絵です。小さな絵ですが、素敵だと思いませんか?

・・・ああ、私の苦悩をさらに苦くするもの、それは君が私の心を予感だにしないこと・・・
彼について、ちょっと触れて知り得たことだけでも書きたいことが頭の中いっぱいに広がってしまいました。
健忘がちな頭の中を整理するのにブログは打って付けなので、読んでくださる側の大変さも考えずに( ご免なさい!)つい打ちまくってしまいますが、まだまだ書きたりない気分。パソコンの不調もあり遅れた分、早くアップをしないと新鮮さが失われるようなのでこの辺りで・・。ふぅ。。
ご免なさい!)つい打ちまくってしまいますが、まだまだ書きたりない気分。パソコンの不調もあり遅れた分、早くアップをしないと新鮮さが失われるようなのでこの辺りで・・。ふぅ。。
★この展覧会の最終日は2月28日です。また、佐倉市にある川村記念美術館でも6月24日からパウル・クレー「創造の物語」展を開催するようです。ちょっと遠いけど私の好きな美術館の一つです。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
いつものように、展覧会の後のお楽しみは友人とのランチタイム。
今回は友人の娘さんの勤め先のある東京ビル(TOKIA)に、娘さんお勧めのお店があるとの事でそこに決まり。
TOKIAは東京中央郵便局と東京国際フォーラムの間にあり、線路を行き来する電車を眺めながら、3階にある自然食彩ビュッフェ「食彩健美 野の葡萄」で、野菜たっぷりの食材の数々を頂きました。ランチが一律1600円で、時間制限1時間半です。
2階には線路側に向けて、休憩のできるゆったりした赤いイスが5ツほど置いてあります。
ずべてふさがっていたので、3階のベンチで様子を見ていましたが皆イスにへばりついて、ちっとも空きができませんでした。


うわ~欲張ってるゥ~!きもワリィ~!












 1953年「街」 顔料・和紙
1953年「街」 顔料・和紙
 1957年「アンスタンタネイテ」
1957年「アンスタンタネイテ」 1978年「宇宙1」
1978年「宇宙1」 佐藤助雄 「桃源」 1983年
佐藤助雄 「桃源」 1983年 「EVE」
「EVE」 に表情がとても似ていたんですもの。
に表情がとても似ていたんですもの。






 。・。・
。・。・ 




 )
)
 ウゥゥ・・
ウゥゥ・・ でもやっぱり、私だって行ってみた~い!!
でもやっぱり、私だって行ってみた~い!!








 なんですョ。)
なんですョ。) 日記を書かない私の行動の記録の一部分に
日記を書かない私の行動の記録の一部分に

 としか
としか の向こうで話していたにも拘らず、疑問視していました。
の向こうで話していたにも拘らず、疑問視していました。 ↓
↓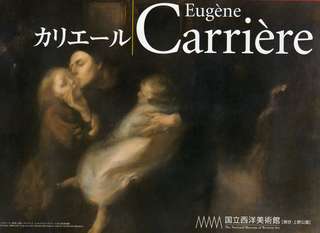








 ―
―

