4日(金)。NHK交響楽団の公式サイトによると、大阪フィル、読売日響でコンサートマスターを歴任した長原幸太が、4月1日付でN響第1コンサートマスターに就任しました ちなみに長原氏は東京藝大 ⇒ ジュリアード音楽院で研鑽を積みました
ちなみに長原氏は東京藝大 ⇒ ジュリアード音楽院で研鑽を積みました 広島県出身で、広島カープファンとしても知られています
広島県出身で、広島カープファンとしても知られています
一方、読売日響の公式サイトによると、2021年から読響のコンサートマスターを務めてきた林雄介が、4月1日付で読響第1コンサートマスターに就任しました ちなみに林氏はウィーン国立音楽大学修士課程修了
ちなみに林氏はウィーン国立音楽大学修士課程修了 ドイツ・ヴッパータール響の第1コンサートマスターなどを歴任しました
ドイツ・ヴッパータール響の第1コンサートマスターなどを歴任しました 読売ジャイアンツファンかどうかは不明です
読売ジャイアンツファンかどうかは不明です
ということで、わが家に来てから今日で3734日目を迎え、米政治サイトのポリティコが、米電気自動車大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者が近くトランプ政権を離れる見通しだと報じたことを受け、2日の米株式市場でテスラの株価が前日終値と比べ5%上昇した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

政府効率化省を率いて 多方面で人員整理の大ナタを振るったからね 民意は”本来業務に戻れ!”だね





昨日、夕食に「ビーフカレー」「生野菜とアボカドとチーズのサラダ」を作りました ビーフカレーはブロック肉ではなく 切り落としを使いましたが、柔らかくて美味しくできました
ビーフカレーはブロック肉ではなく 切り落としを使いましたが、柔らかくて美味しくできました






佐藤正午「正午派2025」(小学館文庫)を読み終わりました 佐藤正午は1955年長崎県生まれ。1983年「永遠の1/2」で第7回すばる文学賞を受賞
佐藤正午は1955年長崎県生まれ。1983年「永遠の1/2」で第7回すばる文学賞を受賞 2015年「鳩の撃退法」で第6回山田風太郎賞を受賞。2017年「月の満ち欠け」で第157回直木賞を受賞。ほかに「Y」「ジャンプ」「身の上話」「小説家の四季」など多数
2015年「鳩の撃退法」で第6回山田風太郎賞を受賞。2017年「月の満ち欠け」で第157回直木賞を受賞。ほかに「Y」「ジャンプ」「身の上話」「小説家の四季」など多数

本書は2009年11月刊行の単行本「正午派」の増補版として新たに編纂された文庫オリジナルです 作家生活40年にわたる佐藤正午作品の集大成で、収録された短編小説やエッセイなどすべてが文庫初収録という正午ファン待望の「佐藤正午読本」です
作家生活40年にわたる佐藤正午作品の集大成で、収録された短編小説やエッセイなどすべてが文庫初収録という正午ファン待望の「佐藤正午読本」です
あまり熱心な読者ではない私は、本書を読んで初めて知った事実があります その一つは佐藤正午が2014年(「鳩の撃退法」が刊行された頃)に結婚していたことです
その一つは佐藤正午が2014年(「鳩の撃退法」が刊行された頃)に結婚していたことです これまで読んできたエッセイには「妻」という言葉も、「結婚」という文字も現れていなかったので、てっきり生涯独身で通すつもりでいるのかと思っていました
これまで読んできたエッセイには「妻」という言葉も、「結婚」という文字も現れていなかったので、てっきり生涯独身で通すつもりでいるのかと思っていました もう一つは、それに関連して、長年住んだ古いマンションから2階建ての新築住居に引っ越していたことです
もう一つは、それに関連して、長年住んだ古いマンションから2階建ての新築住居に引っ越していたことです 無知蒙昧の私は、この2つの事実に心底驚きました
無知蒙昧の私は、この2つの事実に心底驚きました
さて、今回初めて読んだ短編小説やエッセイに接して、「若い頃から一貫して、書き方のスタイルは変わっていないんだな」と思いました 2004年から足掛け6年間、携帯メール小説を対象に「佐藤正午賞」を授賞していますが、第46回の受賞作に対する佐藤氏の選評が載っています(2008年4月)。その冒頭には次のように書かれています
2004年から足掛け6年間、携帯メール小説を対象に「佐藤正午賞」を授賞していますが、第46回の受賞作に対する佐藤氏の選評が載っています(2008年4月)。その冒頭には次のように書かれています
「小説を書くのに必要なもの・・・皮肉とユーモアのセンス、と誰かが言っていましたが、今回はその言葉を思い出しながら選びました 」
」
まさに「皮肉とユーモア」こそが佐藤正午の小説やエッセイの大きな特徴です
また、同賞の「グランプリ2008」の選評では、小説の書き方について、次のように語っています
「小説を書いたことのある人ならわかると思いますが、1行目を書き出すのはわりに簡単です。先のことさえ考えなければ誰にでも書けます (中略)難しいのは、たぶん小説をどう終わらせるかなのです
(中略)難しいのは、たぶん小説をどう終わらせるかなのです 」
」
これは佐藤正午の小説やエッセイを読むとその苦労の跡が見えて、彼の言葉の意味がよく分かります 私が佐藤正午の作品を初めて読んだのは「身の上話」ですが、最後の1行を読んで「えっ
私が佐藤正午の作品を初めて読んだのは「身の上話」ですが、最後の1行を読んで「えっ  」と声を出して叫んでしまいました
」と声を出して叫んでしまいました まさかの展開が待っていたのです
まさかの展開が待っていたのです それ以来、佐藤正午の作品を片っ端から読むようになりました
それ以来、佐藤正午の作品を片っ端から読むようになりました
本書は佐藤正午が1955年8月25日に長崎県佐世保市に生まれてから、2018年の12月までの間に執筆・刊行した小説やエッセイ、サイン会などのイベント等を一覧表の形で紹介しています それと並行して、その時々に書いた短編小説やエッセイ(文庫初登場分)を紹介しています
それと並行して、その時々に書いた短編小説やエッセイ(文庫初登場分)を紹介しています いわば「佐藤正午のすべて」が収録されています。佐藤正午ファンにとっては文字通り「永久保存版」です
いわば「佐藤正午のすべて」が収録されています。佐藤正午ファンにとっては文字通り「永久保存版」です 佐藤正午ファンの方はすでにお持ちでしょうから、広く文学ファンの皆さんにお薦めします
佐藤正午ファンの方はすでにお持ちでしょうから、広く文学ファンの皆さんにお薦めします















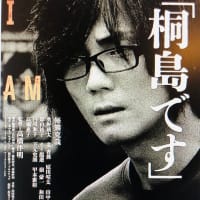





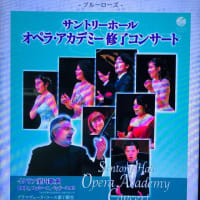





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます