毎日、毎日お弁当
大変だけど、どうやったら手際よくできるだろうか とか、楽をするコツは
とか、楽をするコツは とか、
とか、
そういうことを考えながら作業するのは、意外と快感。
ついでに、買ったばかりのカメラで、美味しそうに撮る練習も。
そのうちに、冷凍食品品評会になると思われるので、今、撮っておかないとね。
・パリパリ鶏の甘酢和え (夕食の残りをオーブンで焼きなおす)
・たまごやき
・ブロッコリー
・プチトマト
・フキ (おじいちゃんの家のフキを前の日に煮たよ)
・筍のカレー煮 (パパの会社の方が、裏山から採ってきた筍 )
)
・いちご
・煮豚 (夕食の残り)
・フキ
・プチトマト
・かぼちゃの蜂蜜煮 (レンジでチン!の3分料理)
・スナックエンドウ
・チーズ入りちくわ
・りんごとキウイ
・アスパラベーコン巻き
・プチトマト
・里芋の煮物
・デコポン
3月に購入した、お弁当の本。
簡単で美味しい♪キレイ♪色ごとに、メニューがわかれています。
中高生用には、分量を増やさないといけないけれど、適当に増やしても
なんとかなります。なんとかなるっていうのが、重要なポイントですね。
こんなに頑張って作ったお弁当、なんと、15分で食べないといけないんだそうです。
15分って、有り得ない・・・。どうにか、ならないのかしらん。
息子くん、家に帰ってくると、まずは、「今日も、頑張って全部食べたよ~」のご報告。
そのあと、急いで食べすぎて、何回むせたかを報告してくれます。
それから、今日のメニューは、むせやすいから15分弁当には、むかないとかを熱弁。
さすが、「夕飯をゆっくり食べられないから塾には行かない!」と宣言した男です。
食べることが、彼の中心であります。
(たぶん、お弁当 と部活
と部活 で、息子の中学生活は成り立っています)
で、息子の中学生活は成り立っています)
それが正しいと、今のところ、母も思っています。
ただし、テストの結果を見て、食事よりも塾に行けと、考えを翻す可能性もアリ。
新しいことが始まる春。
違う自分になれるような気がして、何でも出来るような気がして・・・大好きだったなあ。
だから、息子が、楽しそうに中学校に出かけていく姿を見ると、私まで、ドキドキ・ワクワク♪
そんな母だから、自己紹介カードを作成してくる・・・なんていう宿題が出た息子の横から、
どうしても、離れることが出来ず、ついに、「見るな!あっち行け!」と怒鳴られる始末。
けれど、中学校に入っての目標の欄に、「忘れものをなくす」と書いてあるのを、
しっかり見届けました。
小学校の時と、全く、同じ目標~ 情けないやら、嬉しいやら。
情けないやら、嬉しいやら。
そんな、中学生ライフ。
入学式の翌々日には、お弁当が始まり、その翌日には、部活に仮入部してきたという息子。
さらに、その翌日には、朝練でした
これが、入学式のあった週に、すべて起こったから、たまりません。
母は、慣れないお弁当づくりに四苦八苦。おまけに、朝練 勘弁してくれ~
勘弁してくれ~
で、週末の朝は、グッタリでした。
毎日のお弁当づくりを、ちょっとだけ、楽しみにしていた母だったのだけれど、
1週間で、自分の甘さを思い知りました。
中学生男子のお弁当箱は、大きいです。いくら詰めても、隙間があきます
3日間頑張って、学んだことは、
① 必ず、前の晩のおかずに、一つ煮物を作ること。(つまり、残り物弁当 )
)
② プチトマトと冷凍枝豆とフルーツを切らさないようにすること。
毎日、見事なお弁当をブログに載せておられる方々に、尊敬の念を抱きつつ、
今日から、また、私のお弁当の一週間がはじまりました。
(と言っても、今日は、昨夜のハンバーグの残りだけど・・・)
今週は、娘の自主保育の開所式があり、またまた、「新しい場所」に向かいます。
きっと、ゴールデンウィークぐらいまでは、落ち着かないだろうなあ・・・
それでも、春を楽しむ心の余裕だけは、残しておきたいです。
この数日間で、すっかり、半そでの陽気。春は、あっという間ですもんね。

先日、遊びにいった図書館のお話し会で、先輩から頂いた「クローバーの花冠」。
作り方を聞いたのに、やっぱり、帰ってきたら、忘れていました がっかり。
がっかり。
この固い頭が、憎らしい でも、あきらめずに、もう一度、挑戦してみたいと思います。
でも、あきらめずに、もう一度、挑戦してみたいと思います。
春さん、もう少し、ここにいてね。
 アリさんのお宅
アリさんのお宅 訪問?
訪問?
まだまだ寒い日もあるけれど、土の中は、もう、すっかり春です。
おままごと用の「つくし」摘みが日課となっている娘 ですが、先日、つくしの横に
ですが、先日、つくしの横に
大きなアリ の巣を発見
の巣を発見
大忙しで、巣の中の土を運んで外に投げています。その姿に、娘さん 釘付け
釘付け
巣と離れた所にアリ がいるのを発見すると、世話焼き・仕切りやの血が騒ぐのか
がいるのを発見すると、世話焼き・仕切りやの血が騒ぐのか
「こっちよ!こっちよ!」と、必死に、アリ に、巣の場所を教えます。
に、巣の場所を教えます。
当然ながら、アリ には、娘
には、娘 の気持ちは届かず・・・・・。
の気持ちは届かず・・・・・。
ならばと、強硬手段に打って出る娘 。無理矢理、
。無理矢理、 を巣に運びます。
を巣に運びます。
最初こそ、微笑ましい光景だわ~ とニコニコしている母ですが、さすがに、一時間近く
とニコニコしている母ですが、さすがに、一時間近く
アリ の巣の前にいると、気持ち的にも身体的にも辛いです
の巣の前にいると、気持ち的にも身体的にも辛いです
全く、子どもの集中力には、適わないなあ
天気が良い日 には、もう、日焼け止めが必要かもしれません。うむ~。買い忘れてる
には、もう、日焼け止めが必要かもしれません。うむ~。買い忘れてる
春の準備に忙しいのは、アリ だけでなく、人間もですね。
だけでなく、人間もですね。 お弁当用「シリコンカップ」
お弁当用「シリコンカップ」
こちら、4月から中学生になる息子のために買った一品。
去年の秋から始めた「生活クラブ」で求めた「シリコンカップ」です。
お弁当の仕切りのアルミカップを、その度ごとに捨てることに、以前から、抵抗が
あったので、これを見つけた時は、大喜びでした。
届いてみたら、その色に、さらに大喜び 春色です
春色です


他にも、お弁当の本を一冊と、娘と一緒にピクニックに行こうと、おすび用の
竹のランチボックスも購入。
春の準備 、着々と、です。
、着々と、です。
曇り の予報が、青空
の予報が、青空 でした。
でした。
キラキラの暖かい春の日。あの小さかった息子の、小学校の卒業式。
例年より1週間近く早い日取りは、
「三連休の後では、担任が子どもたちの様子を把握することができないから」
という理由だと、懇談会で説明を受けました。
そんな説明に、思わず頷いてしまう程、元気な・・・元気すぎる、やんちゃな学年でした。
はじめての授業参観では、座っていられない子の多さに呆然 としたのを、今でも、
としたのを、今でも、
はっきり覚えています。
毎日、誰かしらの体操服や上履きがなくなってしまう クラスの時もありました。
クラスの時もありました。
「休み時間に一人でいると、アリバイがないから、先生に、犯人だと疑われるんだよ。」と
息子が教えてくれた時には、卒倒 しそうになったっけ。
しそうになったっけ。
毎日、「取っ組み合いの大喧嘩」が一つは起き、誰かしら保健室送りになる!
というクラスになった事もありました
息子の破かれたノートや青あざを見る度に、泣きたい気持ちになった日々。
どの一線を越えたら、先生に相談すればよいのか?自分の中で、その線引きに迷い、
電話とにらめっこの日々。
そのクラスでは、とうとう、いじめにエスカレートして、学校に来れなくなる子まで出て、
先生は、女の子達の反抗に堪えられず教室で泣いてしまったとかで、懇談会は、
教頭先生が付きそう始末。
本当に、ハラハラしっぱなしの4年間でした
5年生になって担任が変わり、子どもたちの有り余るパワーが、別の所に、向かうようになりました。
残念ながら、息子のクラス以外では、パワーの使い道が、プラスの方向に向くことが出来ず、
ひどい悪戯を受けて学校に来れなくなった子や、喧嘩の繰り返しになってしまったクラスも・・・
先生への反抗がエスカレートし、学校の備品がことごとく破壊され、先生にパンを投げつけるは、
床に牛乳は撒き散らされるは、デザートの生クリームは、ご丁寧にビニールにつめられ、
先生に落とされる・・・という惨状。(キンパチセンセイ?)
校長先生が巡回し、6年の2学期を過ぎてからは、息子の担任の先生も、しょっちゅう、
応援に出かけるようになりました。
正直、同じクラスのお母さん以外には、申し訳なくて、担任の先生の話など、出来ない位の
状況だったのです。
それでも、卒業式。
緊張気味の子ども達の顔は、どの子も、みんな同じように輝いて いました。
いました。
卒業証書授与の場面で、校長先生が、困ったちゃんの子どもたちに、長々と声をかけている
場面を見て、クスリと笑えてしまうほど、どの子もあどけないのです。
どの子もみんな、同じ。悪い子なんて、いないのですよね。
パワーの使い方を、ちょっと間違えてしまっているだけなのです。
どうにかならなかったのだろうか?答えは、私の中でも、まだ見つかりません。
さて、そんな卒業式が終わった後の最後のホームルーム。
後から、保護者たちがクラスに到着し、「さあ、花道に向かうために廊下に並びましょう」
となったとき、先生が、おっしゃいました。
「さあ、みんなで最後に暗唱しよう。間違えてもいいからねー!」
詩は、もちろん、『雨ニモマケズ』。先生は、やっぱり、最後まで、先生だったなー。
その後は、子ども達、特に、先生を熱狂的に支持していた男の子達 の涙が止まらず、
の涙が止まらず、
先生も、つられて泣き出してしまう というハプニング。
というハプニング。
周りで見ていた母親達も、涙 涙
涙
強がりの息子くんは、最後まで涙を見せることはありませんでしたが、やはり、先生から
離れることが出来ないようでした。
でもね、と、帰り道に息子が、教えてくれました。
「卒業しても、時々は遊びに来て、ドッチボールしていいんだって。ボールは、
貸してあげるけど、出来たら、持ってきてくれると嬉しいって言ってたよ、先生。」























ほーんとに、楽しい2年間だったね。
本物のオヤジ先生の言うオヤジギャグ。はじめて貰ったゲンコツ
放課後、一緒に野球をやってもらったこと。
詩を通して、自分を表現する素晴らしさを教えてもらったこと。
テストの前は、家で勉強するものだということも、間違えたテストこそ大切なのだということも、
教えてもらったね。
社会は、調べることの大切さ、理科は、観察することの大切さを教えてもらった。
(あまりに面白く、素晴らしいノートが完成していくので、母は、いつも楽しみにしていたのです )
)
図工では、どんなに夢中になっても、時間がかかってもいいんだということを、はじめて
許してくれた先生でもありました
何より、クラスみんなで作り上げることを、大切にしておられた先生でしたね。
思い出すのは、「行ってきます。」と出て行った後、友だちに意地悪されて、泣きながら帰って
くる息子を、こちらまで泣きたくなるのを我慢して、送り出した日々。
殴ったり、蹴ったりされた経験のない息子に、喧嘩のやり方を教えた日々。
辛いことも、悲しいことも、悩んだことも、もちろん一杯あったけれど、それすらも、
この日につながっていたのだと、思えてくるから不思議です。
(今は、立派に喧嘩 もこなすようになったことが、正しかったかどうか
もこなすようになったことが、正しかったかどうか これも答えが
これも答えが
出ないままなのですが・・・・・・・・)
素晴らしい先生、楽しい仲間、そして、親友と呼べる友との出会い。
何より、素晴らしい笑顔で卒業証書を抱くことが出来たこと、これに勝る幸せがあるでしょうか。
ハラハラしっぱなしだったけれど、君のお母さんで、本当に良かった
ありがとう。ありがとう。ありがとう。
もう、体操服いらないって。
もう、絵の具いらないって。習字の道具も、裁縫箱も。
理科も社会も、今日で、終わりだって。
一つ一つ、「終わり」の授業が増えていって、とうとう、算数と国語と卒業式の練習
しか、授業がなくなりました。あと3日で、卒業式です。
そして、迎えた、最後の「詩の授業」。
卒業に向けた今の想いを、何でも良いから、色紙の上に、好きなもので表現して
みようと言われ、息子は、桜の絵と「絆」の一文字を書きました。
「絆」って、書いたんだ!と息子が教えてくれたとき、心の中で「なんだ詩じゃないのか」
って、ちょっとガッカリした母さんでしたが、いいえ、それが一番息子らしいのだと、今は、
心から思います。
形になんて囚われず、自由に、心のままに表現する。表現することの素晴らしさ。
それが、一文字だって、格言だって、絵だって構わない。
それこそ、息子が、2年間かけて、先生から学んだことでした。
スポンジのように、先生から、色々なことを吸収した2年間だったと、改めて思います。
そんな先生が、最後の最後に選んだ詩は、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」。
暗唱しようと言われたとかで、何度も何度も読み込んで、宿題に、国語のノートへの
書き取りが出た日もありました。
3月に入ってから、何度も、クラスみんなで、声をあげて読みあったのだとか。
息子が言うには、どんどん声が大きくなって、最後に「ワタシハナリタイ!」と、みんなで
声を張り上げるのが(たぶん、男子だけだと思うが)、とにかく、面白いのだそうです。
誰が、一番声がデカイとか、誰は、顔を真っ赤にして叫んだとか。
そんなことを、楽しそうに話します。詩の内容は、あれ?どこかに忘れているみたい
この詩の凄さ、素晴らしさ、この詩のように生きることの難しさを理解できるのは、
まだまだ、先のことかもしれなくて、
今は、ただ、みんなでふざけて読んで楽しかった!という思い出でしか、なかったとしても、
それでも、卒業を前にして、先生が選んでくれたのがこの詩であったということに、いつか、
感謝する日が来るんだろうなと思います。
もしかしたら、その時、はじめて、スゴイ先生に教えてもらったのだと気づくかもしれません。
心の奥底に残った言葉が、ふとした時に蘇ってくる日が、いつか、きっとあると思う。
その時、みんな、どんな大人になっているんだろうね。
先生、子ども達に、素晴らしい授業のプレゼントをありがとうございました。
雨ニモマケズ 風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク 決シテ瞋ラズ イツモシヅカニワラッテヰル
一日ニ玄米四合ト 味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ ソシテワスレズ
野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ
東ニ病気ノコドモアレバ 行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ 行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ
南ニ死ニサウナ人アレバ 行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ
北ニケンクヮヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ
ヒドリノトキハナミダヲナガシ サムサノナツハオロオロアルキ
ミンナニデクノボートヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ
サウイフモノニ ワタシハナリタイ
お友だちから、春風のような絵葉書が届いた日、村上春樹のエルサレム賞授賞式を
めぐってのインタビューと、講演の原文が掲載された「文芸春秋」を手にしました。
読みながら、また、涙が込み上げてきて、何度も何度も、
「どうか、この世界が、良いほうに進んでいきますように」
と、祈らずには、いられませんでした。
世界中の人たちに、春が訪れますように・・・・・・。
本当に、全文を読んで良かった!
一つ一つの言葉が、深く深く、胸に沁みていく、そんな文章でした。
これは、ファンだから・・・だけでは、ないと思うのです。
どうか、多くの人に読んで貰えますように。そして、多くの人が、このことについて
考えてくれますように。
「文芸春秋」は、今日発売です。(立ち読みできる量です)
私は、あの夜から、何故か、ずっと頭にちらついている『世界の終わりとハードボイ
ルド・ワンダーランド』を、再読したいな。
 グツグツグツグツ いいにおい♪
グツグツグツグツ いいにおい♪
5月生まれのせいか、初夏の頃が大好き♪
今年のバレンタインデイは、2月であることを忘れさせる、そんな陽気でした。
喜んでよいのか?・・・・・・・いやいや、やっぱり、2月は、もっと寒くないと駄目。
今年は、とうとう、一度も積雪なしの冬になりそうで、
なんだか、とても大切なものを失ったような気がして、悲しくて仕方がないのです。
そんなバレンタインデイに、頂いたまま放置されていた「夏みかん」をマーマレードにしました。
途中、娘が大騒ぎで、料理どころでなくなったのだけれど、息子の友だちのママが、
娘を公民館のお祭りに連れて行ってくれるという、なんとも嬉しい申し出が。
人見知りしない娘は、ママに軽く手をふって出かけていきました。
ママが望みさえすれば、すでに、手が離れている感のある娘さん。
喜んでいいのか?・・・・・・・いやいや、これは、素直に喜んでおきましょう。
去年、煮つめすぎて、大失敗だったマーマレード。
「もう少し煮詰めたほうがいいかな?」のタイミングで火を消すと教えてもらいました。
でも・・・・・・・・・・・。
「もう少し煮詰めたほうがいいかな?」と、どの程度で思ったらいいのかがわかりません(笑)
しゃもじで、グルグル。グルグル。グルグル。
何度も迷って、そのタイミングをはかりました。
なんだか、魔女になった気分。終わってみれば、なんとも楽しい、グルグルの時間でした。
自分で作るマーマレードは、なんと美味しいのでしょう。
マーマレード作り。ちょっと、はまりそう。
-----------------------------------------------------------------
さてさて、それから一日おいて月曜日。今日は、一転、冬の空でした。
ニュースで、村上春樹のエルサレム賞の授賞スピーチを聞きました。
彼の授賞に異を唱えていた方々が、満足したか?満足しなかったか?は、わかりません。
あの場所にいたイスラエルの方たちが、どんな気持ちを抱いたのかもわかりません。
でも、ファンとして言わせて頂ければ、そんな次元を超えたところに、村上さんは
いるんだなと思う、そんなスピーチでした。
村上さんの真っ直ぐな気持ちが、ストレートに届いて、心が痛いくらいでした。
それは、たぶん・・・・・・私だけではなかった。それだけは、わかります。
あの場で、あの席で、起立して拍手を送った方が、あんなにもいたこと。
言葉は、時に誤解や衝突を生むけれど、やはり、言葉は、人間の宝なのだなと思いました。
はじめて、ニュースというものをビデオにとって、3回再生して、3回泣きました。
(パソコンがあるのだから、動画を観れば良いのかと、先ほど気がつきました)
壁は、イスラエルにだけあるのではない。世界には、自分こそが「正しい」という
正義の壁が立ち並んでいます。だとしたら、
いつでも卵の殻の側に寄り添える、そんな正義を私も選びたいと思いました。
ああ一つ 前の席なら 受かった、と
宝くじかよ! 受験番号
予想通り・・・・・いや、残念ながらと言うべきでしょうね。
息子の受験の結果は「不合格」でした。
答案用紙を半分白紙で出した時点で、今日の結果は、予想していたようなのだけれど
息子は、自分の一つ前の受験番号が合格だったことが気になって仕方ない。
で、何を言うかと思ったら・・・・・・・・・
「あー。一つ前の席だったら良かったのに。惜しいなー」
夕方、大くんの散歩をしている時に、近所のお友だちとパパに会い、
(お友だちも、残念ながら不合格 )
) 「そういう問題かよっ!」と、突っ込まれていた息子なのでした。
「そういう問題かよっ!」と、突っ込まれていた息子なのでした。
駄目だと判っていても、やっぱり、どこかで「かすかな期待」をしていた
母同士は、そんな、「悲しかったのは、駄目と聞いたときだけ」の息子たち
(大抵のことは、3歩歩くと忘れる息子たち)
の様子に、呆れながらも、少し元気づけられ
「さあ!高校受験は、今日から始まったのよ~!」と、狼煙をあげたのでした。
残念なのは、当の本人たちが、ちっともその気ではなくて、すっかり
「じゅあ、部活、何に入ろうか?」モードに入っていること。
剣道部で決まりのはずの息子は、たぶん、ちょっとだけ
「実は、すごいピッチャーになれるかもしれない」と思っていて、
野球部への未練がある様子。
似た者同士の友だちは、息子と一緒に、いつも運動会で痛い目に会うのだけれど
やっぱり、ちょっとだけ、
「実は、サッカーやバスケの選手になれるかもしれない」と思っていて、
二人とも、夢が、想像が、ぐんぐん広がります。
現実を知っている母たちは、そんな息子たちを温かく・・・・・見守ってあげなくては
いけないと思いつつ、ついつい、心配してしまいます。
結局、この構図は、永遠と続くのね お互いに、タメイキ交じりの夕方なのでした
お互いに、タメイキ交じりの夕方なのでした
受験の日の朝 空は、ぴかぴかに輝いていて、それはそれは、美しくて・・・・・・。
空は、ぴかぴかに輝いていて、それはそれは、美しくて・・・・・・。
空を見上げていたら、不思議なほど、緊張はありませんでした。
(息子は、はなから緊張していませんでしたが)
前日、「明日の準備をしなさい!」と言ったら、何を思ったのか、洗面所で
「合成皮とスポンジ」で出来た筆箱を、ジャブジャブ洗い出した息子に、父も母も、
すっかり腰を抜かしてしまった

 ・・・という、お約束のハプニングあり
・・・という、お約束のハプニングあり
(いくら拭いても水 が垂れてくるのを見かねて、旦那がドライヤーをかけてくれました)
が垂れてくるのを見かねて、旦那がドライヤーをかけてくれました) 「もし、作文のテストの課題が『入試に向けて頑張ったこと』だったら、絶対に、
「もし、作文のテストの課題が『入試に向けて頑張ったこと』だったら、絶対に、
筆箱を洗ったことを書きなさいよ!」と言ったら、 「うん!絶対に、オレしかいないもんね!ナンバーワンだよね!!」と、
「うん!絶対に、オレしかいないもんね!ナンバーワンだよね!!」と、
とびきりの笑顔で答えた息子くん。(オンリーワンの間違いだろう、君。)
そんな息子だもん。
「時間がなくて、半分ぐらいしかやれなかった 」
」 と、受験会場から、頭を抱えて
と、受験会場から、頭を抱えて
出てきたときも、母は、ちっともガックリきませんでした 頑張った。頑張った。
頑張った。頑張った。
出来そうな問題だったのにと、本人は、とても悔しそうだったけれど、仕方ないよね。
それもまた、今の実力。
それより、嬉しかった報告あり
作文のテストで、配られた原稿用紙一杯に、作文を書けたのだそうです。
母がはったヤマは、見事にはずれ 正真正銘、自分の力だけで書き上げた作文。
正真正銘、自分の力だけで書き上げた作文。
もちろん、入試の方は、量じゃなくて内容が重要だということは、わかっているけれ
ど、それでも、母は、嬉しいのです。
二年前、新しい担任の先生に代わって、頻繁に作文を書くことになり、
息子が、驚く・・・・というか、5年生として恥ずかしい程に作文が書けないことが、
判明しました。あわてて書かせてみた日記に、
きょう○○くんと△△くんとあそびました。とてもたのしかたです。
と書いてあるのを見たときの衝撃たるや!
これは、1年生並・・・いや、1年生の方が上手じゃないか
それから、約2年。作文力に力を注ぐ担任の先生は、 季節ごとに、画用紙に「詩と絵」を書く(消しゴムやトレーで作った烙印付き)
季節ごとに、画用紙に「詩と絵」を書く(消しゴムやトレーで作った烙印付き) 新聞のスクラップを作る(記事に対する感想や意見を付けて)
新聞のスクラップを作る(記事に対する感想や意見を付けて) 行事ごとの作文
行事ごとの作文 特別授業や遠足などで、お世話になった人へ手紙
特別授業や遠足などで、お世話になった人へ手紙 テープレコーダーから流れる物語の朗読を聴いて、内容を要約して書く
テープレコーダーから流れる物語の朗読を聴いて、内容を要約して書く 週に一度の日記提出
週に一度の日記提出 本の紹介 (息子が一人で本を読み出したのも、これがキッカケでした)
本の紹介 (息子が一人で本を読み出したのも、これがキッカケでした)
といった授業を、授業数が足りない中、少しずつ工面して、行ってくれました。
先日、宿題の日記のノートを覗いてみたら、ページ一杯に書かれた生き生きとした
文章が。
接続詞の使い方が間違っていたり、句読点がなかったり、誤字脱字があったりと、
まだまだ・・・・・・の息子ですが、書きたいことが溢れている!ということがスゴイ。
毎年、4月になると、自己紹介アンケートのようなものを書かされて、授業参観の時、
決まって、教室に貼り出されてあるのだけれど、いつも、読んでる方が恥ずかしくな
るような小さな字で、自信なさそうに書いてあって
(小さく書いたって、読まれるんだっつうの!)
がっかりしながら、戻ってきていたのを思い出します。
今、学校に行くと、いつだって、大きな自信たっぷりの字で書かれた詩やスクラップ。
ああ、この子は、2年間、先生が伝えたいと言い続けていたことを、体得したのだな
あと心から思うのです。(→★)
しかも、それを文章に表現する術を教えてもらったのです。
実は、受験は、今週末にもう一日あって(今度は、グループ討議のようなもの)、
本当は、まだ、緊張していないといけないのだけれど、母は、この作文の件で、
すっかり満足。
入試の採点会場に言って、「どうです!すごいでしょう!!」と叫びたい衝動にかられます
先生で、子どもは変わる 教育で、子どもは変わる
教育で、子どもは変わる 本当に、変わるのです。
本当に、変わるのです。
日本中の先生方、どうぞ、頑張って下さい


息子くん、こんなんですが、一応、受験生です。
気づかれないことが多いけれど、一応、受験生です。
受験のための塾も通信教育もやっていなくて、暗くなるまで、友だちと野球三昧。
全国学習調査では、自己申告どおり、半分も点数がとれなくて 学校の平均点を
学校の平均点を
大幅に減らした息子くん。
これで合格したら、たぶん、母には出版依頼(「たくさん遊んで合格する!」本とか)
が殺到すると思うのだけれど、
それでも、新設される中高一貫校に、自分で「行きたい 」と言って、
」と言って、
一年間、毎朝(キャンプの日は出来なかったが)、30分だけだけど早起きして、
勉強したことは(内容はともかく)息子としては、とてもとてもスゴイことでした。
いつの間にか、親の夢ではなく、自分の夢を抱く年頃になったのだと、眩しく思ったものでした。
それなのに、それなのに・・・・・・・・インフルエンザ
市内の学校が学校閉鎖になり、隣のクラスが学級閉鎖になり、いつかは、
来るだろうなあとは、思っていたけれど、やっぱり来たかあ。。。
予防接種を受けていたせいか、熱はあるけど元気一杯 それでも、受験のことを
それでも、受験のことを
話したら、お医者さんが、リレンザという薬を薦めてくれました。
「インフルエンザ菌を強くしないためにも、健康な人は薬を飲まないで治す」
がモットーの母も、しばらく悩んで、「お願いします。」を言いました。
そのせいか、今日は、朝から平熱で、熱が下がってから2日したら学校へ行って良い
ということなので、受験どころか、月曜日から学校にも行けそうです。
リレンザさまさま。。。
憧れの「学級閉鎖」が、とうとう、自分のクラスに訪れたにも関わらず、自分が
インフルエンザになってしまった息子くん。
それでも、欠席扱いにはならないって。皆勤賞、駄目にならなくて良かったね。
どうか、どうか、熱がぶりかえしませんように
日曜日。一問も解けなくてもいいから、精一杯、自分の力を出し切れますように
明けまして おめでとう ございます
色々あった12月でしたが、家族みな、無事にお正月を迎えられたこと、
とても、幸せだなあ・・・・と、つくづく噛み締めながらの今日の日でした。
こんなに風邪をこじらせたことないかも・・・ という位にこじらせた風邪は、
という位にこじらせた風邪は、
最後に、私の声を出せなくするという、とんでもない、残し物をしていきましたが、
それ以外は、すっかり、「さようなら」してくれたようです。良かった
マスクしながら作った御節料理も、家族には、評判上々で、これまた良いスタート
今年も、一つ一つの季節の行事を、子ども達と一緒に楽しんでいけたらいいな。
息子は、中学生になるけれど、その急激な流れにも、今まで通りのスタイルで
望んでいきたいなと思います。
そんな訳で、今年の息子の年賀状~
去年の芋版のリベンジを誓っていた息子でしたが、12月が、未だかつてない
大変な月だったので、計画していた木版画はやめ、消しゴムはんこになりました。
それでも、まあ、味のある彫りが出るのは、何故?子どもマジック
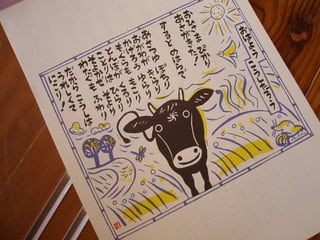
作品が出来上がってから、今年も購入した「のはらうたカレンダー」をめくったら
なんだか、似た子が出てきました あらあら
あらあら
今年のカレンダーは、なんと、旦那さまが「注文しないの?」と、リクエストして
注文したのです。
あんなに、そんなのをトイレに置いたら、息子が、ますますトイレから出なくなる
と文句を言っていたのにね
去年は、一年間、元気な「のはらうた」が、トイレから響いていましたが、
さすがに、中学生の息子は、朝から詩を大声で朗読したりしないだろうな・・・
そんなことを考えたら、なんだか、胸がキュン となりました。(トイレの中だけど)
となりました。(トイレの中だけど)
卒業式まで、あと2ヶ月以上あるのに、今からこれで、どうしましょう
こんな、相変わらずの私ですが、
みなさま、どうぞ今年もよろしくお願いいたします


今年も、たくさんの素敵な本、楽しい本と出会える年でありますように。
小さなきらきらを、一つ一つ、心に刻んで歩んでいける年でありますように。

『ファーザー・クリスマス』。
指輪物語で有名な作家トールキンのユーモアと愛情がたっぷり詰まった、この本を
息子と一緒に楽しんだのは、去年の12月のことでした。
それ以来、本は一度も開いてはいないのだけれど、クリスマスの話になると、息子の
口から出るのは、この本で語られるサンタクロースの生活ぶりのことでした。
そして、今年、この本が大活躍。
そうです。この本と同じように、サンタクロースから、息子に手紙 が届いたのです。
が届いたのです。
来年は中学生の息子。
我が家では、両親からのプレゼント、両家のおばちゃん達からのプレゼント、
両家の祖父母からのプレゼント、それに、サンタクロースからのプレゼントという、
たくさんのプレゼントが、いつも、ツリーの前に並びます。
この状態をいつまで続けるのか?何度も、何度も、夫婦で話し合いました。
本当は、息子が、自分から卒業してくれるのが一番だったのですが、どうやら、
息子くん、サンタクロースを未だに信じているらしい。
いや、もしかしたら、プレゼントをもらうために信じているのかもしれない?
なんて、話し合いは、いつも平行線。
パパは、「中学生になったら、当然、サンタは卒業だ!」の意見をかえず、そこで、
私も、最後に手紙を渡すことで、卒業にしようということになりました。
手紙を渡すことで、サンタクロースの手伝いをしている人のことがバレてしまうのでは?
クリスマスを前に、もう一度悩んだけれど、そこは、6年生。
それはそれで、私達の気持ちを理解してくれるだろうと決心しました

手紙 は、もちろん、トールキンの本を片手に、寒さに震えた文字で決まりです。
は、もちろん、トールキンの本を片手に、寒さに震えた文字で決まりです。
しかも、スペシャルにふさわしい内容にしようと、息子の好きな推理小説風の
「暗号」付きの手紙にしました。
まずは、娘へのプレゼントと並べて、息子への手紙。
そこに、プレゼントの「ありか」が隠された暗号が書かれているという寸法です。
それだけでは、つまらないと、母さん、調子にのりました。
 最初の暗号を解くと、まずは、一つ目のプレゼントと、さらに、暗号付きの手紙。
最初の暗号を解くと、まずは、一つ目のプレゼントと、さらに、暗号付きの手紙。
 その暗号を解くと、またプレゼントと暗号付きの手紙。
その暗号を解くと、またプレゼントと暗号付きの手紙。
 最後の最後に、息子が欲しいと言ってサンタへの手紙に書いていた「漫画」の
最後の最後に、息子が欲しいと言ってサンタへの手紙に書いていた「漫画」の
入った袋と、今まで手紙をありがとうの手紙。
差出人は、もちろん、「北極 崖屋敷 サンタ・クロース」です。
内容は、「私って、詐欺師?」と思うほどスラスラと書けて、自分でも驚いてしまいました。
もしかしたら、サンタクロースが、本当に、のりうつったのかもしれないと、今でも
思うくらいです。
そのせいか、最後のプレゼントに添えた手紙にも、「さようなら」とか「最後」の文字は、
書かれませんでした。
「これからもずっと、わしを忘れないでいておくれ。」 どうして、さようならを書かなかったのか。その答えは、きっと、サンタ・クロースだけが
どうして、さようならを書かなかったのか。その答えは、きっと、サンタ・クロースだけが
知っているのでしょう。
暗号は、新聞の文字を切り貼りする作業で、とても一人でこなせなくなった為、
旦那さまが、心良く引き受けてくれました。それにしても・・・・・・
プレゼントの隠し場所をシャッフルして、貼り付けていくときの気持ちの高揚たるや!!
夫婦で、ワイワイと作業。なんとも、楽しい時間でした♪ そんなこんなで、駐車場の車の中から、息子のベッドの横の引き出し、最後は、
そんなこんなで、駐車場の車の中から、息子のベッドの横の引き出し、最後は、
屋根裏部屋にまで隠されたプレゼントをめぐって、クリスマスの朝は、大変な
事件がおこりました。
私は、娘が泣いていたので一緒にいられなかったのだけれど、旦那が教えてくれたには、
最初は、手紙 だけが置かれているのを見て、涙すら浮かべていた息子が、どんどん
だけが置かれているのを見て、涙すら浮かべていた息子が、どんどん
手紙に引き込まれていくのがわかった!のだとか。
ばれちゃうかなあ・・・・・そんな不安も、全く、見当違いに終わったようです。
旦那が、夜、私に「驚いたよ。」と声をかけました。
息子くん、サンタ・クロースからの手紙を、大切そうにリボンで結び
(いつも、私が書いてあげる誕生日カードなんて、1週間ぐらい、リビングに放置してある
のだけれど)、愛おしそうに抱えて階段をあがっていったとか。
そして・・・・・・・・そのとき、興奮あまって、ブツブツと独り言を言っていたのだそうです。
「ありがとうサンタ ありがとう。ありがとう。ああ。これで、もう、充分だよ!!」
ありがとう。ありがとう。ああ。これで、もう、充分だよ!!」 「あいつ、やっぱり、本気で信じてんだな」ーって、旦那。
「あいつ、やっぱり、本気で信じてんだな」ーって、旦那。 本当にねえ。
本当にねえ。
この12年間、ずーっと、ずーっと、サンタ・クロースとの時間を大切にしてきて良かったねえ。
でもね。その息子のひとり言を聞いて、私も教えてもらった気がするのです。 サンタ・クロースは、プレゼントを用意する人にも、大切な大切なプレゼントを
サンタ・クロースは、プレゼントを用意する人にも、大切な大切なプレゼントを
くれていたのだなあって。
小さかった息子と一緒に書いた、サンタへの手紙のこと、旦那と二人、夜中にこそこそ、
プレゼントを用意したこと。すべてが、夢のように思い出された素晴らしい瞬間でした。
サンタ・クロースよ、息子よ、本当にありがとう。
メールの確認すら出来ない日々が続いていました。
私の首のムチ打ちから始まった負の連鎖は、とどまるところを知らず

クリスマスの前の週には、4年間皆勤賞だった息子をノロウイルスに倒れさせ

(嘔吐しながら「最後の皆勤賞が~
 」と泣いた息子)
」と泣いた息子)そして、サンタクロースの仕事を見届けた母を、クリスマスの晩に、倒れさせました

大人になってからは、めったに、お目にかからなかった39度代の熱

そして、嘔吐、倦怠感。それが、二日も続いた所で、さすがに旦那に
「病院に行くように」と、言われました。
結果は、
「インフルエンザにしては、熱以外の症状(咳や鼻水)がない、ノロウイルスにしては
熱が高すぎるし、嘔吐が軽い。随分、やっかいなのをもらってきたねえ~。」
という、現代医学とは思えぬ言葉
 を頂き、
を頂き、「母乳あげてるなら、カロナールだけしかあげられないから。まあ、熱が少しでも
下がれば、今よりは、楽になるでしょう。」
と、トホホな結果

だーから、病院なんて、行きたくなかったのにさー
二時間も待ったのにさーと、心の中で、旦那に八つ当たりしてみたりして

でも、看護婦さんが、ものすごく出来た仕事をされる人で、久しぶりに、胸が熱く
なりました。
嘔吐用のビニール袋片手に、
「あー。こういう仕事をしたいもんだなー」と、つくづく感じ入る私って、どういう性格なのでしょう。
看護婦さんの素晴らしい
 心配りと声かけのおかげで、裏のベッドで休んでいる
心配りと声かけのおかげで、裏のベッドで休んでいるうちに、すっかり、体も軽くなった気がし、まあ、どのような状況でも得るものは
あるのだなあと、思ってみたりして

そのような訳で、本日、四日目。
ようやく、ようやく、午後をまわっても、平熱をキープ。治ったかも

お昼ごはんも、久しぶりに、ちゃんと食べることが出来ました

気が付けば、クリスマスは終わり、あちらこちらで掃除機の音。
今年のクリスマスは、娘のプレゼントに、息子には、サンタさんからの手紙が始めて
届くという
 特別な年だったのにも関わらず、この状況。
特別な年だったのにも関わらず、この状況。本当に、情けないなあ~

久しぶりに外に出て、クリスマスなんて、実は、夢だったのじゃないか?と、
思ってしまったのだけれど、
ここでは、サンタさんの仕事を忘れないうちに、クリスマスのこと、
ぼちぼちと書いていけたらいいなと思っています。
 枯葉のベッドで遊んだよ♪
枯葉のベッドで遊んだよ♪
いつの間にか、カレンダーは、12月。
師走を前にして、病院通いの忙しい毎日を送っていました。
始まりは、私。娘をおんぶしようとしたのだけれど、悪戯娘が、ふざけて後ろに
引っくり返り、そのまま、一緒にドーン
・・・・・・・・そのまま、起き上がれず ホント、年はとりたくない
ホント、年はとりたくない
「骨が何ともなくて本当に、良かったね。」と、整形外科の先生に慰めてもらいましたが、
ムチ打ち状態の首は、2日間、痛みのために動かすことが出来ず。くすん。
そして、首をやった日。当然ながら、娘 から目を離している時間が長く・・・・・・・
から目を離している時間が長く・・・・・・・
その日の夜、娘の鼻が、片方だけ、やけに詰っていることに気が付きました。
夜中の授乳も、かなり苦しそう。。。(母は、首が苦しかったけど)
翌日、「吸引してきてもらって」と、パパに頼んだら・・・・・・・なんと
鼻づまりの原因は、オシロイバナの種だったのです

ああ・・・たしか、あの日、娘と散歩して、種を集めて遊んだのだった
外来の看護婦さんが呼び集められ、みんなで羽交い絞め


念のため、スコープで全部検査して、ようやく、帰ってきたのだとか。
風邪だと思って、耳鼻科に行かなかったら、どうなっていたんだろう・・・オソロシイ
全くもう
 の娘を連れて、その翌日は、インフルエンザの予防接種。
の娘を連れて、その翌日は、インフルエンザの予防接種。
ふー。なんだか、あっという間の一週間だなあと思っていたら、最後の最後に、
とんだ通院が待っていました。
旦那が、持病の腰痛でダウン。歩けないほどの痛みに、今度ばかりは手術に
なるかもしれないと、大学病院を受診し、2週間の療養を言い渡されました。
療養休暇という名の休日は、私が、日ごろ、どれだけ家事を分担してもらっているかを
思い知らせてくれました。
おまけに、朝晩の大くんの散歩です(いつもは、一回ずつの分担)。
なんと、たった数日で、1キロの体重減
いやあ。一人で頑張っているお母さんは、なんて、偉いんだろう。恥ずかしかったデス
もちろん、娘が昼寝をしたからと言って、パソコンに向かう訳にもいかず
そして、本日、MRI検査。その後、手術が必要かどうかの診察です。
ようやく、車の運転も出来る位に回復してきたので、今日は、送り迎えナシ。
どうなるのかなー。
そんな、大変な日々を過ごしていましたが、落ち込んでばかりいた訳でもなくて、
ちゃんと、サンタクロース の仕事も、こなしておりました。
の仕事も、こなしておりました。
我が家の父と母からのプレゼント は、毎年、本と決まっているのだけれど、
は、毎年、本と決まっているのだけれど、
壊し屋の娘に絵本をプレゼントする気になれず、今年は、私が、布絵本を作ることになりました。
忙しい毎日を、ますます忙しくさせていたのは、このサンタ の針仕事のせい。
の針仕事のせい。
ちくちくちくちく
娘が寝ている時限定の針仕事は、ちっとも、はかどりません。
で、左開きの本の予定が、右開きになってしまいました。
ホント、焦って仕事をすると、ろくな事がないです
 刺繍より、スナップ付けの方が難しいことが判明
刺繍より、スナップ付けの方が難しいことが判明
それでも、ようやく、土台の完成が見えてきました。
童謡の絵本にするか、動物の絵本するかと考えていましたが、「おままごと」命
の娘 のために、「お出かけ用おままごとセット」を作ることにしました。
のために、「お出かけ用おままごとセット」を作ることにしました。
表紙をめくると、お皿が出てきて、そこに料理がマジックテープではれる予定。
本屋さんで立ち読みした 「シール絵本」をヒントに作っています。
「シール絵本」をヒントに作っています。
昔、買ったはずの「マジックテープが貼れる布」やら、ためこんでいた「フエルト」やらを、
納戸から引っ張り出してきての大仕事
さあ、クリスマスまでに完成するのか
「トイザラスには、負けないよ 」と、息子に大見得きってしまった母。
」と、息子に大見得きってしまった母。
早く、食材作りにとりかからなければ・・・・・・・・と、少々焦り気味。
サンタの仕事は、ここからが勝負です
 手元の本は、この写真よりも、もっと淡い色づかいなのだけれど。
手元の本は、この写真よりも、もっと淡い色づかいなのだけれど。
『深呼吸の必要』 長田弘
大切な人が辛い思いをしているとき、周りにいる人に、一体何ができるだろう?
何もできない、自分の未熟さに腹が立ちます。
もう40歳にもなるといのに、出来ることと言ったら、心配することだけ。
心配なんて、なんの解決にもならないのに、それでも、心配することしか出来ません。
どうか、この心配の心が神様に届いて、あの人と私に、素敵な魔法をかけてくれないかな・・・
ざわざわざわの心を持て余して、もうどうしようもなくなって、昨夜、一冊の本を手に取った。
私が、はじめて、長田弘という詩人と出会った本。
仲良しの友だちが、誕生日に贈ってくれた本。
この本を開くたび、友だちのことを思い出し、友だちが暮している故郷を思い出し、
そこで暮している家族のことを思い出します。
「あのときかもしれない」
を読むたび、子どもの頃の自分を思い出し、美しかった故郷の自然を思い出し
自分が、どんなに輝く世界の中で育ってきたのかを確認し、幸せで胸が一杯になります。
「路地」
という詩にたどり着くと、その後の人生に想いが巡ります。
故郷を出てからのこと、出会った人のこと、旅のこと。
そして、ばらばらと本をめくり、最後に必ず読む詩が、
「散歩」
迷ったときは、いつもこの詩を手にとります。
ただ歩く。手に何ももたない。急がない。気に入った曲がり角がきたら、すっと曲がる。
この出だしが大好き。
そして、歩こうと思う。ゆっくりと、ゆっくりと。一歩、一歩。
・・・・・・・・・・どこけへゆくためにでなく、歩くことをたのしむために街を歩く。とても簡単なことだ。とても簡単なようなのだが、そうだろうか。どこかへ何かをしにゆくことはできても、歩くことをたのしむために歩くこと。それがなかなかにできない。この世でいちばん難しいのは、いちばん簡単なこと。










