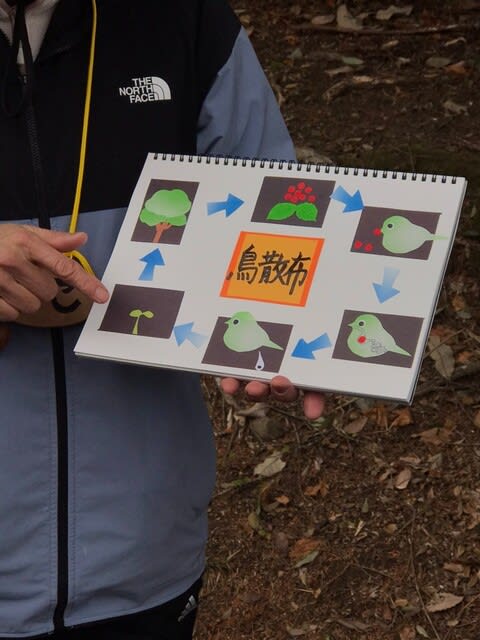5月のテーマ 【植物と刀】切っても切れない仲とは~
刀鍛冶の町関市、刀と植物の意外な関係を探ってみよう♪
展望台目指して出発!
ホオノキ

大きな木なので見上げての観察です。ちょうど大きな花を咲かせていました。
この木で刀の鞘が作られます。
適度な柔らかさで加工しやすく錆の原因となる灰汁や油分が少ないためです。
カツラ

たたらの神様「金屋子神」が降り立ったご神木です。
たたら場にはこの木が必ず植えてあります。
今日は若いハート形の葉を見てもらい、なぜかしらhappyな気持ちになりました♡
ヤマボウシ

花が満開だったのでこの花をスルーすることはできませんでした。
山帽子ではなく山法師です。
白い花弁のように見えるものは総苞片という
中心の花序(花の集合)を包む葉です。
タカノツメ コシアブラ

タカノツメ、コシアブラは別名刀の木と呼びます。
枝の皮をこすると芯と皮がきれいに分離し、刀と鞘のように見えるからです。
これを山で作って遊んだ経験をもつ案内人が作る所を実演しました。
気持ちいいくらいにスルッと抜けました。
水分を吸い上げる今の時期の枝が適しているようです。
ウラジロ

家康の兜の前立てにこのウラジロが使われています。
長寿や繁栄を象徴する縁起物とされていたためです。
アカマツ

日本刀作りに必要な炭はこの赤松から作られた松炭が使われます。
火力が強く燃焼温度をコントロールしやすく灰が少ないためです。
赤松の前に幼木が生えていました。
幼いながらにしっかり根を張っていました。大きくな~れ!
クマバチ

クマバチがホバリングしているところを網で見事にキャッチ!
雄であることを確認して近くで見てもらいました。
顔に白い三角おにぎりの模様があるのが雄です。
雄は針を持たないので刺される心配はありません。
丸くてモフモフでなんとも可愛らしい顔をしていました。
展望台から見る風景

この風景を皆さんに見て頂きたかったのです。
なぜなら・・・ここから見える奥美濃の峰々はまるで刀の刀紋のようなのです。
アオギリ、フジ、ニガナ

広場にてアオギリ、フジ、ニガナをクイズ形式で紹介しました。
アオイ科のアオギリ、樹姿が桐に似ているところからこの名が付きました。
桐や藤は武将の家紋として用いられました。
ニガナはキク科、キク科の花は刀の鞘や鍔のデザインとして多く使われています。
ムクノキ

かつて刀の鞘の表面を磨くためにこの葉が使われていました。
ざらついた葉は研磨剤になります。
この葉を使って実際に爪を磨いて頂きました。
びっくりするほどピカピカな爪に変身!

最後にある参加者の方が素敵な句を詠んで下さいました。
「薫風や 展望の山 刀紋のごと」