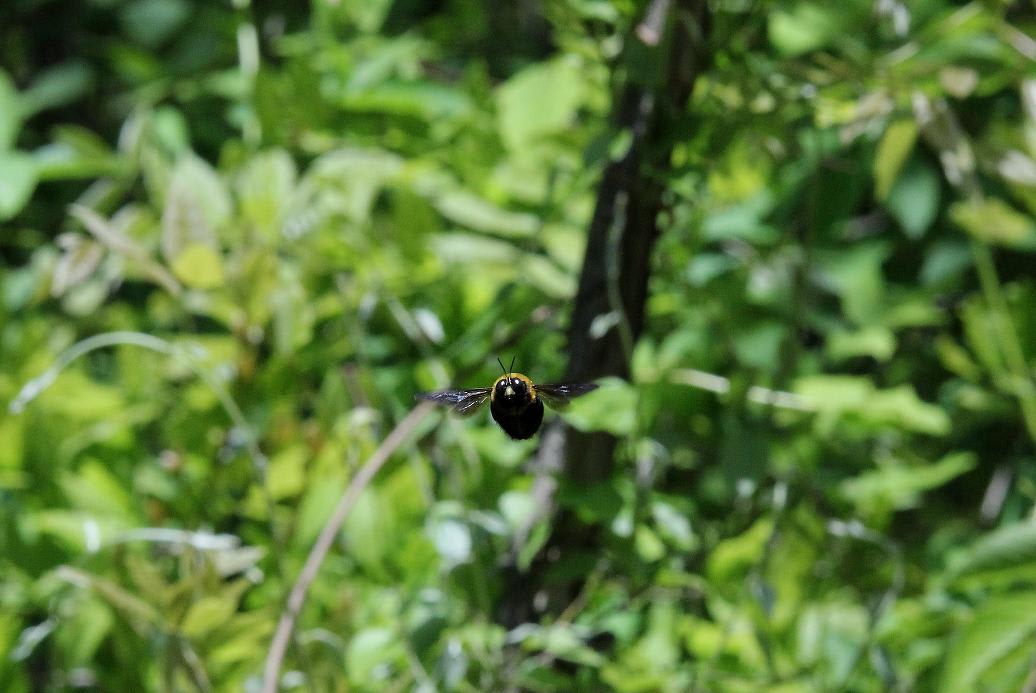近畿地方は一昨日、梅雨入りしました。
例年より10日早く、昨年より11日早い梅雨入りだそうです。
早く始まったんだから梅雨明けも早ければいいのですが、どうやら長期予報で梅雨明けは
例年並みの7月25日とか・・・どうやら今年の梅雨は長引きそうです。
まあ、少しポジティブに考えれば雨には雨の良さというか情緒のようなものもあって
この時期、雨にしっとりと濡れた紫陽花の花などは是非 で狙ってみたい被写体の一つでは
で狙ってみたい被写体の一つでは
ないでしょうか?
さて、今日の画像ですが、二次林の林縁などで日当たりの良いところに生える常緑の多年草、
ヒメハギです。草丈は8~15㌢程度で、初夏に紅紫色で、ちょっと見た目には萩の花のような
小さな花を咲かすことから、和名は「姫萩」ですが、植物分類学上はヒメハギ科ヒメハギ属で
マメ科ハギ属とは全く別系統の植物です。
ヒメハギ<ヒメハギ科 ヒメハギ属> 常緑多年草
この花の構造は、一種独特のもので、如何にも花弁のように横に広がる大きな2枚(側弁)と
後方に立っている小さな2枚(旗弁)は共に萼片で、花弁はその中心にある筒状の部分で
ナワシロイチゴはバラ科キイチゴ属の落葉低木で、名前から受ける印象では、昔は農道付近で、
ごく身近に見られるイチゴだったようです。
しかしながら、現在のように整備された農道の近くではほとんど見ることがありません。
城陽市内でこの植物が観察できるのは、主に木津川河川敷の日当たりの良い土手や草原が
中心なので、恐らくその他の地域でも似た環境で普通に見られると思います。
6月の苗代の頃に赤く熟する果実はこの種のキイチゴの中では甘みの強い方で、生食のほか
リキュールやジャムにするのに好適です。
ナワシロイチゴ<バラ科 キイチゴ属> 落葉低木
花は他のキイチゴとはちょっと違った珍しい形をしています。画像の白い星型の部分が萼で
中心部にピンク色の花弁が4枚あり、雌蕊と雄蕊を包み込んでいますが、花弁はこの様に
閉じたままで、枯れるまで開くことはありません。
画像を見て頂くと、閉じた花弁から少し突き出ているものがありますが、これは雌蕊で、雄蕊は
この状態では未だ花弁に包まれたままです。
雄蕊が露出するのは花弁が枯れた後になりますが、時期をずらすことによって、自家受粉を
キランソウは低山の麓や、人里の湿った石垣などに普通に生えるシソ科の多年草で
山野草に少しでも興味のある人には比較的、馴染みの深い植物だと思います。
和名の漢字表記では、「金襴草」と「金瘡小草」の2種類が使われています。
和名の意味ははっきりしませんが、”キランソウ”と読めるのは前者の方で、金瘡小草は
漢方薬としての薬効を強調した名前のようです。
一説によると、この植物の薬効は驚くべきもので、一度は死にかけた病人も生き返ると
いう意味から「ジゴクノカマノフタ」という別名があります。
まあ、それ程の効果があるかどうかは別にして、主な薬効としては鎮咳、去痰、腫れ止め
虫さされ等で、生薬名では全草を乾燥させたものを「筋骨草」と呼んでいます。
キランソウ<シソ科 キランソウ属> 多年草
ハルジオンは北アメリカ原産のキク科ムカシヨモギ属の多年草で、大正時代に観賞用植物として
輸入されましたが、主に東京方面で栽培されていたものが逸出して野生化し、第2次世界大戦後急に
都市周辺を中心に全国に広がって、現在ではごく一般的に見られる雑草になっています。
開花時期は、地方によって多少のバラつきはありますが、凡そ4月~6月で、頭花は白色または
淡紅色で、観賞用植物として渡来してきたのも充分納得できる美しさを備えています。
この花より少し遅れて、6月~10月に白色または淡紫色の花を付けるものが見られますが
それらは、同じく北アメリカ原産で、明治初期に渡来したヒメジョオン(姫女苑)です。
外見上の相違点として判り易いのは、ハルジオンの場合、茎に付く葉が茎を抱いている(抱き葉)のに対して
ヒメジョオンの葉は茎を抱いていないことで見分けられます。
また茎では、ハルジオンは中空、ヒメジョオンは茎が白い髄で満たされていることでも区別できます。
ところで、以前、ハルジオンはこの時期には城陽市の平地の至るところで見られたものですが、
最近何故か、見られるのは山間部の麓から中腹にかけてで、市内の平地部では全くといっていいほど
姿を見かけなくなりました。
このような生態系の変化については、今後注意深く観察してみる必要がありそうです。
ハルジオン<キク科 ムカシヨモギ属> 帰化植物 多年草
ヤマフジ(山藤)と花期が重なっている紫色の花は、遠くから眺めるとヤマフジが咲いているのと
間違うほどよく似た眺めを醸し出しています。
古くから箪笥などの家具や高級下駄の他、日本古来の楽器である琴などの材として植栽されて
きて、各地の里山で自生状態のものも多く見られます。
この様に私達にとって馴染の深いキリ(桐)ですが、これは一体、何科に属する植物なんでしょうか?
実は、これ良く判っていないんです。
見る図鑑によって、ノウゼンカズラ科とするものや、ゴマノハグサ科とする説、また独立したキリ科であると
する説などが乱立しているようです。
落花した花冠を見ると、花の色や形などからゴマノハグサ科というのも少しは納得できそうですが、
ゴマノハグサ科のほとんどが小さな草本であることから少し首を傾げたくなります。
これに対して、成るほどと思わされるのがノウゼンカズラ科・・・
この中でも、アメリカノウゼンカズラという種類は花の形がかなり桐に似ている上に木本で
幹の長さは10m以上にも達します。
ちなみに、私のもっている図鑑「日本の樹木」(山と渓谷社刊)でもノウゼンカズラ科となっています。
しかし、「無理にどちらかにくっ付けなくてもいいじゃないか」というキリ科説にも配慮?して、
ここでは科名不詳としておきましょうか(笑)
キリ<科名不詳 キリ属> 落葉高木