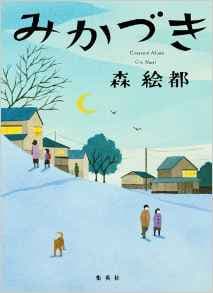ここ2週連続で日曜出勤があったので、ちょっとヘロヘロ気味だったけど
そんな中でも読む手を止められずにぐいぐい読めたのがこの本。
久々の森絵都作品で、かなりのボリュームだったんだけど読むのが辛くなる感じではない。
舞台はまず昭和30年代の日本で、学校の用務員室で子どもに勉強を教えていた主人公が
教わりに来ていた児童の母親(これがまた強烈なキャラで教育に熱い)と学習塾を立ち上げて
結婚し、塾を経営していく中でいろんなことが起きて…というざっくりしたあらすじで
上に書いたように、最初は昭和30年からスタートして、最後は平成の時代、主人公の孫の世代になる
3世代の大河ドラマなわけよね。
最初は塾を運営していく中での山あり谷ありで、塾運営の話がメインだと思ってたんだけど
まあそれは一本ベースにありつつも、教育をベースにした家族の物語で
本当にそれぞれの人物が平凡であるけどイキイキと描かれていて、まさに「大河ドラマ」
私教育と公教育の対立やそれぞれの立場の人たちの思い。
熱かった。この本を読んだあとに、サボさんといろいろ語り、
やっぱり教育ってこうあるべきだよね~、でもうまくいかないよね~など
話しこんだりもして、最初思ってた話とは違う展開の作品ではなかったけど、
すごく熱くて、人々の思いが伝わるし、魅力的な人々と出会えたいい作品だったわね。
森絵都、やっぱりいいわ~。
今年のベスト3に入る1冊だったわね。
そんな中でも読む手を止められずにぐいぐい読めたのがこの本。
久々の森絵都作品で、かなりのボリュームだったんだけど読むのが辛くなる感じではない。
舞台はまず昭和30年代の日本で、学校の用務員室で子どもに勉強を教えていた主人公が
教わりに来ていた児童の母親(これがまた強烈なキャラで教育に熱い)と学習塾を立ち上げて
結婚し、塾を経営していく中でいろんなことが起きて…というざっくりしたあらすじで
上に書いたように、最初は昭和30年からスタートして、最後は平成の時代、主人公の孫の世代になる
3世代の大河ドラマなわけよね。
最初は塾を運営していく中での山あり谷ありで、塾運営の話がメインだと思ってたんだけど
まあそれは一本ベースにありつつも、教育をベースにした家族の物語で
本当にそれぞれの人物が平凡であるけどイキイキと描かれていて、まさに「大河ドラマ」
私教育と公教育の対立やそれぞれの立場の人たちの思い。
熱かった。この本を読んだあとに、サボさんといろいろ語り、
やっぱり教育ってこうあるべきだよね~、でもうまくいかないよね~など
話しこんだりもして、最初思ってた話とは違う展開の作品ではなかったけど、
すごく熱くて、人々の思いが伝わるし、魅力的な人々と出会えたいい作品だったわね。
森絵都、やっぱりいいわ~。
今年のベスト3に入る1冊だったわね。