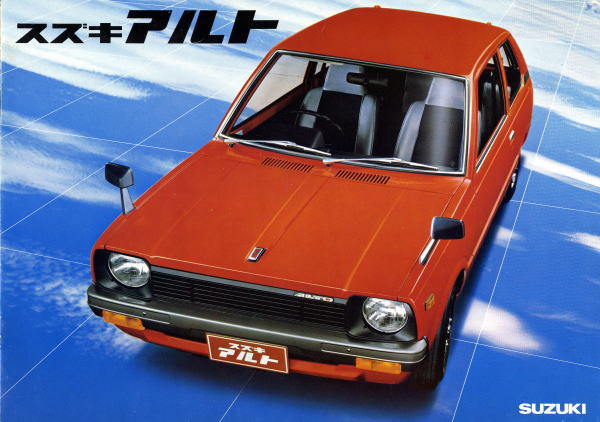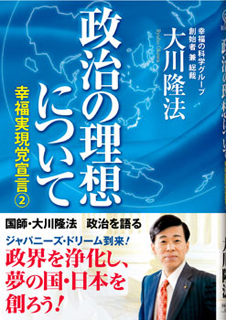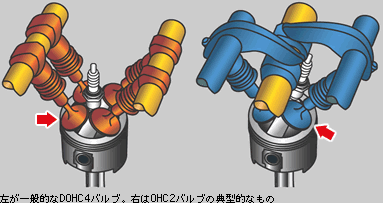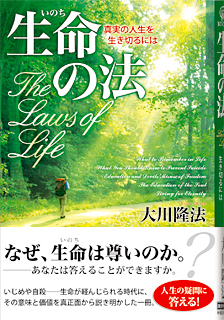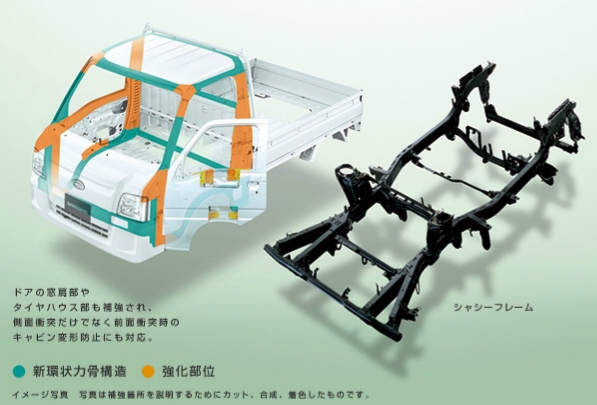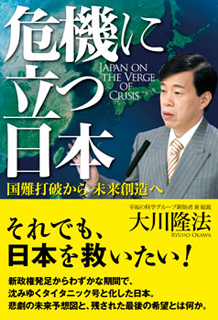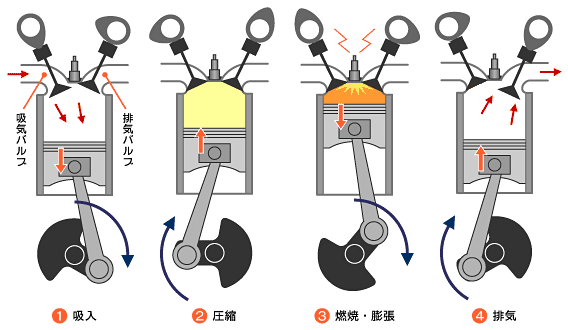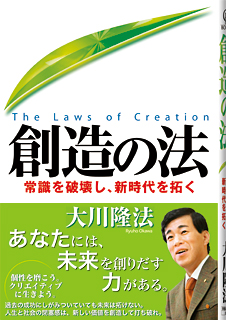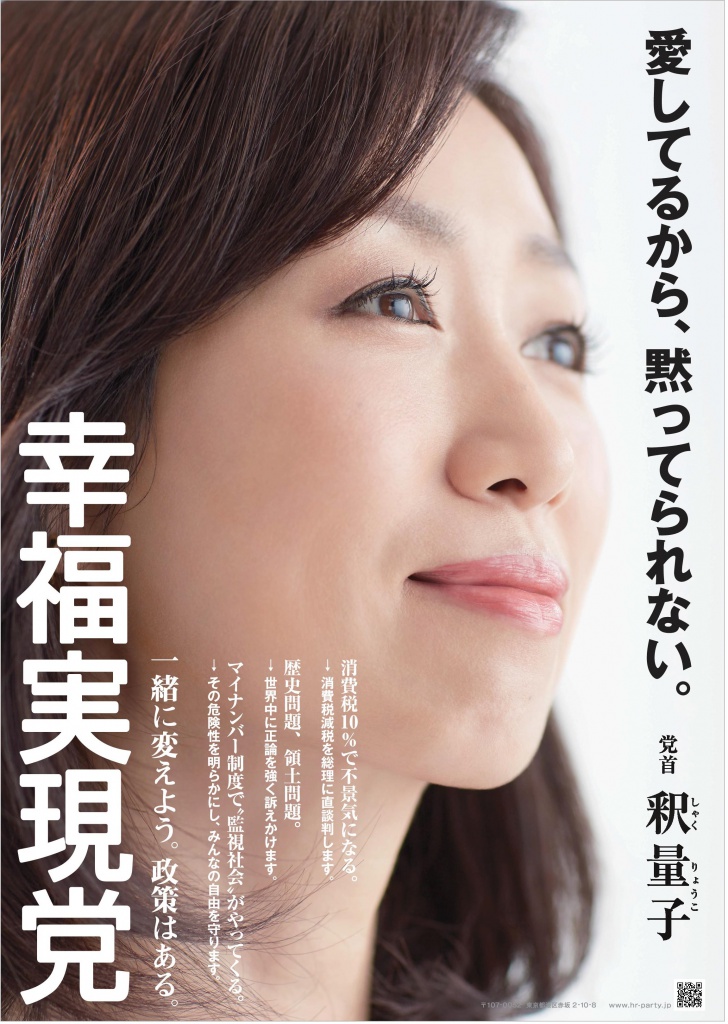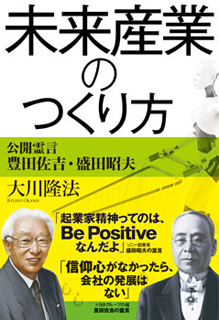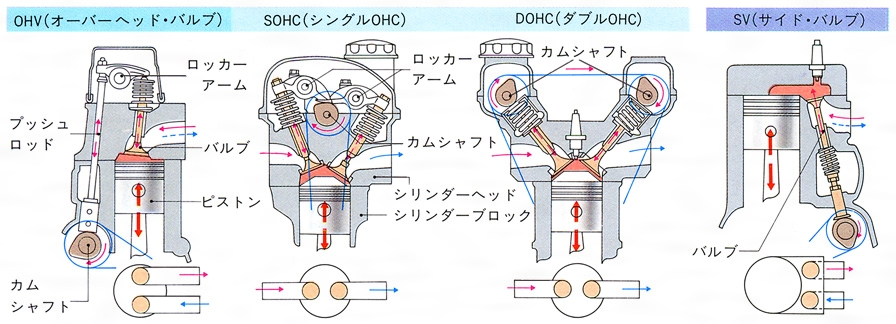時折ですが、ブログのアクセスがピンチになったら(笑)投降させていただいている自動車関連記事です。
宗教布教ブログにあるまじき企画ではあるのですが、これ、結構評判イイんですよ。
幸福の科学は幸福実現党支持ですので、「この自動車関連記事からも、幸福実現党の党としての性格が現わせているのでは?」と代表管理人の私は自負しちょります。
今日の演題は、通称、マークⅡ3兄弟と呼ばれた、トヨタの中型セダンのシリーズから。
私は、「自動車は、極めて社会性の強い商品だ。」と思っておりますが、私にそう印象付けたのは、このマークⅡ3兄弟なんですね。
まず、なぜマークⅡ3兄弟と呼ばれているかと申しますと、同じボディーで、デザインの小変更で、マークⅡ・チェイサー・クレスタという、キャラクターの違う3つの商品を作って売っていたからです。
こういうのを、兄弟車と言いますが、昔は結構ありました。
カローラとスプリンター(トヨタ)とか、カリーナとセリカ(トヨタ)とか、セドリックとグロリア(日産)、ギャランのΣ(シグマ)とΛ(ラムダ)(三菱)などで、同一車種ですので、製造数を増やせてコストダウンになります。
また自動車企業は、開発費が膨大なので、売れなければ最悪破産という、一種の博打的要素があるのですが、キャラクターが分散していれば、大失敗のリスク回避ができるわけですね。
自動車というのは、消費者の強い趣味性によって、販売数が読み切れないところがありますので、大量生産効果による製造コストダウンと、販売リスク回避が同時にできるというのは、とても大きな経営判断なのですね。

トヨタスプリンタートレノ(左)&カローラレビン(右)車両形式は同じくAE86
トヨタのマークⅡ3兄弟が売れたのは、1985~1995年くらいの期間でしょうか?
トヨタの大ベストセラーカローラをしのぎ、年間販売台数1位の常連となり、結構高額車でしたが、バブルがはじけても尚、ベストセラーカーであり続けましたので、私は「世の中、ホンマに不景気なんかいな?」と思ったことでした。
後で学んだことによると、バブル景気はときの政治とマスメディアによる、人為的バブル潰しと言えて、製造業を中心に、日本経済は健全な部分が多かったようです。
つまりバブル景気が幻想だったのではなく、「バブル潰しが幻想」であったということですね。
私は日本の自動車の歴史において、「マークⅡ3兄弟勃興によって、カローラの衰退がはじまった。」と言えると思うのですね。
と申しますのも、商品カテゴリーで言えば、カローラもマークⅡも、「小さな高級車」もしくは「お買い得な高級車」に分類できる、同じ分野の商品だと思うからで、国民所得の向上に伴い、カローラが持っていた顧客が、マークⅡに流れたのではないかと、私は思うのですが。
単なる、バブル景気の申し子的なヒットなら、10年以上に渡り、ベストセラーであり続けるのは不可能ではないかと思うのです。
つまり、バブル景気前後に、「小さな高級車」というカテゴリーの移譲が、カローラからマークⅡの間でなされていたことで、トヨタの屋台骨を支え続けたマークⅡ3兄弟の長期大ヒットがあったということです。

そして、今マークⅡという商品はなくなっていて、マークXという商品になっていますが、それほど影響力を持ってはいませんが、それはこの「小さな高級車(お買い得高級車)」というカテゴリーが、トヨタの別の車種である、プリウスやアルファードや、海外ではカムリに移譲されているのではないかと思うのです。
またそこからは、選択における、ひとつの法則があると思うのですが、残念ながら、記事を書く時間がなくなりましたので、本日はここまでとさせていただきます。
オッと、大事な布教をせねば。(笑)
本日は、ノーベル賞受賞経済学者、ハイエクの霊言『未来創造の経済学』(幸福の科学出版)より、計画経済と言われ、福祉を重視するカール・マルクスの提唱した共産主義経済と、「金の亡者」と呼ばれがちな自由主義経済との違いが、とても良くわかる部分のおすそ分けでございます。
(ばく)
可能性無限大!“考える力”の高め方 天使のモーニングコール1325回 (2017.2.18,19)
モーターランド2: A31 日産セフィーロ vs X80 トヨタ・マークII
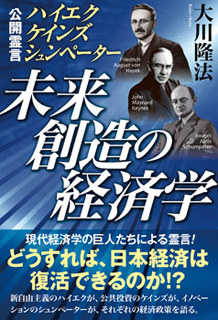 https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=81
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=81
原点は「自己弁護」だと思うんですよ。自分が貧しくて事業に成功しなかったことなどを、全部、基本的には、外部に責任を押しつける考え方を持っていると思うんですね。
それは、あなたがたの宗教でも教えている「自己責任」ではなくて、他の責任にする生き方ですよね。
そういう自己弁護のためだけに、あの膨大な経済哲学をつくり上げた人だと思う。
「自分が貧しいのは、なぜか。それは大資本家が悪いからだ」ということを理論化したわけですね。
経済というものは、まあ、あなたがたも食べるでしょうが、一つのピザパイのようなものです。
これに刻みを入れ、六等分や八等分にしてあると、「人が何人いたら一人に何切れ当たるか」ということが分かります。(中略)
そして、マルクスの考え方は、
「大資本家が、そのパイの大部分を取っている。例えば、八等分できるパイがあっても、大資本家が、八切れのうちの七切れを取って、労働者には一切れしかくれない。これは、けしからん。これが、労働者が貧しい理由である。大資本家から残りのパイを取り戻せ。一切れしかもらっていない労働者たちが集まって、労働組合による政治を行い、全員で、きちんと正しく配分しようじゃないか。大資本家には、八分の一以上は与)えないようにしようじゃないか」
というものです。
基本的には、そういう考えなんです。
だから、マルクス主義には高度な累進課税があります。
土地とか工場とか、こういう大きな生産手段が富の格差を生むからです。(中略)
それから、マルクス主義では、相続をさせないようにするため、生産手段を国有化して個人には渡さないようにし、「国家が国民を公平に処遇する」という美名の下に政治体制が出来上がっています。
「プロレタリアート独裁というかたちで、労働者が独裁する国家が生む平等な社会によって、最終ユートピアが出来上がる」と、まあ、こう考えるわけですね。
ただ、「プロレタリアート独裁」という言葉はきれいだけれども、実際には、労働者は世界中にいるわけです。
世界に何十億人もいる労働者たちに、どうやって独裁ができるんでしょうか。できるわけがありません。
あるとしたら、そういう人たちが、不平不満を持っている相手をつるし上げるかたちでの独裁しかありえないですよね。
「こいつが悪いことをした」と犯人を決めつけて、その人をギロチンにかける。絞首台に乗せる。電気椅子に座らせる。(中略)
結局、共産党員という名のエリートが出てきて、それが支配する。
中国に十三億人の国民がいたって、結局、七千万人ぐらいの共産党員が中国を支配している。
しかも、七千万人もの人がいても、そのほとんどは下部の者であり、上位層にいるのは、ごく一部にすぎず、その一部の人たちが支配する。
そこにあるのは、言論の統制、信教の自由の統制、思想・良心の自由の統制です。
そして、反政府的な言論には、全部、統制をかけていきます。
そのように、実際には、マルクスが考えていたことと、ちょっと違うようになってきたのです。
ただ、彼の思想自体には、要するに、「自分よりも成功した人は、みな悪人だ」と見る考えがあると思うんですね。(中略)
真理の面において、やはり、間違っているところがあったと思うんです。
『未来創造の経済学』(幸福の科学出版)P42~47