あけましておめでとうございます。旧年中、ルナのブログを訪問してくださったことに感謝いたします。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年はわたしの干支でして、人生も最後のターンに来たと受けとめております。30代半ばまでカルト宗教にくすぶっていたわたしには、多くの方々がお持ちのような充実した「青春の想い出」などはありません。何を以って「充実」というか、と申しますと、自分の内奥から自然にわいてくる興味や関心、意欲を自分のフィールドに選び、そこで自己を目いっぱい試す、という行動を経験することを、わたしは人間の生=「Life」の充実だと確信しています。そしてそれこそがカルト宗教に迷いこんでしまう人たちの求める「人生の意味」だと、これは議論の余地のない事実であると、わたしは考えています。そういう充実を若い時代に放棄してしまっていた代わりに、まだあれこれ努力・加工すればそこそこ若く見せれる今の時期を、わたしはおもいきり楽しもうと思っています。
人生を豊かにするコツは、「いい年になりますように」と願うものではなく、「いい年にしよう」と決断することです。さらに、ほんとうは不満に思う出来事なのに、それを権力を持つ他人の見地に置き換えて、「これこれこういう意義があるので“いいこと”なのだ」という欺きを行うわないことでもあります。
いやなことはいやなことだ。人間の自然な感情、自然な意欲を抑えつけるものに不快感や怒りを感じるのは当然のことです。当然のことを当然に主張できない時代、雰囲気、そうさせない「世間」という人間関係は病んでいるのです。
「いかに男子本然の要求であっても、女子にとって不都合な制度なら私は絶対に反対します」(山川菊栄)。
かつて政府が売春を制度化していた時代、公娼制度廃止を強く訴えていた女性活動家の文章を、今年の初めにご紹介します。
山川菊栄。
わたしが敬愛する、いわば心の「師」です。みなさんもそれぞれ、自分に最も影響を与えた人物への敬愛という感情をお持ちでしょう。「敬愛」が度を越して「崇拝」に至ると病的で、身のまわりの人々のうち、自分が崇拝する人と異なるタイプの人たちの人格や個性を否定するようになり、周囲に緊張や対立を醸成させます。そして自分の偶像のイメージを損なわない人々を味方に選びますが、その人たちの間にも不快感と屈従感を与えてしまいます。なぜなら、自らの偶像の影を薄くしない範囲に人々を画一化させようとするからです。彼らに自然な「自分」でいることを許さないからです。しかしそういう方針がやがて、時がたつにつれて彼自身を孤独にしてゆくのです。
それはこういう過程を経ます。周囲の人々の、屈従感に起因する不満が一定の限度に達すると怒りに変わり、怒りが蓄積されると抗議を生むのです。抗議は偶像崇拝者の偶像との対立を生み、やがて分裂に至ります。こうして偶像崇拝者は孤立するようになるのです。ここでは個々の人間関係のことで言いましたが、これは実は、ファシズムあるいは全体主義が案外早いうちに必ず衰退してゆくことの理由でもあります。持続的な社会というのは互いが互いを尊重しようとする対等な人間関係、民主的な価値観に基づくのです。
一方、自分が自然に尊敬するようになった人への自然で健康な「敬愛」は、自己を成長させる大きな要素です。「敬愛」には過度で不自然な賞賛がありません。敬愛する人の欠点も十分分かった上で (しかも敬愛する人の批判すべき点にはしっかり批判を表明しながら) なお尊敬するのです。人間が成長してゆくにはこういう敬愛の対象となるよいお手本が必要です。ほんとうは親がそうであるのが理想ですが、残念ながらわたしの親は未熟な人間で、子どもの甘えを受けとめることのできないどころか、子どもに甘えかかる、という日本に多いパターンの頑固親でした。わたしの場合、心に感銘を与えてくれたよいお手本は親ではなく、この山川菊栄さんなのです。
菊栄は1890年11月3日、東京の麹町に生まれました。父、森田竜之介は足軽出身、苦学してフランス語を修めて、陸軍省の通訳となりましたが、後に畜産業技術のさきがけとなって、「養豚新説」という著作も残したそうです。母は由緒ある血統を持つ人で、千世さんといいます。千世さんは、水戸藩の儒学者で藩校・弘道館の教授だった青山延寿という人の娘さんだった、とのこと。青山家は代々学者の家系だったそうです。千世さんは今のお茶の水女子大学の第一回卒業生でした。すごいですね。要するに、上流階級っぽい家系に菊栄は生まれたわけです。4人きょうだいの第三子、次女でした。
菊栄は1912年に今の津田塾大学(当時は、女子英学塾。)を卒業し、その後定職につかず、三省堂の英語辞典の編集手伝いや翻訳のアルバイトで家計を助けていました。1915年、後に社会党の衆議院議員になる神近市子(かみちかいちこ)に誘われて大杉栄の平民講演会に出席して、社会主義に接しました。翌16年に平民講演会の例会で共産主義者の山川均(ひとし)と出会い、11月に結婚します。
大正デモクラシーの時代、女性を拘束する旧式の道徳からの解放を意図する運動も起こりました。女性を男性の付属物という立場から、主権を主張する「市民」という立場におこうとする運動に、菊栄は身を投じます。当時の女性解放運動で名乗りを上げていたのは、俳人与謝野晶子と平塚らいてうがいましたが、菊栄は彼らとは一線を描した活動家でした。らいてうや晶子は国家主義や旧式の女性観の枠に捉われるきらいがあったのに対し、菊栄は女性を男性と同じ「市民」と捉え、労働者階級の女性が自らの運動によって、「平等」と「保護」をともに「正当な権利」としてたたかい取ろうという、現代的な思考をした人でした。菊栄がそういう思想を持つようになった原体験がありました。これはこういうものです。
-------------------------------
私はまた、七、八年前、救世軍や女子青年会(*)の人々と共に、押上(おしあげ)の大工場を観に行ったある冬の日のことをよく想い出す。
監獄のような高い長い煉瓦塀にとりまかれた一廓、その中には二月の極寒に羽織を着ている者はほとんどなく、十五、六から二十歳くらいの娘たちの多くの集まりの中に、細帯 -というより紐のような- もの(ふつうの帯をせず、紐を代わりに用いた姿。だらしない装い)ばかりしたのもだいぶ目についた。素肌に袷(あわせ。裏地がある着物。夏服。)を着ている者も少なくなかった、足袋をはいている者はまずなかったように思われた。中にはきれいな日本髪に結っていたのもあるが、たいてい頭髪はギリギリ頭の頂上へ巻き上げたきりか、いつ櫛の歯を通したともわからぬのばかりであった。
その日は月に一度のその工場の休日にあたり、救世軍の人々がこの日を利用して有志の女工に伝道をするのであった。
女工は何百畳かありそうな広い部屋の冷たい畳の上に -数えたら七、八十人だったと思う- 寒そうに薄着の身体を集めていた。そこに集まった若い、活気のない、無知な顔、救世軍の人々のわざとらしい誇張した身振りや口調に感心して、半ば口を開けたままドンヨリ演壇を見つめた、空虚な暗い鈍いその表情!
ああ、これが人間(のありさま)だ、これが私たちの姉妹だ、そう思ったとき、私の胸はかきむしられるように感じた。彼らの魂、彼らの青春は早くすでに何ものかに吸い尽くされて、ここにあるのはただ彼らの残骸なのではないか、生きながら屍とならんとしつつある彼らではあるまいか。
私は胸を圧しつけられるように感じた。
しかし私の沈思は長く続くことを許されなかった。それはちょうどこのとき、私が一方に女工らのみじめな顔や姿を見入りつつ、耳にとめていた救世軍の人の説法はその極点に達し、それと同時にその説くところの虚偽に対する私の憤りが猛然と炎え立った(もえたった:原文ママ)からであった。
彼(説教師)といま一人の救世軍の婦人は、女工に歌を唄って聞かせ、一節ごとにそれを繰り返して女工に暗んじさせた(そらんじさせた)。その歌というのは、イエス・キリストは大工の子である、彼も労働者で、よく働いて、不平をいわなかった。働く者には神の恵みがある、われわれもキリストにならって不平なき「よき労働者」となり、神の恵みにあずかろう、労働は神聖である、といったようなものであった。
そして救世軍士官(説教師のこと。救世軍は軍隊式に組織するので、説教師をこのようにいう)の説法はこの歌を敷衍(ふえん:ある陳述などを、例証などでさらにくわしく説明すること)したもので、いっそう馬鹿げた、いっそう労働者の不利益になるような道徳を鼓吹したものであった。
話半ばに私は幾度席を立ち上がろうとしたことだろう? 唇をかみしめつつ、そしてそんな話にあるいは笑わされ、あるいは感心させられながら聞き入っている女工らの顔を見た私の心は、実にいいようのない悲痛に燃え立ったのであった。私は他の来観者と一所にいたプラットフォームからとび下りて女工らの中に行きたかった。私は彼らに詫びたかった、私は彼らの前に平伏したかった -何故なら、私は、私たちは彼らを汚している、彼らを欺いている、彼らを踏み躙っているという良心の呵責に堪えなかったから- 。
実際私は彼らの敵と共に、火鉢のある演壇のうえから、火の気のない大広間(聴衆である女工たちの席)に素足で座らされている彼らを見おろした気持ち、そのときの良心の悩みを今なお忘れることができずにいる。
さらに工場に付属する病室を見舞ったときの光景や、機械に手首をとられた娘の顔や、帰り際に二言三言口を利いた十五になるといった女工の「国に帰りたい」、「夜業があってつらい」といって涙ぐんだ眼など、いずれも私の脳裡に消すことのできぬ印象を刻んでいる。「あの子をどうかしてやりたい」と切に思いつつ遂にどうしてやることもできなかった私は、今もなお、「あの子はどうしたろう」としばしば思い出す。そして同時にその子と同じ運命にある幾十万の姉妹の上を思わせられるのである。
(「労働階級の姉妹へ」/ 山川菊栄・著 『日本評論』1919年2月号より/ 「山川菊栄評論集」所収 )
-------------------------------
菊栄の目線は人間にあったこと、これが菊栄をして他の女性解放運動家たちと、いえ、労働者解放運動家たちと大きな一線を画していた違いでした。菊栄はいわゆる「上から目線」ではなかったのです。あたりまえのことを言うようですが、これができない人が多いのです。
キリスト教団体の伝道は「上から目線」でした。極寒の二月に暖房のない職場や集会所で夏服を細帯だけでまとい、素足で置かれている女工たちに、その状態で労働することを励ましていたのです。当時の女性にはわたしたちと同じような「人権」、現行憲法で保障されている生存権、日本国憲法13条の「個人の尊重」、「生命、自由、幸福の追求は権利であり、立法その他の国政のうえで最大の尊重を必要とする」ということが保障されていない時代だったのです。
そういうふうに放置され、置き去りにされている女工たちの現状を追認しておきながら、どんな高邁な理想をたれようともそれが何を成し遂げるでしょうか。菊栄は同じ論文の中でこう書いています。
「私たちが一般の労働者のうえに期待しているような(全て人間は等しく幸福になる権利があるという意識への)覚醒や活動と、彼らの現状との間に横たわる距離を思うとき、真に憮然たるものなきをえないのである。ある人は日本における労働運動不振の理由を女工の多きことに帰しているが、これは確かに一理ある観察と思われる。女工の間における団結意識の困難は、日本ほどに官憲の圧迫が厳しくなく、日本ほどに婦人の卑屈を尊ばぬ外国においてさえ、既にしばしば絶望的な嗟嘆(さたん。なげくこと)を招かしめたのであることを思えば、日本における同様の試みがさらに幾倍の困難に遭遇すべきことは当然予想されねばならない(上掲書より)」。
当時に教育を受けた社会科学者たちの意欲は、女工たちを含む一般労働者には理解されず、かえって反発さえ受けたことでしょう。なぜならば、彼らはじっくり腰を落ち着けてものごとを考える精神的余裕すら持ち合わせていなかったからです。菊栄が観察したとおり、「そこに集まった若い、活気のない、無知な顔、救世軍の人々のわざとらしい誇張した身振りや口調に感心して、半ば口を開けたままドンヨリ演壇を見つめた、空虚な暗い鈍いその表情!」からそれは明らかにうかがえるものでした。
ちょっと脱線して、大日本帝国憲法下の女工たちの労働状況を調べてみますと、
-------------------------------
しかしてその労働時間は如何と見るに、一定の時間を示すを得ずといえども、先ず朝未明より夜の十時までは通例なるが如し、家によりては十一時まで夜業せしむるところあり、あるいは四時頃より起きて働かしむるところあれども、その間休息することを得るは飲食時間のほかはなし。夏七、八月頃に至れば、午後一時より二時頃まで休息せしむるのみ(「日本の下層社会」/ 横山源之助・著/ 明治31年刊)。
およそ紡績工場くらい長時間労働を強いられる処はない。大体においては十二時間制が原則となっているが、先ずこれを二期に分けて考えねばならぬ。第一期は工場法発布以前であってこの頃は全国の工場ほとんど、紡績十二時間、織布十四時間であった。しかして第二期に当たる工場法後から今日(大正14年ころ)へかけては紡績十一時間、織布十二時間というのが最も多数を占める。ところがここに『夜業』があるため、紡績工場の労働時間割はなかなか面倒になってくる。十一時間制だから十一時間働けばいいというごとく、簡単に片付かないのである。
この『夜業』がまた問題だ、これは二様に解釈される。つまり昼間一定の働きをしたうえ更に夜分若干の労働を加えること、これをむかしから『よなび』と言ったのだが、女工たちの場合は違う。それは昼間働く代わりに夜通し働く、すなわち深夜業のことを意味するのである。
日本でも欧米でも手工業時代には(工場に労働者が集まって働く工場制労働ではなく、家庭ではたらく手工業の形態)、夜寝る前に若干の時間を労働するというほかは、深夜を徹して働くなどということはなかった。これは飽くまで近代工業の所産であり、しかも日本がその創始者であるのはいかにしても申し訳が立たない次第だ。ちなみに組織だった大仕掛けな(深)夜業の始まりは、明治16年大阪紡績(1914年三重紡績と合併して東洋紡績となった)においてなされたものであった(「女工哀史」/ 細井和喜蔵・著/ 大正14年刊)。
-------------------------------
ものすごい長時間労働ですが、しかも福利厚生関係もすさまじく悪かったのです。前者の「日本の下層社会」にはこんなふうにルポされています。
-------------------------------
「かれら(女工たち)苦なきか、果たして平らかならざるものなきか、声を揃えて楽しげに謡うを聴けば、『嫌だ嫌だよ機織止めて甲斐絹織屋のおかみさん』、更に謡うものに耳を傾くれば、『お鉢引き寄せ割飯(わりめし:麦と米の混合飯)眺め、米はないかと目に涙』。…かれらが日々食するところの食物といえば、飯は米と麦を等分にせるワリ飯、朝と晩は汁あれども昼食には菜なく、しかも汁というも特に塩辛くせる味噌汁の中へ入りたるは通例菜葉、秋に入りたれば大根の刻みたるものありとせば、即ちこれ珍膳佳肴(ちんぜんかこう:豪華でおいしいごちそう、の意。大根が刻み込まれていればそれでごちそうだった、ということ)。お鉢引き寄せ割飯眺め米はないかと目に涙の哀歌を謡うもの、また宜(むべ:なるほどそのとおりだ、という意。肯定の意を表す)ならずや。さればかれら、物日(ものび:祝祭日のこと)の来るを数日前より指折り待ち、その日来れば胃の損ずるをも顧みずして腹に詰め、無常の快事なりとはなせり」。
-------------------------------
筆者は、こんな食生活をしているのは、「監獄の囚人と禅堂に業を修する居士のほかあらざるべし」とも感想を述べています。当時の女工たちはこういう生活を宿舎に監禁されたまま何年も何年も続けていました。女工といっても今日のような高卒、大卒ではもちろんありません。若い子なら12歳から見習いで紡績工場に入ります。「年限はおおむね3年ないし7年の間なりと見て可なり(「日本の下層社会」)」。年限ということから、いつでも辞めたくなったら辞められるというのではなく、要するに奉公に上がるというような形態だったんでしょうね。しかもお給料の支払いもいいかげんで、失敗作を出すと減給、失敗の程度に寄れば支給停止という措置が取られたため、失敗を出して給金をもらえない日が多くなると前借などをして、それをまた返済するのに年限が延びるというようなこともあたりまえにあったようです。
日本の近代化は「上から押しつけられてきた」ものだったので、日本型資本主義の当初はこんなだったんですね。こういう反省から、日本国憲法には基本的人権を保障し、労働権などの社会権も保障されるようになったのですが、近年、労働者はどんどん生存権が縮められてきています。「北朝鮮の脅威」とやらの官製のアジに乗せられて、MD配備に歓声を上げているどころじゃないぞ、とわたしは思うのですけれどもね。
特に上記引用文から発見したことは、深夜労働への当時の知識人の違和感です。現代人のわたしからすると、コンビニなどがふつうにある時代ですので、深夜労働など当然に思っていて、それを問題に思うことなどありませんでした。仲買市場など夜から仕事は始まりますしね。深夜労働の問題はまた別の機会に書いてみます。なんでも「あたりまえ」で片づけてしまうのは思考停止でしかありませんから、ね。
こういう生活を長期間強いられていると、人間は精神的に荒廃してゆくようです。「女工哀史」には「女工の心理」という章が設けられていて、詳細に観察されているのですが、これも機会を改めます。「日本の下層社会」には簡潔に書かれていますので、それをご紹介しましょう。
-------------------------------
…日々涙を以って郷国を慕い居れる可憐の場合にては、なお我儘(わがまま)を見ることなきも、年一年と慣るるに従い、いつとはなく父母を忘れ、朋輩に我を祈る事をなさず、もとより彼らに教育の素あるにもあらざれば、己を抑えむはずもなく、勝手出で我儘となり、すなわち衝突を見ることなるべし。しかして我儘出づると共に、かれらは父母と別れたる素志を忘れ、橋の上に集まり故国の事を語り合う事なくなると共に、彼女らは歩一歩救うべからざる堕落の境に身を陥るにはあらざるか。
…先ず工場に入りてかれらの言動挙動に注意せよ。米はないかと眼に涙の哀れむべきものを謡うに次ぎて、洒然として常に謡えるは「親が承知で機織させて、浮気するなと先きぁ無理だ」というが如き猥褻聴くに堪えざるものを耳にすることしばしばなり。これなお可なり、ここに挙ぐるを憚るを以って敢えて記せざれども、更に甚だしきものを平然として謡い居るなり。
かつてある機屋に工女の風儀を矯正せんとて一の規則を定めたる事あり。曰く、密交の確証ある者は罰金五円を課する事、(男性と)談話し居る場合を発見せられたる者は罰金3円、共に入浴せる時は罰金1円50銭といえる、これなり。
驚くべく、笑うべきが如しといえども、一にこれを以って見るもいかにかれら工女が風俗の乱れ居るかを推するに難からざるべし。
(「日本の下層社会」/ 横山源之助・著)
↓(下)へつづく
今年はわたしの干支でして、人生も最後のターンに来たと受けとめております。30代半ばまでカルト宗教にくすぶっていたわたしには、多くの方々がお持ちのような充実した「青春の想い出」などはありません。何を以って「充実」というか、と申しますと、自分の内奥から自然にわいてくる興味や関心、意欲を自分のフィールドに選び、そこで自己を目いっぱい試す、という行動を経験することを、わたしは人間の生=「Life」の充実だと確信しています。そしてそれこそがカルト宗教に迷いこんでしまう人たちの求める「人生の意味」だと、これは議論の余地のない事実であると、わたしは考えています。そういう充実を若い時代に放棄してしまっていた代わりに、まだあれこれ努力・加工すればそこそこ若く見せれる今の時期を、わたしはおもいきり楽しもうと思っています。
人生を豊かにするコツは、「いい年になりますように」と願うものではなく、「いい年にしよう」と決断することです。さらに、ほんとうは不満に思う出来事なのに、それを権力を持つ他人の見地に置き換えて、「これこれこういう意義があるので“いいこと”なのだ」という欺きを行うわないことでもあります。
いやなことはいやなことだ。人間の自然な感情、自然な意欲を抑えつけるものに不快感や怒りを感じるのは当然のことです。当然のことを当然に主張できない時代、雰囲気、そうさせない「世間」という人間関係は病んでいるのです。
「いかに男子本然の要求であっても、女子にとって不都合な制度なら私は絶対に反対します」(山川菊栄)。
かつて政府が売春を制度化していた時代、公娼制度廃止を強く訴えていた女性活動家の文章を、今年の初めにご紹介します。
山川菊栄。
わたしが敬愛する、いわば心の「師」です。みなさんもそれぞれ、自分に最も影響を与えた人物への敬愛という感情をお持ちでしょう。「敬愛」が度を越して「崇拝」に至ると病的で、身のまわりの人々のうち、自分が崇拝する人と異なるタイプの人たちの人格や個性を否定するようになり、周囲に緊張や対立を醸成させます。そして自分の偶像のイメージを損なわない人々を味方に選びますが、その人たちの間にも不快感と屈従感を与えてしまいます。なぜなら、自らの偶像の影を薄くしない範囲に人々を画一化させようとするからです。彼らに自然な「自分」でいることを許さないからです。しかしそういう方針がやがて、時がたつにつれて彼自身を孤独にしてゆくのです。
それはこういう過程を経ます。周囲の人々の、屈従感に起因する不満が一定の限度に達すると怒りに変わり、怒りが蓄積されると抗議を生むのです。抗議は偶像崇拝者の偶像との対立を生み、やがて分裂に至ります。こうして偶像崇拝者は孤立するようになるのです。ここでは個々の人間関係のことで言いましたが、これは実は、ファシズムあるいは全体主義が案外早いうちに必ず衰退してゆくことの理由でもあります。持続的な社会というのは互いが互いを尊重しようとする対等な人間関係、民主的な価値観に基づくのです。
一方、自分が自然に尊敬するようになった人への自然で健康な「敬愛」は、自己を成長させる大きな要素です。「敬愛」には過度で不自然な賞賛がありません。敬愛する人の欠点も十分分かった上で (しかも敬愛する人の批判すべき点にはしっかり批判を表明しながら) なお尊敬するのです。人間が成長してゆくにはこういう敬愛の対象となるよいお手本が必要です。ほんとうは親がそうであるのが理想ですが、残念ながらわたしの親は未熟な人間で、子どもの甘えを受けとめることのできないどころか、子どもに甘えかかる、という日本に多いパターンの頑固親でした。わたしの場合、心に感銘を与えてくれたよいお手本は親ではなく、この山川菊栄さんなのです。
菊栄は1890年11月3日、東京の麹町に生まれました。父、森田竜之介は足軽出身、苦学してフランス語を修めて、陸軍省の通訳となりましたが、後に畜産業技術のさきがけとなって、「養豚新説」という著作も残したそうです。母は由緒ある血統を持つ人で、千世さんといいます。千世さんは、水戸藩の儒学者で藩校・弘道館の教授だった青山延寿という人の娘さんだった、とのこと。青山家は代々学者の家系だったそうです。千世さんは今のお茶の水女子大学の第一回卒業生でした。すごいですね。要するに、上流階級っぽい家系に菊栄は生まれたわけです。4人きょうだいの第三子、次女でした。
菊栄は1912年に今の津田塾大学(当時は、女子英学塾。)を卒業し、その後定職につかず、三省堂の英語辞典の編集手伝いや翻訳のアルバイトで家計を助けていました。1915年、後に社会党の衆議院議員になる神近市子(かみちかいちこ)に誘われて大杉栄の平民講演会に出席して、社会主義に接しました。翌16年に平民講演会の例会で共産主義者の山川均(ひとし)と出会い、11月に結婚します。
大正デモクラシーの時代、女性を拘束する旧式の道徳からの解放を意図する運動も起こりました。女性を男性の付属物という立場から、主権を主張する「市民」という立場におこうとする運動に、菊栄は身を投じます。当時の女性解放運動で名乗りを上げていたのは、俳人与謝野晶子と平塚らいてうがいましたが、菊栄は彼らとは一線を描した活動家でした。らいてうや晶子は国家主義や旧式の女性観の枠に捉われるきらいがあったのに対し、菊栄は女性を男性と同じ「市民」と捉え、労働者階級の女性が自らの運動によって、「平等」と「保護」をともに「正当な権利」としてたたかい取ろうという、現代的な思考をした人でした。菊栄がそういう思想を持つようになった原体験がありました。これはこういうものです。
-------------------------------
私はまた、七、八年前、救世軍や女子青年会(*)の人々と共に、押上(おしあげ)の大工場を観に行ったある冬の日のことをよく想い出す。
監獄のような高い長い煉瓦塀にとりまかれた一廓、その中には二月の極寒に羽織を着ている者はほとんどなく、十五、六から二十歳くらいの娘たちの多くの集まりの中に、細帯 -というより紐のような- もの(ふつうの帯をせず、紐を代わりに用いた姿。だらしない装い)ばかりしたのもだいぶ目についた。素肌に袷(あわせ。裏地がある着物。夏服。)を着ている者も少なくなかった、足袋をはいている者はまずなかったように思われた。中にはきれいな日本髪に結っていたのもあるが、たいてい頭髪はギリギリ頭の頂上へ巻き上げたきりか、いつ櫛の歯を通したともわからぬのばかりであった。
その日は月に一度のその工場の休日にあたり、救世軍の人々がこの日を利用して有志の女工に伝道をするのであった。
女工は何百畳かありそうな広い部屋の冷たい畳の上に -数えたら七、八十人だったと思う- 寒そうに薄着の身体を集めていた。そこに集まった若い、活気のない、無知な顔、救世軍の人々のわざとらしい誇張した身振りや口調に感心して、半ば口を開けたままドンヨリ演壇を見つめた、空虚な暗い鈍いその表情!
ああ、これが人間(のありさま)だ、これが私たちの姉妹だ、そう思ったとき、私の胸はかきむしられるように感じた。彼らの魂、彼らの青春は早くすでに何ものかに吸い尽くされて、ここにあるのはただ彼らの残骸なのではないか、生きながら屍とならんとしつつある彼らではあるまいか。
私は胸を圧しつけられるように感じた。
しかし私の沈思は長く続くことを許されなかった。それはちょうどこのとき、私が一方に女工らのみじめな顔や姿を見入りつつ、耳にとめていた救世軍の人の説法はその極点に達し、それと同時にその説くところの虚偽に対する私の憤りが猛然と炎え立った(もえたった:原文ママ)からであった。
彼(説教師)といま一人の救世軍の婦人は、女工に歌を唄って聞かせ、一節ごとにそれを繰り返して女工に暗んじさせた(そらんじさせた)。その歌というのは、イエス・キリストは大工の子である、彼も労働者で、よく働いて、不平をいわなかった。働く者には神の恵みがある、われわれもキリストにならって不平なき「よき労働者」となり、神の恵みにあずかろう、労働は神聖である、といったようなものであった。
そして救世軍士官(説教師のこと。救世軍は軍隊式に組織するので、説教師をこのようにいう)の説法はこの歌を敷衍(ふえん:ある陳述などを、例証などでさらにくわしく説明すること)したもので、いっそう馬鹿げた、いっそう労働者の不利益になるような道徳を鼓吹したものであった。
話半ばに私は幾度席を立ち上がろうとしたことだろう? 唇をかみしめつつ、そしてそんな話にあるいは笑わされ、あるいは感心させられながら聞き入っている女工らの顔を見た私の心は、実にいいようのない悲痛に燃え立ったのであった。私は他の来観者と一所にいたプラットフォームからとび下りて女工らの中に行きたかった。私は彼らに詫びたかった、私は彼らの前に平伏したかった -何故なら、私は、私たちは彼らを汚している、彼らを欺いている、彼らを踏み躙っているという良心の呵責に堪えなかったから- 。
実際私は彼らの敵と共に、火鉢のある演壇のうえから、火の気のない大広間(聴衆である女工たちの席)に素足で座らされている彼らを見おろした気持ち、そのときの良心の悩みを今なお忘れることができずにいる。
さらに工場に付属する病室を見舞ったときの光景や、機械に手首をとられた娘の顔や、帰り際に二言三言口を利いた十五になるといった女工の「国に帰りたい」、「夜業があってつらい」といって涙ぐんだ眼など、いずれも私の脳裡に消すことのできぬ印象を刻んでいる。「あの子をどうかしてやりたい」と切に思いつつ遂にどうしてやることもできなかった私は、今もなお、「あの子はどうしたろう」としばしば思い出す。そして同時にその子と同じ運命にある幾十万の姉妹の上を思わせられるのである。
(「労働階級の姉妹へ」/ 山川菊栄・著 『日本評論』1919年2月号より/ 「山川菊栄評論集」所収 )
-------------------------------
菊栄の目線は人間にあったこと、これが菊栄をして他の女性解放運動家たちと、いえ、労働者解放運動家たちと大きな一線を画していた違いでした。菊栄はいわゆる「上から目線」ではなかったのです。あたりまえのことを言うようですが、これができない人が多いのです。
キリスト教団体の伝道は「上から目線」でした。極寒の二月に暖房のない職場や集会所で夏服を細帯だけでまとい、素足で置かれている女工たちに、その状態で労働することを励ましていたのです。当時の女性にはわたしたちと同じような「人権」、現行憲法で保障されている生存権、日本国憲法13条の「個人の尊重」、「生命、自由、幸福の追求は権利であり、立法その他の国政のうえで最大の尊重を必要とする」ということが保障されていない時代だったのです。
そういうふうに放置され、置き去りにされている女工たちの現状を追認しておきながら、どんな高邁な理想をたれようともそれが何を成し遂げるでしょうか。菊栄は同じ論文の中でこう書いています。
「私たちが一般の労働者のうえに期待しているような(全て人間は等しく幸福になる権利があるという意識への)覚醒や活動と、彼らの現状との間に横たわる距離を思うとき、真に憮然たるものなきをえないのである。ある人は日本における労働運動不振の理由を女工の多きことに帰しているが、これは確かに一理ある観察と思われる。女工の間における団結意識の困難は、日本ほどに官憲の圧迫が厳しくなく、日本ほどに婦人の卑屈を尊ばぬ外国においてさえ、既にしばしば絶望的な嗟嘆(さたん。なげくこと)を招かしめたのであることを思えば、日本における同様の試みがさらに幾倍の困難に遭遇すべきことは当然予想されねばならない(上掲書より)」。
当時に教育を受けた社会科学者たちの意欲は、女工たちを含む一般労働者には理解されず、かえって反発さえ受けたことでしょう。なぜならば、彼らはじっくり腰を落ち着けてものごとを考える精神的余裕すら持ち合わせていなかったからです。菊栄が観察したとおり、「そこに集まった若い、活気のない、無知な顔、救世軍の人々のわざとらしい誇張した身振りや口調に感心して、半ば口を開けたままドンヨリ演壇を見つめた、空虚な暗い鈍いその表情!」からそれは明らかにうかがえるものでした。
ちょっと脱線して、大日本帝国憲法下の女工たちの労働状況を調べてみますと、
-------------------------------
しかしてその労働時間は如何と見るに、一定の時間を示すを得ずといえども、先ず朝未明より夜の十時までは通例なるが如し、家によりては十一時まで夜業せしむるところあり、あるいは四時頃より起きて働かしむるところあれども、その間休息することを得るは飲食時間のほかはなし。夏七、八月頃に至れば、午後一時より二時頃まで休息せしむるのみ(「日本の下層社会」/ 横山源之助・著/ 明治31年刊)。
およそ紡績工場くらい長時間労働を強いられる処はない。大体においては十二時間制が原則となっているが、先ずこれを二期に分けて考えねばならぬ。第一期は工場法発布以前であってこの頃は全国の工場ほとんど、紡績十二時間、織布十四時間であった。しかして第二期に当たる工場法後から今日(大正14年ころ)へかけては紡績十一時間、織布十二時間というのが最も多数を占める。ところがここに『夜業』があるため、紡績工場の労働時間割はなかなか面倒になってくる。十一時間制だから十一時間働けばいいというごとく、簡単に片付かないのである。
この『夜業』がまた問題だ、これは二様に解釈される。つまり昼間一定の働きをしたうえ更に夜分若干の労働を加えること、これをむかしから『よなび』と言ったのだが、女工たちの場合は違う。それは昼間働く代わりに夜通し働く、すなわち深夜業のことを意味するのである。
日本でも欧米でも手工業時代には(工場に労働者が集まって働く工場制労働ではなく、家庭ではたらく手工業の形態)、夜寝る前に若干の時間を労働するというほかは、深夜を徹して働くなどということはなかった。これは飽くまで近代工業の所産であり、しかも日本がその創始者であるのはいかにしても申し訳が立たない次第だ。ちなみに組織だった大仕掛けな(深)夜業の始まりは、明治16年大阪紡績(1914年三重紡績と合併して東洋紡績となった)においてなされたものであった(「女工哀史」/ 細井和喜蔵・著/ 大正14年刊)。
-------------------------------
ものすごい長時間労働ですが、しかも福利厚生関係もすさまじく悪かったのです。前者の「日本の下層社会」にはこんなふうにルポされています。
-------------------------------
「かれら(女工たち)苦なきか、果たして平らかならざるものなきか、声を揃えて楽しげに謡うを聴けば、『嫌だ嫌だよ機織止めて甲斐絹織屋のおかみさん』、更に謡うものに耳を傾くれば、『お鉢引き寄せ割飯(わりめし:麦と米の混合飯)眺め、米はないかと目に涙』。…かれらが日々食するところの食物といえば、飯は米と麦を等分にせるワリ飯、朝と晩は汁あれども昼食には菜なく、しかも汁というも特に塩辛くせる味噌汁の中へ入りたるは通例菜葉、秋に入りたれば大根の刻みたるものありとせば、即ちこれ珍膳佳肴(ちんぜんかこう:豪華でおいしいごちそう、の意。大根が刻み込まれていればそれでごちそうだった、ということ)。お鉢引き寄せ割飯眺め米はないかと目に涙の哀歌を謡うもの、また宜(むべ:なるほどそのとおりだ、という意。肯定の意を表す)ならずや。さればかれら、物日(ものび:祝祭日のこと)の来るを数日前より指折り待ち、その日来れば胃の損ずるをも顧みずして腹に詰め、無常の快事なりとはなせり」。
-------------------------------
筆者は、こんな食生活をしているのは、「監獄の囚人と禅堂に業を修する居士のほかあらざるべし」とも感想を述べています。当時の女工たちはこういう生活を宿舎に監禁されたまま何年も何年も続けていました。女工といっても今日のような高卒、大卒ではもちろんありません。若い子なら12歳から見習いで紡績工場に入ります。「年限はおおむね3年ないし7年の間なりと見て可なり(「日本の下層社会」)」。年限ということから、いつでも辞めたくなったら辞められるというのではなく、要するに奉公に上がるというような形態だったんでしょうね。しかもお給料の支払いもいいかげんで、失敗作を出すと減給、失敗の程度に寄れば支給停止という措置が取られたため、失敗を出して給金をもらえない日が多くなると前借などをして、それをまた返済するのに年限が延びるというようなこともあたりまえにあったようです。
日本の近代化は「上から押しつけられてきた」ものだったので、日本型資本主義の当初はこんなだったんですね。こういう反省から、日本国憲法には基本的人権を保障し、労働権などの社会権も保障されるようになったのですが、近年、労働者はどんどん生存権が縮められてきています。「北朝鮮の脅威」とやらの官製のアジに乗せられて、MD配備に歓声を上げているどころじゃないぞ、とわたしは思うのですけれどもね。
特に上記引用文から発見したことは、深夜労働への当時の知識人の違和感です。現代人のわたしからすると、コンビニなどがふつうにある時代ですので、深夜労働など当然に思っていて、それを問題に思うことなどありませんでした。仲買市場など夜から仕事は始まりますしね。深夜労働の問題はまた別の機会に書いてみます。なんでも「あたりまえ」で片づけてしまうのは思考停止でしかありませんから、ね。
こういう生活を長期間強いられていると、人間は精神的に荒廃してゆくようです。「女工哀史」には「女工の心理」という章が設けられていて、詳細に観察されているのですが、これも機会を改めます。「日本の下層社会」には簡潔に書かれていますので、それをご紹介しましょう。
-------------------------------
…日々涙を以って郷国を慕い居れる可憐の場合にては、なお我儘(わがまま)を見ることなきも、年一年と慣るるに従い、いつとはなく父母を忘れ、朋輩に我を祈る事をなさず、もとより彼らに教育の素あるにもあらざれば、己を抑えむはずもなく、勝手出で我儘となり、すなわち衝突を見ることなるべし。しかして我儘出づると共に、かれらは父母と別れたる素志を忘れ、橋の上に集まり故国の事を語り合う事なくなると共に、彼女らは歩一歩救うべからざる堕落の境に身を陥るにはあらざるか。
…先ず工場に入りてかれらの言動挙動に注意せよ。米はないかと眼に涙の哀れむべきものを謡うに次ぎて、洒然として常に謡えるは「親が承知で機織させて、浮気するなと先きぁ無理だ」というが如き猥褻聴くに堪えざるものを耳にすることしばしばなり。これなお可なり、ここに挙ぐるを憚るを以って敢えて記せざれども、更に甚だしきものを平然として謡い居るなり。
かつてある機屋に工女の風儀を矯正せんとて一の規則を定めたる事あり。曰く、密交の確証ある者は罰金五円を課する事、(男性と)談話し居る場合を発見せられたる者は罰金3円、共に入浴せる時は罰金1円50銭といえる、これなり。
驚くべく、笑うべきが如しといえども、一にこれを以って見るもいかにかれら工女が風俗の乱れ居るかを推するに難からざるべし。
(「日本の下層社会」/ 横山源之助・著)
↓(下)へつづく














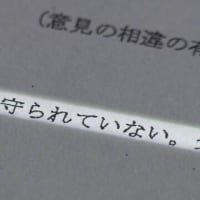
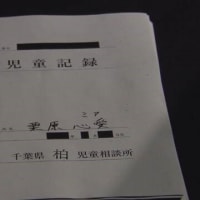







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます