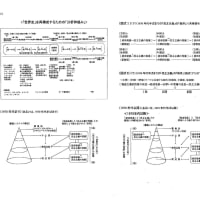私の語る「システム」論から、ここ最近の注目すべき「円安」問題について、「歴史叙述の神話」という観点から再考するとき
*これから数回にわたっておそらく書いていくであろう一連の記事の内容をここで要約すれば、以下のようになる。
①「円安」問題は、世間で言われている日米の金利差とか米国社会のインフレの動向や労働市場における雇用情勢を踏まえたFRBによる金利操作に関わる云々の話ではないということである。ここで何より大切な視点は、「1対99」といった図式で語られる1%の米国社会を動かしていると言われてきた、いわゆる世界の超富裕層がいかなる金利や為替相場を望んでいるのかということをまずは押さえておかなければならないということである。もし彼らが、歴史のある段階においては、金利高とドル高が彼らの利益になると判断すれば、そうなるということであり、それがすべてに最優先されると同時にまた、歴史的出来事に対して大きな影響を及ぼすということである。
②その超富裕層が支配する私の語る「システム」においては、覇権システムの下で〈覇権国―中心国(1970年代までのAグループを構成)―半周辺国(同じくBグループを構成)ー周辺国(同じくCグループを構成)〉といった「親分ー子分」関係がつくり出されてきたが、今そうした関係が従来のA、B、CからB、C、Aへと転換・変容している最中にあり、その動きが同時にまた①の出来事にも影響・関係している、と私はみている。その際、重要なのは、日米関係をどのように位置づけ理解するかということである。とくに、米国が戦後からある時期に至るまで、覇権国として君臨していたという点である。
③そうした覇権システムにおいて、覇権国である米国との日米関係は、両者を対等の独立した主体的な主権国家同士の関係としては捉えられないということである。日米関係は、その意味において、米国という親会社である株式会社の本店と、地球儀や地図には「日本」と記されてはいるが、現実には子会社として位置する米国の本店の系列をなす米国支店として位置づけ理解できる関係なのだ。最初から日米関係など存在してはいないのだ。それゆえ、日本と米国の経済関係などあるはずもなかろう。すべては、米国内の本店と支店の出来事として、本来は語られなければならない物語であるということなのだ。ここで、日本は米国の51番目の州であると言われてきた話を思い浮かべるといいかもしれない。もっとも、残りの50州とは、その存在自体において大きな隔たりがあるのは言うまでもないのだが。
以上、①②③の話を念頭におきながら、これからの数回の話をまとめていきたい。
前回記事を書いてから、あっという間に一カ月が過ぎようとしている。この間にもいろいろな出来事があったのだが、私の思考はほとんど停止したままであった。やはり心身の老化のスピードを、少しでも緩やかにするためにも、何でもいいから記事を書き続けた方がいいのは確かである。そんな思いで、今回記事を書こうとしているのだが、これといって何か目新しい切り口が思いついたというわけでもないのだ。
それというのも、私の書きたかったことは、2014年に上梓した拙著でほとんど書き尽くしたからだ。その後の2016年に拙稿を発表してからは、このブログ記事でこれまでの拙著や拙論に関して補足説明を兼ねて、あれやこれやと書いてきただけであったから、もはや新しい何かを提示・提供できるはずもない。ただ、そんな中でも、記事を書きながら、このくだりは少し違う自分を発見できたと思うこともしばしばあったのも記憶しているのだが、同時にまた毎度のこと、「それがどうした」の連続でもあった。
そんな中でも、私が悔しく思うのは、私たちが手にする周りの出来事に関する情報は、「あちら側」から流されるそれであり、私にはほとんどその真偽を確認できないものばかりなのだ。それゆえ、私はそれらの情報を、私の頭の中で捉え直す作業を繰り返すことによって、あちら側との距離を取りながら、何とか私自身が納得できる情報へと練り直してきたのだ。そんなことを繰り返す中で、「こちら側」と思われていた情報も、なんだか怪しくなってしまい、気がつくと、私の書くものは世間一般の常識とはかけ離れたものになってしまった感が強まるばかり。
こうした点を断った上で、早速今次の問題に向き合うことにしよう。その際、これまた何度も論述してきたことだが、日本の今の円安の流れは、私の語る「システム」というか取り分けその中でも覇権システムの観点から位置づけ理解する必要があることを強調しておきたいのである。すなわち、日本の円安基調を、日米の金利差を始めとした日米間の経済関係を軸としてしばしば語られるのだが、そもそも日米関係とは何を意味しているのだろうか。
私たちは日米関係というとき、親分の米国と子分の日本とに置き換えて述べるのだが、その場合、「宗主国」の米国と「属国」の日本との関係は、対等の関係にはないことが連想されているのではあるまいか。つまり、ともに主権国家として位置づけ理解できないそうした関係としての日米関係が前提とされているのではあるまいか。それゆえ、そこから導かれるのは、議論の最初から、日米関係を、独立した主体的な主権国家間の関係として描くことは難しいということである。
日米の経済関係というとき、日本と米国がそれぞれ切り離された独自の独立した経済圏を保持しながら、両者の関係がつくられてきたとみることは、始めからおかしいのである。日本という経済圏は、覇権システムの中で、「親分ー子分」関係を前提としながら、親分の意向に従ってつくられてきたということを、議論の前提としなければならない、と私はみている。すなわち、日本に独自の主体的な経済圏に関する自由裁量権などありもしないのである。
ところがなのである。主権国家としての独自の自由裁量権などない日本であるにもかかわらず、あたかもそれが存在しかつ可能であるかのような論の展開をするから、私たちの議論はおかしなものとなるのではあるまいか。勿論、これは経済圏の話ばかりではなく、政治圏においても該当する話である。こうした点を踏まえるとき、最初から日米関係など存在していないのだ。あるのは、すべてが米国の政治経済圏であり、その中に米国の思い通りとなる、米国が創造した「日本」という空間とその政治経済圏が含まれているということなのだ。それゆえ、すべてが米国の政治経済圏の話に過ぎないにもかかわらず、オメデタイ私たちはあたかも主権国家として独立した主体的な国家として、日本国家の日本経済の担い手としての日本人を演じているのである。
何度でも言うが、私たちがみている日本と日本人の姿は蜃気楼であるのだ。その本当の姿は、米国という支配者に呑み込まれたままであり、そこにあるとして語られている姿は、残念ながら今も見えないのである。それにもかかわらず、私たちの議論は、こちら側においても、あちら側と同じように、日本とか日本経済の実態が存在しているかのように語っているのだから、これほどおかしなこともないだろう。たとえば、日本は米国のぞ国であると一方で語りながら、他方において、その属国である日本が主体的にあるべき日本経済の復活が可能であるかのように論じるのだから、これほどおかしな論の展開はないだろう。
宗主国と属国の関係であるとして日米関係を語るのであれば、それは日本の政治圏でも経済圏でも、社会・文化圏でも、独自の主体としての活動は到底望む術もなかろう。もしそれを可能とするのであれば、それこそ宗主国と属国の関係を、すなわち「親分ー子分」関係を「打破」することから始めなければならないに違いない。それは覇権システムの差別と排除の関係に目を向けることを意味する。日本の円安問題は、こうした覇権システムの「親分ー子分」関係に象徴される暴力関係に注目しないのであれば、ほとんど意味のある議論など望むことはできない。
だが、これはまたまた私たちを難しい地点に導くのである。そもそも日本の経済繁栄は、米国が日本を米国を親会社とする株式会社の本店に組み込まれた子会社としての米国支店として創造してくれたことによる。米国の覇権システムと「システム」における世界戦略によって、日本は戦後の驚異的な経済復興と発展・繁栄を謳歌したのだが、これは同時に米国の経済圏の中での出来事であったことを看過してはならない。つまり、日本の反映であるのは蜃気楼に過ぎなかったということだ。なぜなら、あの戦争の敗北と米国による占領統治以降、日本という独立した主体的な主権国家など存在しなかったからだ。そこにあったのは米国という株式会社を本社とした場合、米国本社の傘下としての米社支店でしかなかったということである。
こうした「事実」を、私たちが流布してきた政治経済に関する「常識」は見事に隠蔽してきたのだ。今もそうである。日本など存在していないにもかかわらず、日本の財務省や日銀が為替操作をして、米国の高金利やドル高政策に何とかして対策を講じているかのような話がほとんどだが、これまたインチキな議論の繰り返しではあるまいか。あたかも独立した独自の主体的な主権を保持する日本という国家が政府が存在しているかのように私たちは日々論じているのだが、滑稽な話ではあるまいか。
もっとも、こうしたおかしな話を、おかしくないかのようにあちら側の利害関係者は述べるのだが、こちら側の利害関係者も負けずと劣らずの論を繰り返すから、私は呆れてしまう。これまた何度も指摘したが、第9条論者は、護憲論者は、さらには改憲論者もそうなのだが、私たちが独立した主権国家の中で生きていないにもかかわらず、あたかもそうであるかのようにマヤカシの論を展開するのは、私には納得しかねることなのだ。
とにかく、嘘はダメである。少なくとも、私はそう言わざるを得ない。
だが、それでは日本保守党の飯山氏が先頃の東京15区の衆議院議員補欠選挙で論陣を張ったように、「強い国家と豊かな日本を取り戻せ」云々の主張は、はたしてどれほどの有効性を持つのだろうか。独立した主体的な主権国家となるためには、最低限度の国力と豊かな国民が存在しなければならないのは当然のことだとしても、問題は、私たちはどのような社会の中で生きてきたのかを、もう一度、振り返る必要があるだろう。結論を先取りして言うならば、それは私の語る「システム」の中で生きてきたということである。すなわち、覇権システム、世界資本主義システム、世界民主主義システムという三つの下位システムから構成される一つの「システム」である。(続)
*これから数回にわたっておそらく書いていくであろう一連の記事の内容をここで要約すれば、以下のようになる。
①「円安」問題は、世間で言われている日米の金利差とか米国社会のインフレの動向や労働市場における雇用情勢を踏まえたFRBによる金利操作に関わる云々の話ではないということである。ここで何より大切な視点は、「1対99」といった図式で語られる1%の米国社会を動かしていると言われてきた、いわゆる世界の超富裕層がいかなる金利や為替相場を望んでいるのかということをまずは押さえておかなければならないということである。もし彼らが、歴史のある段階においては、金利高とドル高が彼らの利益になると判断すれば、そうなるということであり、それがすべてに最優先されると同時にまた、歴史的出来事に対して大きな影響を及ぼすということである。
②その超富裕層が支配する私の語る「システム」においては、覇権システムの下で〈覇権国―中心国(1970年代までのAグループを構成)―半周辺国(同じくBグループを構成)ー周辺国(同じくCグループを構成)〉といった「親分ー子分」関係がつくり出されてきたが、今そうした関係が従来のA、B、CからB、C、Aへと転換・変容している最中にあり、その動きが同時にまた①の出来事にも影響・関係している、と私はみている。その際、重要なのは、日米関係をどのように位置づけ理解するかということである。とくに、米国が戦後からある時期に至るまで、覇権国として君臨していたという点である。
③そうした覇権システムにおいて、覇権国である米国との日米関係は、両者を対等の独立した主体的な主権国家同士の関係としては捉えられないということである。日米関係は、その意味において、米国という親会社である株式会社の本店と、地球儀や地図には「日本」と記されてはいるが、現実には子会社として位置する米国の本店の系列をなす米国支店として位置づけ理解できる関係なのだ。最初から日米関係など存在してはいないのだ。それゆえ、日本と米国の経済関係などあるはずもなかろう。すべては、米国内の本店と支店の出来事として、本来は語られなければならない物語であるということなのだ。ここで、日本は米国の51番目の州であると言われてきた話を思い浮かべるといいかもしれない。もっとも、残りの50州とは、その存在自体において大きな隔たりがあるのは言うまでもないのだが。
以上、①②③の話を念頭におきながら、これからの数回の話をまとめていきたい。
前回記事を書いてから、あっという間に一カ月が過ぎようとしている。この間にもいろいろな出来事があったのだが、私の思考はほとんど停止したままであった。やはり心身の老化のスピードを、少しでも緩やかにするためにも、何でもいいから記事を書き続けた方がいいのは確かである。そんな思いで、今回記事を書こうとしているのだが、これといって何か目新しい切り口が思いついたというわけでもないのだ。
それというのも、私の書きたかったことは、2014年に上梓した拙著でほとんど書き尽くしたからだ。その後の2016年に拙稿を発表してからは、このブログ記事でこれまでの拙著や拙論に関して補足説明を兼ねて、あれやこれやと書いてきただけであったから、もはや新しい何かを提示・提供できるはずもない。ただ、そんな中でも、記事を書きながら、このくだりは少し違う自分を発見できたと思うこともしばしばあったのも記憶しているのだが、同時にまた毎度のこと、「それがどうした」の連続でもあった。
そんな中でも、私が悔しく思うのは、私たちが手にする周りの出来事に関する情報は、「あちら側」から流されるそれであり、私にはほとんどその真偽を確認できないものばかりなのだ。それゆえ、私はそれらの情報を、私の頭の中で捉え直す作業を繰り返すことによって、あちら側との距離を取りながら、何とか私自身が納得できる情報へと練り直してきたのだ。そんなことを繰り返す中で、「こちら側」と思われていた情報も、なんだか怪しくなってしまい、気がつくと、私の書くものは世間一般の常識とはかけ離れたものになってしまった感が強まるばかり。
こうした点を断った上で、早速今次の問題に向き合うことにしよう。その際、これまた何度も論述してきたことだが、日本の今の円安の流れは、私の語る「システム」というか取り分けその中でも覇権システムの観点から位置づけ理解する必要があることを強調しておきたいのである。すなわち、日本の円安基調を、日米の金利差を始めとした日米間の経済関係を軸としてしばしば語られるのだが、そもそも日米関係とは何を意味しているのだろうか。
私たちは日米関係というとき、親分の米国と子分の日本とに置き換えて述べるのだが、その場合、「宗主国」の米国と「属国」の日本との関係は、対等の関係にはないことが連想されているのではあるまいか。つまり、ともに主権国家として位置づけ理解できないそうした関係としての日米関係が前提とされているのではあるまいか。それゆえ、そこから導かれるのは、議論の最初から、日米関係を、独立した主体的な主権国家間の関係として描くことは難しいということである。
日米の経済関係というとき、日本と米国がそれぞれ切り離された独自の独立した経済圏を保持しながら、両者の関係がつくられてきたとみることは、始めからおかしいのである。日本という経済圏は、覇権システムの中で、「親分ー子分」関係を前提としながら、親分の意向に従ってつくられてきたということを、議論の前提としなければならない、と私はみている。すなわち、日本に独自の主体的な経済圏に関する自由裁量権などありもしないのである。
ところがなのである。主権国家としての独自の自由裁量権などない日本であるにもかかわらず、あたかもそれが存在しかつ可能であるかのような論の展開をするから、私たちの議論はおかしなものとなるのではあるまいか。勿論、これは経済圏の話ばかりではなく、政治圏においても該当する話である。こうした点を踏まえるとき、最初から日米関係など存在していないのだ。あるのは、すべてが米国の政治経済圏であり、その中に米国の思い通りとなる、米国が創造した「日本」という空間とその政治経済圏が含まれているということなのだ。それゆえ、すべてが米国の政治経済圏の話に過ぎないにもかかわらず、オメデタイ私たちはあたかも主権国家として独立した主体的な国家として、日本国家の日本経済の担い手としての日本人を演じているのである。
何度でも言うが、私たちがみている日本と日本人の姿は蜃気楼であるのだ。その本当の姿は、米国という支配者に呑み込まれたままであり、そこにあるとして語られている姿は、残念ながら今も見えないのである。それにもかかわらず、私たちの議論は、こちら側においても、あちら側と同じように、日本とか日本経済の実態が存在しているかのように語っているのだから、これほどおかしなこともないだろう。たとえば、日本は米国のぞ国であると一方で語りながら、他方において、その属国である日本が主体的にあるべき日本経済の復活が可能であるかのように論じるのだから、これほどおかしな論の展開はないだろう。
宗主国と属国の関係であるとして日米関係を語るのであれば、それは日本の政治圏でも経済圏でも、社会・文化圏でも、独自の主体としての活動は到底望む術もなかろう。もしそれを可能とするのであれば、それこそ宗主国と属国の関係を、すなわち「親分ー子分」関係を「打破」することから始めなければならないに違いない。それは覇権システムの差別と排除の関係に目を向けることを意味する。日本の円安問題は、こうした覇権システムの「親分ー子分」関係に象徴される暴力関係に注目しないのであれば、ほとんど意味のある議論など望むことはできない。
だが、これはまたまた私たちを難しい地点に導くのである。そもそも日本の経済繁栄は、米国が日本を米国を親会社とする株式会社の本店に組み込まれた子会社としての米国支店として創造してくれたことによる。米国の覇権システムと「システム」における世界戦略によって、日本は戦後の驚異的な経済復興と発展・繁栄を謳歌したのだが、これは同時に米国の経済圏の中での出来事であったことを看過してはならない。つまり、日本の反映であるのは蜃気楼に過ぎなかったということだ。なぜなら、あの戦争の敗北と米国による占領統治以降、日本という独立した主体的な主権国家など存在しなかったからだ。そこにあったのは米国という株式会社を本社とした場合、米国本社の傘下としての米社支店でしかなかったということである。
こうした「事実」を、私たちが流布してきた政治経済に関する「常識」は見事に隠蔽してきたのだ。今もそうである。日本など存在していないにもかかわらず、日本の財務省や日銀が為替操作をして、米国の高金利やドル高政策に何とかして対策を講じているかのような話がほとんどだが、これまたインチキな議論の繰り返しではあるまいか。あたかも独立した独自の主体的な主権を保持する日本という国家が政府が存在しているかのように私たちは日々論じているのだが、滑稽な話ではあるまいか。
もっとも、こうしたおかしな話を、おかしくないかのようにあちら側の利害関係者は述べるのだが、こちら側の利害関係者も負けずと劣らずの論を繰り返すから、私は呆れてしまう。これまた何度も指摘したが、第9条論者は、護憲論者は、さらには改憲論者もそうなのだが、私たちが独立した主権国家の中で生きていないにもかかわらず、あたかもそうであるかのようにマヤカシの論を展開するのは、私には納得しかねることなのだ。
とにかく、嘘はダメである。少なくとも、私はそう言わざるを得ない。
だが、それでは日本保守党の飯山氏が先頃の東京15区の衆議院議員補欠選挙で論陣を張ったように、「強い国家と豊かな日本を取り戻せ」云々の主張は、はたしてどれほどの有効性を持つのだろうか。独立した主体的な主権国家となるためには、最低限度の国力と豊かな国民が存在しなければならないのは当然のことだとしても、問題は、私たちはどのような社会の中で生きてきたのかを、もう一度、振り返る必要があるだろう。結論を先取りして言うならば、それは私の語る「システム」の中で生きてきたということである。すなわち、覇権システム、世界資本主義システム、世界民主主義システムという三つの下位システムから構成される一つの「システム」である。(続)