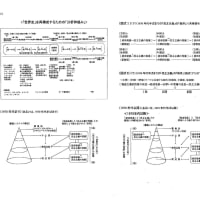「主権・国民・国家」とその背後に控える私的な利権・利害関係はどのように結びついているのかー私の語る「システム」論から、「〈開かずの間〉としての政治領域」の黙認によって、「日本」と「日本人」の自滅へと至る歩みは加速する-私の語る「システム」論から、都知事選関連報道を介して垣間見られる「自滅」へと至る身近な問題を考えるとき(続・続・続・続・続)
(最初に一言)
今回記事では、前回記事で論述できなかった重要な論点について補足しておきたい。
その前に、前回記事に関するごくごく簡単な補足説明をしておきたい。私の素朴な思いというか疑問を前回記事で述べていたのだが、それは日本の国家・政府の後押し?を受けた日本の大手銀行や大企業を介した中国への日本国土(領土)内にある動産・不動産の売り渡し感の強い活発な経済・交易活動は野放しであるのに対して、領海や領空への中国艦船や戦闘機による度重なる侵犯には目を怒らせるかのような反応を示すことである。私にはこの両者の出来事とその関係が見えにくいというか、あまりにも国民を愚弄する日本の政治・外交ではあるまいかと言わざるを得ない。もっとも、こうした出来事とその関係は、日本だけに限定されない。米国と中国においても、またEU諸国と中国との間でも見られるのである。
中国に対する激しい反発や嫌悪を示す日本の国家・政府さらにはその背後にいる国民は、中国との経済・交易関係をやめてしまえばいいはずなのに、それをしようとはしない。すべてを国内で賄えるように、鎖国時代の日本に戻ればいいはずなのに、と皮肉を言いたくもなる。ところが、私の見る限り、私の疑問は、多くの国民には共有されていないかのように思われて仕方がない。そんなに嫌いな中国ならば、と私は感じるのだが、どうも商売というか経済と政治は切り離しているようである。いわゆる「経済と政治は別物」という考え方である。この種の見方は一見したところ、非常に便利に棲み分けできる範疇として位置づけ理解できるとしても、それは危険な見方である、と私は言わざるを得ない。ここにも、経済と政治の両者を、その背後で結び付けている世界・セカイとそこでの戦争・センソウの舞台である覇権システムが見えていないのである。
それに関して付言すれば、以前にもこうした議論が流行したことがある。日米貿易摩擦・戦争と呼ばれた時代に、日本を称して、経済は一流、政治は二流と言われ、その一流と二流の両者の関係を問う議論はほとんど顕在化しなかった。さらに、日本の高度経済成長期において、またその後のバブルがはじけて米国との関係がぎくしゃくし始めるまで、日本は米国の半植民地であるとか属国云々の議論はメディアや論壇でもさほど話題にされてはいなかったように、私には思われる。経済は一流の時代においても、日本は米国に頭が上がらないままであり、米国あっての日本であったのだ。それゆえ、政治も経済も一流とか二流云々の話以前に、日本は主権国家として存在しているのかを自問自答するべきであったのだ。
それを踏まえるとき、ずっと私たちは私たち自身に対して嘘をついて生きてきたということである。そんな私たちだから、もう嘘には相当に寛容なのかもしれない。安倍元首相時代の彼とその取り巻き連中の数限りない大嘘を、私たち国民は野放しにしてきた。無論、そこにはメディアやそのお雇い知識人や芸能人たちの洗脳云々が関係していたことは否定できないものの、私たち国民の多くが総選挙で彼を信任することによって、嘘にうそをつき通してきた張本人とそのお仲間連中に無罪放免のお墨付きを与えたこと、これこそ諸悪の根源ではなかったろうか。そして、今また東京都知事選挙における小池学歴詐称問題が問われているのだが、これまた無罪放免となってしまうのか。これまた今更なのだが、本当に私たちはダラシナサを通り越しているのではあるまいか。
前回記事での「日本は終わっている」云々の話は、こうした問題とも関連するのは言うまでもない。だが、問題はさらにもっと別のところにある、と私は思うのだ。私は今も考えているのだが、どうも私自身を納得させる論の展開は、なお十分にはできていないので、当然ながら、読者にもどれほど私の考えていることが伝わっているか、それは心もとないのだが、とにかく、もう少し以下に論を展開しておきたい。何よりも私が一番感じていることは、前回記事との関連でいえば、蓮舫氏が以前に批判のやり玉にされた「二重国籍」問題とも関連するのだが、そもそも私たちは「一国家・一国民」という考え方の下で教育されそれを当然のこととして生きてきたのだが、果たしてそれは本当に間違いのない生き方であると、どこまで心底言い切れるものなのだろうか。
そもそも、この「一国家・一国民」の在り様は、どのような社会(世界・セカイ)の仕組みの中でつくられたものなのだろうか。その一国家・一国民という生き方には、いわゆる「正義」はあるのだろうか。本当に、一国家と一国民を創造したのは一国家と一国民の力だけで実現できたのであろうか。その際、例えば、中国は56の多民族によって構成されているものの、その多民族から一つの中華民族と、それが担い手となる一国民としての中国国民が誕生するとしても、果たして中国という国家は、また中国国民という国民は、中国一国家と一国民の存在の力だけで創造できたのか、と私は問い直したいのである。その問い直しは、日本や英国にも米国や仏国あるいはその他の国に対しても向けられる問題であるのは言を俟たない。
また、この問い直しと関連する問題にいわゆる「私」と「公」の関係がある。一個人として存在する「私」は、別の複数以上の「私」との関係において、「公」としての関係に転化すると言われてきた。それに対して、私はこのブログ記事でも指摘しているように、「私」という個人がたとえ複数以上集合したとしても、それはやはり私であり、それ以上の存在にはなり得ない、と述べていた。「私」が「公」に転化するためには、その私的存在を超越する何かが加わる必要があるとして、その際に付言していたのである。そこには、巨大な私的権力を行使できる「私」と、自分の命と暮らしを維持することさえままならぬ「私」の存在を前提としたとき、そうした私の構成する集合体を公としてしまっては、私的な巨大権力と、その存在を前にして何もできない無力な一人の存在でしかない無数の私の集合体を公として位置づけ理解してしまうならば、トドノツマリは、公的空間を独占し、支配できる私的巨大権力の力(暴力)を公的存在として、正当化・合法化する危険性を生じてしまう、と危惧したからである。今まさにグローバル化の時代の中で、そうした私の危惧した状況・状態が世界において、また日本において常態化しているのではあるまいか。
そんな私と公の関係を鑑みるとき、国民や国家をただそれだけの存在でもって公的存在としてみなすことは、あまりにも危険極まりない思考の在り方ではあるまいか。こうした私自身の問題意識を前提としたとき、「一国家・一国民」的生き方を、正義の御旗として掲げることには違和感を禁じざるを得ないのだ。それゆえ、既に拙著『21世紀の「日本」と「日本人」と「普遍主義」ー「平和な民主主義」社会の実現のために「勝ち続けなきゃならない」世界・セカイとそこでの戦争・センソウ』(晃洋書房 2014年)において詳しく論述しているのだが、行論の都合上、ここで再度いわゆる主権国家・国民国家の創造に至る流れを簡単に要約しておきたい。
私たちは歴史叙述の神話の呪縛の下にフランス革命とともに、一国民国家・一国民が誕生したと教えられてきた。私はこうした見方に対して、もしそれを認めるとしても、いきなりそうなるのではなく、覇権システムの形成と発展の歩みの中で、先のフランス革命に至る歴史を捉え直す必要性を語ってきた。いわゆるポルトガル、スペイン、そしてオランダからイギリスへと続く覇権国家の興亡史の歩みの中で、主権国家の誕生を見るのだが、その際、どうしても子の興亡史の歩みを押さえておかない限り、主権国家からそれを前提として誕生する国民国家へと向かう歩みを語れない、と私はみているのである。
そうした点を踏まえて提示されたのが、私の語る「システム」論で描かれる〈「システム」とその関係の歩み〉とそのモデル({[A]→(×)[B]→×[C]})に他ならない。(*なお、モデルは共時態型・省略形である。詳しくは前景拙著または以前のブログ記事で紹介しているくだりを参照されたい。)私がそこで強調したのは、主権国家、そして国民国家と国民は、そのモデルで描かれるA、B、C間の差別と排除の関係を前提とすることによって、初めて実現できたということであった。そこから私が読者に是非ともお伝えしたかったのは、たとえばフランスの主権国家、国民国家と国民の誕生は、フランス一国家だけの、一国民だけの力では到底、実現するのは困難であったという、まさにA、B、Cの関係を前提とすることによって初めて実現可能であったという話であった。
それゆえ、こうした自己決定権の獲得とその実現のために繰り返される争奪戦を介してつくり出された差別と排除の暴力関係を前提として誕生した国家や国民を公的象徴とすることは、私のモデルで描く差別と排除の関係を正当化合法化することに手を貸してしまうことを意味する。さらには、そうすることで、この差別と排除の関係の形成と発展そしてその維持と存続にい大きく与った王族や貴族、大商人、聖職者を始めとする私的特権層の私的利権・利害関係を、公的な装いの下に隠蔽する、見えなくしてしまうのだ。それは今まさに、私たちの眼前に展開されている光景ではあるまいか。都知事選に絡めていえば、小池氏が手掛けた一連の都民の生活をより豊かにする云々の施策は、見事に私的な利権・利害関係勢力を肥え太らせてきた都政を如実に反映したものというしかあるまい。
(最後に一言)
それでは、小池氏とその取り巻き連中が悪いのだろうか。勿論、そうではなかろう。悪いのは都民の中の、資産をあまり持たない普通の庶民であり、選挙にもいかない力のない「私」である。結局は自業自得というしかないのだ。小池氏を取り巻く連中は、巨大な私的権力集団を構成している。それは動かない事実であり、また私たち?にとっての壁でもある。だが、力のない私という存在は数では勝っているのもこれまた事実なのだ。都知事選挙で、たとえ蓮舫氏が勝利したとしても、またその余勢をかって、次の総選挙で立憲と共産党と社民党と令和新撰組が勝利したとしても、私の語る「システム」はほとんど微動だにしないに違いない。
それは確かにそうだろうが、それでも、もうそろそろこの辺で自公政権とは、たとえ表面的なものに過ぎないとしても、少しは毛色の違った政治を選択してもいい、と私は思っているし、切に願っているのだ。私のできることはそれこそほとんどないのだが、それでも何とかできる範囲で、記事を書いていきたい。(続)
(最初に一言)
今回記事では、前回記事で論述できなかった重要な論点について補足しておきたい。
その前に、前回記事に関するごくごく簡単な補足説明をしておきたい。私の素朴な思いというか疑問を前回記事で述べていたのだが、それは日本の国家・政府の後押し?を受けた日本の大手銀行や大企業を介した中国への日本国土(領土)内にある動産・不動産の売り渡し感の強い活発な経済・交易活動は野放しであるのに対して、領海や領空への中国艦船や戦闘機による度重なる侵犯には目を怒らせるかのような反応を示すことである。私にはこの両者の出来事とその関係が見えにくいというか、あまりにも国民を愚弄する日本の政治・外交ではあるまいかと言わざるを得ない。もっとも、こうした出来事とその関係は、日本だけに限定されない。米国と中国においても、またEU諸国と中国との間でも見られるのである。
中国に対する激しい反発や嫌悪を示す日本の国家・政府さらにはその背後にいる国民は、中国との経済・交易関係をやめてしまえばいいはずなのに、それをしようとはしない。すべてを国内で賄えるように、鎖国時代の日本に戻ればいいはずなのに、と皮肉を言いたくもなる。ところが、私の見る限り、私の疑問は、多くの国民には共有されていないかのように思われて仕方がない。そんなに嫌いな中国ならば、と私は感じるのだが、どうも商売というか経済と政治は切り離しているようである。いわゆる「経済と政治は別物」という考え方である。この種の見方は一見したところ、非常に便利に棲み分けできる範疇として位置づけ理解できるとしても、それは危険な見方である、と私は言わざるを得ない。ここにも、経済と政治の両者を、その背後で結び付けている世界・セカイとそこでの戦争・センソウの舞台である覇権システムが見えていないのである。
それに関して付言すれば、以前にもこうした議論が流行したことがある。日米貿易摩擦・戦争と呼ばれた時代に、日本を称して、経済は一流、政治は二流と言われ、その一流と二流の両者の関係を問う議論はほとんど顕在化しなかった。さらに、日本の高度経済成長期において、またその後のバブルがはじけて米国との関係がぎくしゃくし始めるまで、日本は米国の半植民地であるとか属国云々の議論はメディアや論壇でもさほど話題にされてはいなかったように、私には思われる。経済は一流の時代においても、日本は米国に頭が上がらないままであり、米国あっての日本であったのだ。それゆえ、政治も経済も一流とか二流云々の話以前に、日本は主権国家として存在しているのかを自問自答するべきであったのだ。
それを踏まえるとき、ずっと私たちは私たち自身に対して嘘をついて生きてきたということである。そんな私たちだから、もう嘘には相当に寛容なのかもしれない。安倍元首相時代の彼とその取り巻き連中の数限りない大嘘を、私たち国民は野放しにしてきた。無論、そこにはメディアやそのお雇い知識人や芸能人たちの洗脳云々が関係していたことは否定できないものの、私たち国民の多くが総選挙で彼を信任することによって、嘘にうそをつき通してきた張本人とそのお仲間連中に無罪放免のお墨付きを与えたこと、これこそ諸悪の根源ではなかったろうか。そして、今また東京都知事選挙における小池学歴詐称問題が問われているのだが、これまた無罪放免となってしまうのか。これまた今更なのだが、本当に私たちはダラシナサを通り越しているのではあるまいか。
前回記事での「日本は終わっている」云々の話は、こうした問題とも関連するのは言うまでもない。だが、問題はさらにもっと別のところにある、と私は思うのだ。私は今も考えているのだが、どうも私自身を納得させる論の展開は、なお十分にはできていないので、当然ながら、読者にもどれほど私の考えていることが伝わっているか、それは心もとないのだが、とにかく、もう少し以下に論を展開しておきたい。何よりも私が一番感じていることは、前回記事との関連でいえば、蓮舫氏が以前に批判のやり玉にされた「二重国籍」問題とも関連するのだが、そもそも私たちは「一国家・一国民」という考え方の下で教育されそれを当然のこととして生きてきたのだが、果たしてそれは本当に間違いのない生き方であると、どこまで心底言い切れるものなのだろうか。
そもそも、この「一国家・一国民」の在り様は、どのような社会(世界・セカイ)の仕組みの中でつくられたものなのだろうか。その一国家・一国民という生き方には、いわゆる「正義」はあるのだろうか。本当に、一国家と一国民を創造したのは一国家と一国民の力だけで実現できたのであろうか。その際、例えば、中国は56の多民族によって構成されているものの、その多民族から一つの中華民族と、それが担い手となる一国民としての中国国民が誕生するとしても、果たして中国という国家は、また中国国民という国民は、中国一国家と一国民の存在の力だけで創造できたのか、と私は問い直したいのである。その問い直しは、日本や英国にも米国や仏国あるいはその他の国に対しても向けられる問題であるのは言を俟たない。
また、この問い直しと関連する問題にいわゆる「私」と「公」の関係がある。一個人として存在する「私」は、別の複数以上の「私」との関係において、「公」としての関係に転化すると言われてきた。それに対して、私はこのブログ記事でも指摘しているように、「私」という個人がたとえ複数以上集合したとしても、それはやはり私であり、それ以上の存在にはなり得ない、と述べていた。「私」が「公」に転化するためには、その私的存在を超越する何かが加わる必要があるとして、その際に付言していたのである。そこには、巨大な私的権力を行使できる「私」と、自分の命と暮らしを維持することさえままならぬ「私」の存在を前提としたとき、そうした私の構成する集合体を公としてしまっては、私的な巨大権力と、その存在を前にして何もできない無力な一人の存在でしかない無数の私の集合体を公として位置づけ理解してしまうならば、トドノツマリは、公的空間を独占し、支配できる私的巨大権力の力(暴力)を公的存在として、正当化・合法化する危険性を生じてしまう、と危惧したからである。今まさにグローバル化の時代の中で、そうした私の危惧した状況・状態が世界において、また日本において常態化しているのではあるまいか。
そんな私と公の関係を鑑みるとき、国民や国家をただそれだけの存在でもって公的存在としてみなすことは、あまりにも危険極まりない思考の在り方ではあるまいか。こうした私自身の問題意識を前提としたとき、「一国家・一国民」的生き方を、正義の御旗として掲げることには違和感を禁じざるを得ないのだ。それゆえ、既に拙著『21世紀の「日本」と「日本人」と「普遍主義」ー「平和な民主主義」社会の実現のために「勝ち続けなきゃならない」世界・セカイとそこでの戦争・センソウ』(晃洋書房 2014年)において詳しく論述しているのだが、行論の都合上、ここで再度いわゆる主権国家・国民国家の創造に至る流れを簡単に要約しておきたい。
私たちは歴史叙述の神話の呪縛の下にフランス革命とともに、一国民国家・一国民が誕生したと教えられてきた。私はこうした見方に対して、もしそれを認めるとしても、いきなりそうなるのではなく、覇権システムの形成と発展の歩みの中で、先のフランス革命に至る歴史を捉え直す必要性を語ってきた。いわゆるポルトガル、スペイン、そしてオランダからイギリスへと続く覇権国家の興亡史の歩みの中で、主権国家の誕生を見るのだが、その際、どうしても子の興亡史の歩みを押さえておかない限り、主権国家からそれを前提として誕生する国民国家へと向かう歩みを語れない、と私はみているのである。
そうした点を踏まえて提示されたのが、私の語る「システム」論で描かれる〈「システム」とその関係の歩み〉とそのモデル({[A]→(×)[B]→×[C]})に他ならない。(*なお、モデルは共時態型・省略形である。詳しくは前景拙著または以前のブログ記事で紹介しているくだりを参照されたい。)私がそこで強調したのは、主権国家、そして国民国家と国民は、そのモデルで描かれるA、B、C間の差別と排除の関係を前提とすることによって、初めて実現できたということであった。そこから私が読者に是非ともお伝えしたかったのは、たとえばフランスの主権国家、国民国家と国民の誕生は、フランス一国家だけの、一国民だけの力では到底、実現するのは困難であったという、まさにA、B、Cの関係を前提とすることによって初めて実現可能であったという話であった。
それゆえ、こうした自己決定権の獲得とその実現のために繰り返される争奪戦を介してつくり出された差別と排除の暴力関係を前提として誕生した国家や国民を公的象徴とすることは、私のモデルで描く差別と排除の関係を正当化合法化することに手を貸してしまうことを意味する。さらには、そうすることで、この差別と排除の関係の形成と発展そしてその維持と存続にい大きく与った王族や貴族、大商人、聖職者を始めとする私的特権層の私的利権・利害関係を、公的な装いの下に隠蔽する、見えなくしてしまうのだ。それは今まさに、私たちの眼前に展開されている光景ではあるまいか。都知事選に絡めていえば、小池氏が手掛けた一連の都民の生活をより豊かにする云々の施策は、見事に私的な利権・利害関係勢力を肥え太らせてきた都政を如実に反映したものというしかあるまい。
(最後に一言)
それでは、小池氏とその取り巻き連中が悪いのだろうか。勿論、そうではなかろう。悪いのは都民の中の、資産をあまり持たない普通の庶民であり、選挙にもいかない力のない「私」である。結局は自業自得というしかないのだ。小池氏を取り巻く連中は、巨大な私的権力集団を構成している。それは動かない事実であり、また私たち?にとっての壁でもある。だが、力のない私という存在は数では勝っているのもこれまた事実なのだ。都知事選挙で、たとえ蓮舫氏が勝利したとしても、またその余勢をかって、次の総選挙で立憲と共産党と社民党と令和新撰組が勝利したとしても、私の語る「システム」はほとんど微動だにしないに違いない。
それは確かにそうだろうが、それでも、もうそろそろこの辺で自公政権とは、たとえ表面的なものに過ぎないとしても、少しは毛色の違った政治を選択してもいい、と私は思っているし、切に願っているのだ。私のできることはそれこそほとんどないのだが、それでも何とかできる範囲で、記事を書いていきたい。(続)