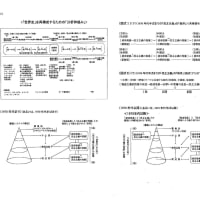「中国〈脅威〉論」の危うさー私の語る「システム」論から、「過敏症」を自認する私の気になることをあれこれと思い浮かべるとき(続・続)
(最初に一言)
何を書いても言っても、「独り言」の域を出ないので、ブログ記事の投稿も意味はないと思いつつも、それでもまた今日のNHKの朝の番組での「中国脅威」云々の発言に接した?ので、やはり独り言でも述べておきたいとの思いが強くこれから書いてみたい。
私の記憶違いであれば、申し訳ないのだが、今日の午前中のNHKの番組で確か前駐米大使の杉山氏が、「中国脅威」を注視すべき云々の発言をしていたように、私には聞き取れた「公共」放送のNHKで、国民の税金が投入されているテレビ局の、NHKが出演要請を依頼したであろう政治番組での話なのだ。しかも、そうした一方に偏した発言に対して、「公平・公正」を保持するためのバランスある別の論者の発言はないのだから、これはもうオカシイを通り越した偏向報道である、と私は感じた次第なのだ。
元来、NHKの政治関連番組にはこうした偏向報道はつきものだと、私はいつも思っていたから、もう今さらなのだが、それにしても、こんな番組内容を素直に受け入れる視聴者がいるならば、それこそ日本の現状を的確に位置づけ理解するのはますます難しくなるに違いない。私には、この種の中国脅威論は、それこそそれ自体が私の命と暮らしを守るための安全保障における脅威とならざるを得なくなる。私には覇権国(超大国)として君臨してきた米国もかなりの脅威として受け止められる。もっとも、そこには但し書きを必要とする。私の語る「システム」とその下位システムの一つである覇権システムが何よりも脅威をつくり出している。そうした「システム」と覇権システムの下での米国によって脅威が導かれるのだが。それを踏まえて言うとき、これまでは中国というよりも米国の方がずっと日本には脅威であった、と私はみている。
私は不思議に思うのだが、どうして先の杉山氏は米国脅威を、中国脅威と同様に、あるいはそれ以上に扱わないのか、と。勿論、こんな野暮な物言いもおかしな話だが、米国は中国と比べて、もはやというかずっと以前から、脅威の対象でもないのだ。どうしてなのか。親分の米国に子分としての日本が組み込まれているので、米国に対しては、「同等」の力関係にはないことから、もはや驚異などとして位置づけられることなどできないのである。私には、そうした子分として、従属国として組み込まれてきた日米関係を何の疑いもなく受容できる態度こそが脅威なのである。
それに対して、杉山氏は中国脅威論の必要性を唱えるのだが、私にはこれまたおかしなことに思えるのだ。米国は中国を対等の戦略的競争相手として位置づけ理解している。そんな中国に対して、日本のような「弱小国」があたかも中国と同等の力を保持しているかのような観点から、中国脅威論の必要性云々の議論を展開するのは、少々ずれすぎているのではあるまいか。それが意識されないのは、おそらく杉山氏の頭の中には、米国べったりの日本が前提とされていて、あくまでも米国と合体した、米国に呑み込まれた日本を前提とした中国脅威論となるのではあるまいか。もし米国に、そのハシゴを外された時には、いったい私たちはどうするのだろうか。こんな由々しき事態を鑑みることのない脅威論は、それこそそれ自体が脅威をつくり出すのは必至であろう。
私は、自己決定権の獲得とその実現を目指すための争奪戦を介した「親分ー子分」関係に見いだされる差別と排除の関係を刻印する覇権システムと、私の語る「システム」の中で生きることを余儀なくされているシステム人の一人であることから、私にとってはすべてが脅威とならざるを得ないのだ。私自身も元より潜在的な脅威の対象としか思われない存在であり、そんな私のような人間の集合体である日本もまた脅威として映っている。勿論、それは米国であろうが、中国だろうが、イギリス、フランス、ロシアだろうが、「システム」に組み込まれている国とそこに暮らす人々は、いつ何時私たちと彼らの関係が激変するかもわからない。もっとも、それは仕方がないことでもある。差別と排除の関係を前提としてつくり出されてきた「システム」の中で生きている以上、何が引き起こされたとしても、おかしくはないからである。問題は、こうした覇権システムや「システム」の中で生き続けているがゆえに、私たちが直面するであろう脅威に私たちの目を向ける代わりに、ある特定の諸国や彼らの政治体制を槍玉に挙げるというやり方である。私たちの政治体制に関する研究は、私の見る限り、まだまだ偏向した研究段階にあるとしか思われないのだ。
(最後に一言)
もっと早く書き始めればよかった。もう心身にはきつくなったので、この辺でやめておきたい。覇権システムや「システム」、政治体制についての話は、拙著や拙論を参照されたい。
(最初に一言)
何を書いても言っても、「独り言」の域を出ないので、ブログ記事の投稿も意味はないと思いつつも、それでもまた今日のNHKの朝の番組での「中国脅威」云々の発言に接した?ので、やはり独り言でも述べておきたいとの思いが強くこれから書いてみたい。
私の記憶違いであれば、申し訳ないのだが、今日の午前中のNHKの番組で確か前駐米大使の杉山氏が、「中国脅威」を注視すべき云々の発言をしていたように、私には聞き取れた「公共」放送のNHKで、国民の税金が投入されているテレビ局の、NHKが出演要請を依頼したであろう政治番組での話なのだ。しかも、そうした一方に偏した発言に対して、「公平・公正」を保持するためのバランスある別の論者の発言はないのだから、これはもうオカシイを通り越した偏向報道である、と私は感じた次第なのだ。
元来、NHKの政治関連番組にはこうした偏向報道はつきものだと、私はいつも思っていたから、もう今さらなのだが、それにしても、こんな番組内容を素直に受け入れる視聴者がいるならば、それこそ日本の現状を的確に位置づけ理解するのはますます難しくなるに違いない。私には、この種の中国脅威論は、それこそそれ自体が私の命と暮らしを守るための安全保障における脅威とならざるを得なくなる。私には覇権国(超大国)として君臨してきた米国もかなりの脅威として受け止められる。もっとも、そこには但し書きを必要とする。私の語る「システム」とその下位システムの一つである覇権システムが何よりも脅威をつくり出している。そうした「システム」と覇権システムの下での米国によって脅威が導かれるのだが。それを踏まえて言うとき、これまでは中国というよりも米国の方がずっと日本には脅威であった、と私はみている。
私は不思議に思うのだが、どうして先の杉山氏は米国脅威を、中国脅威と同様に、あるいはそれ以上に扱わないのか、と。勿論、こんな野暮な物言いもおかしな話だが、米国は中国と比べて、もはやというかずっと以前から、脅威の対象でもないのだ。どうしてなのか。親分の米国に子分としての日本が組み込まれているので、米国に対しては、「同等」の力関係にはないことから、もはや驚異などとして位置づけられることなどできないのである。私には、そうした子分として、従属国として組み込まれてきた日米関係を何の疑いもなく受容できる態度こそが脅威なのである。
それに対して、杉山氏は中国脅威論の必要性を唱えるのだが、私にはこれまたおかしなことに思えるのだ。米国は中国を対等の戦略的競争相手として位置づけ理解している。そんな中国に対して、日本のような「弱小国」があたかも中国と同等の力を保持しているかのような観点から、中国脅威論の必要性云々の議論を展開するのは、少々ずれすぎているのではあるまいか。それが意識されないのは、おそらく杉山氏の頭の中には、米国べったりの日本が前提とされていて、あくまでも米国と合体した、米国に呑み込まれた日本を前提とした中国脅威論となるのではあるまいか。もし米国に、そのハシゴを外された時には、いったい私たちはどうするのだろうか。こんな由々しき事態を鑑みることのない脅威論は、それこそそれ自体が脅威をつくり出すのは必至であろう。
私は、自己決定権の獲得とその実現を目指すための争奪戦を介した「親分ー子分」関係に見いだされる差別と排除の関係を刻印する覇権システムと、私の語る「システム」の中で生きることを余儀なくされているシステム人の一人であることから、私にとってはすべてが脅威とならざるを得ないのだ。私自身も元より潜在的な脅威の対象としか思われない存在であり、そんな私のような人間の集合体である日本もまた脅威として映っている。勿論、それは米国であろうが、中国だろうが、イギリス、フランス、ロシアだろうが、「システム」に組み込まれている国とそこに暮らす人々は、いつ何時私たちと彼らの関係が激変するかもわからない。もっとも、それは仕方がないことでもある。差別と排除の関係を前提としてつくり出されてきた「システム」の中で生きている以上、何が引き起こされたとしても、おかしくはないからである。問題は、こうした覇権システムや「システム」の中で生き続けているがゆえに、私たちが直面するであろう脅威に私たちの目を向ける代わりに、ある特定の諸国や彼らの政治体制を槍玉に挙げるというやり方である。私たちの政治体制に関する研究は、私の見る限り、まだまだ偏向した研究段階にあるとしか思われないのだ。
(最後に一言)
もっと早く書き始めればよかった。もう心身にはきつくなったので、この辺でやめておきたい。覇権システムや「システム」、政治体制についての話は、拙著や拙論を参照されたい。