昨日の朝日新聞夕刊に、「はみ出し歴史ファイル パスツール 折れぬ研究心、細菌学の基礎築く」という記事がありました。
青木裕司・河合塾講師が、世界史のユニークな話題を紹介してくださるコーナーです。
細菌やウイルスを研究することで、病気を予防する「予防医学」は、この150年ほどで急速に発展したのだそうです。
「予防医学」や「細菌学」の基礎を作ったのは、ルイ・パスツール(フランスの科学者、1822~1895年)です。
ロゼワインの産地として有名な、フランスのジェラ地方に生まれました。
32歳で、リール大学の理学部長になっています。
1863年、フランスが輸出したワインが大量に腐敗するという事件が起きます。
腐敗したワインは、520万キロリットル、瓶だと70億本にあたる量でした。
パスツールは、ワインが腐敗した原因は、細菌の繁殖と考えました。
ワインの香りや風味はそのままに、殺菌する方法を研究しました。
55度という低音で殺菌する方法を、発見しました。
「パスツール法」(低音殺菌法)は、英語の動詞だとパスチャライズになります。
牛乳瓶の殺菌等には、今でもこの方法が使われていて、「パスチャライズ」と瓶に書かれているそうです。
この研究を発表した頃、パスツールは多くの不幸に見舞われました。
父親、続いて娘2人が、腸チフスで亡くなりました。
パスツール自身も、脳溢血で左半身の自由がなくなりました。
それでも、研究心は折れることなく、狂犬病の研究に取り組み、狂犬病のワクチンの生成に成功しました。
1895年、パスツールは亡くなり、研究所内に埋葬されました。
1940年に、ナチス・ドイツがパリを占領しました。
ドイツの軍医が、パスツールの墓の場所を尋ねると、墓守の老人は墓を見せることを拒み、自殺してしまったそうです。
この墓守は、メステルという人で、少年時代にパスツールから狂犬病ワクチンを投与されて、命を救われた、ということでした。
-------------------
「パスツール研究所」等の名前は聞きますが、パスツールがどんな方だったかは知りませんでした。
ウィキペディアの「ルイ・パスツール」の項を読むと、皮なめし職人の息子として生まれたとあります。
1843年に高等師範学校に入学、
1846年に博士号を取得しました。
化学を専攻ましたが、初めは才能がみられず、指導した教授の一人は彼を「平凡である」(日本的には「普通」の評価。5段階で3くらい)と評しました。
1865年には、養蚕業の救済に取り組みました。
その頃、微粒子病と呼ばれる病気により、たくさんのカイコが死んでいました。
カイコの生態を知るために、ファーブルに教えてもらうため、訪問したともありました。
ファーブル(昆虫学者)もフランス人で、意外な2人の接点があったのだと興味深く感じました。


青木裕司・河合塾講師が、世界史のユニークな話題を紹介してくださるコーナーです。
細菌やウイルスを研究することで、病気を予防する「予防医学」は、この150年ほどで急速に発展したのだそうです。
「予防医学」や「細菌学」の基礎を作ったのは、ルイ・パスツール(フランスの科学者、1822~1895年)です。
ロゼワインの産地として有名な、フランスのジェラ地方に生まれました。
32歳で、リール大学の理学部長になっています。
1863年、フランスが輸出したワインが大量に腐敗するという事件が起きます。
腐敗したワインは、520万キロリットル、瓶だと70億本にあたる量でした。
パスツールは、ワインが腐敗した原因は、細菌の繁殖と考えました。
ワインの香りや風味はそのままに、殺菌する方法を研究しました。
55度という低音で殺菌する方法を、発見しました。
「パスツール法」(低音殺菌法)は、英語の動詞だとパスチャライズになります。
牛乳瓶の殺菌等には、今でもこの方法が使われていて、「パスチャライズ」と瓶に書かれているそうです。
この研究を発表した頃、パスツールは多くの不幸に見舞われました。
父親、続いて娘2人が、腸チフスで亡くなりました。
パスツール自身も、脳溢血で左半身の自由がなくなりました。
それでも、研究心は折れることなく、狂犬病の研究に取り組み、狂犬病のワクチンの生成に成功しました。
1895年、パスツールは亡くなり、研究所内に埋葬されました。
1940年に、ナチス・ドイツがパリを占領しました。
ドイツの軍医が、パスツールの墓の場所を尋ねると、墓守の老人は墓を見せることを拒み、自殺してしまったそうです。
この墓守は、メステルという人で、少年時代にパスツールから狂犬病ワクチンを投与されて、命を救われた、ということでした。
-------------------
「パスツール研究所」等の名前は聞きますが、パスツールがどんな方だったかは知りませんでした。
ウィキペディアの「ルイ・パスツール」の項を読むと、皮なめし職人の息子として生まれたとあります。
1843年に高等師範学校に入学、
1846年に博士号を取得しました。
化学を専攻ましたが、初めは才能がみられず、指導した教授の一人は彼を「平凡である」(日本的には「普通」の評価。5段階で3くらい)と評しました。
1865年には、養蚕業の救済に取り組みました。
その頃、微粒子病と呼ばれる病気により、たくさんのカイコが死んでいました。
カイコの生態を知るために、ファーブルに教えてもらうため、訪問したともありました。
ファーブル(昆虫学者)もフランス人で、意外な2人の接点があったのだと興味深く感じました。










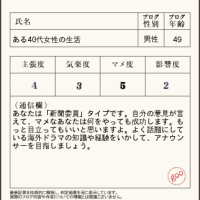
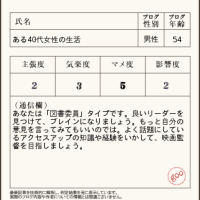





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます