今日の朝日新聞に、「災害用ロボ 日本ピカイチ 米のコンテスト、首位で決勝進出」という記事がありました。
アメリカで行われた災害現場用ロボットのコンテストで、日本のチームが1位になったのだそうです。
このコンテストは、アメリカ国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)の主催です。
東京電力福島第一原発事故をきっかけに、開催されました。
危険な現場で、人間の代わりに作業するロボットの開発を目標にしています。
日程は2日間、16チームが参加し、日本の「SCHAFT(シャフト)」チームが1位になりました。
「SCHAFT(シャフト)」チームは、東京大学のロボット研究者らのチームです。
二足歩行ロボットで、車の運転(多くのチームが苦戦)や約75メートルのジグザグ道の完走をしました。
16チーム中でトップの27点で1位となりました。
2位は、フロリダ州の研究機関「IHMC」 ということです。
-------------------------------
アメリカ等のチームが集まる中、日本のチームが1位とはすばらしいです。
福島原発の事故では、何種類かの機械が投入されたようですが、その時はあまり成果をあげることができなかったようです。
それを機会に、コンテストが企画されたのですね。
どうやって、並みいる強豪に勝つことがきでたのでしょう?
「SCHAFT」で見てみました。
「『SCHAFT』が優勝! 全種目クリアでぶっちぎりの1位 - ガジェット通信」というニュースサイトの記事が3番目に出てきました。
(http://getnews.jp/archives/480260参照)
競技会の正式名称は、災害救助ロボット競技会『DARPA Robotics Challenge TRIALS 2013』というようです。
全8種目を完了したのは参加16チーム中で唯一。32点満点中27点を獲得し、2位以下のチームに圧倒的な差をつけての優勝だった。
資金にも才能にも恵まれていそうなNASAや理系最高峰の頭脳が集うMITらの強豪を押しのけての勝利は値千金。
とありました。
車の運転は、8種目の中の「Vehicle」という種目で、
車を運転(ハンドル、アクセル・ブレーキを操作)して規定コースを走破する のだそうです。
自分で考え、機械が自分で運転できるものなんですね。
ロボットは、そこまで進んでいるのかと驚きました。
こんな世界のトップになるようなロボットを作った「SCHAFT」は、いったいどういうチームなのでしょう?
「SCHAFT社CFO加藤氏に聞く、Google買収までの舞台裏【@itmsc ...」という日本や世界の技術に関するブログの記事が5番目にありました。
(http://techwave.jp/archives/schaft_cfo_takashi_kato_interview.html参照)
「2011年当時に東京大学の研究室で人型ロボットの研究をしていた中西雄飛氏と浦田順一氏だが、技術が実用につながらないことや思うように予算が得られないことを歯がゆく感じ、自分たちで起業したいと思い描いていた」
「創業当時、なかなか資金の調達が決まらず、中西氏、浦田氏と数々のファンドを回る日々の中で、彼らをサポートしてくれる協力者が次第に増えていき、そこからGoogleへつながる人脈を得た。アメリカの国防総省が主催するロボットのコンテスト「DARPA Robotics Challenge(DRC)」に参加していたことも功を奏した」
「2013年11月、Googleが日本のロボット開発会社「SCHAFT」を買収した。この買収劇の中で大きな役割を果たしたのが、SCHAFT社の共同創業者および元取締役CFOの加藤崇氏だ」
とあり、「SCHAFT」はgoogleに買収されたようです。
記事を読むと、ロボットを開発するにはかなりまとまった資金が必要で、そこに成功したことが大きかったようです。
技術面での開発の話をと思って探し始めたのですが、資金面がそんなに重要とは知りませんでした。
このコンテストは、2年間のコンテストで、
「今回の勝利により、同チームは来年開催される決勝戦への進出が決定。そこでさらに優勝すれば200万ドルの賞金を獲得することになる」
(ガジェット通信)
ということです。
「SCHAFT(シャフト)」チームを応援していきたいと思います。


アメリカで行われた災害現場用ロボットのコンテストで、日本のチームが1位になったのだそうです。
このコンテストは、アメリカ国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)の主催です。
東京電力福島第一原発事故をきっかけに、開催されました。
危険な現場で、人間の代わりに作業するロボットの開発を目標にしています。
日程は2日間、16チームが参加し、日本の「SCHAFT(シャフト)」チームが1位になりました。
「SCHAFT(シャフト)」チームは、東京大学のロボット研究者らのチームです。
二足歩行ロボットで、車の運転(多くのチームが苦戦)や約75メートルのジグザグ道の完走をしました。
16チーム中でトップの27点で1位となりました。
2位は、フロリダ州の研究機関「IHMC」 ということです。
-------------------------------
アメリカ等のチームが集まる中、日本のチームが1位とはすばらしいです。
福島原発の事故では、何種類かの機械が投入されたようですが、その時はあまり成果をあげることができなかったようです。
それを機会に、コンテストが企画されたのですね。
どうやって、並みいる強豪に勝つことがきでたのでしょう?
「SCHAFT」で見てみました。
「『SCHAFT』が優勝! 全種目クリアでぶっちぎりの1位 - ガジェット通信」というニュースサイトの記事が3番目に出てきました。
(http://getnews.jp/archives/480260参照)
競技会の正式名称は、災害救助ロボット競技会『DARPA Robotics Challenge TRIALS 2013』というようです。
全8種目を完了したのは参加16チーム中で唯一。32点満点中27点を獲得し、2位以下のチームに圧倒的な差をつけての優勝だった。
資金にも才能にも恵まれていそうなNASAや理系最高峰の頭脳が集うMITらの強豪を押しのけての勝利は値千金。
とありました。
車の運転は、8種目の中の「Vehicle」という種目で、
車を運転(ハンドル、アクセル・ブレーキを操作)して規定コースを走破する のだそうです。
自分で考え、機械が自分で運転できるものなんですね。
ロボットは、そこまで進んでいるのかと驚きました。
こんな世界のトップになるようなロボットを作った「SCHAFT」は、いったいどういうチームなのでしょう?
「SCHAFT社CFO加藤氏に聞く、Google買収までの舞台裏【@itmsc ...」という日本や世界の技術に関するブログの記事が5番目にありました。
(http://techwave.jp/archives/schaft_cfo_takashi_kato_interview.html参照)
「2011年当時に東京大学の研究室で人型ロボットの研究をしていた中西雄飛氏と浦田順一氏だが、技術が実用につながらないことや思うように予算が得られないことを歯がゆく感じ、自分たちで起業したいと思い描いていた」
「創業当時、なかなか資金の調達が決まらず、中西氏、浦田氏と数々のファンドを回る日々の中で、彼らをサポートしてくれる協力者が次第に増えていき、そこからGoogleへつながる人脈を得た。アメリカの国防総省が主催するロボットのコンテスト「DARPA Robotics Challenge(DRC)」に参加していたことも功を奏した」
「2013年11月、Googleが日本のロボット開発会社「SCHAFT」を買収した。この買収劇の中で大きな役割を果たしたのが、SCHAFT社の共同創業者および元取締役CFOの加藤崇氏だ」
とあり、「SCHAFT」はgoogleに買収されたようです。
記事を読むと、ロボットを開発するにはかなりまとまった資金が必要で、そこに成功したことが大きかったようです。
技術面での開発の話をと思って探し始めたのですが、資金面がそんなに重要とは知りませんでした。
このコンテストは、2年間のコンテストで、
「今回の勝利により、同チームは来年開催される決勝戦への進出が決定。そこでさらに優勝すれば200万ドルの賞金を獲得することになる」
(ガジェット通信)
ということです。
「SCHAFT(シャフト)」チームを応援していきたいと思います。










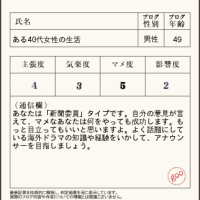
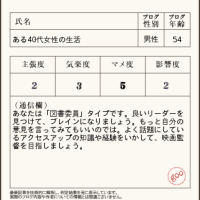





すごいですね。1位ですね。
マイクロソフトがオーナーのチームでしたっけ?
日本は東日本大震災で大きな痛手を受けましたが、それを教訓にいろいろな開発がすすめられていますね。
嬉しいニュースです。
ポチッ
今年もコメントをいただきありがとうございました。
世界のいろいろな国で開発が行われているとは知りませんでしたので、驚きました。
来年の決勝も楽しみです。
ポチッ