先日、友達とランチしました。
子どもの不登校を経験しているお友達です。
少し前ですが、
高校生の娘さんが、学校をお休みするようになってしまったそうです。
娘さんは何か起きると親に吐き出してくるタイプ。
お休みした時も、
泣きながら訴えてきたそうです。
こんなことがあった。
こんなに嫌な思いをしている。
この気持ちをわかってほしい。。。
子どもが辛い思いをしているのなら、
話を聞いてあげて
寄り添って
なんとか支えてあげたい。
そう思うのが母親かもしれません。
でも、お世話になっている先生に
子どもは悩むことが仕事。
辛そうだからといって、
寄り添って話を聞いてあげたり、アドバイスしたり
子どもから悩むことを奪ってはいけない。
子どもは悩み自分で考え乗り越えていく。
それが自立。
親が自立を妨げてはならない。
子どもが吐き出してきた時、
親がいつも寄り添い囲ってあげていると
親にかまってもらいたくて、アピールが強くなっていく。
自分を自分で落して、母に話を聞いてもらって、いたわってもらうことで
自分の気持ちが上がっていくのを感じたいだけ。
「病院に行きたい」と言うのも、
「病院に行きたいくらい辛い」というアピール。
病院に行けば、必ず、診断がつく。
子どもを病人にしてしまう。
親は、病院を探したり、連れて行ったりするのではなく、
「病院に行くほど辛いんだね」と言ってあげるだけでいい。
子どものアピールをそのまま受け取るのではなく、
沁み出てきた物をさらっとふき取る程度。
このようにアドバイスされ、
子どもとの距離をとり、
親の方からは話しかけない。
パッシブな対応。
これを貫いたそうです。
すると、娘さんは学校に向かったとのこと。
今は問題なく通っているそうです。
一見すると冷たいと思えるような対応。
でも、この子はきっと乗り越えていける。
そう、信じてあげることでもあると思います。
お友達は以前、
娘さんが吐き出せば、
一生懸命話を聞いてあげて、ご機嫌とりもして
時には抱きしめて・・・
そうやって気持ちを立て直してあげていたそうです。
でも、それでは
何時までたっても、何かあった時に親へのアピールが止まらない。
親が立て直してあげなければならなくなる。
子どもが学校に行かなくなると、吐き出しも増えてくる。
親も子どもの心の動きを察するあまり、
どうしても、寄り添い傾向になると思います。
それが親子の共依存を招いてしまうことも。
そうなる前に
対応を学べてよかったと友達が言っていました。
娘さん
今でもいろいろアピールしてくるそうです。
そんなに簡単に変われるわけじゃないですものね。
親が対応を変えれば、不安が募り、
一時的にアピールが強くなったりもするかもしれません。
でも、子どもの問題に立ち入ることをせず
「そういう気持ちわかるよ」とか
「私もそうだった~」程度で返すだけ。
沁み出たきたものをさらっとね。
(これが難しいんだけどね)
パッシブといっても決して無視するわけじゃないしね。
すると娘さんはブツブツ言いながらも、自分に向き合い、
なんとか自分で答えをだしているそうです。
本来、子どもは黙っていれば、勝手に自立していくもの。
以前、本で読んだことがあります。
もっと子どもの本来の力を信じてあげたいですね。
私も、とても勉強になりました。
ポチよろしくお願いします
↓
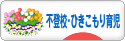 にほんブログ村
にほんブログ村
子どもの不登校を経験しているお友達です。
少し前ですが、
高校生の娘さんが、学校をお休みするようになってしまったそうです。
娘さんは何か起きると親に吐き出してくるタイプ。
お休みした時も、
泣きながら訴えてきたそうです。
こんなことがあった。
こんなに嫌な思いをしている。
この気持ちをわかってほしい。。。
子どもが辛い思いをしているのなら、
話を聞いてあげて
寄り添って
なんとか支えてあげたい。
そう思うのが母親かもしれません。
でも、お世話になっている先生に
子どもは悩むことが仕事。
辛そうだからといって、
寄り添って話を聞いてあげたり、アドバイスしたり
子どもから悩むことを奪ってはいけない。
子どもは悩み自分で考え乗り越えていく。
それが自立。
親が自立を妨げてはならない。
子どもが吐き出してきた時、
親がいつも寄り添い囲ってあげていると
親にかまってもらいたくて、アピールが強くなっていく。
自分を自分で落して、母に話を聞いてもらって、いたわってもらうことで
自分の気持ちが上がっていくのを感じたいだけ。
「病院に行きたい」と言うのも、
「病院に行きたいくらい辛い」というアピール。
病院に行けば、必ず、診断がつく。
子どもを病人にしてしまう。
親は、病院を探したり、連れて行ったりするのではなく、
「病院に行くほど辛いんだね」と言ってあげるだけでいい。
子どものアピールをそのまま受け取るのではなく、
沁み出てきた物をさらっとふき取る程度。
このようにアドバイスされ、
子どもとの距離をとり、
親の方からは話しかけない。
パッシブな対応。
これを貫いたそうです。
すると、娘さんは学校に向かったとのこと。
今は問題なく通っているそうです。
一見すると冷たいと思えるような対応。
でも、この子はきっと乗り越えていける。
そう、信じてあげることでもあると思います。
お友達は以前、
娘さんが吐き出せば、
一生懸命話を聞いてあげて、ご機嫌とりもして
時には抱きしめて・・・
そうやって気持ちを立て直してあげていたそうです。
でも、それでは
何時までたっても、何かあった時に親へのアピールが止まらない。
親が立て直してあげなければならなくなる。
子どもが学校に行かなくなると、吐き出しも増えてくる。
親も子どもの心の動きを察するあまり、
どうしても、寄り添い傾向になると思います。
それが親子の共依存を招いてしまうことも。
そうなる前に
対応を学べてよかったと友達が言っていました。
娘さん
今でもいろいろアピールしてくるそうです。
そんなに簡単に変われるわけじゃないですものね。
親が対応を変えれば、不安が募り、
一時的にアピールが強くなったりもするかもしれません。
でも、子どもの問題に立ち入ることをせず
「そういう気持ちわかるよ」とか
「私もそうだった~」程度で返すだけ。
沁み出たきたものをさらっとね。
(これが難しいんだけどね)
パッシブといっても決して無視するわけじゃないしね。
すると娘さんはブツブツ言いながらも、自分に向き合い、
なんとか自分で答えをだしているそうです。
本来、子どもは黙っていれば、勝手に自立していくもの。
以前、本で読んだことがあります。
もっと子どもの本来の力を信じてあげたいですね。
私も、とても勉強になりました。
ポチよろしくお願いします

↓













