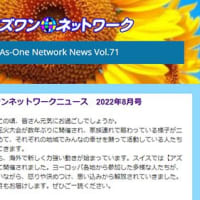旅のレポートはこれで終わりです。
ただ、おしまいに、もう少し「宮地」にこだわってみたいです。
これから先、これほどまでにこだわることも無い予感もするので、もう少し
宮地にまつわることを整理してみたいです。
「姓氏家系辞典」で「宮地」を引くと、「宮所」「宮道」「宮路」も名前の起源は
そんなに違いはないようです。
「古事記」「日本書紀」では「中臣宮地連」とか「中臣宮地朝臣」とか出ている
ようですが、そこまでいくと具体的なことの関心から離れてしまいそうです。
「宮地」の地名や姓が多いところは全国に結構あることがわかりました。
三河・甲斐・美濃・尾張・飛騨・美作・備後・土佐・筑前・肥後など。
兄の話によると、尾道の祖父の先祖を辿っていくと、1400年代まで遡れると
いいます。それでいえば、ちょうど尾道鳴滝山を拠点にして宮地氏が時の
ながれに翻弄されていた頃になります。
ここからは、すこし脱線です。
広島県福山市出身の作家井伏鱒二は「さざなみ軍記」という小説を昭和5年
(1930)に書いています。
平家一門が木曾義仲から帝都を追われて、瀬戸内海を逃亡します。
平家一門高貴な位の方の子息が戦さの指揮をとることになって、その顛末が
少年大将の日記として小説に仕立ててあります。
この少年大将には二人の老練な策士がつき従っていました。
その一人が宮地小太郎といって、瀬戸内海の水運に熟知した因島の豪族の
領頭というわけです。
小太郎というから少年みたいに思ってしまうのですが、すでに60歳になり、
平家の危急を救うべく、馳せ参じてきているのです。
平家一門の命運は須磨一の谷から帝都奪還のため攻め上るか、そこで守り
にはいるのかの岐路にありましたが、宮地小太郎たちがすすめる帝都奪還
にはならないで、平家一門は一の谷で総崩れになります。
宮地小太郎はそのとき悲壮な最期をとげます。
その場面。小説では・・・
――このときわが宮地小太郎が陣頭に進み出て、鎧を踏ん張り突っ立ちあがって
大音声に「これは去年の冬、備後の向島、伊予の大三島、備中の水島、三カ度の
合戦に打ち勝って、高名をきわめたる生年御年十六歳の武蔵守の侍大将、泉寺の
覚丹の部下にその人ありと知られたる、生年六十歳の宮地小太郎である。
わが生国、備後のくに因島を出てよりこのかた、まだ一度も不覚をとったおぼえが
ない。
汝ら源氏の武者どもは、きのうの院宣が下りたのを知らないか。
されば梶原とやら、汝は兇賊となってこの宮地小太郎に討ちかかれよ」と呼ばわった。
小太郎の声はかねて水軍を叱咤して鍛えあげられ、その大音声は城内にくまなく
響き渡った。
この後、敵兵の放った矢が小太郎の膝に突き刺さり、体勢を立て直す隙に源氏の
武士に体当たりをされて、馬から落ちるところで首をはねられたという描写が続き
ました。ちょっと、生唾をのみこみました。
井伏鱒二は小説が完成した昭和13年に作品について話しています。
テーマは少年大将がだんだんませていくようすを表現したかったようです。
そしてこんなことも言っています。
「全部空想で書いたが、風景は、鞆ノ浦を意識に入れて、室の津としたもの。
・・下士官出身みたいな宮地小太郎をつい戦死させてしまったのはまずかった。
あれは生き残しておきたかった」
なぜ「まずかった」のか、なぜ「生き残しておきたかったのか」、いまのぼくには
想像が出来ません。
それにしても「全部空想」というので納得しましたが、1300年ごろから「宮地」は
歴史に登場するようですが、源平合戦のころは、どこでどんなことしていたので
しょうか。
これでもかということになりますが・・・
井伏の作品に「シグレ島叙景」と言う作品があります。
昭和4年、井伏氏三十一歳。
瀬戸内海らしきところにあるシグレ島に座礁した
廃船に中年の二人の男女がアパート代わりに住んでいる。
二人は夫婦ではない。ここに来たとき男は野ウサギを持ち込み、女は
家ウサギを持ち込み、いまでは400匹になるほどに増えている。
それがだれのものかわからなくなっている。
そこへ新しく「私」が参入して、二人の言い合いにまきこまれていくと
いう筋書き。
その中年の男の名前が宮地伊作なのでした。
「口論はいつもの法則通り兎を売る売らぬという問題にはいっていった」
宮地伊作としたら、女「オタツ」がウサギを売れという話題を持ち出さな
ければ「私らもオタツらと、いっそ懇ろにしたのだりました」という気持ちは
あるのでした。あるとき、口論のあと、オタツがいなくなります。
しばらくして、オタツは帰ってきて「伊作に足袋を買ってきた」と明かすの
ですが、話はふたたびウサギのことになるのです。
オタツは伊作に言い募るのです。「こくな、お前らは何故に兎を売ろうと
はせなんだか」
ここの宮地は「さざなみ軍記」の宮地とはおおいに違います。
井伏氏はよほど、宮地という名前に親しみをもっているのでしょうか。
ぼくのばあい、名前というよりシグレ島の伊作さんに、より親近感を
覚えるのをどうすることもできません。
<これでほんとにおしまいです>
人間ピラミッド 北原宗積(きたはらむねかず)
気がつくと
父を 母を ふんでいた
父も母も それぞれ
祖父を 祖母を ふんでいた
祖父母もまた
そのふた親をふみ
むかしのひとびとをふみ
いのちの過去から未来へと
時のながれに きずかれていく・・・
人間ピラミッド
そびえたつ そのいただきに
ぼくは たち
まだいない 子に 孫に
未来のいのちに ふまれていた
いまのじぶんから25代遡ると、6718万8062人によって、
ここに「ぼく」がいることになるらしい。
計算したらそうなるんですね。
25代といったら、700年前、鎌倉時代になるのです。
詩のなかでは、「そびえたつ そのいただきに ぼくは たち」と
ありますが、そういう自覚はあったろうかとはっとさせられました。
そうして「未来のいのちに ふまれていた」ということにも、
あらためていまのじぶんがどう感じているか、考えさせられています。
太郎が祖父の墓参りをしたいと言い出したのがキッカケでしたが、
これからも続くにせよ、なにかこころたのしい旅をさせてもらったと
思っています。
(おしまい)