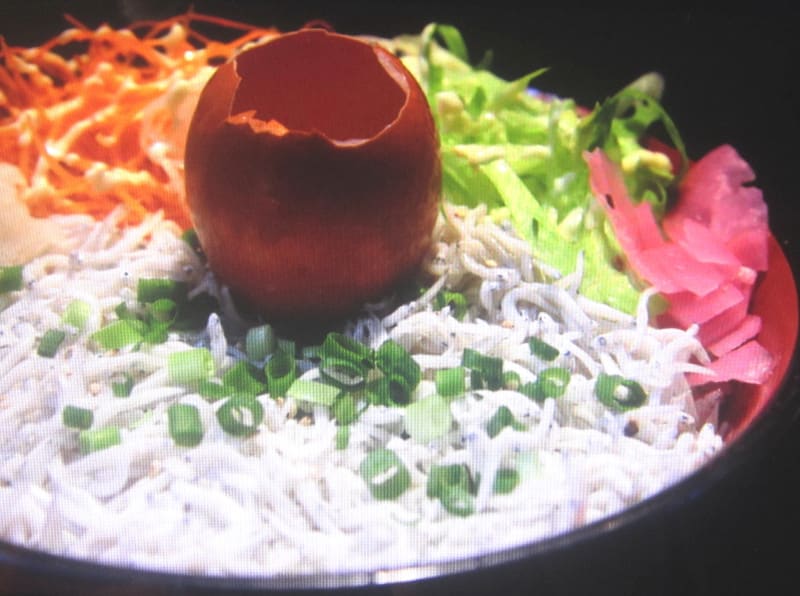【チ-ズサ-モン丼】
「チ-ズサ-モン丼」は、雪印メグミルク大樹工場で生産する「さけるチ-ズ」と、大樹漁協がブランド化している秋サケをメインにした天麩羅が。丼飯の上に載った天丼。
町職員や若手商工会員らで創る「ご当地グルメを創る会」が中心となり、12年9月から試食を繰り返し、改良してきた。
口にした関係者は「さきイカのようなさけるチ-ズの食感がいい」「サケに下味がついていてスパシイ-」などと感想を語り、「おもてなしの心を忘れずに、誰からも愛されるチ-ズサ-モン丼を創る。道外の人にも是非食べてほしい」と決意を語っている。
なお、「チ-ズサ-モン丼」は、13年7月に芽室町で開催される「新・ご当地グルメグランプリ北海道」に出品される。
【シカ肉のソ-スカツ丼】
「シカ肉のソ-スカツ丼」は、長野県上伊那郡中川村の第三セクターの宿泊施設「望岳荘」が、村で捕殺したニホンシカの肉を使って開発したソ-スカツ丼。
農林業被害対策でシカ肉活用に力を入れている中川村の名物にしようと、村産リンゴの果汁を入れた特製ソ-スでサッバリとした味付け。他地域のソ-スカツ丼との差別化を図った。
価格を抑え、食感や味の違いを楽しんでもらう狙いで、シカ肉と豚肉を80グラムずつカツに揚げる。シカ肉は牛乳で下処理するなどして特有の匂いを和らげた。
望岳荘は13年2月の節分に、シカ肉のカツを入れた「恵方巻」を販売。予想を上回る約230本が売れ、「カツ丼を食べたい」との声も寄せられたため、シカ肉料理の第二弾として考案した。
なお、エゾシカの農林被害対策で、南富良野町でも「シカ肉カツ丼」を、陸別町では「シカ肉ジャ-キ-」、白糠町の焼肉店では「焼き肉」などを販売しているが、被害が大きい北海道でもっともっとシカ肉を活用する活動が必要なのでは。