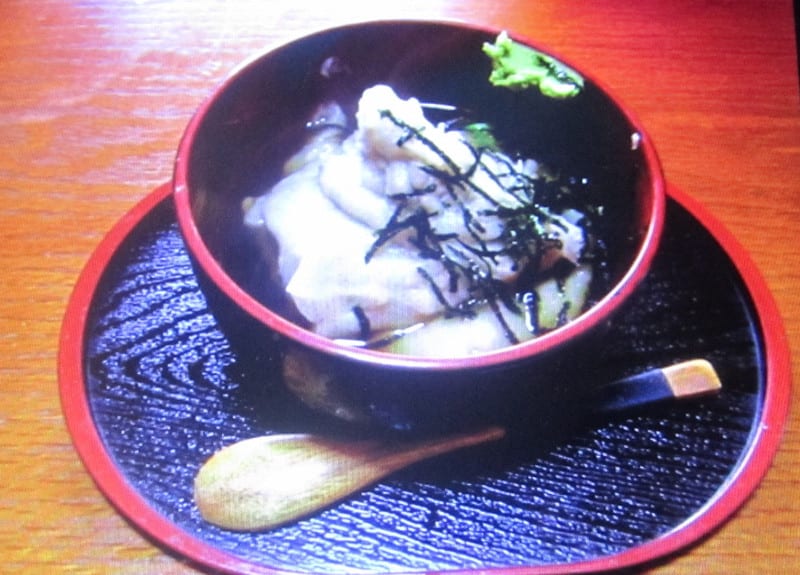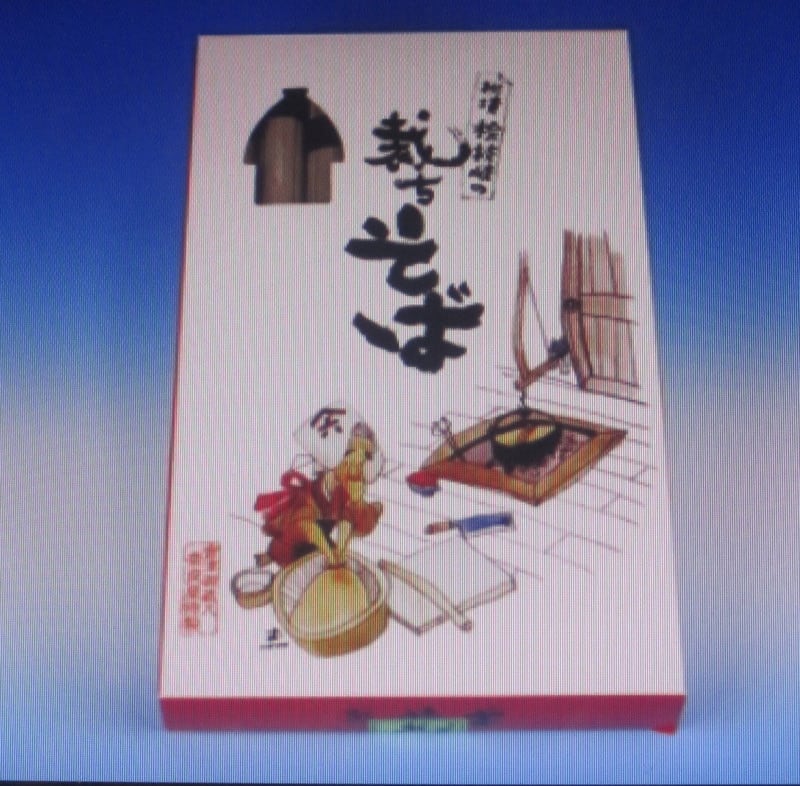【ますのすし】
駅弁ランキング1位。「ますのすし」は、北陸本線・富山駅で食べられる駅弁である。鱒寿司は、富山県の郷土料理であるため、富山県の駅弁としても知られている寿司である。鱒はサクラマスを発酵させずに酢で味付けした、早ずしと呼ばれる、押し寿司の一種である。そしてこの寿司の呼び名は一定でなく、ます寿司、ますの寿司、鱒の寿司、などと称されることも多いがこれらは全て同じものを指している。鱒の切り身を塩漬けにした後、味付けをして、「曲物」と呼ばれる、木製の曲物の底に笹の葉を放射状に敷かれた物の上に並べる。その上に酢飯を押しながら詰めたら、笹を折り曲げて包み込み、その上から重石を置き、押し寿司のようにするのであるが、現在は曲物の上下に青竹をあて、ゴムで締めた状態で流通している。食べ方は、放射状に切り分けて食べるのであるが、駅弁などの商品化されている「ますのすし」は、専用のプラスチック製の小型ナイフが添付されていることが多い。
【いかめし】
駅弁ランキング3位。「いかめし」は、函館本線め森駅の駅弁。そもそも烏賊飯は、イカを使った北海道渡島地方の郷土料理であり、その作り方は、まずイカの下足を取り外し、腹ワタを取り除いた烏賊の胴身に、洗ったもち米とうるち米を合わせた生米を、イカに詰め込むのである。爪楊枝等で中の米が飛び出さないように留めた後、醤油ベ-スの出汁汁。甘辛のタレでじっくり炊き上げたもので、胴身に詰める具材としては、下足を細かく刻んだものや筍ど山菜を入れることもある。
■今日からは「駅弁シリ-ズ」です。