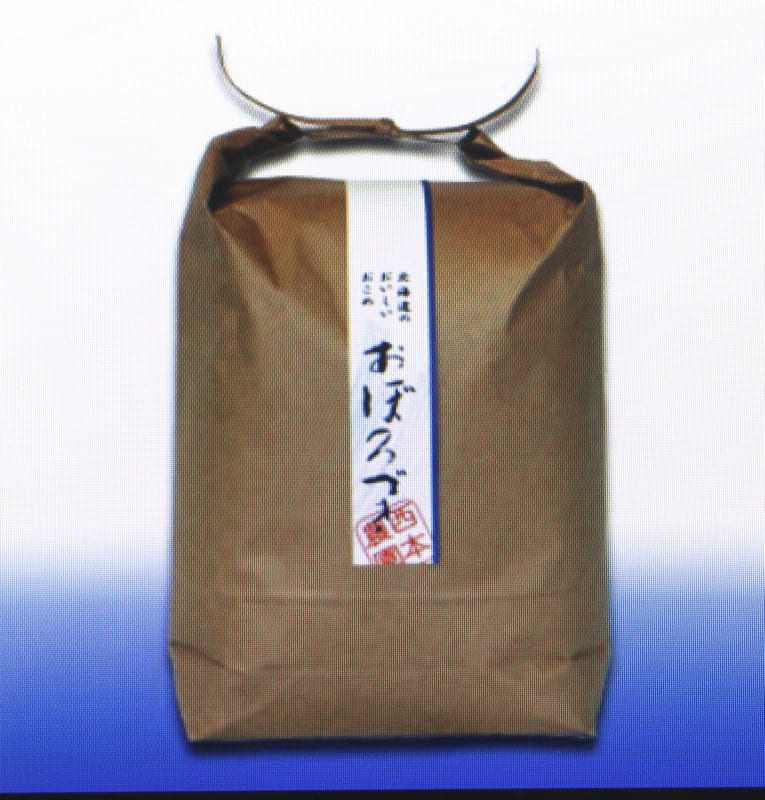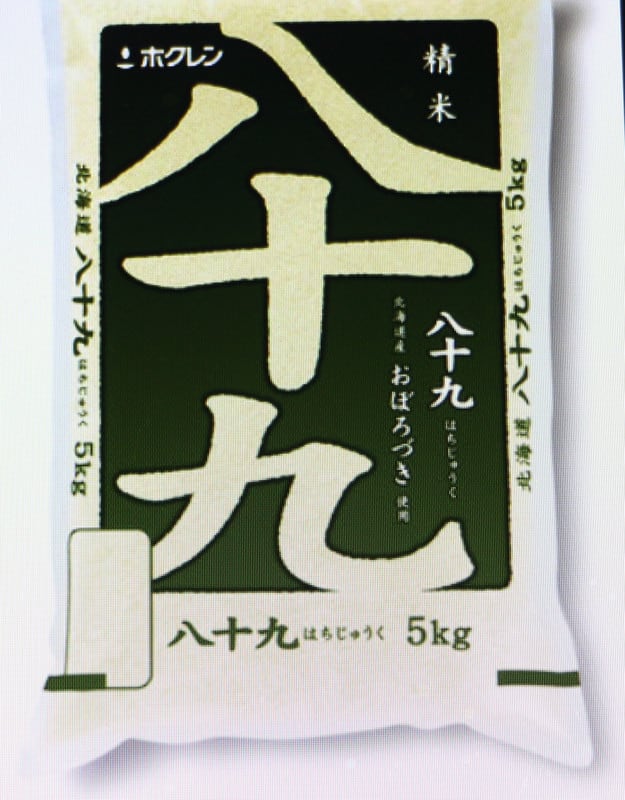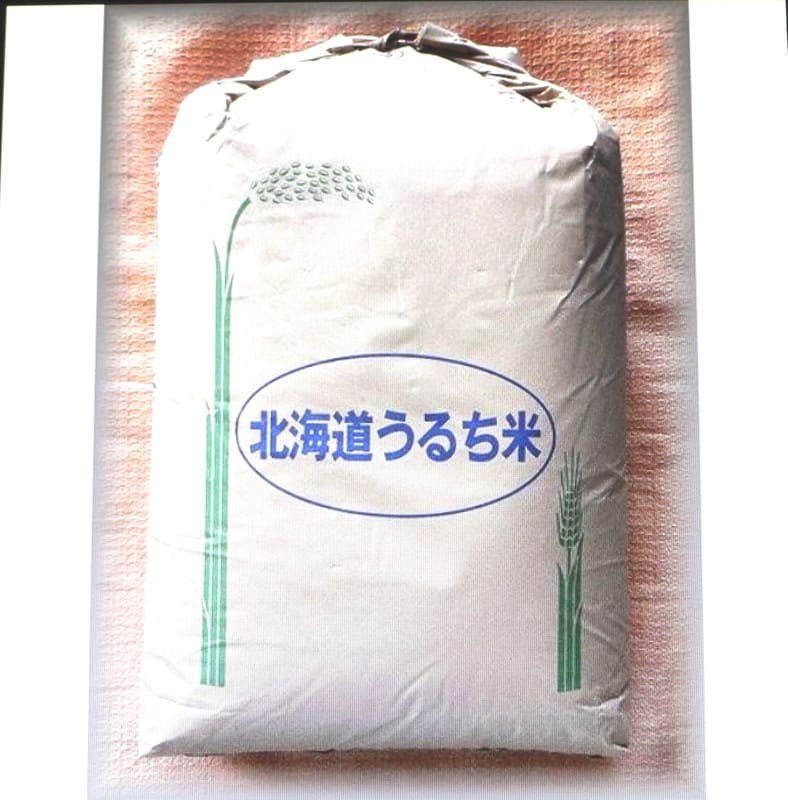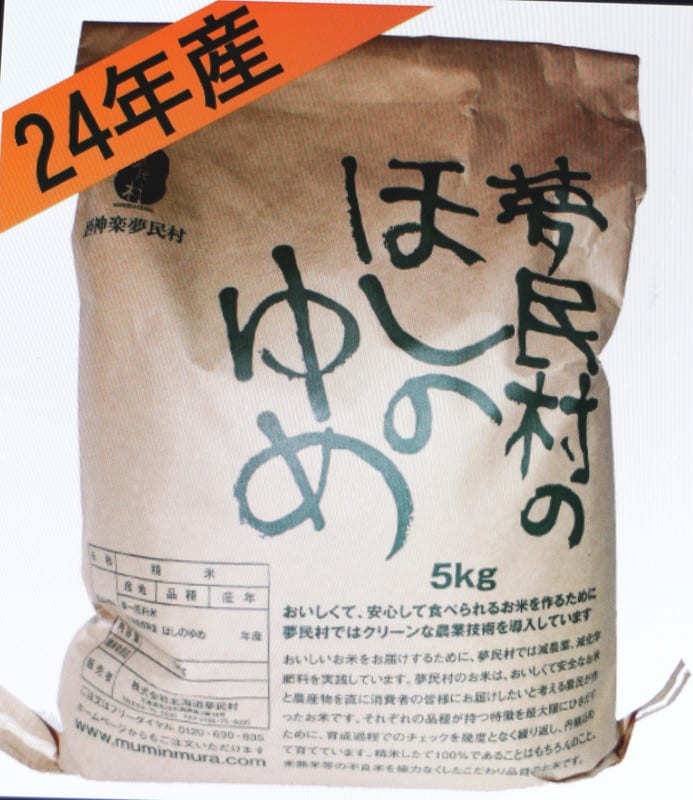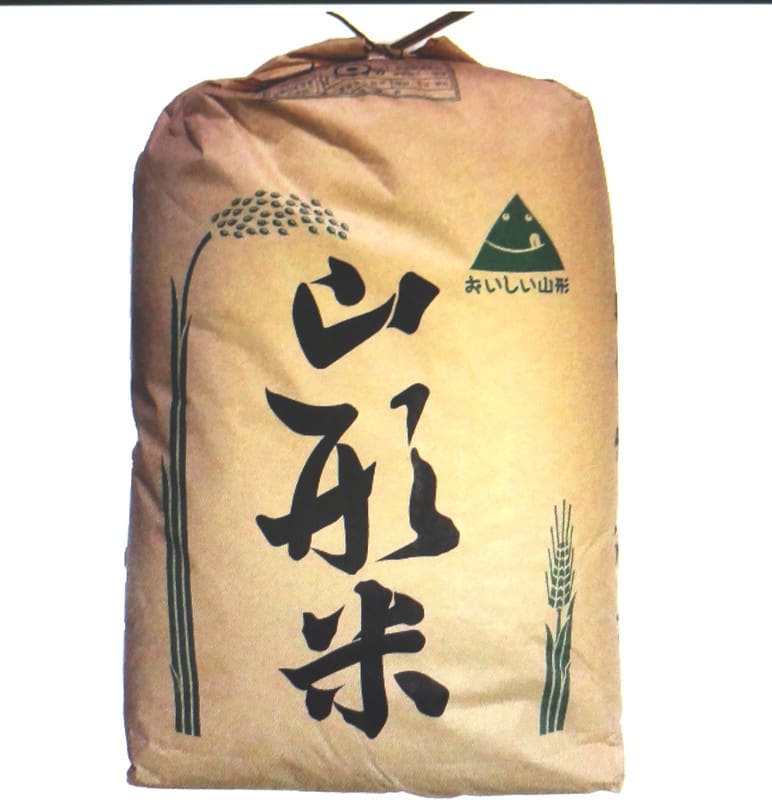【チリコンカーン】
「チリコンカーン」は、代表的なテクス・メクス料理及びアメリカ料理で、アメリカ合衆国の国民食のひとつでもある。
『概要』
「チリコンカーン」は米国ではスペイン語(Chili con Carne)を英語読みしチレコンカーネと発音され、チリという総称で呼ばれるヒスパニック系アメリカ人の多い米国の南西部の地域では、非ヒスパニック系の間でも、よりスペイン語に近いチリコンカネルと呼ばれる。日本では「チリコンカーン」の他、チリコンカンとも呼ばれている。
テキサス州のメキシコに近い地域で発祥したとされ、「テキサス州の料理」に指定されている。
水に戻したインゲン豆を柔らかくなるまで煮て、そこに挽肉、タマネギ、トマト、チリパウダーなどを加えて煮込んだものが最もよく知られている。肉は牛肉であることが多いが豚肉、鶏肉、七面鳥の肉などでも作られる。マサ・アリナ(トウモロコシ粉)やオートミールでとろみをつけることが多い。
『歴史』
名称はスペイン語で「肉入りトウガラシ」を意味するが、「チリコンカーン」の起源ははっきりしない。香辛料と煮込んだテハーノの料理が起源とも、カウボーイのベミカンに似た保存食が起源とも推測されている。
チリが全米に普及したのは、1930年代の世界恐慌や、肉類が配給制になった第二次世界大戦がきっかけである。肉が手に入り難くなった時に、挽肉にインゲン豆やトマトを入れてボリューム感の汁物仕立てにしたチリは家庭で重宝された。現在、最も一般的なトマトや豆の入ったチリは中西部で生まれたもので、あまり辛くなく、香辛料の使い方も南西部のチリとは異なっている。テキサス州のチリにはインゲン豆もトマトも入っていなかったが、1920年代あたりになって中西部でチリに豆が入れられるようになり、1930年代から1940年代になってトマトが入るようになった。クラッカーやチーズを入れる食べ方も中西部で生まれた習慣である。
『バリエーション』
「テキサス風チリ」
テキサス州本来のチリには、トウガラシ以外の野菜は入らない。肉は牛肉または仔牛肉が好まれ、べカン大に切るか粗挽きにして用いる。煮込んだインゲン豆を付け合わせることはあるが、豆をチリに入れるのは邪道とされる。
「シンシナティ風チリ」
オハイオ州シンシナティの名物チリは、マケドニアからの移民が1920年代に考案したものである。
普通のチリよりも汁気が多く、シナモンで風味をつけるため味も独特である。ホットドックやスパケティの上に「チリコンカーン」をかけて食べる点が特徴で、チリとスパゲティだけの組合せを「トウウェイ」、これにおろしたチェダーチーズ、豆、刻みタマネギのどれかをトッピングすると「スリーウェイ」、どれか2つをトッピングすると「フォーウェイ」、3つ全てをトッピングると「ファイブウェイ」と呼ばれる。
「ベジタリアンチリ」
ベジタリアン・チリあるいはチリシンカーンは、肉の代わりに豆を主体としてタンパク質を補ったチリである。色々な野菜を刻んで加えたり、数種の豆を加えて味に変化をつけることが多い。
「その他」
ホットドッグに豆の入らないチリをかけた「チリドック」や、ナチョスのトッピングとしても人気がある。ルイジアナ州に近い米作の盛んなテキサス州東部では、ガンボの食べ方に似た、炊いた白飯にチリをかける食べ方がある。


【ガンボ】
「ガンボ」は、アメリカ合衆国ルイジアナ州を起源とするシチューあるいはスープ料理である。
『概要』
「ガンボ」はアメリカ合衆国南部メキシコ湾一帯に浸透している料理である。基本的には濃いスープストック、肉または甲殻類、とろみ成分、および「聖なる三位一体」と呼ばれる野菜(セロリ・ピーマン・タマネギ)で構成される。伝統的に、ガンボ・スープは、米にかける形で供される。四句節の際のガンボ・サーブというルーでとろみをつけた緑色のガンボも存在する。
ガンボは、ルイジアナ州のクレオールの人々の間で一般的であるのを始め、テキサス州南東部、ミシシッピ州南部、アラバマ州、サウスカロライナ州のチャールストン周辺のロウカントリー、ジョージア州どの地域で食されている。通常は寒い時期の料理として知られる。
スープストックは、シーフード・ガンボであれば魚介類、チキン・ガンボであれば鶏肉を使って可能な限り濃く作る。
典型的なガンボは、鶏肉類、甲殻類、豚肉の燻製のいすれかのひとつ、もしくは複数を使う。鶏肉類としては、鶏、アヒル、ウズラなとが使われるのが通常である。地元の甲殻類としては、ザリガニ、メキシコ湾産のカニ、エビなどが使われることが多い。タッソ(ケイジャン・ハム)、アンドゥイユ(燻製ソーセージ)を入れることにより、料理にスモークの香りが加わる。
ガンボはとろみをつけるのにオクラを使うか、フィレ・パウダーを使うかによって分けることができる。いずれの場合においてもルーを加えることは可能だが、近年はルー単体で使うのが通例である。ルイジアナでは、
オクラとフィレを混ぜるのは一般的てはない。
ケイジャンとクレオールのスタイルで分けることもできる。クレオールのガンボで使うルーは、通常ある程度茶色付いているものの色は浅めで、トマトを入れることもあるが、ケイジャンのガンボより濃い色のルーを使用、トマトを入れることはない。
『歴史』
ガンボはルイジアナがアメリカ料理に対して行った最大の貢献であると言われている。この料理の歴史は、複数の文化か出会った18世紀まで遡る。フランス料理のブイヤベースがその基礎とななった。チョクトー族インディアンの使用したフィレ・パウダーと地元の魚介類が加わったことにより、地方色が強まることになる。西アフリカの奴隷たちがオクラを持ち込み、これがルイジアナの台所にもたされた。ガンボの語原はオクラを意味するアフリカの言葉から来ている。ピーマン、トマト、それに調理されたタマネギは、スペインの入植者たちによってもたされた。
ガンボは、使われるとろみ成分によって分類することができる。オクラを使ったもの、フィレ・パウダーを使ったもの、およびこれらを使わずルー単体でとろみをつけたものの3タイプである。近年のレシピでは、オクラ及びフィレ使用のタイプは、更にとろみと風味を付けるために、色の濃いルーの使用を指定しているものが一般的である。伝統的にオクラとフィレ・パウダーは、同じ料理に一緒に使われることはない。しかし、甘い風味を出すために色の浅いルーと粘ったオクラとフィレを調理後に加えるケースもある。
夏にはオクラ、冬にはフィレを使う習慣があり、これがガンボのタイプによっての特定の季節を連想させる要因となっているが、これは厳密なルールではなく、どちらかと言えば一般的な慣例である。例えば、魚介類のみを使ったガンボは通常フィレでとろみを付けることはなく、一方肉のみを使用したガンボはオクラを使用しない。これは、伝統的に漁を暖かい季節に行い、狩猟は寒い季節に行っていた習慣から来てるものである。