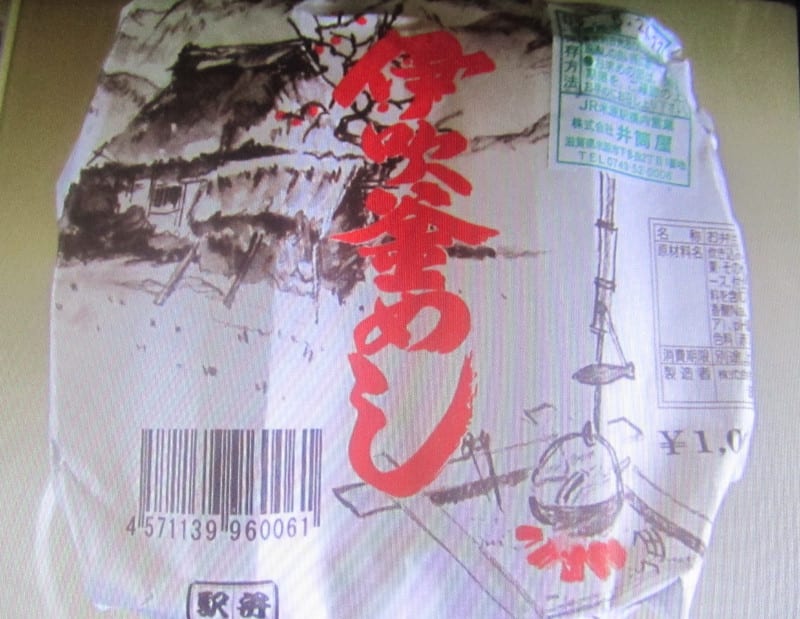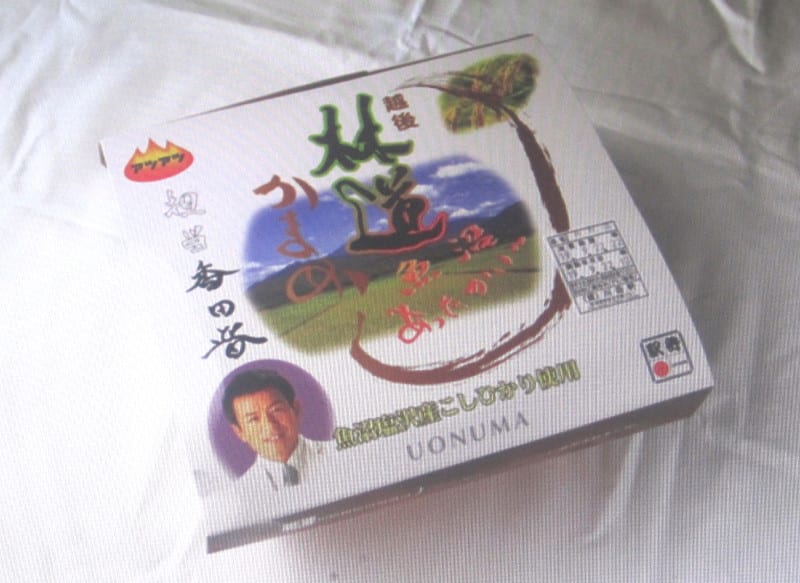●今日からは食べ物のシリ-ズです。
【軍艦巻き】
軍艦巻きとは、握った寿司飯の側面を海苔で巻き、イクラやウニなど崩れやすいネタを乗せた寿司の総称。
軍艦巻きの名は、横から見た姿が軍艦に似ていることから付いたものである。
軍艦巻きを考案したのは、昭和16年、東京銀座の高級寿司店『久兵衛』の主人で、常連客の「イクラの寿司が食べたい」という要望から考えたものといわれる。
現在では、イクラの軍艦巻き以外にも、カニ味噌やネギトロなど、柔らかく崩れやすいネタを使った様々な軍艦巻きが作られるようになった。
【鉄火巻き】
鉄火巻きとは、マグロの切り身の赤身に山葵をつけて芯にした海苔巻き寿司。
鉄火巻きの「鉄火」は、もともと真っ赤に熱した鉄をさす語である。
マグロの赤い色とワサビの辛さを「鉄火」に喩えたもので、気質の荒々しい者を「鉄火肌」や「鉄火者」というのと同じである。
賭博場を意味する「鉄火場」に由来し、手に酢飯が付かず、鉄火場で博打をしながらでも手軽に食べられることからとする説もあるが、「鉄火」の付く食べ物には「鉄火丼」や「鉄火味噌」もあり、これらに共通するのは「赤い色」と「辛さ」で「鉄火場」も「手軽さ」も関係ないため、この説は間違いと言える。
ただし、「鉄火場」の「鉄火」も同源で、熱して鉄のように博徒が熱くなるからという。