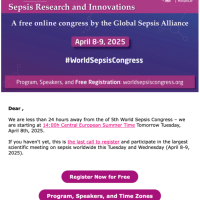2008年 周術期管理と免疫グロブリン療法 NO.1
京都大学大学院医学研究科
初期診療・救急医学分野
松田直之
はじめに
心臓血管麻酔管理や急性心不全などの心血管病態に合併する全身性炎症反応症候群(SIRS: systemic inflammatory response syndrome)に後発する抗炎症反応症候群(CARS: compensatory anti-Inflammatory response syndrome)では,免疫機能の低下が具現化し,感染症の合併により,重症敗血症や敗血症性ショックとして全身管理が複雑となる1)。現在の心臓血管麻酔は交感神経緊張に伴う急性相反応の抑制は可能であるものの,心ポンプ失調や組織虚血に伴うSIRSやCARS,随伴するショックや多臓器不全,さらには免疫機能低下の抑制には,未だ多くの課題を残しており,血管内皮細胞保護2),さらにはスタチンのSIRS抑制の可能性などは重要な論点となる3)。
静注用免疫グロブリン(IVIG: intravenous immunoglobulin)は,川崎病,特発性血小板減少性紫斑病,重症感染症,慢性炎症性脱髄性多発根神経炎,無γ-グロブリン血症などを含むさまざまな病態で有効性が確認されている血漿分画製剤である。血漿分画製剤としての副作用や合併症に十分な注意が必要であるものの,近年では,このIVIG療法が,移植手術後や心不全の病態改善に有効であるという論文が散見される。心臓・大血管手術の術後では液性免疫の低下により,感染症罹患率が高まり,重症敗血症やウイルス感染症に移行しやすい可能性は古くから報告されている。
本稿では,集中治療医の免疫グロブリンに対する理解を深め,IVIG療法のSIRS病態における役割を考察し,心臓血管麻酔領域を含めた周術期炎症管理に対するIVIGの応用を探ることを目的とする。
免疫グロブリンについて
免疫グロブリンは,細菌やウイルスなどの微生物や微生物の産生する異物を認識する糖蛋白であり,主に5種類のサブタイプからなる抗体の総称である。免疫グロブリンは,リンパ節,脾臓,粘膜リンパ組織などの末梢リンパ器官や骨髄由来に存在するB細胞により産生される。こうした免疫グロブリンを含む血清蛋白の分離は,1900年まで,主に塩濃度により沈殿する蛋白が異なるという現象を応用した塩析法で行われていた。血清蛋白は,この塩析法を用いて50%飽和硫酸アンモニウムで沈殿するグロブリン,50%飽和硫酸アンモニウムで沈殿しないアルブミンに分類されていた。1929年にHeidelbergerにより免疫沈降法が公表され,さらに1930年にTiseliusにより電気泳動法が開発されると,これらの手法を用いてグロブリンはさらにα1,α2,β,γの4つの分画に分類され,このγグロブリン分画に免疫を担当する「免疫グロブリン」が存在することが明らかとされた(図1)。現在,IVIGは健康成人の血清より抽出したポリクローナル抗体として世界各国で臨床使用されており,その世界における需要は年間90トン以上と見積もられている。本邦で臨床使用されているIVIG製剤はIgG抗体を抽出したものであり,現在,血漿1Lより約3.3 gのIgGが精製されている。海外ではIgG抗体にIgM抗体とIgA抗体を含有したものも臨床応用されている。
IVIGには多種多様な免疫グロブリンが含有されており,これらは細菌やウイルスの認識抗体だけではない。Tumor necrosis factor-α(TNF-α),interleukin-1(IL-1),interleukin-6(IL-6),macrophage migration inhibitory factorなどの炎症性サイトカインや,TNF-α受容体などのサイトカイン受容体,さらには,アポトーシス誘導リガンドであるFasなどの,炎症とアポトーシスに関与する分子に対する抗体が,IVIGには含まれている4, 5)。炎症性受容体や炎症性リガンドは,免疫担当細胞に限らず,さまざまな主要臓器の細胞で炎症を惹起し,アポトーシスを加速させることが確認できる6)。さらに,IVIGには,サイトメガロウイルス,アデノウイルス,水痘帯状疱疹ウイルス,麻疹ウイルス,風疹ウイルス,ムンプスウイルス,インフルエンザウイルス,エンテロウイルス,コクサッキーウイルスなどの抗ウイルス抗体や,抗菌薬活性の期待しにくいメタロ-β-ラクタマーゼ産生緑膿菌,バンコマイシン低感受性メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA),バンコマイシン低感受性腸球菌属,メタロ-β-ラクタマーゼ産生セラチア,カンジダ属,多剤耐性緑膿菌などを認識する抗体が含有されている。本邦では,これらのウイルスや細菌に対する抗体価がIVIGのロットごとに報告されているため,重症敗血症に移行した際にはIVIGロットの有効性が確認しやすく,理論的には十分に抗菌薬の補助手段となる可能性がある。

免疫グロブリンの作用機序
免疫は,innate immunity(自然免疫,先天免疫,非特異的免疫)と,acquired immunity(獲得免疫,適応免疫,特異的免疫)の2種に分類される。自然免疫による微生物進入の防御機構は主に上皮バリアが重要であるが,SIRS病態では,消化管,気道粘膜をはじめとするさまざまな上皮バリアが広範に傷害され,浮腫状変化をきたす。このため,自然免疫の第1関門である上皮バリアは異物に突破されやすく,これに代わりマクロファージやナチュラルキラー細胞(NK細胞)などが活性化し,自然免疫を高めようとする。一方,獲得免疫は,T細胞が担当する細胞性免疫と,B細胞が担当する液性免疫の2つに分類される。
胸腺由来のリンパ球であるT細胞は,既に細胞内に進入した微生物の断片と自己のmajor histocompatibility complex(MHC)の複合体を認識する。HMCは,白血球の血液型として免疫学的自他の認識を担当し,ヒトでは白血球抗原(HLA:human leukocyte antigen),マウスではH-2(histocompatibility-2)とも呼ばれている。CD4を細胞膜に発現するヘルパーT細胞はHMCクラスII分子と結合し,Th1細胞としてマクロファージや樹状細胞の細胞内消化を促進させ, Th2細胞としてB細胞の抗体産生能を高める。一方,CD8を細胞膜に発現するキラーT細胞は,ウイルスなどの寄生細胞や腫瘍細胞の断片とHMCクラスI分子との複合体を認識し,それらの細胞にアポトーシスを誘導する。
抗体産生の基盤であるB細胞は,10億を超える抗原特異的な受容体を1つのB細胞に1つだけ発現できることが知られている。抗原に反応したB細胞は,そのシグナルをB細胞内で活性化させ,同じ抗原特異性を持つクローンB細胞を増殖させる。このようなクローンB細胞群は形質細胞に分化をとげ,一つの抗体を産生する分泌細胞群として機能する。患者の罹患過程で産生される抗体産生を待つ代わりに,IVIG療法は短時間で外来的に抗体を補充する療法であり,全身性炎症反応で生体内に浸潤する微生物の浸潤を他の健常者の力を借りて抑制する可能性を持つ。集中治療管理での最も望ましいIVIG療法は,心血管イベントや心臓血管手術の後に退院した患者より精製したIVIGを,他の患者の急性期管理に用いることである。しかし,このような検討は,未だ存在しない。
血中に最も多く存在するIgGの基本構造を,図2に示した。IgGは,分子量約5~7万のH鎖(heavy chain)と分子量約2.2~2.4万のL鎖(light chain)による4本のポリペプチドであり,H鎖とL鎖はいくつものジスルフィド結合(S-S結合)で架橋されている。生体内で10億を超える抗体分子の抗原特異性は,この構造におけるvariable region(V領域)で決定され,constant region(C領域)は関与しない。IgGのH鎖のC領域は,3つのCH1,CH2,CH3のC領域ドメインで構成され,CH1とCH2の境界にヒンジ領域と呼ばれるちょうつがい構造の屈曲領域が存在し,抗原との結合に弾力性を持たせている。抗原との結合領域はL鎖のVL領域とH鎖のVH領域であり,VL領域では3箇所,VH領域では4箇所にアミノ酸ループ構造が存在し,抗原をはさむように結合することが知られている。免疫グロブリンは,血清中の量の多い順にIgG,IgA,IgM,IgD,IgEの5種類が存在するが,これらは,異なるH鎖で構成され,各々に対応するH鎖はγ鎖,α鎖,μ鎖,δ鎖,ε鎖である(表1)。各免疫グロブリンのVL領域はκ鎖かλ鎖のいずれかで構成されており,微細な構造に差があるものの,免疫グロブリンとしての種差はない。
このような抗体のうち,特にIgGは,1)微生物や炎症性物質の作用の中和,2)微生物のオプソニン化による貪食細胞の貪食能の促進,3)NK細胞の貪食細胞への細胞傷害性の亢進,4)補体の古典的経路の活性化,5)B細胞活性化の抑制の作用を持つ。これらの機能は,上述の各細胞の細胞膜上のFc受容体(FcR)にIgGが結合することで,特異的に惹起される(表2)。抗体のCH領域には,パパインで切断されるC末端領域のFc部分(fragment of crystallizable)が存在し,この抗体のFc部分をリガンドとするのがFcRである。マクロファージや好中球は, FcRの1サブタイプであるFcRIを介してIgGと結合した微生物や炎症性物質を認識し,それらの細胞内貪食や殺菌作用を高める。これに対して,IgAは微生物や炎症性物質の作用の中和を主作用とし,IgMは補体の古典的経路の活性化作用を高めることを主作用とする。IgEは,マスト細胞に存在するFcRIを介して,ヒスタミンなどの脱顆粒を促進する。



小児心臓手術後の乳糜胸に伴う低γ-グロブリン血症
ミズーリ大学Tobias JDらのグループ7)は,2001年の段階で,心臓術後の小児に乳糜胸が合併すると低IgG血症となり,感染症罹患率が高まる可能性があると報告した。さらに,彼らは,2003年までの小児ICU領域における血清IgGレベルを調査し,20症例中14例に低IgG血症が認められたと報告している8)。このうち,完全大血管転位症や心室中隔欠損症などの小児心臓手術後の4症例では,全例で血清IgGレベルが正常の33~66%レベルに低下していた。また,2003年のOrange JSらによる小児乳糜胸8例による報告9)でも,全例でリンパ球減少症を伴い,8例中4例は重症敗血症を合併し,血清IgGレベルが179±35 mg/dLレベルに低下していたという。一方,Kovacikova Lら10)は,小児心臓術後に乳糜胸を合併した16例中,4例にのみIgGレベルの低下が見られるに過ぎないと報告している。
このように,現在のところ,乳糜胸による低IgG血症の発症率にはばらつきが認められるものの,乳糜胸では低IgG血症が生じる可能性は否定できず,定期的な血清IgG濃度の測定により,IVIG療法の施行を評価する必要がある。小児の心奇形が低ガンマグロブリン血症を合併しやすいことは,ジョージワシントン大学のOnigbanjo MTら11)のグループでも検証されている。
成人心不全に対するIVIG療法
クリーブランドクリニックのYamani MHらによる心臓移植術後220例の報告12)では,血清IgG濃度は,心臓移植前の平均1137±353 mg/dLより,心臓移植術後に約26%で500 mg/dL未満に,約10%で350 mg/dL未満に減少している。彼らの報告では,血清IgG濃度は,心移植後に緩徐に低下し,平均約196日で最低値に達している。サイトメガロウイルス(CMV)抗体を豊富に含む150 mg/kg のCMV-IVIG(CytoGam®)を1回投与した結果,日和見感染の発症率が64%から11%に有意に減じられ,拒絶反応が有意に抑制されたという。
一方,心臓移植に持ち込むまでのventricular assist device(VAD)の装着時期にも,IgGレベルが低下することが知られている。同じクリーブランドクリニックのYamani MHらのグループ13)は,VADを装着している76名の患者を血清IgG濃度700 mg/dL前後で2群にわけ,感染症罹患率を比較している。血清IgG濃度700 mg/dL未満では感染症罹患率が56%から95%に高まり,さらにCMV感染率が16%から45%に高まっている。Yamani MHら13)のVAD装着では,血清IgG濃度の低値を認めなくとも,50%を超える高い感染症合併率を示している。1999年のHolman WL ら14)のVAD装着患者の解析では,2年生存率が38%であり,敗血症の罹患により2年生存率が8%に減じている。2002年4月より2004年12月までVADを装着された70名のSharples Lらによる解析15)では,2005年3月までの間に心移植を受けることなく43%が死亡し,7%がVADを装着し続けていたという。44%が心移植に持ち込まれ,6%は心機能回復によりVADから離脱できたという。このSharples Lら15)の報告でも,VAD装着中の感染症罹患が,死因の上位として挙げられている。
このような心不全状態において,IVIGは炎症に付随する心臓のアポトーシスを抑制する可能性が示唆されている。うっ血性心不全では,急性期よりTNF-αやIL-1βなどの炎症性サイトカインの血中濃度が上昇し,炎症性物質が産生されるばかりか,アポトーシスが進行することが知られている16, 17)。ノルウェー大学のGullestad Lら18)は,急性冠症候群あるいは特発性拡張型心筋症でうっ血性心不全に移行した40名の患者を対象として, 5日間の0.4 g/kg のIVIG療法を行い,1ヶ月ごとに0.4 g/kgのIVIGを5ヶ月間追加するプロトコールを立てた。対象とした患者群の左室駆出率は,IVIG群で最終的に26±2%より31±3%に増加したが,プラセボ群では左室駆出率の改善が認められていない。IVIG治療により,TNF-α/可溶性TNF受容体比やIL-1βが有意に低下し,抗炎症性サイトカインであるIL-10が有意に上昇している。以上より,Gullestad Lら18)は,うっ血性心不全の増悪因子として,炎症性サイトカインが関与する可能性を示し,IVIG療法は炎症性サイトカインの有意な状態から抗炎症性サイトカインの有意な状態へサイトカインシフトさせ,心機能を改善すると結論した。また,同時期の2001年に検証されたピップバーグ大学のMcNamara DMら19)の62名の拡張型心筋症患者を対象とした研究では, IVIGの投与は1g/kgの2日間に設定されている。McNamara DMら20)のデータでは,IVIG療法による統計学的に有意な改善が認められていない。Gullestad Lら21)とMcNamara DMら19)の治療効果の違いは,うっ血性心不全の発症後の経過の違いとIVIGの投与スケジュールの違いにあるかもしれない。McNamara DMら19)のデータは症状出現より6ヶ月以内の比較的早期の拡張型心筋症を対象にしており,プラセボ群の治療成績が極めて良いために,IVIG群との差が認められなかった可能性がある。
このような結果を検証するものとして,2003年に京都大学の岸本ら20)により,症状出現より6ヶ月以内のNew York Heart Association(NYHA)class ⅢあるいはIVの左室駆出率40%未満の9名の患者を対象として,IVIG 1~2 g/Kgの1回投与による治療効果が評価された。岸本ら20)の9症例の原疾患の内訳は,急性心筋炎6名,急性拡張型心筋症3名である。IVIG施行前の左室駆出率の平均は19.0±7.5%だったが,IVIG療法の施行後約12日で,左室駆出率が35.4±9.1%に改善し,さらに, TNF-αとIL-6の血漿濃度はIVIG療法後に患者すべてで著明に減少し,酸化ストレスのマーカーである血漿チオレドキシン濃度も有意に減少していた。この研究はプラセボ群のないものではあるが, IVIGが有害となる結果は全例に認められず,診断に用いた心筋生検の結果からすれば,心筋の炎症のみならず,心筋傷害を軽減させる可能性を示している。
京都大学大学院医学研究科
初期診療・救急医学分野
松田直之
はじめに
心臓血管麻酔管理や急性心不全などの心血管病態に合併する全身性炎症反応症候群(SIRS: systemic inflammatory response syndrome)に後発する抗炎症反応症候群(CARS: compensatory anti-Inflammatory response syndrome)では,免疫機能の低下が具現化し,感染症の合併により,重症敗血症や敗血症性ショックとして全身管理が複雑となる1)。現在の心臓血管麻酔は交感神経緊張に伴う急性相反応の抑制は可能であるものの,心ポンプ失調や組織虚血に伴うSIRSやCARS,随伴するショックや多臓器不全,さらには免疫機能低下の抑制には,未だ多くの課題を残しており,血管内皮細胞保護2),さらにはスタチンのSIRS抑制の可能性などは重要な論点となる3)。
静注用免疫グロブリン(IVIG: intravenous immunoglobulin)は,川崎病,特発性血小板減少性紫斑病,重症感染症,慢性炎症性脱髄性多発根神経炎,無γ-グロブリン血症などを含むさまざまな病態で有効性が確認されている血漿分画製剤である。血漿分画製剤としての副作用や合併症に十分な注意が必要であるものの,近年では,このIVIG療法が,移植手術後や心不全の病態改善に有効であるという論文が散見される。心臓・大血管手術の術後では液性免疫の低下により,感染症罹患率が高まり,重症敗血症やウイルス感染症に移行しやすい可能性は古くから報告されている。
本稿では,集中治療医の免疫グロブリンに対する理解を深め,IVIG療法のSIRS病態における役割を考察し,心臓血管麻酔領域を含めた周術期炎症管理に対するIVIGの応用を探ることを目的とする。
免疫グロブリンについて
免疫グロブリンは,細菌やウイルスなどの微生物や微生物の産生する異物を認識する糖蛋白であり,主に5種類のサブタイプからなる抗体の総称である。免疫グロブリンは,リンパ節,脾臓,粘膜リンパ組織などの末梢リンパ器官や骨髄由来に存在するB細胞により産生される。こうした免疫グロブリンを含む血清蛋白の分離は,1900年まで,主に塩濃度により沈殿する蛋白が異なるという現象を応用した塩析法で行われていた。血清蛋白は,この塩析法を用いて50%飽和硫酸アンモニウムで沈殿するグロブリン,50%飽和硫酸アンモニウムで沈殿しないアルブミンに分類されていた。1929年にHeidelbergerにより免疫沈降法が公表され,さらに1930年にTiseliusにより電気泳動法が開発されると,これらの手法を用いてグロブリンはさらにα1,α2,β,γの4つの分画に分類され,このγグロブリン分画に免疫を担当する「免疫グロブリン」が存在することが明らかとされた(図1)。現在,IVIGは健康成人の血清より抽出したポリクローナル抗体として世界各国で臨床使用されており,その世界における需要は年間90トン以上と見積もられている。本邦で臨床使用されているIVIG製剤はIgG抗体を抽出したものであり,現在,血漿1Lより約3.3 gのIgGが精製されている。海外ではIgG抗体にIgM抗体とIgA抗体を含有したものも臨床応用されている。
IVIGには多種多様な免疫グロブリンが含有されており,これらは細菌やウイルスの認識抗体だけではない。Tumor necrosis factor-α(TNF-α),interleukin-1(IL-1),interleukin-6(IL-6),macrophage migration inhibitory factorなどの炎症性サイトカインや,TNF-α受容体などのサイトカイン受容体,さらには,アポトーシス誘導リガンドであるFasなどの,炎症とアポトーシスに関与する分子に対する抗体が,IVIGには含まれている4, 5)。炎症性受容体や炎症性リガンドは,免疫担当細胞に限らず,さまざまな主要臓器の細胞で炎症を惹起し,アポトーシスを加速させることが確認できる6)。さらに,IVIGには,サイトメガロウイルス,アデノウイルス,水痘帯状疱疹ウイルス,麻疹ウイルス,風疹ウイルス,ムンプスウイルス,インフルエンザウイルス,エンテロウイルス,コクサッキーウイルスなどの抗ウイルス抗体や,抗菌薬活性の期待しにくいメタロ-β-ラクタマーゼ産生緑膿菌,バンコマイシン低感受性メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA),バンコマイシン低感受性腸球菌属,メタロ-β-ラクタマーゼ産生セラチア,カンジダ属,多剤耐性緑膿菌などを認識する抗体が含有されている。本邦では,これらのウイルスや細菌に対する抗体価がIVIGのロットごとに報告されているため,重症敗血症に移行した際にはIVIGロットの有効性が確認しやすく,理論的には十分に抗菌薬の補助手段となる可能性がある。

免疫グロブリンの作用機序
免疫は,innate immunity(自然免疫,先天免疫,非特異的免疫)と,acquired immunity(獲得免疫,適応免疫,特異的免疫)の2種に分類される。自然免疫による微生物進入の防御機構は主に上皮バリアが重要であるが,SIRS病態では,消化管,気道粘膜をはじめとするさまざまな上皮バリアが広範に傷害され,浮腫状変化をきたす。このため,自然免疫の第1関門である上皮バリアは異物に突破されやすく,これに代わりマクロファージやナチュラルキラー細胞(NK細胞)などが活性化し,自然免疫を高めようとする。一方,獲得免疫は,T細胞が担当する細胞性免疫と,B細胞が担当する液性免疫の2つに分類される。
胸腺由来のリンパ球であるT細胞は,既に細胞内に進入した微生物の断片と自己のmajor histocompatibility complex(MHC)の複合体を認識する。HMCは,白血球の血液型として免疫学的自他の認識を担当し,ヒトでは白血球抗原(HLA:human leukocyte antigen),マウスではH-2(histocompatibility-2)とも呼ばれている。CD4を細胞膜に発現するヘルパーT細胞はHMCクラスII分子と結合し,Th1細胞としてマクロファージや樹状細胞の細胞内消化を促進させ, Th2細胞としてB細胞の抗体産生能を高める。一方,CD8を細胞膜に発現するキラーT細胞は,ウイルスなどの寄生細胞や腫瘍細胞の断片とHMCクラスI分子との複合体を認識し,それらの細胞にアポトーシスを誘導する。
抗体産生の基盤であるB細胞は,10億を超える抗原特異的な受容体を1つのB細胞に1つだけ発現できることが知られている。抗原に反応したB細胞は,そのシグナルをB細胞内で活性化させ,同じ抗原特異性を持つクローンB細胞を増殖させる。このようなクローンB細胞群は形質細胞に分化をとげ,一つの抗体を産生する分泌細胞群として機能する。患者の罹患過程で産生される抗体産生を待つ代わりに,IVIG療法は短時間で外来的に抗体を補充する療法であり,全身性炎症反応で生体内に浸潤する微生物の浸潤を他の健常者の力を借りて抑制する可能性を持つ。集中治療管理での最も望ましいIVIG療法は,心血管イベントや心臓血管手術の後に退院した患者より精製したIVIGを,他の患者の急性期管理に用いることである。しかし,このような検討は,未だ存在しない。
血中に最も多く存在するIgGの基本構造を,図2に示した。IgGは,分子量約5~7万のH鎖(heavy chain)と分子量約2.2~2.4万のL鎖(light chain)による4本のポリペプチドであり,H鎖とL鎖はいくつものジスルフィド結合(S-S結合)で架橋されている。生体内で10億を超える抗体分子の抗原特異性は,この構造におけるvariable region(V領域)で決定され,constant region(C領域)は関与しない。IgGのH鎖のC領域は,3つのCH1,CH2,CH3のC領域ドメインで構成され,CH1とCH2の境界にヒンジ領域と呼ばれるちょうつがい構造の屈曲領域が存在し,抗原との結合に弾力性を持たせている。抗原との結合領域はL鎖のVL領域とH鎖のVH領域であり,VL領域では3箇所,VH領域では4箇所にアミノ酸ループ構造が存在し,抗原をはさむように結合することが知られている。免疫グロブリンは,血清中の量の多い順にIgG,IgA,IgM,IgD,IgEの5種類が存在するが,これらは,異なるH鎖で構成され,各々に対応するH鎖はγ鎖,α鎖,μ鎖,δ鎖,ε鎖である(表1)。各免疫グロブリンのVL領域はκ鎖かλ鎖のいずれかで構成されており,微細な構造に差があるものの,免疫グロブリンとしての種差はない。
このような抗体のうち,特にIgGは,1)微生物や炎症性物質の作用の中和,2)微生物のオプソニン化による貪食細胞の貪食能の促進,3)NK細胞の貪食細胞への細胞傷害性の亢進,4)補体の古典的経路の活性化,5)B細胞活性化の抑制の作用を持つ。これらの機能は,上述の各細胞の細胞膜上のFc受容体(FcR)にIgGが結合することで,特異的に惹起される(表2)。抗体のCH領域には,パパインで切断されるC末端領域のFc部分(fragment of crystallizable)が存在し,この抗体のFc部分をリガンドとするのがFcRである。マクロファージや好中球は, FcRの1サブタイプであるFcRIを介してIgGと結合した微生物や炎症性物質を認識し,それらの細胞内貪食や殺菌作用を高める。これに対して,IgAは微生物や炎症性物質の作用の中和を主作用とし,IgMは補体の古典的経路の活性化作用を高めることを主作用とする。IgEは,マスト細胞に存在するFcRIを介して,ヒスタミンなどの脱顆粒を促進する。



小児心臓手術後の乳糜胸に伴う低γ-グロブリン血症
ミズーリ大学Tobias JDらのグループ7)は,2001年の段階で,心臓術後の小児に乳糜胸が合併すると低IgG血症となり,感染症罹患率が高まる可能性があると報告した。さらに,彼らは,2003年までの小児ICU領域における血清IgGレベルを調査し,20症例中14例に低IgG血症が認められたと報告している8)。このうち,完全大血管転位症や心室中隔欠損症などの小児心臓手術後の4症例では,全例で血清IgGレベルが正常の33~66%レベルに低下していた。また,2003年のOrange JSらによる小児乳糜胸8例による報告9)でも,全例でリンパ球減少症を伴い,8例中4例は重症敗血症を合併し,血清IgGレベルが179±35 mg/dLレベルに低下していたという。一方,Kovacikova Lら10)は,小児心臓術後に乳糜胸を合併した16例中,4例にのみIgGレベルの低下が見られるに過ぎないと報告している。
このように,現在のところ,乳糜胸による低IgG血症の発症率にはばらつきが認められるものの,乳糜胸では低IgG血症が生じる可能性は否定できず,定期的な血清IgG濃度の測定により,IVIG療法の施行を評価する必要がある。小児の心奇形が低ガンマグロブリン血症を合併しやすいことは,ジョージワシントン大学のOnigbanjo MTら11)のグループでも検証されている。
成人心不全に対するIVIG療法
クリーブランドクリニックのYamani MHらによる心臓移植術後220例の報告12)では,血清IgG濃度は,心臓移植前の平均1137±353 mg/dLより,心臓移植術後に約26%で500 mg/dL未満に,約10%で350 mg/dL未満に減少している。彼らの報告では,血清IgG濃度は,心移植後に緩徐に低下し,平均約196日で最低値に達している。サイトメガロウイルス(CMV)抗体を豊富に含む150 mg/kg のCMV-IVIG(CytoGam®)を1回投与した結果,日和見感染の発症率が64%から11%に有意に減じられ,拒絶反応が有意に抑制されたという。
一方,心臓移植に持ち込むまでのventricular assist device(VAD)の装着時期にも,IgGレベルが低下することが知られている。同じクリーブランドクリニックのYamani MHらのグループ13)は,VADを装着している76名の患者を血清IgG濃度700 mg/dL前後で2群にわけ,感染症罹患率を比較している。血清IgG濃度700 mg/dL未満では感染症罹患率が56%から95%に高まり,さらにCMV感染率が16%から45%に高まっている。Yamani MHら13)のVAD装着では,血清IgG濃度の低値を認めなくとも,50%を超える高い感染症合併率を示している。1999年のHolman WL ら14)のVAD装着患者の解析では,2年生存率が38%であり,敗血症の罹患により2年生存率が8%に減じている。2002年4月より2004年12月までVADを装着された70名のSharples Lらによる解析15)では,2005年3月までの間に心移植を受けることなく43%が死亡し,7%がVADを装着し続けていたという。44%が心移植に持ち込まれ,6%は心機能回復によりVADから離脱できたという。このSharples Lら15)の報告でも,VAD装着中の感染症罹患が,死因の上位として挙げられている。
このような心不全状態において,IVIGは炎症に付随する心臓のアポトーシスを抑制する可能性が示唆されている。うっ血性心不全では,急性期よりTNF-αやIL-1βなどの炎症性サイトカインの血中濃度が上昇し,炎症性物質が産生されるばかりか,アポトーシスが進行することが知られている16, 17)。ノルウェー大学のGullestad Lら18)は,急性冠症候群あるいは特発性拡張型心筋症でうっ血性心不全に移行した40名の患者を対象として, 5日間の0.4 g/kg のIVIG療法を行い,1ヶ月ごとに0.4 g/kgのIVIGを5ヶ月間追加するプロトコールを立てた。対象とした患者群の左室駆出率は,IVIG群で最終的に26±2%より31±3%に増加したが,プラセボ群では左室駆出率の改善が認められていない。IVIG治療により,TNF-α/可溶性TNF受容体比やIL-1βが有意に低下し,抗炎症性サイトカインであるIL-10が有意に上昇している。以上より,Gullestad Lら18)は,うっ血性心不全の増悪因子として,炎症性サイトカインが関与する可能性を示し,IVIG療法は炎症性サイトカインの有意な状態から抗炎症性サイトカインの有意な状態へサイトカインシフトさせ,心機能を改善すると結論した。また,同時期の2001年に検証されたピップバーグ大学のMcNamara DMら19)の62名の拡張型心筋症患者を対象とした研究では, IVIGの投与は1g/kgの2日間に設定されている。McNamara DMら20)のデータでは,IVIG療法による統計学的に有意な改善が認められていない。Gullestad Lら21)とMcNamara DMら19)の治療効果の違いは,うっ血性心不全の発症後の経過の違いとIVIGの投与スケジュールの違いにあるかもしれない。McNamara DMら19)のデータは症状出現より6ヶ月以内の比較的早期の拡張型心筋症を対象にしており,プラセボ群の治療成績が極めて良いために,IVIG群との差が認められなかった可能性がある。
このような結果を検証するものとして,2003年に京都大学の岸本ら20)により,症状出現より6ヶ月以内のNew York Heart Association(NYHA)class ⅢあるいはIVの左室駆出率40%未満の9名の患者を対象として,IVIG 1~2 g/Kgの1回投与による治療効果が評価された。岸本ら20)の9症例の原疾患の内訳は,急性心筋炎6名,急性拡張型心筋症3名である。IVIG施行前の左室駆出率の平均は19.0±7.5%だったが,IVIG療法の施行後約12日で,左室駆出率が35.4±9.1%に改善し,さらに, TNF-αとIL-6の血漿濃度はIVIG療法後に患者すべてで著明に減少し,酸化ストレスのマーカーである血漿チオレドキシン濃度も有意に減少していた。この研究はプラセボ群のないものではあるが, IVIGが有害となる結果は全例に認められず,診断に用いた心筋生検の結果からすれば,心筋の炎症のみならず,心筋傷害を軽減させる可能性を示している。