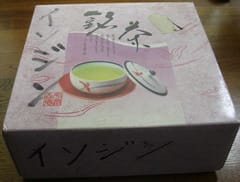昨日辺りからウルトラ160M回線の下り速度が大幅に低下して今朝まで続いている。公称最大速度が160Mで、実測80M台を維持してきたのにさらにその20分の1近くまで下がっている。今朝は少々上がったもののそれでも7M台で上り速度よりも遅い。一体何が起こったのだろう。岩手・宮城内陸地震の影響でもあるのだろうか。それとも速度測定システムに異常が生じたのだろうか。J:COMからは何の知らせもない。これから二三日の旅に出かけるので、帰ってくるまでに復旧して欲しいものだ。上図が6月15日08:24、下図が6月16日07:16の結果である。


追記(6月19日)
旅から戻り今朝通信速度を測定しても下りが依然として遅い。J:COMのサービスセンターに電話をしてやりとりの結果、モデムに問題があるのではということになりモデム交換することになった。このシステムになって三台目である。ちなみに現在はモデムとルーターの電源をオフ・オンすることで下りの通信速度は81.92Mbpsに回復している。


追記(6月19日)
旅から戻り今朝通信速度を測定しても下りが依然として遅い。J:COMのサービスセンターに電話をしてやりとりの結果、モデムに問題があるのではということになりモデム交換することになった。このシステムになって三台目である。ちなみに現在はモデムとルーターの電源をオフ・オンすることで下りの通信速度は81.92Mbpsに回復している。