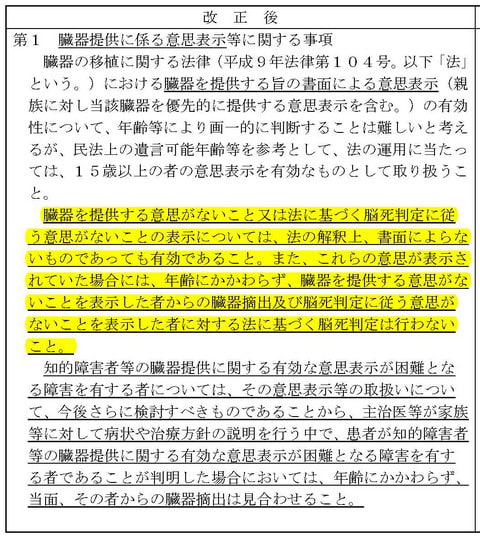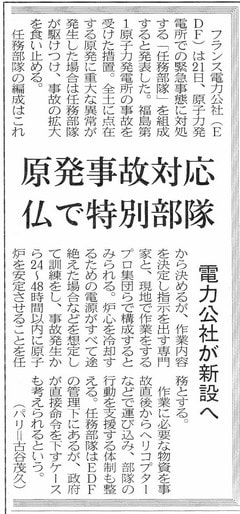私はイージス艦「あたご」に漁船清徳丸が衝突し、船体が二つに割れて沈没した事件では、衝突した側の清徳丸船長が衝突するまでにいったい何をしていたのだろうと不思議に思い、謝罪する相手を間違えたイージス艦「あたご」艦長で次のように記した。当時の状況の一部も分かるのでお目通しいただけたらと思う。
(2008年)2月22日の朝日朝刊には、事故直前まで清徳丸と一緒にいた漁船の乗組員らの情報に基づき、衝突に至までの経緯が艦船の相互の動きの図解があったので、それにもとづいての私の見解であった。その図解を再掲する。

この図ではどうみても「あたご」の右舷前方より清徳丸その他の僚船が、「あたご」に接近しつつあることになる。これを横浜地裁での裁判で明らかにされた次の清徳丸の航跡(時事ドットコム)とくらべると、清徳丸が「あたご」に接近する航跡が見方によっては正反対であることに驚いた。衝突直前に注目すると、清徳丸が「あたご」の右舷後方から急接近しているのである。

報道では裁判所が独自に衝突までの僚船の航跡を描いたとのことであるが、毎日新聞がそのイメージ図を出しているので、参考に引用する。

裁判の判決では検察側主張の航跡を否定したとのことであるが、それは航跡作製にあたってその根拠となった僚船船長らの調書が恣意的と判断されたことによるとして、そのことばかりがマスメディアにより報道されているが、私には弁護側主張の航跡と検察側主張の航跡の違いが、どの点で判決を左右することになるのか、裁判記録を子細に見ない限り判断のしようがない。なぜなら弁護側、検察側(裁判所も含めて)の主張する清徳丸の航跡が、衝突のほぼ3分前からは一致しているからである。衝突時の速度が上のブログにも引用したように「あたご」が時速19キロで清徳丸が28キロであったとすると、より高速の清徳丸が「あたご」に急接近して右舷後方から艦首に突っ込んでいったとしか見ようがないではないか。まるで尖閣沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に、この時は船尾へであったが、体当たりした状況と同じではないかと私は思った。
裁判記録を見ない限りこれ以上踏み込んだことは言えない。しかしこの航跡図を見る限り、清徳丸の方が「あたご」に突っ込んでいったと誰しも思うのではなかろうか。清徳丸の船長は衝突に至るまで、何はともあれ2回、舵を切っているのである。何を考えたのかはやっぱり見えてこない。
それにしても事故直後の朝日新聞(だけとは限らないと思うが)に掲載された誤解を与えやすい図解がどうして生まれたのか、検証が欲しいものである。検察側と弁護側の違いより、この両者に対する朝日新聞の方が大本において大きく違っているのである。
2月26日のブログ清徳丸はなぜ為す術がなかったのだろうで、清徳丸の船長は衝突するまでいったい何をしていたのだろうと私は疑問を投げかけた。そこで引用した図解によると、清徳丸の僚船である幸運丸は「あたご」の前方約2.7kmほどで大きく右へ旋回して「あたご」を回避した。また清徳丸の後方を航行していた僚船金平丸も、その操舵が適法だったのかどうかは知らないが、いったん右に向かった後で左へ大きく回避し、とにかく「あたご」を避けている。幸運丸と金平丸の間に挟まれて進んでいた清徳丸だけがなぜ「あたご」と衝突したのか、これは誰しも持つ疑問ではなかろうか。それが現時点では明らかにされていない。
海は皆のものである。海上自衛隊の艦船であれ漁船であれ、日本では平等である。お互いが安全航行を心がけるのは当然のことである。しかし7000トンの護衛艦と7トンの漁船では自ずと操艦、操船の心がけが違っているのではなかろうか。7000トンもの護衛艦が戦闘中でもあるまいし、右や左にくるくる舵を切ってくれては、すれ違う船はいったいどう身を躱せばいいのかかえって途方にくれることだろう。大きい船は静々とひたすら前を見て行くものだ、というのが海の男の常識にでもなっておれば、おのずとより小さくて小回りの効く船がちゃんと避ける、そのほうが事がスムーズに運ぶのではなかろうか。報道によると「あたご」の乗組員は漁船が避けてくれると思ったらしいが、そのような(暗黙の)ルールがあってもいいのではないか。
2月26日の東京新聞は《あたごは一〇・五ノット(時速約一九キロ)、漁船団は約一五ノット(約二八キロ)で進んでおり、一分で八百メートル接近する。》と報じていた。なんと「あたご」の1.5倍の速度で漁船団は進んでいたのである。高速道路を80kmの速度で走っている大型トレーラーを自動二輪が120kmであっという間に追い越していく、それぐらいの速度差があったのである。この時点での機動性は漁船の方が「あたご」より遙かに勝っていたのである。だからこそ幸運丸と金平丸は衝突を回避できたのであろう。清徳丸だけ、いったい何をしていたのだろう。
海は皆のものである。海上自衛隊の艦船であれ漁船であれ、日本では平等である。お互いが安全航行を心がけるのは当然のことである。しかし7000トンの護衛艦と7トンの漁船では自ずと操艦、操船の心がけが違っているのではなかろうか。7000トンもの護衛艦が戦闘中でもあるまいし、右や左にくるくる舵を切ってくれては、すれ違う船はいったいどう身を躱せばいいのかかえって途方にくれることだろう。大きい船は静々とひたすら前を見て行くものだ、というのが海の男の常識にでもなっておれば、おのずとより小さくて小回りの効く船がちゃんと避ける、そのほうが事がスムーズに運ぶのではなかろうか。報道によると「あたご」の乗組員は漁船が避けてくれると思ったらしいが、そのような(暗黙の)ルールがあってもいいのではないか。
2月26日の東京新聞は《あたごは一〇・五ノット(時速約一九キロ)、漁船団は約一五ノット(約二八キロ)で進んでおり、一分で八百メートル接近する。》と報じていた。なんと「あたご」の1.5倍の速度で漁船団は進んでいたのである。高速道路を80kmの速度で走っている大型トレーラーを自動二輪が120kmであっという間に追い越していく、それぐらいの速度差があったのである。この時点での機動性は漁船の方が「あたご」より遙かに勝っていたのである。だからこそ幸運丸と金平丸は衝突を回避できたのであろう。清徳丸だけ、いったい何をしていたのだろう。
(2008年)2月22日の朝日朝刊には、事故直前まで清徳丸と一緒にいた漁船の乗組員らの情報に基づき、衝突に至までの経緯が艦船の相互の動きの図解があったので、それにもとづいての私の見解であった。その図解を再掲する。

この図ではどうみても「あたご」の右舷前方より清徳丸その他の僚船が、「あたご」に接近しつつあることになる。これを横浜地裁での裁判で明らかにされた次の清徳丸の航跡(時事ドットコム)とくらべると、清徳丸が「あたご」に接近する航跡が見方によっては正反対であることに驚いた。衝突直前に注目すると、清徳丸が「あたご」の右舷後方から急接近しているのである。

報道では裁判所が独自に衝突までの僚船の航跡を描いたとのことであるが、毎日新聞がそのイメージ図を出しているので、参考に引用する。

裁判の判決では検察側主張の航跡を否定したとのことであるが、それは航跡作製にあたってその根拠となった僚船船長らの調書が恣意的と判断されたことによるとして、そのことばかりがマスメディアにより報道されているが、私には弁護側主張の航跡と検察側主張の航跡の違いが、どの点で判決を左右することになるのか、裁判記録を子細に見ない限り判断のしようがない。なぜなら弁護側、検察側(裁判所も含めて)の主張する清徳丸の航跡が、衝突のほぼ3分前からは一致しているからである。衝突時の速度が上のブログにも引用したように「あたご」が時速19キロで清徳丸が28キロであったとすると、より高速の清徳丸が「あたご」に急接近して右舷後方から艦首に突っ込んでいったとしか見ようがないではないか。まるで尖閣沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に、この時は船尾へであったが、体当たりした状況と同じではないかと私は思った。
裁判記録を見ない限りこれ以上踏み込んだことは言えない。しかしこの航跡図を見る限り、清徳丸の方が「あたご」に突っ込んでいったと誰しも思うのではなかろうか。清徳丸の船長は衝突に至るまで、何はともあれ2回、舵を切っているのである。何を考えたのかはやっぱり見えてこない。
それにしても事故直後の朝日新聞(だけとは限らないと思うが)に掲載された誤解を与えやすい図解がどうして生まれたのか、検証が欲しいものである。検察側と弁護側の違いより、この両者に対する朝日新聞の方が大本において大きく違っているのである。