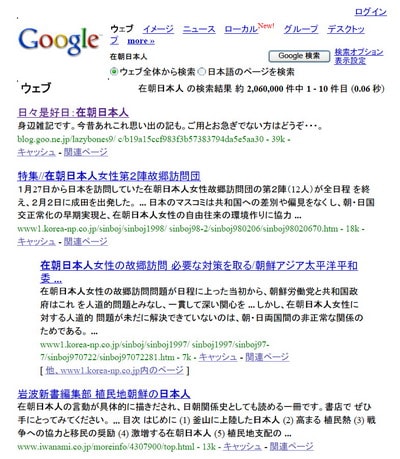堀川哲著「エピソードで読む西洋哲学史」(PHP新書)とほぼ同じ頃に岩波新書で熊野純彦著「西洋哲学史 古代から中世へ」が出た。『岩波』という名前に弱い私は岩波の本ならついついタイトルを見ただけで買うことが多い。もちろん当たりはずれがあるが、この本はどちらかといえば『はずれ』だった。
著者は「まえがき」でこのように言っている。
《この本は三つのことに気をつけて書かれています。
(中略)
第三に、個々の哲学者自身のテクストあるいは資料となるテクストを、なるべくきちんと引用しておくこと、です。
(中略)
哲学とは、人間の経験と思考をめぐって、その可能性と限界を見さだめようとするものであること、最後に、そうした思考がそれぞれに魅力的なテクストというかたちで残されているしだいを、すこしだけでも示すことができれば、と考えています。》
私はこの狙いが成功しているとは思わない。
テクストを引用するということ自体、執筆上の一つのスタイルとも言える。ところが現実に引用テクストに出会うとこれが難儀なのである。一番最初に出てくるテクストを見てみよう。少し長いが省略なしに引用する。
《哲学のはじまりをめぐる、アリストテレスの証言を引いておく。哲学の始原にかんして論じられる場合に、かならずしたじきになっている文章である。(注 熊川氏)
さて、あの始めに哲学したひとびとのうち、その大部分は素材の意味での原理だけを、いっさいの存在者の原理であると考えていた。すなわち、全ての存在者が、そのように存在するのは、それ(傍点付き)からであり、それらのすべてはそれ(傍点付き)から生成し、その終末にはそれ(傍点付き)へと消滅してゆくそれ(傍点付き)(中略)をかれらは、いっさいの存在者の構成要素であり、原理であると言っている。 (『形而上学』第一巻第三章)》 (4ページ)
さて、このテクストをまず読んで内容を正しく理解できる人がどれぐらいいるだろうか。『哲学』を職業にしている人ならともかく、一般人ではインテリを自負する人にも無理であろう。
これに続けて著者は『注釈』を加えている。
《 「素材」と訳しておいたギリシア語は「ヒュレー」であって、アリストテレスの用語としては「質料」のことである(本書、第7章参照)。ともあれアリストテレスはいま引いた文章のすぐあとに、問題の一文をしるしていた。「タレスは、かの哲学の始祖であるけれども、水がそれ(傍点付き)である、といっている」。
文脈上「水」がそれ(傍点付き)である「それ」とは、「原理」のことである。右では原理とかりに訳しておいた語は「アルケー」であって、「はじまり」という意味をもつ。アリストテレスの時代すでに、断片的な伝承だけがのこされていたにすぎないタレスは、水こそがいっさいの存在者のはじまりであり、存在者が存在する原理であって、すべてがそこへと滅んでゆく終局であると主張していたというのが、さしあたりはアリストテレスそのひとの証言にほかならない。》
確かにこの『注釈』を読めば、アリストテレスの引用で、それ(傍点付き)を「水」と置き換えればよいことがわかって、少しは文章の通りがよくなる。しかしそれがわかったぐらいで、この引用が著者の意図している『魅力的なテクスト』にはなりえない。はやい話が、《「素材」と訳しておいたギリシア語は「ヒュレー」であって》とか《原理とかりに訳しておいた語は「アルケー」であって》なんて教えて貰っても一般読者にどういう意味をもつのだろう。それがどうした、で終わりである。
この叙述のスタイルは「エピソードで読む西洋哲学史」のところで引用した、アダム・スミスが罵倒するオックスフォード大学教師による『外書講読』を思い出させる。『何も勉強しない。だから講義ができない』オックスフォード大学の教師とは違って、著者の熊野氏この本にその学殖を傾注しておられることはわかる。しかしこの叙述スタイルが教室における講義ならともかく、不特定多数の読書人を相手とする『新書』にはそぐわないのである。
著者は『哲学』を説いている。では科学者が『科学』を説く場合を想定してみよう。
科学者が実験を行い、データを解析して結論を得る。それをある科学的な概念としてまとめて論文に発表する。この論文はアリストテレスの「形而上学」という原著に相当するものと考えていただこう。
科学者の思考のエッセンスが含まれているからといって、原著論文を一般読者を相手の著書に引用したとする。たとえば次ような文章はどうであろう。
《The novel feature of the sturcture is the manner in which the two chains are held together by the purine and pyrimidine bases. The planes of the bases are perpendicular to the fibre axis. They are joined together in pairs, a single base from one chain being hydrogen-bonded to a single base from the other chain, so that the two lie side by side with identical z-co-ordinates. One of the pair must be a purine and the other a pyrimidine for bonding to occur. The hydrogen bonds are made as follows: purine position 1 to pyrimidine position 1; purine position 6 to pyrimidine position 6.》
これはワトソンとクリックがDNA二重らせん発見を報じたNATURE論文(1953年)の主要な箇所で、この論文はその後の科学・技術の世界ははもちろん人間の生き方までも大きく変えてしまったほどのインパクトをもつものである。紺地に金泥で文章を記し、表装して欄間に掲げておきたいぐらいのものである。
しかし、このテクストを日本語に訳し、化学の初歩も含めて懇切丁寧な注釈を加えたとしても、この論文の真髄をもともと科学の素養の乏しい人に伝えることは不可能であろう。ここに科学ライターの出番があるのであって、原著論文をはじめ多くの資料に当たりながらもその内容を噛み砕き、自分の言葉でそのエッセンスを読者に語りかけることになる。読者にどのように伝わるだろうか、ということを絶えず意識して文章をまとめないことには、科学の成果を多くの人に伝えることはできない。同じことが哲学についてもいえる。
『哲学』は『科学』の『科』を『哲』で置き換えたようなもの、『哲学』を職業としていない人にとっては、原著のほんの『かけら』を目の前に示されて、ペダンチックな注釈をしてもらっても、そのようなものは豚に真珠、猫に小判であろう。その『かけら』が真に真珠であり小判であるならば、であるが。
熊野氏がご自分が咀嚼したたとえば「形而上学」の引用部分を、読者の平均的読解力をも念頭に置いて、現代語訳のような形で紹介されるスタイルを取られなかったことを私は残念に思う。私は堀川哲氏の本からは何人かの哲学者の代表作を読んでみたいという気にさせられた。ところが熊野氏の本には最初から素直に入っていけなかったので、ハイ、それまでよ、であった。