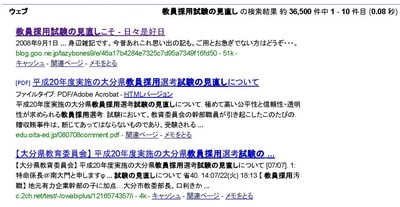この頃ついテレビのニュースを見逃すし、新聞も見出し程度で終わることが多い。ところが《橋下知事「手を出さないとしょうがない」 体罰容認発言》(asahi.com 2008年10月26日22時49分)が目を引いた。現在、教育の場で体罰がどのように行われているのか私はなにも知らないが、この見出しからは元来体罰が禁止されているにもかかわらず橋下知事が容認したとのニュアンスで受け取ったからである。それで「ウィキペディア(Wikipedia)」で「体罰」を調べてみると、昭和22年制定の学校基本法第11条に体罰についての規定がなされているのである。
《第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。》
ところで体罰とはなにか。ウィキペディアは《日本の学校で、正課教育に関連して伝統的に行われている/行われていた体罰の主なものには、以下のものがある。》として、
○教鞭などで頭を打つ。
○廊下等に立たせる。
○頬を平手で打つ。
○顔を殴る。
○尻を打つ。
○正座をさせる。
などの例を挙げている。
昔はどうだったか。戦時中の国民学校で女先生が鞭で生徒の手の甲をピシッと叩いたのを見たし、また私自身、男先生に額を爪弾きされたことがあった。国民学校で罰を受けたことは後にも先にもこのことだけなのでその状況は今でもよく覚えている。授業の最中に鼻を親指と人差し指でつまみ鼻の穴を押しつぶし、口をつぐんで空気を吸い込む。その頃ははな垂れが珍しくなかったので鼻汁の粘着力で鼻の穴が引っ付いてしまう。そこで指を離しどれだけ長い時間鼻の穴をふさいで居られるかを隣席の友達と競い合っていた。それを先生に見つかって二人ともパッチンとやられたのである。その上あろうことかそのことを通信簿に書かれてしまった。母が朝鮮から引き揚げの時に持ち帰ってくれた通信簿の通信欄にある「時々粗野ナル言動アリ」の実態は上のような大気圧を視覚化する独創的理科実験だったのである。なんだ、教師はえらい大げさな物言いをするものだな、と思ったものである。

ところがウィキペディアに次のような文章が続いているのを見て驚いた。《誤解が多いが下記(上記の体罰例、注)のような体罰が行われ始めたのは主に戦後からであり、戦前は小学校令(戦時中に制定された国民学校令も同様)により体罰は一貫して禁止されており、小さな体罰でも教師が処分されることがあった。》なんと、体罰は戦後になって行われるようになったというのである。そういえば教師は鞭で頭を打つことはせずに手の甲を打ったし、私も額を爪弾きされたことは上の体罰例には当てはまらない。『小さな体罰でも教師が処分されることがあった』ということを教師はちゃんと心得ていたのだろうか。となると戦後の体罰はリンチが横行した旧日本軍の復員兵士が教壇に立って始めたことなのだろうか。
そこで橋下知事が実際にどう云ったのか知りたくなって探すと、ちゃんとyoutubeに記録が残っているのである。
これを見て私は橋下知事は戦後の体罰世代なのだな、と思った。自分たちが学校でそのような目にあってきたから、「ちょっと叱って、頭をゴッツンしようものなら、やれ体罰と叫んでくる。これでは先生は教育が出来ない。口で言ってわからないものは、手を出さないとしょうがない」のような言葉が素直に出てきたように思えてきた。
そう思えばこのyoutubeは橋下徹知事と府教育委員らが教育行政について一般参加者と意見を交わす「大阪の教育を考える府民討論会」を録画したものだが、要は全国学力調査で大阪府の成績が振るわなかったから成績を上げなければ、ということに問題の発端があったのだろう。漏れ聞くところではあの全国学力調査は当時文部科学相であった中山成彬氏が「日教組(日本教職員組合)の強いところは学力が低いんじゃないか」との思いつきを調べたくて始めたとか。結果的には中山説を実証できなかったようであるが、そういう無駄なことに国費を使うこともさることながら、その点数という結果に振り回されている橋下知事は体罰に対する姿勢にも現れているように、戦後の『間違った教育』の申し子のようにも見えてくるのである。視野をもっと拡大すべきであろう。
この録画にあるように自分の言葉を語ることの出来る橋下知事はたしかに希有の為政者である。しかし主張の後には人の意見を聞き入れる度量を同時に期待したい。
《第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。》
ところで体罰とはなにか。ウィキペディアは《日本の学校で、正課教育に関連して伝統的に行われている/行われていた体罰の主なものには、以下のものがある。》として、
○教鞭などで頭を打つ。
○廊下等に立たせる。
○頬を平手で打つ。
○顔を殴る。
○尻を打つ。
○正座をさせる。
などの例を挙げている。
昔はどうだったか。戦時中の国民学校で女先生が鞭で生徒の手の甲をピシッと叩いたのを見たし、また私自身、男先生に額を爪弾きされたことがあった。国民学校で罰を受けたことは後にも先にもこのことだけなのでその状況は今でもよく覚えている。授業の最中に鼻を親指と人差し指でつまみ鼻の穴を押しつぶし、口をつぐんで空気を吸い込む。その頃ははな垂れが珍しくなかったので鼻汁の粘着力で鼻の穴が引っ付いてしまう。そこで指を離しどれだけ長い時間鼻の穴をふさいで居られるかを隣席の友達と競い合っていた。それを先生に見つかって二人ともパッチンとやられたのである。その上あろうことかそのことを通信簿に書かれてしまった。母が朝鮮から引き揚げの時に持ち帰ってくれた通信簿の通信欄にある「時々粗野ナル言動アリ」の実態は上のような大気圧を視覚化する独創的理科実験だったのである。なんだ、教師はえらい大げさな物言いをするものだな、と思ったものである。

ところがウィキペディアに次のような文章が続いているのを見て驚いた。《誤解が多いが下記(上記の体罰例、注)のような体罰が行われ始めたのは主に戦後からであり、戦前は小学校令(戦時中に制定された国民学校令も同様)により体罰は一貫して禁止されており、小さな体罰でも教師が処分されることがあった。》なんと、体罰は戦後になって行われるようになったというのである。そういえば教師は鞭で頭を打つことはせずに手の甲を打ったし、私も額を爪弾きされたことは上の体罰例には当てはまらない。『小さな体罰でも教師が処分されることがあった』ということを教師はちゃんと心得ていたのだろうか。となると戦後の体罰はリンチが横行した旧日本軍の復員兵士が教壇に立って始めたことなのだろうか。
そこで橋下知事が実際にどう云ったのか知りたくなって探すと、ちゃんとyoutubeに記録が残っているのである。
これを見て私は橋下知事は戦後の体罰世代なのだな、と思った。自分たちが学校でそのような目にあってきたから、「ちょっと叱って、頭をゴッツンしようものなら、やれ体罰と叫んでくる。これでは先生は教育が出来ない。口で言ってわからないものは、手を出さないとしょうがない」のような言葉が素直に出てきたように思えてきた。
そう思えばこのyoutubeは橋下徹知事と府教育委員らが教育行政について一般参加者と意見を交わす「大阪の教育を考える府民討論会」を録画したものだが、要は全国学力調査で大阪府の成績が振るわなかったから成績を上げなければ、ということに問題の発端があったのだろう。漏れ聞くところではあの全国学力調査は当時文部科学相であった中山成彬氏が「日教組(日本教職員組合)の強いところは学力が低いんじゃないか」との思いつきを調べたくて始めたとか。結果的には中山説を実証できなかったようであるが、そういう無駄なことに国費を使うこともさることながら、その点数という結果に振り回されている橋下知事は体罰に対する姿勢にも現れているように、戦後の『間違った教育』の申し子のようにも見えてくるのである。視野をもっと拡大すべきであろう。
この録画にあるように自分の言葉を語ることの出来る橋下知事はたしかに希有の為政者である。しかし主張の後には人の意見を聞き入れる度量を同時に期待したい。