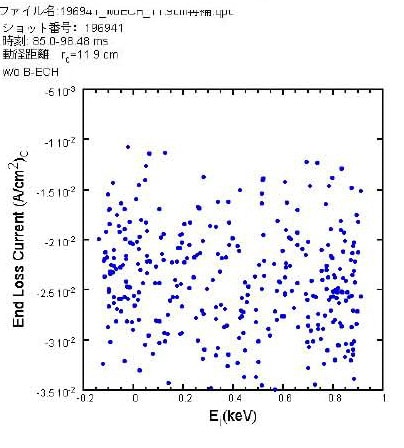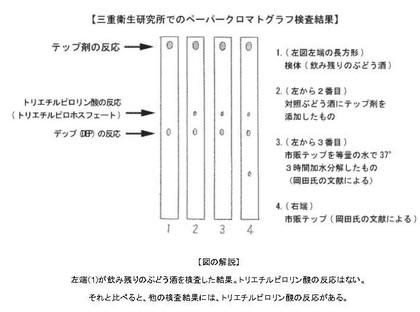クローズアップ現代からは最近遠ざかっているが、今晩はホットな話題でもあるので7時のニュースに引き続いて見た。もう何年も京都大学には足を踏み入れていないので、山中伸弥教授が所長を務める「京都大学iPS細胞研究所」が京大のキャンパスのどこに出来たのか分かるかなと思い、つい周囲の光景を見回した。思ったより大きな建物が印象的だったが、研究室を始め内部はなんだか狭苦しくて、働いている研究者が養鶏場で卵産みに励んでいる鶏のように見えた(失礼!)。山中教授のiPS細胞研究こそ大金を注ぎ込むまたとないターゲットだけに、私の勝手な思い込みであるが、空間的にももっとゆとりのある大らかな感じのする研究所かと期待していたので、それが裏切られたような気がしたのである。
しかし研究リーダーの多くが30歳代とはわが意を得た思いである。この年代の人たちが思う存分力を振るうと、どれほど素晴らしい科学的成果がもたらされるのかその「実験」の場でもある。私は日本における科学の発展に必要なことは、若い研究者に直接研究費が渡り自らのアイディアを伸ばしていくことにあると信じている。その意味での成果もぜひ期待したい。所長の山中教授が「総合力で目指す世界最高」を強調しておられた。そのためのノー・ ハオの蓄積が近い将来日本の科学研究を推し進める大きな駆動力となってほしいものである。
ところが番組を観ていて違和感もあった。特許申請と関係があるのだろうが、研究員が実験ノートをそういう部署のオフイスに持参し、テーブルの上に山積みしている光景である。そのノートに何かが書き込まれていた様子から想像するに、特許申請とかまたは異議申し立てなどの資料としての形式を整えるためのものだろうか。一口で言えばいやーな感じ、これが大学の研究所?と思った。さらにアメリカのベンチャー企業だったか、投資家といえば聞こえがよいが、何でも金儲けの種にしてしまう金主が舌なめずりしているパーティ風景であった。私はこれまでも何回かiPS細胞研究に関わる特許問題について意見を述べてきたが、万能細胞(iPS細胞)研究 マンハッタン計画 キュリー夫人では次のように述べている。
山中教授も番組の中で言っておられた。京都大学の金儲けのためではなくて、より多くの人に(無償で?)利用して貰いたいからである、と。それなら最初から特許を意識せずに重要な発見を次から次へと論文で発表していけばよいのである。周知の事実となればもはや特許の対象とはならないし、世界中の誰もがその成果をもとに自分の研究を推し進めることができるではないか。「総合力で目指す世界最高」の研究所が一切の特許を放棄することを宣言すれば、それだけでもまず金字塔を打ち立てることになるではないか。
iPS細胞の臨床応用の面でも感じることがあった。難病治療の必殺技のような取り上げ方を番組がしているように私は思ったが、人への応用の話はまだまだ早すぎるのではないか。もちろん可能性は否定出来ない。しかし可能性である以上はサラッと紹介する程度に止めるべきで、実際に難病に罹っている患者・家族を番組に登場させるのは行き過ぎである。あまりマスメディアが先行するとその煽りを喰らうのは科学者である。下手するとペテン師にもされかねない。その意味では科学者もマスメディアとの付き合いには慎重のうえにも慎重であるべきだと思った。
しかし研究リーダーの多くが30歳代とはわが意を得た思いである。この年代の人たちが思う存分力を振るうと、どれほど素晴らしい科学的成果がもたらされるのかその「実験」の場でもある。私は日本における科学の発展に必要なことは、若い研究者に直接研究費が渡り自らのアイディアを伸ばしていくことにあると信じている。その意味での成果もぜひ期待したい。所長の山中教授が「総合力で目指す世界最高」を強調しておられた。そのためのノー・ ハオの蓄積が近い将来日本の科学研究を推し進める大きな駆動力となってほしいものである。
ところが番組を観ていて違和感もあった。特許申請と関係があるのだろうが、研究員が実験ノートをそういう部署のオフイスに持参し、テーブルの上に山積みしている光景である。そのノートに何かが書き込まれていた様子から想像するに、特許申請とかまたは異議申し立てなどの資料としての形式を整えるためのものだろうか。一口で言えばいやーな感じ、これが大学の研究所?と思った。さらにアメリカのベンチャー企業だったか、投資家といえば聞こえがよいが、何でも金儲けの種にしてしまう金主が舌なめずりしているパーティ風景であった。私はこれまでも何回かiPS細胞研究に関わる特許問題について意見を述べてきたが、万能細胞(iPS細胞)研究 マンハッタン計画 キュリー夫人では次のように述べている。
京都大学(山中教授)が万能細胞研究の人類全体の医療に及ぼす影響の普遍性にかんがみ、すべての研究者が特許出願を抛棄するべく全世界に率先して働きかけて欲しいものである。研究者が自らの研究の社会的意義を考え、特許を念頭に置かずに研究成果をすべて公表する、これは一人一人の研究者の判断で出来ることであろう。科学者の社会的責任を今原点に戻ってじっくり考えていただきたいと思う。
山中教授も番組の中で言っておられた。京都大学の金儲けのためではなくて、より多くの人に(無償で?)利用して貰いたいからである、と。それなら最初から特許を意識せずに重要な発見を次から次へと論文で発表していけばよいのである。周知の事実となればもはや特許の対象とはならないし、世界中の誰もがその成果をもとに自分の研究を推し進めることができるではないか。「総合力で目指す世界最高」の研究所が一切の特許を放棄することを宣言すれば、それだけでもまず金字塔を打ち立てることになるではないか。
iPS細胞の臨床応用の面でも感じることがあった。難病治療の必殺技のような取り上げ方を番組がしているように私は思ったが、人への応用の話はまだまだ早すぎるのではないか。もちろん可能性は否定出来ない。しかし可能性である以上はサラッと紹介する程度に止めるべきで、実際に難病に罹っている患者・家族を番組に登場させるのは行き過ぎである。あまりマスメディアが先行するとその煽りを喰らうのは科学者である。下手するとペテン師にもされかねない。その意味では科学者もマスメディアとの付き合いには慎重のうえにも慎重であるべきだと思った。