(今更ながらの記事ですが…)
久しぶりに「お練りが見たい!」って思って、行ってきました。
平成27年5月14日(木)
當麻寺のお練りの日です。
とりあえず昼過ぎに当麻寺駅について、まずは腹ごしらえをば…。
と、もくろんでいたものの、
お目当ての駅前のレストランは木曜日が定休日(!)でして。
こんな時は掻き入れ時なのに、商売っけの無いお店だなあ。
まあ、次回来訪時の楽しみにとっておきましょう。
しゃーないので、中将餅で一服してきました。(をい)

本日はお店は大行列。
しかし店内で召し上がる方は少なくて、のほほんとできましたけど。
でも、あんまりのんびりもしてらんないのだ。
一服したらおいとましましたが。
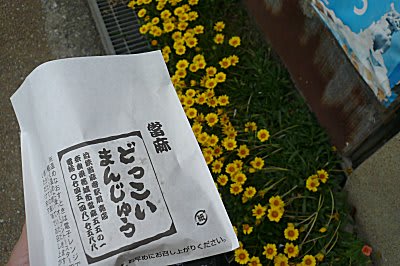
あとは、駅前のどっこいまんじゅうを購入してハグハグ。
これ、作り置きしてないので、注文が入るたびに焼いてくれます。
(そこがちょっと面倒なんだけど)
まんじゅうといってますが、大判焼き風。
皮も中身はさつまいもあんがベースで、
ワタシはさらにチーズが入っているものを選択。
焼きたてのそれは、結構とろんとしていて、実は…食べにくかったです(笑)
(冷めているほうが、固くなって食べやすいのかもよ)
それを食べ歩きしながら當麻寺までの道を進むと、
参詣道すがらの商店も本日は絶賛営業中のところが多い。
まあ、今年一・ニの人出が見込めるお祭りですから、
こんな日は商売するでしょう。
なかでも、一年に一度しか店を開けない(?)「ひめ餅」さんが開いているのを見ました。
ここでもつまみ食いしようかと思ったけど、まあ、いっか~と通り過ぎ。

結構繁盛してました。
駅からまっすぐ歩いてきて15分ほど。
(ここの駅は看板に”最寄り駅”と書いても偽り無しですな。
「岡寺」とか「壷阪山」とかは近所だと思うと痛い目に遭いますから)

練り供養会式は午後四時からなので、
その前に中の坊での當麻曼荼羅の絵解きに参加することに。
當麻曼荼羅の軸をかけて、その絵を見ながら、
仏さんはなあ~あーたらこーたら…と解説をしてくれるのが絵解き。
お経を読んで判らんものは、絵にして、目で見て判るようにして、
極楽とは、地獄とは、来世とは等々を説くのが絵解き。
また、本日4時からおこなわれる練供養も
「阿弥陀如来がお迎えに来るってのは」ってのを
目で見て判るものに置き換えているものです。

私は前もって予約して行ったんだけど、
別に当日飛び込みで受付しても大丈夫みたい。
ってか、「予約しているんですけど…」って受付に申し出ても、
周囲の当日参加の人と同じに扱われましたから。
わざわざ前日までに予約の電話を入れる必要はなかったみたい。
午後一時までに中の坊へあげてもらって、
茶室の脇からグルグルとまわって、廊下をゆき、
絵天井がある写仏道場となっているお部屋まで移動。
ここの建物内部はお抹茶(有料です)をいただいた時に、
茶室と書院の一部を見せていただいたりしたことはありますけど。
今回は階段を上がったり、下ったり、先へどんどん進んだりして、
なんだかたくさん歩いりで写仏道場へたどり着きました。
ここ普段は入室できず、絵天井の公開は四年に一度なもんだから、入ったことはない。
ただし、外から中を覗き込むことは可能だから、
ちらちらっと見たことはありましたけどね>外のお庭から。
ただし、写仏を行う人はここで行いますので、
公開年ではなくても絵天井を拝見できます。
写仏とは仏さまの姿(絵)を写すもので、
→って感じ。
一時過ぎには室内はギューギュー詰めで、
今か今かと始まるのを待っておりました。
そして長老さんが現れて講話開始。
まずはお寺のハナシなどから。
ここの寺は現在は東の門から入ってくるようになっているが、
昔は南の門から入ってくるのが常だった。
昔は竹之内街道からやって来る人がそっちから来ていたから。
金堂の南側にはこの寺で一番古い燈籠がたっているが、
そっちから来る人が多かったってことでしょうなあ、とのこと。
うちは古い塔が二つあるお寺です(えっへん風^^)
昔、薬師寺の高田好胤さんがお写経勧進で有名になった時、
「今度うちにも両塔が建ちますねん(西塔が建ちますねん)」
っていうから、
「うちは大昔からの両塔がありますねん」て返したって。
強気♪
(ふふふ)
先代住職さんは子供がいなかったので、
今の長老さんは子供の頃にお寺にもらわれてきたらしい。
その頃は絵解きをやる坊さんが五人くらいいて、
その役目を自分もやらされていたが、
小僧さんがそれをやっているのがいやでいやで仕方なかった。
それがどんどん高齢化で一人減り二人減りしていって、
誰もやる人がいなくなった。
そこで絵解きは途中で断絶したんだとか。
それが年をとってから、
ああいうのもよかったなあと思って復活させたんだとか。
そして、いよいよ絵解きへ。
もともとの當麻曼荼羅は中将姫が一夜で織ったという”伝承”はとりあえずおいといて、
痛みがひどいので、ぱっと見、絵に見えていたそうですが、
科学的な研究の結果、綴織の錦であるということがわかってます。
作られて早くから痛みが始まったようで、
これまでに、3回の転写本が作られたそうな。
しかし、絵解きで使われるのはそれらの古いものではなく、
前田青邨画伯のお弟子さんの入江正巳画伯が、10年をかけて描き上げたもの。
平成の作なので、色も綺麗で、見やすいし、
これがかなり精密で迫力満点の絵です。
真ん中にどどんと阿弥陀三尊。
その周囲を沢山の菩薩が囲み、さらに花や楽団や天人を配置し、
極楽の様子を描いています。
その周囲を左右と下段に小さいコマ絵が、
コママンガのような配列で描かれています。
(→こんな感じね)
周辺に描かれているのは、
一番下の段が「九品往生」の絵。
人は生前の行いによって「上品上生(じょうぼんじょうしょう)」
から「下品下生(げぼんげしょう)」まで9つのレベルにランク付けされ(!)
それによって死後の扱いが違うんだそうで(ははは)
「上品上生」では仏様御一行様がお迎えに来てくれるけど、
「下品下生」では自力でやってきてやって感じ。
(でも、すべての人は救われるんですけどね>最終的には)
そして左側には下から上に向かってはインドのイダイケ夫人のオハナシが、
くるっとまわっていたり(そろそろ記憶があいまい…だ(汗))
まあ、詰まるところ、仏さんがたくさん描かれてみるだけで幸せなキモチになって、
最後にはどんな人でも仏様は救ってくださるよ、ってことが描かれているんだそうな。
(どんだけ手抜きの説明なんだ…すんません)
そして絵解きに続いては天井に描かれた絵天井の説明。
昭和のはじめに、ここ客殿が解体修理を行った際に、
有名画家たちが絵の寄進を行ったと。
まずは前田青邨画伯を皮切りに、その後も有名画伯たちの奉納が続き、
それらの絵は現在のように天井に掲げられたとのこと。
その後も奉納は続き、天井スペースを増やし、
平成の天井絵もスペースも作られ、今でも増えているようです。
絵天井は四年に一度の公開で、
それ以外では写仏をする人のみ見られるとのこと。
次回は平成30年だそうです。
(どうしても見たかったら、写仏を申し込みましょう←?)
日本画家が主な描き手だけど、おもしろいところではタレントの片岡鶴太郎さんの鯛の絵とか、
「極」という一文字だけが描かれたものもあり、全部見ようとして、
みんな口をあけて天井を眺めているのが面白かったですわ。
(何を見てるねん)
この建物はもともと昭和4年に建てたものがベースなので、
どおりで電気配線とか、鏡とか、流しのタイルとかが古かったわけだ。
なかなか面白い体験でした。
さて。
絵解きを終わって外へ出て、お庭を眺めていたら…なんと、雨が降り出しました。
うそ~!
本人は日傘用にと思って持ってきていた晴雨兼用の傘があったからいいけど、
突然の雨に(天気予報では雨なんて出てなかったはず)傘を求める人が続出。
新緑の濃くなってきた頃なので、また雨もいいもんですね。
なんて強がりを言ったものの、今日のメインイベントはお練りである。
雨になったらどうするの?
ピンポーン。
答えは、曼荼羅堂(本堂)の周辺を歩いて終わりです。
え~何とか、それまでには雨あがってくれ~!

東塔と池(蓮の葉がいっぱい)

写経道場を外から見たもの

植物にとっては惠の雨

緑が一層濃くなった感じです
中の坊を出たら、
「娑婆堂」では、お練りの用意のためにおじちゃんたちが作業をしてました。
すでに娑婆堂から延びる渡り舞台(来迎橋)はまっすぐに曼荼羅堂(極楽堂)に伸びておりましたが、
降り出した雨に、傘を持たない人はしばしその下に避難して雨やどりです。

曼荼羅堂の西隣りの護念院から延びる渡り廊下。
ここから仏様たちがスタンバイして出てきます。
晴れていれば、この来迎橋上をどんどん進んで娑婆堂へ向かうのですが、
雨ともなればどうなりますことやら。

とりあえず雨宿りを兼ねて、曼荼羅堂内でしばし時間をつぶしておりましたが、
途中係りの人の手によって、このカラフルな幕も外されてしまって、
本日の来迎橋でのお練りは中止が決定されました。

ということで、お練りは本堂の周りを回る形で行われることになりましたので、
本堂の東南の角方向の、護念院の白壁の前の場所を確保。
ここならば、護念院から渡ってくる仏様の姿も拝めるし、
回廊が高い場所にあるので傘の波の上からでも、
お練りの様子も見えるだろうと踏んで。
(この読みは正しかったです。この場所は雨天時には有効かも)
そして定刻にはお練りが始まる模様。
仏様たちのお渡りの前にはお寺関係者が、
足元が危なく無いようにと、渡り廊下(?)を一生懸命に雑巾で拭いておられました。
(ご苦労様でした)
そして、いよいよお練り開始です。

お稚児様の列

仏様登場
歩き始める際に、面がずれていると世話役の人が面を直してくれます。
そして登場、
スクイボトケとオガミボトケ

蓮台を持ったのがスクイボトケで、
両手を合掌しているのがオガミボトケ。
つまり観音菩薩(救い仏)と勢至菩薩(拝み仏)です

左右に大きく体をひねりながら、
両腕を高く掲げたり下ろしたりして、一歩一歩ゆっくりと歩み行く姿は、
「練り歩く」=おねりの語感そのもの。
こんな変な動きいうのは、
人間ではない=ホトケであるってのの証明なんだとか。
本堂に入った後は法要が行われて、
それが終わると、スクイボトケの蓮台には中将姫の姿が乗ります。
(従来は娑婆堂で行われる行事だけど、今日だけは本堂で)

蓮台の上には中将姫のお姿があります
そして本堂を出て、再び回廊を練り歩きます。
私は場所を動かず見ていたので、本堂を出て反時計回りで進んでいく行列とは
しばしのお別れになってしまいました。
とりあえず、ぐるっと一周してくれば、
またこの角度へ帰ってくるからとノンキに構えてましたけど。
そして、一周してきた中将姫を捧げ持つ観音菩薩が登場です。
やっぱりここは良いポジションでしたわ♪

続くは勢至菩薩

一歩踏み出しては一歩さがるような感じなのでなかなか進みません★

そのまま護念院への橋を渡っていきます

お練の最終版に来て薄日がさしてきました

二十五菩薩さんたちもお疲れ様でした~
お祭りが午後四時からなんて時間から始まるのには、
こういう”舞台装置”が盛り込まれているからなのね。
つまり、光の中を来迎する仏様の集団を見せるというのが、
この練り供養会式の最高の見せ場。
そこで必要なのが「光」「ライティング」。
野外で行うので、この場合は「夕日」です。
まさに西方極楽浄土から、まばゆい光の中をお迎えに来る仏様たちのお姿を、
「仏さんが迎えに来るってのはこういうもんやで」と、
人々に見せる宗教行事なので、薄日といえどナイスな演出でした。
しかし、終了した途端に晴れてきたってのは…
少々複雑な気持ちになるんですけどね。
まあ、晴れの日のお練りは見たことがあるし、
カメラマンさんたちも珍しいアングルからのお練りを取れたかと思うので、
これはこれで良かったんではないかと。
ポジティブシンキングです♪
(そう思わなきゃやってられないじゃないか!)
雨の日に写真撮るとどんなもんだろと探していたら、
nakaさんのブログでは写真満載の記事を発見!!
練り歩くオガミボトケとスクイボトケはこちらで見られますし、
娑婆堂でのお迎え光景の写真はここにありましたし、
私は場所固定で見ていましたが、雨の日の極楽堂一周の写真はこちらから見られます♪
(すごい!すごい!いろんな場面が見られますよ~必見)
ってことで。
まあ、珍しい光景が撮れた(見られた)と思えば、
雨の中のお練りもよかったのではないでしょうか。
(でも”中の人”は大変だったんでしょうが)

祭りが終わったらすぐさまガランとしてしまいました
最後には金堂&講堂&曼荼羅堂も拝観してきました。
講堂では”例の”油かけ事件”の実物も目にしてしまって…激怒。
芽出度い&有り難い気分が、少し凹みましたけど。
自分も信仰するものがあるのだったら、
他人の信仰にも敬意を払うべきだろうに(ぷんぷん)
ま、それらのこともありましたが、
帰る頃には夕日も照らしてきて、
當麻の夕暮れは綺麗でした。

帰りは道すがら綺麗に咲いているよそのお宅の花などながめながら

駅に着いたら本日のお練り特別運行で当麻寺に特別に止まる電車に乗れました。
これも普段の行いのよさ?(へへへ)
これに乗って一路奈良駅へと向かいます。
(次の日につづく)
久しぶりに「お練りが見たい!」って思って、行ってきました。
平成27年5月14日(木)
當麻寺のお練りの日です。
とりあえず昼過ぎに当麻寺駅について、まずは腹ごしらえをば…。
と、もくろんでいたものの、
お目当ての駅前のレストランは木曜日が定休日(!)でして。
こんな時は掻き入れ時なのに、商売っけの無いお店だなあ。
まあ、次回来訪時の楽しみにとっておきましょう。
しゃーないので、中将餅で一服してきました。(をい)

本日はお店は大行列。
しかし店内で召し上がる方は少なくて、のほほんとできましたけど。
でも、あんまりのんびりもしてらんないのだ。
一服したらおいとましましたが。
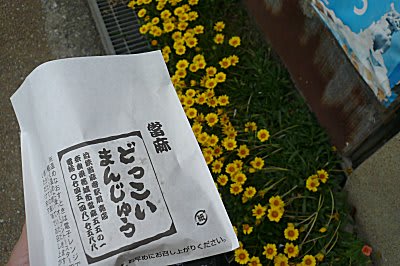
あとは、駅前のどっこいまんじゅうを購入してハグハグ。
これ、作り置きしてないので、注文が入るたびに焼いてくれます。
(そこがちょっと面倒なんだけど)
まんじゅうといってますが、大判焼き風。
皮も中身はさつまいもあんがベースで、
ワタシはさらにチーズが入っているものを選択。
焼きたてのそれは、結構とろんとしていて、実は…食べにくかったです(笑)
(冷めているほうが、固くなって食べやすいのかもよ)
それを食べ歩きしながら當麻寺までの道を進むと、
参詣道すがらの商店も本日は絶賛営業中のところが多い。
まあ、今年一・ニの人出が見込めるお祭りですから、
こんな日は商売するでしょう。
なかでも、一年に一度しか店を開けない(?)「ひめ餅」さんが開いているのを見ました。
ここでもつまみ食いしようかと思ったけど、まあ、いっか~と通り過ぎ。

結構繁盛してました。
駅からまっすぐ歩いてきて15分ほど。
(ここの駅は看板に”最寄り駅”と書いても偽り無しですな。
「岡寺」とか「壷阪山」とかは近所だと思うと痛い目に遭いますから)

練り供養会式は午後四時からなので、
その前に中の坊での當麻曼荼羅の絵解きに参加することに。
當麻曼荼羅の軸をかけて、その絵を見ながら、
仏さんはなあ~あーたらこーたら…と解説をしてくれるのが絵解き。
お経を読んで判らんものは、絵にして、目で見て判るようにして、
極楽とは、地獄とは、来世とは等々を説くのが絵解き。
また、本日4時からおこなわれる練供養も
「阿弥陀如来がお迎えに来るってのは」ってのを
目で見て判るものに置き換えているものです。

私は前もって予約して行ったんだけど、
別に当日飛び込みで受付しても大丈夫みたい。
ってか、「予約しているんですけど…」って受付に申し出ても、
周囲の当日参加の人と同じに扱われましたから。
わざわざ前日までに予約の電話を入れる必要はなかったみたい。
午後一時までに中の坊へあげてもらって、
茶室の脇からグルグルとまわって、廊下をゆき、
絵天井がある写仏道場となっているお部屋まで移動。
ここの建物内部はお抹茶(有料です)をいただいた時に、
茶室と書院の一部を見せていただいたりしたことはありますけど。
今回は階段を上がったり、下ったり、先へどんどん進んだりして、
なんだかたくさん歩いりで写仏道場へたどり着きました。
ここ普段は入室できず、絵天井の公開は四年に一度なもんだから、入ったことはない。
ただし、外から中を覗き込むことは可能だから、
ちらちらっと見たことはありましたけどね>外のお庭から。
ただし、写仏を行う人はここで行いますので、
公開年ではなくても絵天井を拝見できます。
写仏とは仏さまの姿(絵)を写すもので、
→って感じ。
一時過ぎには室内はギューギュー詰めで、
今か今かと始まるのを待っておりました。
そして長老さんが現れて講話開始。
まずはお寺のハナシなどから。
ここの寺は現在は東の門から入ってくるようになっているが、
昔は南の門から入ってくるのが常だった。
昔は竹之内街道からやって来る人がそっちから来ていたから。
金堂の南側にはこの寺で一番古い燈籠がたっているが、
そっちから来る人が多かったってことでしょうなあ、とのこと。
うちは古い塔が二つあるお寺です(えっへん風^^)
昔、薬師寺の高田好胤さんがお写経勧進で有名になった時、
「今度うちにも両塔が建ちますねん(西塔が建ちますねん)」
っていうから、
「うちは大昔からの両塔がありますねん」て返したって。
強気♪
(ふふふ)
先代住職さんは子供がいなかったので、
今の長老さんは子供の頃にお寺にもらわれてきたらしい。
その頃は絵解きをやる坊さんが五人くらいいて、
その役目を自分もやらされていたが、
小僧さんがそれをやっているのがいやでいやで仕方なかった。
それがどんどん高齢化で一人減り二人減りしていって、
誰もやる人がいなくなった。
そこで絵解きは途中で断絶したんだとか。
それが年をとってから、
ああいうのもよかったなあと思って復活させたんだとか。
そして、いよいよ絵解きへ。
もともとの當麻曼荼羅は中将姫が一夜で織ったという”伝承”はとりあえずおいといて、
痛みがひどいので、ぱっと見、絵に見えていたそうですが、
科学的な研究の結果、綴織の錦であるということがわかってます。
作られて早くから痛みが始まったようで、
これまでに、3回の転写本が作られたそうな。
しかし、絵解きで使われるのはそれらの古いものではなく、
前田青邨画伯のお弟子さんの入江正巳画伯が、10年をかけて描き上げたもの。
平成の作なので、色も綺麗で、見やすいし、
これがかなり精密で迫力満点の絵です。
真ん中にどどんと阿弥陀三尊。
その周囲を沢山の菩薩が囲み、さらに花や楽団や天人を配置し、
極楽の様子を描いています。
その周囲を左右と下段に小さいコマ絵が、
コママンガのような配列で描かれています。
(→こんな感じね)
周辺に描かれているのは、
一番下の段が「九品往生」の絵。
人は生前の行いによって「上品上生(じょうぼんじょうしょう)」
から「下品下生(げぼんげしょう)」まで9つのレベルにランク付けされ(!)
それによって死後の扱いが違うんだそうで(ははは)
「上品上生」では仏様御一行様がお迎えに来てくれるけど、
「下品下生」では自力でやってきてやって感じ。
(でも、すべての人は救われるんですけどね>最終的には)
そして左側には下から上に向かってはインドのイダイケ夫人のオハナシが、
くるっとまわっていたり(そろそろ記憶があいまい…だ(汗))
まあ、詰まるところ、仏さんがたくさん描かれてみるだけで幸せなキモチになって、
最後にはどんな人でも仏様は救ってくださるよ、ってことが描かれているんだそうな。
(どんだけ手抜きの説明なんだ…すんません)
そして絵解きに続いては天井に描かれた絵天井の説明。
昭和のはじめに、ここ客殿が解体修理を行った際に、
有名画家たちが絵の寄進を行ったと。
まずは前田青邨画伯を皮切りに、その後も有名画伯たちの奉納が続き、
それらの絵は現在のように天井に掲げられたとのこと。
その後も奉納は続き、天井スペースを増やし、
平成の天井絵もスペースも作られ、今でも増えているようです。
絵天井は四年に一度の公開で、
それ以外では写仏をする人のみ見られるとのこと。
次回は平成30年だそうです。
(どうしても見たかったら、写仏を申し込みましょう←?)
日本画家が主な描き手だけど、おもしろいところではタレントの片岡鶴太郎さんの鯛の絵とか、
「極」という一文字だけが描かれたものもあり、全部見ようとして、
みんな口をあけて天井を眺めているのが面白かったですわ。
(何を見てるねん)
この建物はもともと昭和4年に建てたものがベースなので、
どおりで電気配線とか、鏡とか、流しのタイルとかが古かったわけだ。
なかなか面白い体験でした。
さて。
絵解きを終わって外へ出て、お庭を眺めていたら…なんと、雨が降り出しました。
うそ~!
本人は日傘用にと思って持ってきていた晴雨兼用の傘があったからいいけど、
突然の雨に(天気予報では雨なんて出てなかったはず)傘を求める人が続出。
新緑の濃くなってきた頃なので、また雨もいいもんですね。
なんて強がりを言ったものの、今日のメインイベントはお練りである。
雨になったらどうするの?
ピンポーン。
答えは、曼荼羅堂(本堂)の周辺を歩いて終わりです。
え~何とか、それまでには雨あがってくれ~!

東塔と池(蓮の葉がいっぱい)

写経道場を外から見たもの

植物にとっては惠の雨

緑が一層濃くなった感じです
中の坊を出たら、
「娑婆堂」では、お練りの用意のためにおじちゃんたちが作業をしてました。
すでに娑婆堂から延びる渡り舞台(来迎橋)はまっすぐに曼荼羅堂(極楽堂)に伸びておりましたが、
降り出した雨に、傘を持たない人はしばしその下に避難して雨やどりです。

曼荼羅堂の西隣りの護念院から延びる渡り廊下。
ここから仏様たちがスタンバイして出てきます。
晴れていれば、この来迎橋上をどんどん進んで娑婆堂へ向かうのですが、
雨ともなればどうなりますことやら。

とりあえず雨宿りを兼ねて、曼荼羅堂内でしばし時間をつぶしておりましたが、
途中係りの人の手によって、このカラフルな幕も外されてしまって、
本日の来迎橋でのお練りは中止が決定されました。

ということで、お練りは本堂の周りを回る形で行われることになりましたので、
本堂の東南の角方向の、護念院の白壁の前の場所を確保。
ここならば、護念院から渡ってくる仏様の姿も拝めるし、
回廊が高い場所にあるので傘の波の上からでも、
お練りの様子も見えるだろうと踏んで。
(この読みは正しかったです。この場所は雨天時には有効かも)
そして定刻にはお練りが始まる模様。
仏様たちのお渡りの前にはお寺関係者が、
足元が危なく無いようにと、渡り廊下(?)を一生懸命に雑巾で拭いておられました。
(ご苦労様でした)
そして、いよいよお練り開始です。

お稚児様の列

仏様登場
歩き始める際に、面がずれていると世話役の人が面を直してくれます。
そして登場、
スクイボトケとオガミボトケ

蓮台を持ったのがスクイボトケで、
両手を合掌しているのがオガミボトケ。
つまり観音菩薩(救い仏)と勢至菩薩(拝み仏)です

左右に大きく体をひねりながら、
両腕を高く掲げたり下ろしたりして、一歩一歩ゆっくりと歩み行く姿は、
「練り歩く」=おねりの語感そのもの。
こんな変な動きいうのは、
人間ではない=ホトケであるってのの証明なんだとか。
本堂に入った後は法要が行われて、
それが終わると、スクイボトケの蓮台には中将姫の姿が乗ります。
(従来は娑婆堂で行われる行事だけど、今日だけは本堂で)

蓮台の上には中将姫のお姿があります
そして本堂を出て、再び回廊を練り歩きます。
私は場所を動かず見ていたので、本堂を出て反時計回りで進んでいく行列とは
しばしのお別れになってしまいました。
とりあえず、ぐるっと一周してくれば、
またこの角度へ帰ってくるからとノンキに構えてましたけど。
そして、一周してきた中将姫を捧げ持つ観音菩薩が登場です。
やっぱりここは良いポジションでしたわ♪

続くは勢至菩薩

一歩踏み出しては一歩さがるような感じなのでなかなか進みません★

そのまま護念院への橋を渡っていきます

お練の最終版に来て薄日がさしてきました

二十五菩薩さんたちもお疲れ様でした~
お祭りが午後四時からなんて時間から始まるのには、
こういう”舞台装置”が盛り込まれているからなのね。
つまり、光の中を来迎する仏様の集団を見せるというのが、
この練り供養会式の最高の見せ場。
そこで必要なのが「光」「ライティング」。
野外で行うので、この場合は「夕日」です。
まさに西方極楽浄土から、まばゆい光の中をお迎えに来る仏様たちのお姿を、
「仏さんが迎えに来るってのはこういうもんやで」と、
人々に見せる宗教行事なので、薄日といえどナイスな演出でした。
しかし、終了した途端に晴れてきたってのは…
少々複雑な気持ちになるんですけどね。
まあ、晴れの日のお練りは見たことがあるし、
カメラマンさんたちも珍しいアングルからのお練りを取れたかと思うので、
これはこれで良かったんではないかと。
ポジティブシンキングです♪
(そう思わなきゃやってられないじゃないか!)
雨の日に写真撮るとどんなもんだろと探していたら、
nakaさんのブログでは写真満載の記事を発見!!
練り歩くオガミボトケとスクイボトケはこちらで見られますし、
娑婆堂でのお迎え光景の写真はここにありましたし、
私は場所固定で見ていましたが、雨の日の極楽堂一周の写真はこちらから見られます♪
(すごい!すごい!いろんな場面が見られますよ~必見)
ってことで。
まあ、珍しい光景が撮れた(見られた)と思えば、
雨の中のお練りもよかったのではないでしょうか。
(でも”中の人”は大変だったんでしょうが)

祭りが終わったらすぐさまガランとしてしまいました
最後には金堂&講堂&曼荼羅堂も拝観してきました。
講堂では”例の”油かけ事件”の実物も目にしてしまって…激怒。
芽出度い&有り難い気分が、少し凹みましたけど。
自分も信仰するものがあるのだったら、
他人の信仰にも敬意を払うべきだろうに(ぷんぷん)
ま、それらのこともありましたが、
帰る頃には夕日も照らしてきて、
當麻の夕暮れは綺麗でした。

帰りは道すがら綺麗に咲いているよそのお宅の花などながめながら

駅に着いたら本日のお練り特別運行で当麻寺に特別に止まる電車に乗れました。
これも普段の行いのよさ?(へへへ)
これに乗って一路奈良駅へと向かいます。
(次の日につづく)









