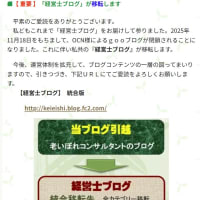■【経営四字熟語で目から鱗が落ちる】6-08 冠履倒易 立場逆転はいつ起こるか解らない ~ 立場や価値が逆転する

四字熟語というのは、漢字四文字で構成された熟語であることはよく知られています。お恥ずかしいながら、その四字熟語というのは、すべてが中国の故事に基づくものとばかり思っていましたが、実はそうではないことを発見しました。
経営コンサルタントという仕事をしていますが、その立場や経営という視点で四字熟語を”診る”と、今までとは異なった点で示唆を得られることが多のです。「目から鱗が落ちる」という言葉がありますが、四字熟語を講演や研修の場で用いたり、自分の仕事や日常会話に活かしたりするようにしましたら、他の人が私を尊敬といいますとオーバーですが、自分を見てくれる目が変わってきたように思えたことがあります。
四字熟語の含蓄を、またそこから得られる意味合いを噛みしめますと、示唆が多いですので、企業経営に活かせるのではないかと考えるようにもなりました。これを「目鱗経営」と勝手に造語し、命名しました。
以前にも四字熟語をご紹介していましたが、一般的な意味合いを中心にお話しました。このシリーズでは、四字熟語を経営の視点で診て、つぶやいてみます。以前の四字熟語ブログもよろしくお願いします。
■ 第6章 仕事上手になる法
論理思考で現状分析をキチンとし、方向性を明確にしてからPDCAサイクルを回し始めても、実際に行動に移したときに旨くいかないことがあります。やりたいという気持ちはあっても、いざ行動に移そうとしたときに、動けないこともあります。
相手の人を説得したり、納得させたりしても、必ずしも相手は期待通りに動いてくれないことがあります。日常生活においてだけではなく、経営者・管理職にとっては、社員や部下が動いてくれないというのは深刻な問題です。
人の価値観というのは、多様性に富んでいます。論理思考で相手を説得したからといって、相手は納得したわけではありません。一つの価値観だけでは、相手は納得してくれません。人は、理屈だけで動いているわけでもなく、感情もあります。
うまくいかない原因として、やろうとしていることにコツやカンというものがあったり、それを行うための技術が必要であったりして、その習得ができていないことでうまく行かないことがあります。コツの飲み込み方が上手な人もいれば、そうでない人もいます。
このような時に、役立つ四字熟語がありますので、ご紹介します。ここでは、四字熟語の中から、相手を理解し、一方、相手にその気になってもらうには、どうしたらよいのか、心に訴えるヒントを感じ取っていただきたいです。
*
■6-08 冠履倒易 立場逆転はいつ起こるか解らない
~ 立場や価値が逆転する ~
日本型企業の特徴として「終身雇用(しゅうしんこよう)」という形がありました。「就職ではなく就社」というのが常識で、「転職するのはガマンがたりない」とか「転職で履歴書を汚すな」などということが言われて来ました。近年、労働力の流動化現象が一般的にありますと、むしろ転職して一歩上のポストに就く「キャリアアップ」という思想が一般的になってきました。
このような時代になりますと、しばしば遭遇するのが後漢書に出てきます「冠履倒易(かんりとうえき)」です。「冠」は文字通り冠のことで、「履」は、音読みで靴などを「はく」という意味です。「倒」は「倒れる」という意味から、ここでは「逆さまになる」という意味で用いられています。「易」は、「入れ替わる」という意味ですので、「冠履倒易」というのは、頭にかぶるべき冠を足に着け、足に履くべき靴を頭にかぶって、逆さまに入れ替わることを指します。
このことから「人の地位や立場の上下が入れ替わる」、また転じて、「物事の価値が上下逆さまで秩序が乱れる」ことを指します。「冠履転倒(かんりてんとう)」「主客転倒(しゅかくてんとう)」とも表現され、またニュアンスは異なりますが、関連する言葉に「本末転倒(ほんまつてんとう)」があります。前項いずれも「転」は「顛」と書くこともあります。
若い人が、自分より年齢の上に立って、人を雇ったり、使ったりする光景は、珍しくなくなりました。上に立つ若い人は、冠履倒易を気にせず、自分が人を使う身ですので、上司として振る舞いますが、使われる年齢の上の人の心境は必ずしも穏やかではありません。それを意識せず、上から目線でばかりに見たり、言ったりしていては、本当の意味での信頼関係は築けないでしょう。
そればかりではなく「因果応報(いんがおうほう)」という言葉もあります。上から目線でのみ相手を見ていますと、「江戸の仇を長崎で討つ」とう言葉がありますように、何処でしっぺ返しを受けるか解りません。
「因」は「因縁」とうことから「原因」という意味です。「果」は「果報」、訓読みしますと「報いを果たす」となり、原因によって生じた結果や報いがあることです。このことから「良いことをすれば良い報いがあり、悪いことをすれば悪い報いがある(新明解四字熟語辞典)」ということになります。もともとは仏教用語で「過去における善悪の業(ごう)に応じて現在における幸不幸の果報を生じ、現在の業に応じて未来の果報を生ずること(広辞苑第六版)」で前世の行いに応じて、因果があるという意味になります。
行為の善悪に応じて、その報いがあるというのがもとの意味ですが、昨今では悪いニュアンスで、「悪行を行いますと、その罰を受ける」という意味で用いられることが多いようです。類義語として「悪因悪果(あくいんあっか)」「善因善果(ぜんいんぜんか)」という表現があります。「悪因悪果」は悪業には、必ず悪い報いがあるということで、「善因善果」は、よい行いをしていれば、いずれよいことが起こるという意味になります。
話を「冠履倒易」に戻したいと思います。自分より、若い上司に仕えるときの心得も見て行きましょう。まず、重要なことは、自分自身を納得させることです。知識としては、「若いとはいえ、上司は上司である」ということは当然持っています。「組織で動く」ということを自分自身が心から、それが正しいことであると信ずることです。これを実践することは容易ではないですが、現実を直視していくうちに自然と受け入れられるようになると信ずることです。
例え若いとは言え上司ですので、相手の顔を立てて、力を「お借りする」という気持ちを忘れず、自分の言葉遣いから配慮してゆきましょう。話を切り出すときに「お願いしたいことがあるのですが」というように始めます。当然、若い上司は、自分の気持ちをくすぐられます。こちらは、それにより「相手は上司」ということを自分自身に意識付けさせることになります。
「実は、先方が値引き攻勢を緩めてくれませんので、部長にマークアップ率をご検討頂き、できれば一緒に先方を訪問してくださいませんでしょうか」という質問をする形で投げかます。勘の良い上司であれば、「自分が同行するから、値引きも自分の権限でしてやれる」ということで、自分の株が上がると計算するかもしれません。
当然のことながら、「部長がそうしてくだされば助かりますし、私も自信を持って折衝に当たることができます。お忙しいにもか変わりませず、お時間を取ってくださりありがとうございました」感謝の気持ちを伝えれば、上司だけではなく、自分も気持ちよく仕事に戻れるでしょう。「お客様を大切にする」ということを第一義として考えていれば、相手が年下の人間であれ、誰であれ、頭を下げることはできるはずです。
上司を上手に使って、自分の成果を上げることは、「組織で動く」ということの大きなメリットのひとつではないでしょうか。逆に、自分が管理職の立場で、部下に接するときにも、相手の人間性を軽視してはならないと思います。あまり感心することではないですが、いつ「冠履倒易」という事態が自分の身に降りかかるか解りませんので、管理職だからと言ってふんぞり返っていないで、平素から言動に注意することも必要でしょう。
部下を叱るときにも、感情的になって、怒鳴りつけますと、決して良い結果は生まれません。部下を叱るときには、場所選びも大切です。しかし、信頼している部下を心から育成していこうと思ったら、腹の底から怒ることが大切です。こちらの気持ちが相手に正しく伝わるでしょう。
部下の管理や育成という観点では、「一張一弛(いっちょういっし)」という見方も重要です。中国の礼記に周の文応の逸話が掲載されています。弓を張ったり、緩めたりするように、人民に対しても緩急をもって接する政治を行ったとあります。すなわち、ケースバイケースで、あるときには締め、あるときには緩める、すなわち厳格にしたり、寛大に接したりすることを言っています。
*
論理思考で現状分析をキチンとし、方向性を明確にしてからPDCAサイクルを回し始めても、実際に行動に移したときに旨くいかないことがあります。やりたいという気持ちはあっても、いざ行動に移そうとしたときに、動けないこともあります。
相手の人を説得したり、納得させたりしても、必ずしも相手は期待通りに動いてくれないことがあります。日常生活においてだけではなく、経営者・管理職にとっては、社員や部下が動いてくれないというのは深刻な問題です。
人の価値観というのは、多様性に富んでいます。論理思考で相手を説得したからといって、相手は納得したわけではありません。一つの価値観だけでは、相手は納得してくれません。人は、理屈だけで動いているわけでもなく、感情もあります。
うまくいかない原因として、やろうとしていることにコツやカンというものがあったり、それを行うための技術が必要であったりして、その習得ができていないことでうまく行かないことがあります。コツの飲み込み方が上手な人もいれば、そうでない人もいます。
このような時に、役立つ四字熟語がありますので、ご紹介します。ここでは、四字熟語の中から、相手を理解し、一方、相手にその気になってもらうには、どうしたらよいのか、心に訴えるヒントを感じ取っていただきたいです。
*
■6-08 冠履倒易 立場逆転はいつ起こるか解らない
~ 立場や価値が逆転する ~
日本型企業の特徴として「終身雇用(しゅうしんこよう)」という形がありました。「就職ではなく就社」というのが常識で、「転職するのはガマンがたりない」とか「転職で履歴書を汚すな」などということが言われて来ました。近年、労働力の流動化現象が一般的にありますと、むしろ転職して一歩上のポストに就く「キャリアアップ」という思想が一般的になってきました。
このような時代になりますと、しばしば遭遇するのが後漢書に出てきます「冠履倒易(かんりとうえき)」です。「冠」は文字通り冠のことで、「履」は、音読みで靴などを「はく」という意味です。「倒」は「倒れる」という意味から、ここでは「逆さまになる」という意味で用いられています。「易」は、「入れ替わる」という意味ですので、「冠履倒易」というのは、頭にかぶるべき冠を足に着け、足に履くべき靴を頭にかぶって、逆さまに入れ替わることを指します。
このことから「人の地位や立場の上下が入れ替わる」、また転じて、「物事の価値が上下逆さまで秩序が乱れる」ことを指します。「冠履転倒(かんりてんとう)」「主客転倒(しゅかくてんとう)」とも表現され、またニュアンスは異なりますが、関連する言葉に「本末転倒(ほんまつてんとう)」があります。前項いずれも「転」は「顛」と書くこともあります。
若い人が、自分より年齢の上に立って、人を雇ったり、使ったりする光景は、珍しくなくなりました。上に立つ若い人は、冠履倒易を気にせず、自分が人を使う身ですので、上司として振る舞いますが、使われる年齢の上の人の心境は必ずしも穏やかではありません。それを意識せず、上から目線でばかりに見たり、言ったりしていては、本当の意味での信頼関係は築けないでしょう。
そればかりではなく「因果応報(いんがおうほう)」という言葉もあります。上から目線でのみ相手を見ていますと、「江戸の仇を長崎で討つ」とう言葉がありますように、何処でしっぺ返しを受けるか解りません。
「因」は「因縁」とうことから「原因」という意味です。「果」は「果報」、訓読みしますと「報いを果たす」となり、原因によって生じた結果や報いがあることです。このことから「良いことをすれば良い報いがあり、悪いことをすれば悪い報いがある(新明解四字熟語辞典)」ということになります。もともとは仏教用語で「過去における善悪の業(ごう)に応じて現在における幸不幸の果報を生じ、現在の業に応じて未来の果報を生ずること(広辞苑第六版)」で前世の行いに応じて、因果があるという意味になります。
行為の善悪に応じて、その報いがあるというのがもとの意味ですが、昨今では悪いニュアンスで、「悪行を行いますと、その罰を受ける」という意味で用いられることが多いようです。類義語として「悪因悪果(あくいんあっか)」「善因善果(ぜんいんぜんか)」という表現があります。「悪因悪果」は悪業には、必ず悪い報いがあるということで、「善因善果」は、よい行いをしていれば、いずれよいことが起こるという意味になります。
話を「冠履倒易」に戻したいと思います。自分より、若い上司に仕えるときの心得も見て行きましょう。まず、重要なことは、自分自身を納得させることです。知識としては、「若いとはいえ、上司は上司である」ということは当然持っています。「組織で動く」ということを自分自身が心から、それが正しいことであると信ずることです。これを実践することは容易ではないですが、現実を直視していくうちに自然と受け入れられるようになると信ずることです。
例え若いとは言え上司ですので、相手の顔を立てて、力を「お借りする」という気持ちを忘れず、自分の言葉遣いから配慮してゆきましょう。話を切り出すときに「お願いしたいことがあるのですが」というように始めます。当然、若い上司は、自分の気持ちをくすぐられます。こちらは、それにより「相手は上司」ということを自分自身に意識付けさせることになります。
「実は、先方が値引き攻勢を緩めてくれませんので、部長にマークアップ率をご検討頂き、できれば一緒に先方を訪問してくださいませんでしょうか」という質問をする形で投げかます。勘の良い上司であれば、「自分が同行するから、値引きも自分の権限でしてやれる」ということで、自分の株が上がると計算するかもしれません。
当然のことながら、「部長がそうしてくだされば助かりますし、私も自信を持って折衝に当たることができます。お忙しいにもか変わりませず、お時間を取ってくださりありがとうございました」感謝の気持ちを伝えれば、上司だけではなく、自分も気持ちよく仕事に戻れるでしょう。「お客様を大切にする」ということを第一義として考えていれば、相手が年下の人間であれ、誰であれ、頭を下げることはできるはずです。
上司を上手に使って、自分の成果を上げることは、「組織で動く」ということの大きなメリットのひとつではないでしょうか。逆に、自分が管理職の立場で、部下に接するときにも、相手の人間性を軽視してはならないと思います。あまり感心することではないですが、いつ「冠履倒易」という事態が自分の身に降りかかるか解りませんので、管理職だからと言ってふんぞり返っていないで、平素から言動に注意することも必要でしょう。
部下を叱るときにも、感情的になって、怒鳴りつけますと、決して良い結果は生まれません。部下を叱るときには、場所選びも大切です。しかし、信頼している部下を心から育成していこうと思ったら、腹の底から怒ることが大切です。こちらの気持ちが相手に正しく伝わるでしょう。
部下の管理や育成という観点では、「一張一弛(いっちょういっし)」という見方も重要です。中国の礼記に周の文応の逸話が掲載されています。弓を張ったり、緩めたりするように、人民に対しても緩急をもって接する政治を行ったとあります。すなわち、ケースバイケースで、あるときには締め、あるときには緩める、すなわち厳格にしたり、寛大に接したりすることを言っています。
*
【経営四字熟語】バックナンバー ←クリック
*
■ おすすめブログ コンサルタント・士業に特化したブログ
- 【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記
- 【小説風】竹根好助のコンサルタント起業
- 【経営】 成功企業・元気な会社・頑張る社長
- 【専門業】 経営コンサルタントへの道
- 【専門業】 経営コンサルタントはかくありたい
- 【専門業】 日本経営士協会をもっと知る
- 【専門業】 ユーチューブで学ぶコンサルタント成功法
- 【専門業】 プロの表現力
- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業5つの要諦
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<思考法編>
- 【経営・専門業】 ビジネス成功術
- 【経営・専門業】 経営コンサルタントのひとり言
- 【話材】 話したくなる情報源
- 【話材】 お節介焼き情報
- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業講座
- 【専門業】 経営コンサルタント情報
- 【専門業】 プロのための問題解決技法(0
- 【経営】 経営コンサルタントの本棚
- 【経営】 コンサルタントの選び方
- 【経営】 管理会計を活用する
- 【経営】 経営コンサルタントの効果的な使い方
- 【経営】 ユーチューブで学ぶ元気な経営者になる法
- 【心 de 経営】 菜根譚に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 経営四字熟語
- 【心 de 経営】 徒然草に学ぶ
- 【心 de 経営】 経営コンサルタントのあり方
- 【心 de 経営】 歴史・宗教に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 論語に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 心づかいで人間関係改善
- 【経営】 経営情報一般
- コンサルタントバンク
- 【話材】 お節介焼き情報
- 【話材】 ブログでつぶやき
- 【話材】 季節・気候
- 【話材】 健康・環境
- 【経営コンサルタントのひとり言】
- 【経営】 ICT・デジタル情報
- 【話材】 きょうの人01月
- 【話材】 きょうの人02月
- 【話材】 きょうの人03月
- 【話材】 きょうの人04月
- 【話材】 きょうの人05月
- 【話材】 きょうの人06月
- 【話材】 きょうの人07月
- 【話材】 きょうの人08月
- 【話材】 きょうの人09月
- 【話材】 きょうの人10月
- 【話材】 きょうの人11月
- 【話材】 きょうの人12月
- 【話材】 きょうの人
© copyrighit N. Imai All rights reserved