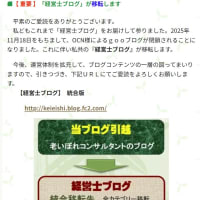■【経営四字熟語で目から鱗が落ちる】6-09 堅白同異 多元論的発想でトラブル回避 ~ 二つのことが同時に成立することはない?

四字熟語というのは、漢字四文字で構成された熟語であることはよく知られています。お恥ずかしいながら、その四字熟語というのは、すべてが中国の故事に基づくものとばかり思っていましたが、実はそうではないことを発見しました。
経営コンサルタントという仕事をしていますが、その立場や経営という視点で四字熟語を”診る”と、今までとは異なった点で示唆を得られることが多のです。「目から鱗が落ちる」という言葉がありますが、四字熟語を講演や研修の場で用いたり、自分の仕事や日常会話に活かしたりするようにしましたら、他の人が私を尊敬といいますとオーバーですが、自分を見てくれる目が変わってきたように思えたことがあります。
四字熟語の含蓄を、またそこから得られる意味合いを噛みしめますと、示唆が多いですので、企業経営に活かせるのではないかと考えるようにもなりました。これを「目鱗経営」と勝手に造語し、命名しました。
以前にも四字熟語をご紹介していましたが、一般的な意味合いを中心にお話しました。このシリーズでは、四字熟語を経営の視点で診て、つぶやいてみます。以前の四字熟語ブログもよろしくお願いします。
■ 第6章 仕事上手になる法
論理思考で現状分析をキチンとし、方向性を明確にしてからPDCAサイクルを回し始めても、実際に行動に移したときに旨くいかないことがあります。やりたいという気持ちはあっても、いざ行動に移そうとしたときに、動けないこともあります。
相手の人を説得したり、納得させたりしても、必ずしも相手は期待通りに動いてくれないことがあります。日常生活においてだけではなく、経営者・管理職にとっては、社員や部下が動いてくれないというのは深刻な問題です。
人の価値観というのは、多様性に富んでいます。論理思考で相手を説得したからといって、相手は納得したわけではありません。一つの価値観だけでは、相手は納得してくれません。人は、理屈だけで動いているわけでもなく、感情もあります。
うまくいかない原因として、やろうとしていることにコツやカンというものがあったり、それを行うための技術が必要であったりして、その習得ができていないことでうまく行かないことがあります。コツの飲み込み方が上手な人もいれば、そうでない人もいます。
このような時に、役立つ四字熟語がありますので、ご紹介します。ここでは、四字熟語の中から、相手を理解し、一方、相手にその気になってもらうには、どうしたらよいのか、心に訴えるヒントを感じ取っていただきたいです。
*
■6-09 堅白同異 多元論的発想でトラブル回避
~ 二つのことが同時に成立することはない? ~
部下を叱るときには「ピグマリオン効果」を使うと成功することが多いです。「ピグマリオン効果」というのは、教育心理学における心理的行動の1つです。教師が期待すると生徒はそれに応えようと努力し、その結果教育効果が上がるというのです。
「君は、このようなミスをするような人ではないはずです。君らしくないですね」と相手への期待や信頼が伝わるように、誠意を込めて話します。人間というのは、期待されるとその期待通りに成長しようとするという、「ピグマリオン効果」を上手に使いましょう。ただし、相手によっては、「何を偉そうに」という反発があるかもしれませんので、本当に期待している相手に限定して、私は使うようにしています。
十分信頼しきれない部下の場合には、自分が冷静になって相手を納得させるようにすることが必要です。理屈や権力で相手をねじ伏せては、説得はできても、相手の納得は得られないでしょう。
一方、最近は「モンスターペアレント」などと言われる理不尽な要求をする人が増えてきています。
こじつけや詭弁のたとえとして「堅白同異(けんぱくどうい)」という四字熟語があります。中国の戦国時代の趙の国にいた公孫竜が「堅白同異之論」というのがあります。堅くて白い石を目で見れば白いことは解りますが、堅いかどうかは解りません。手で触ると堅いと言うことはわかりますが、それが白か他の色香までは解りません。このことから、「堅いことと白いことは同時には成立することはない」というこじつけをいうことを「堅白同異」と言います。詭弁を弄するという意味では「三百代言(さんびゃくだいげん)」もあります。「詭弁を弄する人」という意味ですが、「三百文というわずかなお金で、悪人の代言をする」とうことからもともとは弁護士を罵倒するときに用いる表現でした。
「小人閑居(しょうじんかんきょ)」は、大悪人ではありませんが、「小人」すなわち「得のない人」、「器量の小さい人」は悪いことをするということから「小人物は、暇があると良くないことを考える」という意味です。「小人」は、多くの場合「小心翼翼(しょうしんよくよく)」であることが多いです。「翼翼」は「恭しく、慎み深い」ことをいい、本来は「慎み深い」ことを指しました。昨今では「気が小さく、びくびくしている」様子をいいます。
真実に反したことでも、自分の都合の良いように解釈し、強引な理屈をこじつけることを、別の類似四字熟語で「牽強付会(けんきょうふかい)」といいます。「牽強」は強引なこじつけという意味ですし、「付会」も同じような意味です。夏目漱石の名前の由来でもあります「漱石枕流(そうせきちんりゅ)」も同じような意味です。「石に漱(くちすす)ぎ流れに枕す」と訓読みできます。
広辞苑第六版では、晋書(孫楚伝)として、晋の孫楚が、「石に枕し流れに漱ぐ」と言うべきところを、「石に漱ぎ流れに枕す」と言い誤り、「石に漱ぐ」とは歯を磨くこと、「流れに枕す」とは耳を洗うことと強弁した故事から)こじつけて言いのがれること。まけおしみの強いこととあります。
意見が合わない場合の多くが価値観の違いがあり、必ずしも「話せばわかる」とは限らないことがあります。対立している相手とは、価値観の共有はなく発想は異なり主張が通らないことが多いです。
価値観が異なる場合には、自分もそれをわきまえた上で、「相手の言い分もわかる」という点を探れば、相手の理解を得られる可能性が高まります。「私はあなたの言うようには考えませんが、あなたのような考え方も理解できます」というように持って行きますと、相手もこちらの言うことを受け入れられないまでも、価値観とか文化の違いとかを理解し、敵対的な感情のもつれを回避することができるでしょう。
養老孟司著の「バカの壁」という書籍の中で「話せばわかると思ってはダメ、人と人の間には高く分厚い理解力の壁や思い込みの壁がある」と言っています。「真理は一つ」ではなく、いろいろな発想があってしかるべきという、多元論的な発想が重要と考えます。それにより相手を尊重し、合意点を見出す努力を続けるべきでしょう。
私事になりますが、私は喘息を永年患っています。たばこの煙や仏壇の線香の煙ですら、喘息の発作を起こしてしまいます。ある日、道を歩いていますと、前方からたばこを吸いながらアラフォーの男性が歩いてきました。
「なぜ、俺の顔をジッとみるんだ」
「・・・・・」
「なぜ、俺を睨むのかって言ってんだヨ」
「睨まれているように感ずるのは、あなたが何かやましいことをしているからではありませんか」
「なにを~」
「・・・・・」
―― 条例で歩行喫煙を禁じられていることを知っていながら、照れ隠しですごんでいるようでした。
「私は、あなたを睨んでいたのではなく、あなたがはき出した煙の行方を追っていたのです」
「何で、そんなことをするんだ」
「日本だけで、喘息で二千人以上の人が亡くなっています。多い時には五千人を超えています。たばこをお吸いの方は、嗜好品として愛煙権を振りかざしていればよろしいのかもしれませんが、私はその煙で命を落とすかもしれません。煙の流れる方角を見定めて、歩く経路を模索していたのです。もし、あなたを睨んでいるようにお感じになったのでしたら謝ります」
「わかりゃ、いいんだ」
「ご理解くださり、御協力くださると、同じように睨んでいるような誤解をされて不快な思いをさせることがなくなります」
「解ったよ」
納得は、相手が気づくといとも簡単にしてもらえます。しかし、気づきがありませんと、益々こじれてしまいます。上述の会話例では「愛煙権を振りかざして」という挑発的なことを言っていながら「五千人の死」というような厳しい事実を突きつけられ、その後で「謝ります」と下出に出た、その落差と、こちらが堂々と持論をぶつけたことにより、次第に気持ちが落ち着いてきたのでしょう。喘息患者というのは、常に死と向き併せにいるのだという事実を知り、歩行喫煙は条例違反で制裁金も科されるという事実を思い出された、問題の本質を理解できたことにより、納得したのでしょう。
ビジネスでは、利害が絡むことが多く、難しい面も多いのですが、原点回帰を心がけてみてはどうでしょうか。何ごとにおきましても、実行する目的があるはずです。その目的は、さらに上位概念、例えば経営理念などに基づいているかどうか、という観点で話を進めます。その結果、相手は「なるほど、部長のおっしゃるとおりですね」と自分の非を認めることになるでしょう。
世の中、いつ、何が起こるか解りません。人は見かけによらず、何かすぐれている面を持っていることもあります。それが開花して立場が逆転することもあるでしょう。自分が、失敗して「冠履倒易」が怒ることもあります。私は、相手が年齢や地位の上下に関係なく、「さん」づけで相手を呼ぶようにしています。「さん」づけをすることにより、自分自身に、相手を尊重するように注意を促すことに繋がるのです。平素の接し方において、配慮をすることにより、相手を尊重することに繋がるように思えます。
*
論理思考で現状分析をキチンとし、方向性を明確にしてからPDCAサイクルを回し始めても、実際に行動に移したときに旨くいかないことがあります。やりたいという気持ちはあっても、いざ行動に移そうとしたときに、動けないこともあります。
相手の人を説得したり、納得させたりしても、必ずしも相手は期待通りに動いてくれないことがあります。日常生活においてだけではなく、経営者・管理職にとっては、社員や部下が動いてくれないというのは深刻な問題です。
人の価値観というのは、多様性に富んでいます。論理思考で相手を説得したからといって、相手は納得したわけではありません。一つの価値観だけでは、相手は納得してくれません。人は、理屈だけで動いているわけでもなく、感情もあります。
うまくいかない原因として、やろうとしていることにコツやカンというものがあったり、それを行うための技術が必要であったりして、その習得ができていないことでうまく行かないことがあります。コツの飲み込み方が上手な人もいれば、そうでない人もいます。
このような時に、役立つ四字熟語がありますので、ご紹介します。ここでは、四字熟語の中から、相手を理解し、一方、相手にその気になってもらうには、どうしたらよいのか、心に訴えるヒントを感じ取っていただきたいです。
*
■6-09 堅白同異 多元論的発想でトラブル回避
~ 二つのことが同時に成立することはない? ~
部下を叱るときには「ピグマリオン効果」を使うと成功することが多いです。「ピグマリオン効果」というのは、教育心理学における心理的行動の1つです。教師が期待すると生徒はそれに応えようと努力し、その結果教育効果が上がるというのです。
「君は、このようなミスをするような人ではないはずです。君らしくないですね」と相手への期待や信頼が伝わるように、誠意を込めて話します。人間というのは、期待されるとその期待通りに成長しようとするという、「ピグマリオン効果」を上手に使いましょう。ただし、相手によっては、「何を偉そうに」という反発があるかもしれませんので、本当に期待している相手に限定して、私は使うようにしています。
十分信頼しきれない部下の場合には、自分が冷静になって相手を納得させるようにすることが必要です。理屈や権力で相手をねじ伏せては、説得はできても、相手の納得は得られないでしょう。
一方、最近は「モンスターペアレント」などと言われる理不尽な要求をする人が増えてきています。
こじつけや詭弁のたとえとして「堅白同異(けんぱくどうい)」という四字熟語があります。中国の戦国時代の趙の国にいた公孫竜が「堅白同異之論」というのがあります。堅くて白い石を目で見れば白いことは解りますが、堅いかどうかは解りません。手で触ると堅いと言うことはわかりますが、それが白か他の色香までは解りません。このことから、「堅いことと白いことは同時には成立することはない」というこじつけをいうことを「堅白同異」と言います。詭弁を弄するという意味では「三百代言(さんびゃくだいげん)」もあります。「詭弁を弄する人」という意味ですが、「三百文というわずかなお金で、悪人の代言をする」とうことからもともとは弁護士を罵倒するときに用いる表現でした。
「小人閑居(しょうじんかんきょ)」は、大悪人ではありませんが、「小人」すなわち「得のない人」、「器量の小さい人」は悪いことをするということから「小人物は、暇があると良くないことを考える」という意味です。「小人」は、多くの場合「小心翼翼(しょうしんよくよく)」であることが多いです。「翼翼」は「恭しく、慎み深い」ことをいい、本来は「慎み深い」ことを指しました。昨今では「気が小さく、びくびくしている」様子をいいます。
真実に反したことでも、自分の都合の良いように解釈し、強引な理屈をこじつけることを、別の類似四字熟語で「牽強付会(けんきょうふかい)」といいます。「牽強」は強引なこじつけという意味ですし、「付会」も同じような意味です。夏目漱石の名前の由来でもあります「漱石枕流(そうせきちんりゅ)」も同じような意味です。「石に漱(くちすす)ぎ流れに枕す」と訓読みできます。
広辞苑第六版では、晋書(孫楚伝)として、晋の孫楚が、「石に枕し流れに漱ぐ」と言うべきところを、「石に漱ぎ流れに枕す」と言い誤り、「石に漱ぐ」とは歯を磨くこと、「流れに枕す」とは耳を洗うことと強弁した故事から)こじつけて言いのがれること。まけおしみの強いこととあります。
意見が合わない場合の多くが価値観の違いがあり、必ずしも「話せばわかる」とは限らないことがあります。対立している相手とは、価値観の共有はなく発想は異なり主張が通らないことが多いです。
価値観が異なる場合には、自分もそれをわきまえた上で、「相手の言い分もわかる」という点を探れば、相手の理解を得られる可能性が高まります。「私はあなたの言うようには考えませんが、あなたのような考え方も理解できます」というように持って行きますと、相手もこちらの言うことを受け入れられないまでも、価値観とか文化の違いとかを理解し、敵対的な感情のもつれを回避することができるでしょう。
養老孟司著の「バカの壁」という書籍の中で「話せばわかると思ってはダメ、人と人の間には高く分厚い理解力の壁や思い込みの壁がある」と言っています。「真理は一つ」ではなく、いろいろな発想があってしかるべきという、多元論的な発想が重要と考えます。それにより相手を尊重し、合意点を見出す努力を続けるべきでしょう。
私事になりますが、私は喘息を永年患っています。たばこの煙や仏壇の線香の煙ですら、喘息の発作を起こしてしまいます。ある日、道を歩いていますと、前方からたばこを吸いながらアラフォーの男性が歩いてきました。
「なぜ、俺の顔をジッとみるんだ」
「・・・・・」
「なぜ、俺を睨むのかって言ってんだヨ」
「睨まれているように感ずるのは、あなたが何かやましいことをしているからではありませんか」
「なにを~」
「・・・・・」
―― 条例で歩行喫煙を禁じられていることを知っていながら、照れ隠しですごんでいるようでした。
「私は、あなたを睨んでいたのではなく、あなたがはき出した煙の行方を追っていたのです」
「何で、そんなことをするんだ」
「日本だけで、喘息で二千人以上の人が亡くなっています。多い時には五千人を超えています。たばこをお吸いの方は、嗜好品として愛煙権を振りかざしていればよろしいのかもしれませんが、私はその煙で命を落とすかもしれません。煙の流れる方角を見定めて、歩く経路を模索していたのです。もし、あなたを睨んでいるようにお感じになったのでしたら謝ります」
「わかりゃ、いいんだ」
「ご理解くださり、御協力くださると、同じように睨んでいるような誤解をされて不快な思いをさせることがなくなります」
「解ったよ」
納得は、相手が気づくといとも簡単にしてもらえます。しかし、気づきがありませんと、益々こじれてしまいます。上述の会話例では「愛煙権を振りかざして」という挑発的なことを言っていながら「五千人の死」というような厳しい事実を突きつけられ、その後で「謝ります」と下出に出た、その落差と、こちらが堂々と持論をぶつけたことにより、次第に気持ちが落ち着いてきたのでしょう。喘息患者というのは、常に死と向き併せにいるのだという事実を知り、歩行喫煙は条例違反で制裁金も科されるという事実を思い出された、問題の本質を理解できたことにより、納得したのでしょう。
ビジネスでは、利害が絡むことが多く、難しい面も多いのですが、原点回帰を心がけてみてはどうでしょうか。何ごとにおきましても、実行する目的があるはずです。その目的は、さらに上位概念、例えば経営理念などに基づいているかどうか、という観点で話を進めます。その結果、相手は「なるほど、部長のおっしゃるとおりですね」と自分の非を認めることになるでしょう。
世の中、いつ、何が起こるか解りません。人は見かけによらず、何かすぐれている面を持っていることもあります。それが開花して立場が逆転することもあるでしょう。自分が、失敗して「冠履倒易」が怒ることもあります。私は、相手が年齢や地位の上下に関係なく、「さん」づけで相手を呼ぶようにしています。「さん」づけをすることにより、自分自身に、相手を尊重するように注意を促すことに繋がるのです。平素の接し方において、配慮をすることにより、相手を尊重することに繋がるように思えます。
*
【経営四字熟語】バックナンバー ←クリック
*
■ おすすめブログ コンサルタント・士業に特化したブログ
- 【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記
- 【小説風】竹根好助のコンサルタント起業
- 【経営】 成功企業・元気な会社・頑張る社長
- 【専門業】 経営コンサルタントへの道
- 【専門業】 経営コンサルタントはかくありたい
- 【専門業】 日本経営士協会をもっと知る
- 【専門業】 ユーチューブで学ぶコンサルタント成功法
- 【専門業】 プロの表現力
- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業5つの要諦
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<思考法編>
- 【経営・専門業】 ビジネス成功術
- 【経営・専門業】 経営コンサルタントのひとり言
- 【話材】 話したくなる情報源
- 【話材】 お節介焼き情報
- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業講座
- 【専門業】 経営コンサルタント情報
- 【専門業】 プロのための問題解決技法(0
- 【経営】 経営コンサルタントの本棚
- 【経営】 コンサルタントの選び方
- 【経営】 管理会計を活用する
- 【経営】 経営コンサルタントの効果的な使い方
- 【経営】 ユーチューブで学ぶ元気な経営者になる法
- 【心 de 経営】 菜根譚に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 経営四字熟語
- 【心 de 経営】 徒然草に学ぶ
- 【心 de 経営】 経営コンサルタントのあり方
- 【心 de 経営】 歴史・宗教に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 論語に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 心づかいで人間関係改善
- 【経営】 経営情報一般
- コンサルタントバンク
- 【話材】 お節介焼き情報
- 【話材】 ブログでつぶやき
- 【話材】 季節・気候
- 【話材】 健康・環境
- 【経営コンサルタントのひとり言】
- 【経営】 ICT・デジタル情報
- 【話材】 きょうの人01月
- 【話材】 きょうの人02月
- 【話材】 きょうの人03月
- 【話材】 きょうの人04月
- 【話材】 きょうの人05月
- 【話材】 きょうの人06月
- 【話材】 きょうの人07月
- 【話材】 きょうの人08月
- 【話材】 きょうの人09月
- 【話材】 きょうの人10月
- 【話材】 きょうの人11月
- 【話材】 きょうの人12月
- 【話材】 きょうの人
© copyrighit N. Imai All rights reserved