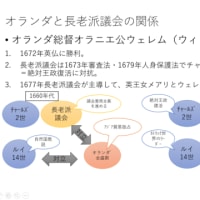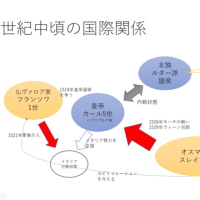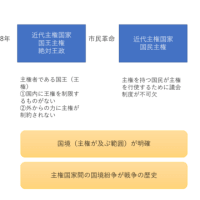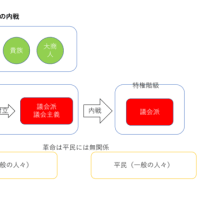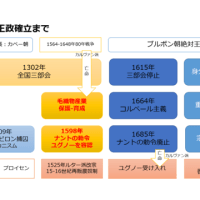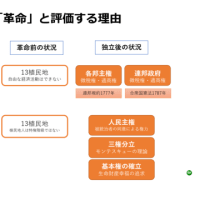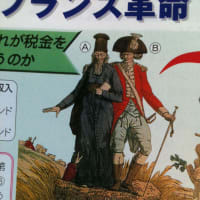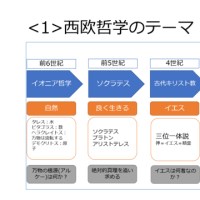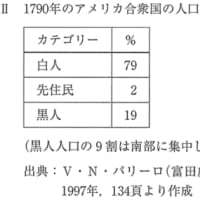モンゴル帝国と元のおおまかな歴史
12世紀末期,モンゴル高原の諸部族のあいだでは統合の機運が高まっていた。その統合に中心的役割を果たしたのが【テムジン】で,彼の指導の下、【1206】年にユーラシア草原地帯を支配するモンゴル帝国が形成され、テムジンは有力者の集いで、【ハン(可汗)位の即位】や大規模な戦争などを決定する【クリルタイ】で【チンギス=ハン】の称号を得た。彼は、その後も強力な騎馬軍団を率いて大規模な遠征を繰り返し、帝国の支配領域を広げていった。
彼の死後もその第3子,【オゴタイ=ハン】が征服事業を継承し,【1234】年に中国華北地方の【金】を滅ぼした後、帝国の都をモンゴル高原の【カラコルム】に定め、契丹人の【耶律楚材】などを登用して、行政・徴税機構の整備に努めた。しかし、この大帝国は宗教・文化のことなる多数の民族をかかえていたため、強力な統治は困難であったし、ハン一族のあいだで対立が深刻化したこともあって,13世紀半ば頃までに、西北モンゴルを支配する【オゴタイ=ハン国】、天山山脈周辺の【チャガタイ=ハン国】、【バトゥ】の西征の際、【1241】年【リーグニッツの戦い】で勝利した後、【南ロシア】で建国された【キプチャク=ハン国】、【1258】年の【フラグ】の西征によって建国した【イラン高原】の【イル=ハン国】、の4ハン国に分裂した。
しかし、当時、モンゴル民族の最大支配領域をなしたのは,中国を支配した【元】であった。元は,すでに雲南やチベット地方を攻略して華北を統治していた。チンギス=ハンの孫にあたる【フビライ】が,モンゴル帝国第5代皇帝に即位した後,都をカラコルムから現在の【北京】にあたる【大都】にうつし,【1271】年,国名を中国風に称したものである。元の成立以降もフビライは中国支配を推し進め,【1279】年には【南宋】を滅ぼして中国全土を征服した。
中国全域が異民族によって支配されたのは史上はじめてのことであった。元は中国を支配するにあたり,【州県制】にもとづく中央集権的な統治を行ったが,中央政府や地方行政機関の要職はモンゴル人が独占し,【モンゴル至上主義】と呼ばれた。また、【ソグド】人などの西域諸民族出身者も重用して財務などの実務にあたらせた。一方、中国人に対しては、【金朝】の支配下にあった人々は【漢人】,【南宋】治下の人々は【南人】と呼び、【科挙】を一時中断した。そのため、従来の征服王朝が中国文明に同化していったのに対して、元は行政・財務などにおいて中国文明の影響を大きく受けなかった。これは、西域や西アジアで高度な【イスラム都市文明】に接していたためと考えられる。また、フビライ=ハンは、【ラマ教】の僧パスパに命じて【パスパ文字】を作成させ、公文書には漢字ではなくパスパ文字を使用している。このようなモンゴル至上主義の結果、儒学は打撃を受けたが,その一方で中国農村地域の大土地所有は温存され,その下での佃戸制も従来どおり継続した。また、【馬致遠】の『【漢宮秋】』や【羅貫中】の『【三国志演義】』などに見られるように、中国人のアイデンティティを守るための【元曲】や小説が書かれ、庶民文化の発展を担った。
フビライの死後,帝位の相続争いが続き,元の政治は混乱した。国教とした【チベット仏教】(【ラマ教】)の保護にもぼう大な費用をかけたため、財政も困窮した。元朝は【交鈔】と称する紙幣を発行していたが,14世紀半ばまでに財政難を打開する必要から、【交鈔】を濫発され、その結果、経済の混乱,物価の高騰を招き,民衆の生活を圧迫した。そうした状況の下、各地で暴動がおこったが,なかでも【白蓮教徒】と呼ばれる農民を一体とする【紅巾の乱】が1351年以降15年にわたってつづけられ.元の統治はにわかに弱体化し,【1368】年,【朱元璋】が派遣した【江南】からの軍に大都をうばわれ,元の中国支配は終わりをとげた。
しかしながら、モンゴル帝国はユーラシア大陸の大部分を統一したため,カラコルムを都としたころから交通路の整備を重視し,帝国全土に幹線道路をはりめぐらす【ジャムチ】という【駅伝制】を敷いた。その結果,内陸路を通じて東西の文化の交流がさかんとなった。東西交流の担い手は【ムスリム商人】で,陸路では【隊商】として貿易活動を営んだ。ムスリム商人はまた、インド洋経由で海上買場にもあたったため,海陸の交通路が発達し,東西交流はますます活発化し、シルクロードは全盛期を迎えた。その過程で,【ジェノヴァ】出身で後に『【東方見聞録】』を書いた【マルコ=ポーロ】や、【モロッコ】出身で『【三大陸周遊記】』を記録した【イブン=バトゥータ】も【大都】を訪れている。さらに、西欧から【カトリック】が始めて中国に伝わり、教皇【インノケンティウス4世】の命で【フランス】人【ルブルック】が【カラコルム】に派遣させ、その後、13世紀末には【モンテ=コルヴィノ】が初代大都大司教になっている。このようなモンゴル帝国時代の東西交流によって,ヨーロッパ人のアジアヘの関心が高まり,後の大航海時代へと連なるのである。
12世紀末期,モンゴル高原の諸部族のあいだでは統合の機運が高まっていた。その統合に中心的役割を果たしたのが【テムジン】で,彼の指導の下、【1206】年にユーラシア草原地帯を支配するモンゴル帝国が形成され、テムジンは有力者の集いで、【ハン(可汗)位の即位】や大規模な戦争などを決定する【クリルタイ】で【チンギス=ハン】の称号を得た。彼は、その後も強力な騎馬軍団を率いて大規模な遠征を繰り返し、帝国の支配領域を広げていった。
彼の死後もその第3子,【オゴタイ=ハン】が征服事業を継承し,【1234】年に中国華北地方の【金】を滅ぼした後、帝国の都をモンゴル高原の【カラコルム】に定め、契丹人の【耶律楚材】などを登用して、行政・徴税機構の整備に努めた。しかし、この大帝国は宗教・文化のことなる多数の民族をかかえていたため、強力な統治は困難であったし、ハン一族のあいだで対立が深刻化したこともあって,13世紀半ば頃までに、西北モンゴルを支配する【オゴタイ=ハン国】、天山山脈周辺の【チャガタイ=ハン国】、【バトゥ】の西征の際、【1241】年【リーグニッツの戦い】で勝利した後、【南ロシア】で建国された【キプチャク=ハン国】、【1258】年の【フラグ】の西征によって建国した【イラン高原】の【イル=ハン国】、の4ハン国に分裂した。
しかし、当時、モンゴル民族の最大支配領域をなしたのは,中国を支配した【元】であった。元は,すでに雲南やチベット地方を攻略して華北を統治していた。チンギス=ハンの孫にあたる【フビライ】が,モンゴル帝国第5代皇帝に即位した後,都をカラコルムから現在の【北京】にあたる【大都】にうつし,【1271】年,国名を中国風に称したものである。元の成立以降もフビライは中国支配を推し進め,【1279】年には【南宋】を滅ぼして中国全土を征服した。
中国全域が異民族によって支配されたのは史上はじめてのことであった。元は中国を支配するにあたり,【州県制】にもとづく中央集権的な統治を行ったが,中央政府や地方行政機関の要職はモンゴル人が独占し,【モンゴル至上主義】と呼ばれた。また、【ソグド】人などの西域諸民族出身者も重用して財務などの実務にあたらせた。一方、中国人に対しては、【金朝】の支配下にあった人々は【漢人】,【南宋】治下の人々は【南人】と呼び、【科挙】を一時中断した。そのため、従来の征服王朝が中国文明に同化していったのに対して、元は行政・財務などにおいて中国文明の影響を大きく受けなかった。これは、西域や西アジアで高度な【イスラム都市文明】に接していたためと考えられる。また、フビライ=ハンは、【ラマ教】の僧パスパに命じて【パスパ文字】を作成させ、公文書には漢字ではなくパスパ文字を使用している。このようなモンゴル至上主義の結果、儒学は打撃を受けたが,その一方で中国農村地域の大土地所有は温存され,その下での佃戸制も従来どおり継続した。また、【馬致遠】の『【漢宮秋】』や【羅貫中】の『【三国志演義】』などに見られるように、中国人のアイデンティティを守るための【元曲】や小説が書かれ、庶民文化の発展を担った。
フビライの死後,帝位の相続争いが続き,元の政治は混乱した。国教とした【チベット仏教】(【ラマ教】)の保護にもぼう大な費用をかけたため、財政も困窮した。元朝は【交鈔】と称する紙幣を発行していたが,14世紀半ばまでに財政難を打開する必要から、【交鈔】を濫発され、その結果、経済の混乱,物価の高騰を招き,民衆の生活を圧迫した。そうした状況の下、各地で暴動がおこったが,なかでも【白蓮教徒】と呼ばれる農民を一体とする【紅巾の乱】が1351年以降15年にわたってつづけられ.元の統治はにわかに弱体化し,【1368】年,【朱元璋】が派遣した【江南】からの軍に大都をうばわれ,元の中国支配は終わりをとげた。
しかしながら、モンゴル帝国はユーラシア大陸の大部分を統一したため,カラコルムを都としたころから交通路の整備を重視し,帝国全土に幹線道路をはりめぐらす【ジャムチ】という【駅伝制】を敷いた。その結果,内陸路を通じて東西の文化の交流がさかんとなった。東西交流の担い手は【ムスリム商人】で,陸路では【隊商】として貿易活動を営んだ。ムスリム商人はまた、インド洋経由で海上買場にもあたったため,海陸の交通路が発達し,東西交流はますます活発化し、シルクロードは全盛期を迎えた。その過程で,【ジェノヴァ】出身で後に『【東方見聞録】』を書いた【マルコ=ポーロ】や、【モロッコ】出身で『【三大陸周遊記】』を記録した【イブン=バトゥータ】も【大都】を訪れている。さらに、西欧から【カトリック】が始めて中国に伝わり、教皇【インノケンティウス4世】の命で【フランス】人【ルブルック】が【カラコルム】に派遣させ、その後、13世紀末には【モンテ=コルヴィノ】が初代大都大司教になっている。このようなモンゴル帝国時代の東西交流によって,ヨーロッパ人のアジアヘの関心が高まり,後の大航海時代へと連なるのである。